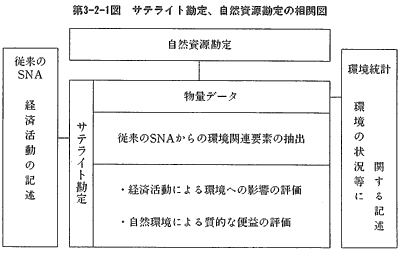
3 環境資源勘定
(1) 環境資源勘定の概要
先に見たように都市・生活型公害や地球環境問題といった今日の環境問題は、経済社会活動一般や国民の日常生活のあり方に根ざしており、これらの問題の解決のためには、経済社会の全ての構成員が、環境保全に関する自主的・積極的な取組を行っていくようにすることが不可欠である。このため、環境政策と経済政策の統合が大きな課題となっている。環境と経済の統合のためには、環境基本計画の策定を含め種々の施策が考えられるが、経済的手法と環境勘定はその主要なもののひとつである。環境負荷の少ない持続可能な経済社会を作り上げていく上で、経済政策の分野での環境に配慮した意思決定に資するべく環境と経済を総合的に評価しうる指標の重要性が国際的に認識されるようになっている。従来の国民経済計算体系(SNA)は、我が国の経済活動の状況を多面的総合的にとらえており、調整勘定においてストックとしての観点から経済価値のある資源の変化についての計算がなされているという点では、環境保全との関連を有する。しかし、生産活動や消費によって生じた環境汚染による国民生活の質の低下を反映しえないこと、野生生物種の減少、鉱物資源の減少など再生不可能な資産の枯渇が将来世代の選択の幅を狭めていることなどが明示的に考慮されていないことなどから、これに代わるあるいは、これを補完する勘定体系の構築が必要とされている。国際的には、1980年代末より、従来のSNAによるGNP、GDP等の経済指標には、環境汚染の局面が反映されていないなどの制約があり、経済政策の分野で環境に配慮した意志決定を行うためには、環境と経済との関わりを総合的に評価しうる指標の開発が重要であるとの認識が高まっている。
環境資源勘定には、いくつかの異なるアプローチがある(第3-2-1図)。
その第一は、森林や水などの自然資源について、そのストックと経済活動による採取・転換・利用・廃棄のフローを体系的に記帳するものである。フランス、ノールウェー及びこれら両国が主導したOECD環境の状況グループ等でこのアプローチがとられている。その第二は、環境汚染による被害や自然資源の減耗の経済的価値を評価し、これを現行のGNPやGDPから減ずることによって、環境面から修正されたGNPやGDPを求めるものである。前者は、「自然資源勘定」と呼ばれることも多く、物量的な勘定である。後者は、貨幣的な勘定である。この例として、1990〜91年に国際連合と世界銀行がメキシコ政府と協力して行ったメキシコに関するパイロットスタディーを見てみよう。同国のNDP(国内純生産)に資源の量的変化に関する補正を加えたEDP(environmentallyadjusted net domestic product)1及び環境の質的変化に関する補正を加えたEDP2の算出を試みている。1985年のメキシコにおけるNDPは、420,605億ペソ(1$=256.87ペソ(1985年平均)IMFによる)である。量的な事項としては、石油の枯渇、新たな油井の発見、木材資源の枯渇、土地利用の変更を取り上げ、これらに関して補正を加えると、EDP1は、396,627億ペソとなる。さらに、これに環境の質的変化に関する補正を加え、EDP2を算出すると第3-2-2図に示されるように、364,483億ペソとなる。これはNDPの約87%であり、差し引き約13%が量的及び質的に補正されたことになる。質的な補正項目としては土壤流出、固形廃棄物、地下水利用、水質汚濁、大気保全では二酸化硫黄、窒素酸化物、炭化水素、一酸化炭素、浮遊粒子状物質による環境への負荷を取り上げている。土壤流出については同様の作物生産レベルを維持するために必要とする肥料の額を、地下水では地下水源への再注入に要する費用を、また、水質、大気は汚染水準の低減に要する費用により貨幣換算した評価を行っている。先進国における環境保全と経済活動の関係の把握には異なる観点も必要となろうが、工業化が進められている段階にある一国の環境保全と経済活動の関わりを理解する上で有益な研究事例といえよう。
次に環境資源勘定を巡る内外の主要な動向について概観してみたい。
(2) 環境資源勘定を巡る国際的な状況
? 地球サミット
経済政策に環境の観点を盛り込むなど環境と経済の統合の必要性は地球サミットの場においても確認されている。先の地球サミットで採択されたアジェンダ21においては、「意志決定における環境と開発の統合D統合された環境・経済勘定システムの確立」、及び「第8章第40章意思決定のための情報」においてその重要性が記述された。
? 国際連合
1993年に、国際連合では国民経済計算体系の改訂を行った。この改訂によりサテライト勘定が導入され、その最も重要なものとして、環境・経済統合勘定(SEEA:Satellite Systemfor integrated Environmental and Economic Accounting)を含めることが決定された。現在、「国民経済計算ハンドブック環境・経済統合勘定」(暫定版)が示されている。SEEAは、環境資源勘定に関して従来開発されてきた様々なアプローチを広く包含し、物的勘定、貨幣的勘定の双方を視野に入れ、また各国における統計のアベイラビリティーに鑑みて段階的に複数のバージョンが用意されている。第1段階は、従来からのSNAの中に記述されてきた環境関連のフローと資産の明細をSNAからとりだして示すことである。第2段階は、物質/エネルギー収支と自然資源勘定の概念をもとに、環境と経済の相互関係を提示する物的勘定が導出され、SNAデータとの結合が行われる。第3段階は、経済活動による環境の劣化と自然資源の枯渇が勘定の中に記述される。第4段階では、生産境界の拡張により、例えば、家計における調理、レクリエーション活動等をも生産活動としてとらえ、その副産物としてのごみの排出を扱うことができることとなる(第3-2-3図)。
? OECD
1989年のパリ・アルシュサミットの経済宣言において、「経済政策と環境政策とを統合する意志決定を行うために役立つ環境指標の開発」が盛り込まれ、OECDにその作業が委嘱された。OECDでは、これを受け、?環境の状況に関する指標、?部門別政策に環境配慮を盛り込むための指標、?マクロ経済政策に環境配慮を盛り込むための環境勘定に分けて検討を進めた。1991年1月のOECD閣僚レベル環境委員会への中間報告では、環境・自然資源勘定手法を?自然資源勘定、?環境に関するサテライト勘定、?国民経済計算体系の修正に分類した。また、今後の進め方としては、国民経済計算体系自身を修正して環境変化を反映させた新たな経済指標(いわゆるグリーンGNP)を現在のGNPに代えて採用することは時期尚早であり、当面は自然資源勘定や、SNAの拡張により環境や自然資源の状況を反映した補足的な勘定(サテライト勘定)の開発に焦点を絞り、これについて世界銀行、国連統計機関等と連携していく旨の報告が行われた。現在、OECD環境の状況グループにおいて検討が進められており、1994年9月に開催予定の会合においては、環境資源勘定をどのように政策決定に利用するかという側面からの討議が行われる予定である(第3-2-4図)。
? 諸外国
米国においては、1994年大統領予算教書において、グリーンGDPの検討を進めるための予算が提案されている。具体的には、3段階に分けて作業を進めることとしている。まず、非再生可能天然資源(石炭、石油、天然ガス、ウラニウム、希少鉱物資源等)の経済的価値についてのプロトタイプ的な推計と、これらの資源の減少を考慮したGDP測定方法を発表し、加えて、再生可能天然資源及び広範囲にわたる環境資産についての経済と環境を統合した計算のための枠組みを示す。次に、非再生可能天然資源勘定を再生可能天然資源(森林、土壤、水、魚)等に広げる。最終的には、清浄な空気やリクリエーション資源としての環境のような環境資産を広範囲にわたって数値化するというものである。ただし、この最終段階は、概念、データ等の点で極めて困難であるとされている。カナダにおいては、天然資源のストック、天然資源の利用、廃棄物・公害、公害防止費用に関するサテライト勘定を開発中である。主要な目的は、資源の質と量の評価を行うこと、環境に関するデータの充実のための枠組みの提供及び経済的な持続可能性を図る方法の改善であるとされる。また、フランスでは、数年来、国家遺産勘定の研究が進められている。概念的には、経済、生態系、社会そして環境を視野に入れたシステムである。ドイツでは、環境サテライト勘定を発展させる方向で研究が進んでいる。環境の状況に関する物理的な状況の把握に加え、経済活動と物理的な状態の変化の関連を見ることを目的としている。ノールウェーでは、物理的な資源勘定のアプローチがとられている。自然資源と汚染物質の流れを捉え、これらの流れと経済活動の関係を分析することとしている。
(3) 我が国の検討状況
環境基本法においても、今後の環境保全に関する科学技術としては、環境保全施策の策定の基礎となる環境の変化の機構の解明、人の活動による環境への負荷の低減に関するものに加えて、環境の保全が社会経済活動と密接に関係していることから、環境と経済との関わりを総合的に評価する新しい指標体系の開発が重要な課題であると認識している。
具体的には、その第三十条において、国は、環境の変化の機構の解明、環境への負荷の低減並びに環境が経済から受ける影響及び経済に与える恵沢を総合的に評価するための方法の開発に関する科学技術その他の環境の保全に関する科学技術の振興を図るものとすると規定している。
平成3年度の予備的研究につづき、平成4年度から、地球環境研究総合推進費により、環境庁国立環境研究所、経済企画庁経済研究所、農林水産省森林総合研究所及び農業総合研究所において環境資源勘定の確立を図るとともに、国民経済計算体系に環境・経済統合勘定(SEEAの手法等に関する検討も含め)を付加する手法等を検討するための研究が進められているところである。
国立環境研究所においては、地球規模の環境変化を反映した勘定体系の開発を目的としてこれまでに「持続可能な発展」の概念のレビュー、今後の重点課題の明確化、主要国・地域間の貿易ODマトリクス表を作成するプログラムを整備し、国際間環境負荷収支を勘定するための基礎データ作成とCO2排出を例とした試算を行っている。
(4) 今後の課題
環境資源勘定には、内外で大きな期待が寄せられているが、これを実際に意志決定の材料に用いるまでには多くの解決すべき課題がある。第一は、方法論上の問題、特に環境の価値の経済的評価手法が十分に確立されていないことである。第二は、データ整備の問題である。いうまでもなく、環境問題は経済のあらゆる活動と結びついており、これに関する情報を収集するには、技術的・組織的・制度的側面のすべてにわたって体系的な取組が必要である。現在は、方法論開発に重点が置かれているが、将来、継続的に数値を算定、報告していくには、それを支えるための環境資源の利用・管理に関する情報収集体制の再編・整備が必要である。
今後は、国際的な研究の動向をも踏まえ、環境資源勘定など環境と経済の状況を総合的に評価する手法を開発し、これを施策に活用し、環境政策と経済政策の統合を進めていくことが必要である。