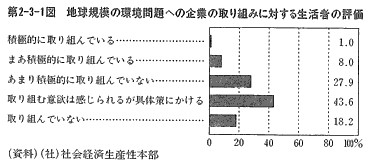
第2節では、産業界における環境に配慮した事業活動への取組について、具体的事例に即して概観してみた。そこでは、これまでの公害防止にとどまらず、今日の地球環境問題をはじめとする環境問題に積極的に対応して行こうとする企業の姿が浮かび上がってきた。さらに、こうした取組が積極的かつ広範囲になるにつれて、エコビジネスという新たな産業分野が形成されつつある。しかし、現実には、使用するエネルギーの量は増加傾向にあり、また廃棄物は増え続けているなど、経済の姿は持続可能なものとはなっていない。産業界においても、自らの社会的責任を果たすべく積極的に行動している面もあるが、中には、環境に配慮した事業活動に向け努力しようにも、何をしたら良いのか分からない企業もある。一方、外部不経済の内部化や環境保全に努力した企業を適正に評価する消費者の行動など、企業の自主的な努力を促進するような体制作りの必要もある。本節では、持続可能な経済社会の構築に向け、産業界において引続き必要な取組について概観するとともに、そうした環境対策が個々の企業に与える経済的な影響について見てみたい。
今日、企業は、我々の経済社会活動の重要な担い手としてその社会的責任を自覚し、持続的発展が可能な経済社会の構築に向けて自主的な努力を積み重ねつつあるが、一方、国民も、企業に環境の保全に向けた積極的な努力を求めている。(社)社会経済国民会議(平成6年4月に(社)社会経済生産性本部に名称変更)が平成4年5月にまとめた企業と生活者を対象にしたアンケート調査(対象は、企業が上場企業約2,000社、有効回収率は25.5%、生活者が都市部の70歳未満の成人男女3,000人、有効回収率は45.1%)の結果によれば、生活者による地球規模の環境問題への企業の取組に対する評価は、「積極的に取り組んでいる」が最も少なく1.0%、「まあ積極的に取り組んでいる」が8.0%と企業に対し積極的と評価するものは1割に満たず、「取り組もうという意欲は感じるが、具体策に欠ける」が最も多く43.6%、「あまり積極的に取り組んでいない」が27.9%、「取り組んでいない」が18.2%と消極的な評価が多くなっている(第2-3-1図)。また、企業の取組状況と生活者が期待していることについては、企業が既に取り組んでいるものとしては、半数以上が「事務用紙などの再生利用」、「製造工程での省資源化・省エネ化」、「産業廃棄物の減量化」などをあげており、重点的に取り組むべきものとしては、やはり半数以上が「産業廃棄物の減量化」を、約4割が「製造工程での省資源化・省エネ化」を、約3割が「環境にやさしい商品の開発」をあげている。一方、生活者が企業に力を入れて欲しいと思う環境対策は、「使用された製品の回収体制の整備」が51.4%、「産業廃棄物の減量化」が40.8%、「商品のパッケージや店舗などでの包装の簡素化」が36.7%であった。こうした差異は、生活者が、主として日常の消費生活のなかで、製品やサービスを接点として企業の環境問題への取組を期待するのに対して、企業では環境負荷の計量的評価や費用対効果、購買意欲効果といった側面からも環境問題への取組がなされていることによるものであると考えられる。こうした差異の存在は、企業と生活者の両者が協力して取り組むべき環境問題に対して両者の協力を妨げる要因にもなりかねない。環境問題に対しては、様々な主体が互いに協力して対策を進められるよう全体的な枠組みが求められており、こうした枠組みのもと、消費者はその消費活動に環境への配慮を組み込み、また企業は環境にやさしい企業行動をとるなど、それぞれの立場で取り組んでいく必要がある。
(自主的な環境管理の枠組みづくり)
近年の地球環境問題をはじめとする環境問題に対し、企業の環境保全対策については、単なる規制の遵守にとどまらない自主的な取組を実施していくことの重要性が認識されるようになってきている。しかし、一般に、企業は市場経済において他の企業と競争しながら事業活動を行い、利益をあげることによって成り立っているものであり、直接目の前の利益と結び付かない環境保全対策は、直接利益に結び付く活動に比べ優先順位が低い場合が多い。こうした場合、自主的に取組を進めるに当たって、どのような取組が望ましい取組なのかという点に関する共通の認識が得られないと、環境保全対策の実効が上がらないことも有り得る。そこで、企業が環境対策を自主的に進めていくための枠組みをどのように構築していくかが重要となってくる。こうした枠組みの一つが環境管理である。自主的な環境管理のイメージとしては、事業活動に伴う環境への負荷を把握、評価し、環境に関する経営方針や目標、行動計画を掲げるとともに、目標や計画の実施に当たっての責任体制を明確にし、目標の達成状況や計画の実施状況を点検しつつ、さらに全体の管理システムの見直しを図るというものである。
このような環境管理の手法については、世界的に標準化の動きが進められている。イギリスでは、1992年(平成4年)3月に、民間企業を含めたあらゆる事業組織に適用されるものとしての、イギリス規格「環境管理システム」が定められた。この規格では、環境管理システムの要素として、環境に関する方針、組織と人員、環境影響の評価と登録、目的・目標の設定、計画、運営管理の記録、監査、全体レビューなどが示されている。
また、国際標準化機構(ISO)では、1993年(平成5年)6月より事業者の環境管理に関する国際標準の策定作業を本格化させている。ISOでは、第207技術委員会(TC207)に、環境管理システム、環境監査及びこれに関連する環境調査、環境ラベリング、環境パフォーマンス評価、ライフサイクルアセスメント、用語と定義の6つの分科委員会(SC)を置き、それぞれ国際標準の策定に向けて、現在活発に議論が行われているところである。
一方、こうした標準化の動きと合わせて、一定の要件を満たす事業活動を推奨する制度の構築も進められている。EC委員会では、1993年(平成5年)6月末に「自主的参加に基づく環境管理・監査スキームに関する規則」を採択した。この規則は、環境管理システムの導入、環境声明書の公表、公認環境検証人による環境声明書の検証などの一連の手続きを自主的に行っている企業に対し、特別のロゴマークの使用を認めるとともに、EC官報に企業名等を掲載するというもので、1995年(平成7年)4月末から施行される予定である。
こうした環境管理システムを導入する動きは我が国の産業界においても始められつつあり、また、政府においても、通商産業省による「環境に関するボランタリープラン」の策定要請(平成3年10月)や、環境庁による「環境にやさしい企業行動指針」の公表(平成5年2月)など、自主的な取組を促進するための施策が実施されている。環境管理に関しては、環境庁が実施した平成5年度環境にやさしい企業行動調査によると、環境に関する企業方針や目標の達成時期等、環境に関する取組を企業内で定期的に点検(内部監査)していると回答した企業は、全体の27.8%を占め、今年度中に実施予定の企業8.1%と合わせ、合計で35.9%の企業がなんらかの環境監査を実施している(第2-3-2図)。また、環境担当役員等に対して、実施責任者からの報告を行うことになっている企業は、全体の65.2%であり、そのうち年一回以上定期的に報告している企業は34.2%であった(第2-3-3図)。
さらに、欧米の一部の先進的な企業においては、環境関連情報を積極的に開示し、消費者に情報提供を行う動きが広まりつつある。我が国では、環境庁が実施した平成5年度環境にやさしい企業行動調査によると、環境問題への取組状況のレポート等(環境報告書)については、「レポートを作成し、公表している」と回答した企業は6.3%で、「レポートは作成しているが、積極的に公表していない」と回答した企業が21.7%であり、「レポートの作成はしていない」と回答した企業が最も多く44.3%を占めていた(第2-3-4図)。環境情報の開示については、ただ公表されればいいというのではなく、それを受け取る消費者が正しく理解し、消費行動に反映させていくことが大切である。消費者が使用する製品の環境に与える影響を考慮して消費活動を行うことにより、新たな消費文化やライフスタイルが生まれ、また、企業の環境保全に向けた取組を促進することにつながるのである。
平成5年11月に成立した環境基本法においては、全ての者の自主的、積極的な行動が求められているところであるが、経済社会の重要な構成員である事業者も具体的な取組を着実に行っていくことが期待されている。企業活動に環境への配慮を組み込む努力を実効あるものとし、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な経済社会の構築を進めるために、事業者の今後の一層の取組が求められている。
(製品の環境影響評価)
今日の複雑化した環境問題に対応するためには、従来の公害問題の場合のように対象となる汚染物質を明確にし、その排出時に対策を実施するという手法に加え、製品のあり方自体を見直し、環境への負荷の少ないものにする努力を進めることが必要である。
製品のあり方という点について、リサイクルの促進という観点から、リサイクル法においては、事業者に対して、第1種指定(家電、自動車等)の設計に際して、製品のリサイクル促進のための部品材料や構造の工夫等について事前評価を求めており、材料の工夫(部品に再生資源としての利用が可能な材料を用いる)、構造の工夫(処理を容易にする)、分別のための工夫(分別を容易にする)、処理に係る安全性の確保(安全に処理できるようにする)といった面について、製品設計等における環境配慮が求められている。
また、これまでの環境負荷評価は、製品使用や廃棄に伴うCFCなどの特定物質の排出の有無や、製品の廃棄に伴う有害物質の排出の有無と処理・処分の容易性、使用後のリサイクルの材料面や製品分解性からみた容易性、再生資源など環境への負荷の低減に寄与する原材料の使用の有無など、ライフサイクルのあるプロセスだけを評価範囲としたものが多かった。
このため、使用、廃棄の段階での環境への負荷が少なくても、原料採取、製造、流通の各段階での環境への負荷が大きく、全体として環境への負荷の低減に寄与しない製品が生産されてしまう可能性がある。今日の環境問題は、我々の経済社会活動全般に起因するものであり、特定の物質の排出を防ぐなどの対症療法でなく、経済社会活動そのものを環境への負荷の少ないものに変革して行く必要があり、平成5年11月に制定された環境基本法においても第24条において、「環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進」を規定している。
こうした中、製品の全段階の様々な環境負荷を総合的に評価する手法が必要となってくる。その際、生産段階から消費、廃棄段階の全ての段階において製品が環境へ与える負荷を総合的に評価する手法がライフ・サイクル・アセスメント(LCA)である。これは製品等の原材料の採取、製造に加え、輸送、使用、廃棄の全過程における環境への影響を総合的に評価する手法である。
LCAは、近年、世界的に注目を集め、各地で研究が進められている。例えば、諸外国の例としては、スイス連邦内務省環境局がエネルギー消費、大気汚染、水質汚濁、廃棄物の項目について、包装材料のLCAの手法と環境負荷データベースを研究し、大手生協がこれらの手法とデータベースに基づき包装材料の見直しを行っている。また、フランスでは、飲料用のスチール罐を対象に、環境負荷をライフサイクル全体で把握することで負荷の高いプロセスを把握し、製品の改善ポイントを抽出したり、改善による環境負荷の低減効果を把握することを目的として、エネルギー消費量、資源消費量、廃棄物の排出量、大気汚染物質、水質汚濁物質についてLCAの手法を研究している。さらに、アメリカの環境毒物・化学学会(SETAC)では、LCAに関するワークショップの開催等を通じ、世界のLCA研究の連携を進めるための努力を行っている。
また、多国的な取組としては、国際標準化機構(ISO)において、国際標準化のための作業が進められており、我が国においても、ISOに加盟している日本工業標準調査会(JISC)において検討を行い、この作業に積極的に参加しているところである。
我が国の研究としては、(社)プラスチック処理促進協会が、平成3年度(1991年度)に「廃プラスチックの処理・再資源化に関する環境影響評価」を実施し、製品間のライフサイクル全体でのエネルギー消費量及び環境負荷について評価を行った。さらに、平成4年度には、この評価結果をもとに、素材毎の天然資源消費量、エネルギー消費量、用水量、大気汚染物質、固形廃棄物についての評価を行っている。環境庁では、平成4年度に、「環境への負荷の評価に関する予備的検討」を実施し、諸外国及び我が国における環境への負荷の低減に向けた製品の開発・評価への取組及びLCAの取組に関する基礎的調査を実施し、製品に関する環境負荷評価、特に、製品のライフサイクルの環境負荷評価手法及びLCAの普及に向けての今後の課題の検討を行っている(第2-3-1表、第2-3-5図)。また、平成6年には、有識者及び企業関係者等によるエコマテリアル研究会より、我が国のLCA研究の現状と課題を詳細にまとめた報告書が公表されている。
このような、LCAの手法については、前述のとおりISOにおいてもその国際標準化の作業が進められているところであり、今後、更に手法が明確になるにつれて、その具体的な事業活動への適用が普及するものと期待される。
(海外進出企業の活動状況)
近年、我が国の経済規模の拡大等に伴い、多数の企業が海外に進出し事業活動を行っている。我が国の企業は、かつての激甚な産業公害を克服した過程において、産業公害を防止しつつ経済発展を成し遂げた経験を有しており、急速な経済発展に伴う産業公害の激化に悩んでいる開発途上国では、現地に進出している日本企業の行動に大きな関心を持っている。また、地球環境問題に対する人々の認識が高まりつつある中、我が国の国民も海外に進出している日系企業の環境保全に向けた行動に大きな関心と期待を寄せている。海外進出企業の環境配慮のあり方については、通産省産業構造審議会より、「海外事業展開に当たって期待される企業行動」の中で、海外に進出した日系企業に望まれる環境配慮のガイドラインが示されているところである。
こうした中、環境庁では、在外日系企業の環境保全への取組に関して実態を把握するべく、平成4年度(1992年度)にタイとマレーシアの2カ国に進出している日系企業を対象にアンケート調査を行ったが、平成5年度(1993年度)は引続き中国に進出している日系企業を対象にアンケート調査を行った(対象企業数363社、回収率は13.5%)。調査結果(中間報告)は以下のとおりである。
まず、立地段階での環境配慮については、回答企業全体の65.3%の企業が立地に当たり環境上の問題は生じなかったと回答しており、自主的な調査を含め立地に際し何らかの環境アセスメントを実施したと回答した企業は40.8%であった(第2-3-6図)。環境アセスメントの結果、計画や設計の変更、対策の強化を行った企業は環境アセスメントを実施した企業の50%であった。なお、環境アセスメントを実施しなかったと回答した企業は42.9%、無回答が8.2%あるが、元来環境への影響が乏しい業態で進出している企業も含まれている点に注意を要する。
次に、操業上の環境対策については、実施している環境対策の目標としては、現地国の基準に合わせた企業が46.9%であり、現地国基準以上の自社基準が12.2%、日本国内の水準が12.2%などであった(第2-3-7図)。また、公害防止管理者等の公害対策組織ないしは環境保全の責任者を置いている企業は44.9%であった。原材料等の買付けに当たっての環境面での配慮としては、無回答の企業が30.6%であったが、回答を得られた企業のうち、環境問題にできるだけ配慮して買付けを行っていると答えた企業はなく、公害や自然破壊を行うような企業等からは買付けないと回答した企業は8.8%であった。環境に配慮した原材料の買付けは困難と回答した企業が8.8%あり、また、特に環境に配慮していないと回答した企業は61.8%であった。環境に配慮できない、あるいは配慮していない理由としては、環境に配慮する必要がないからが最も多かったが、環境に配慮した原材料の入手が不可能であることを挙げている企業もあった。なお、途上国の外資導入による環境保全面でのメリットについては、「途上国の能力等を高めるために相当役だっている」と回答した企業が22.4%、「まあまあ役だっている」が10.2%、「今後役だっていくと思う」が57.1%であった。一方、途上国が日本の進んだ環境保全技術の大きな市場となる可能性があるという点については、「大いに期待できる」と回答した企業が44.9%、「市場としては期待できない」が12.2%であり、日系企業の現地への進出は双方にメリットのあるものだと考えている企業が多いものと思われる。
環境対策を進める上での課題については以下のとおりである。まず、環境保全に関する現地政府との関係については、回答企業全体の約8割の企業が「現地政府の環境規制、指導を巡るトラブルはなかった」と回答しているが、同時に24.5%の企業が「いつかトラブルに巻き込まれるのではないか」との懸念を抱いていることがわかった。また、他の先進国からの進出企業の環境への取組との比較については、「他の先進国の企業の方が円滑である」と回答した企業はなく、「当社と同程度である」と「当社の方が円滑である」を合わせて26.5%であった。環境対策関係の支出の負担感については、「現在は軽いが将来は心配である」と回答した企業が49.0%であり、今後規制が厳しくなった際等に負担が増すことの懸念が見られる。合弁先との関係で環境上の問題で意見の違いが生じた経験については、「ある」と回答した企業は8.2%であり、その原因としては、「環境問題に関する意識の違い」などが挙げられていた。
以上のとおり、今回の調査結果から、在外日系企業の環境保全に向けての取組は、現状の取組状況についてはある程度の自信を持っており、また、合弁先との関係も順調であるが、今後の現地政府の取組への対応については、環境対策の負担が重くなることなどの点で若干の不安を持っているものと考えられる。海外進出企業の環境対策の一層の充実のために役立つ方策についての質問に対しては、現地政府から進出企業への支援策の強化、現地国民の環境保全意識の高まり、廃棄物処理業者等の現地の環境関係業者の能力向上等、現地国側の方策を求める回答が、回答の約8割と多数を占めていた。
(社会貢献)
企業が求められている役割の一つとして、社会貢献があげられる。企業には、社会を形成する一員として、国民一人ひとりに求められるのと同じように社会への貢献が求められている。企業においても、社会の重要な一部分を担うものとして、応分の社会的責任を果たすべきであるという認識は広まりつつある。例えば、前述の経団連地球環境憲章では、社会との共生として、地域環境の保全等の活動に対し、地域社会の一員として積極的に参画するとともに、従業員の自主的な参加を支援するとしている。環境庁の実施した平成5年度環境にやさしい企業行動調査によれば、回答企業の67.6%が環境面での社会貢献活動を実施していると回答しているが、社会貢献活動の実施について具体的な目標を設定している企業は23.1%であった(第2-3-8図)。国民や企業などあらゆる主体が協力して環境への負荷の少ない持続可能な経済社会を構築していくことが求められている中、企業のより積極的な社会貢献活動が求められているところである。
(環境保全経費)
企業が効率的に環境への配慮を事業活動に組み込んで行くためには、環境保全にかかる経費の把握は重要である。正確な費用の把握は、効率的な対策の選択に不可欠であり、さらに、環境保全コストの削減に資するものでもある。個々の企業は収益を重視し、経費に敏感で環境対策に係る過重な経費負担を避ける傾向があると一般的に言われており、企業自身でも現下の不況下では環境対策へ投資する余力は無いという主張が見られる。しかし、実態面では、環境庁の調査(前述の平成5年度環境にやさしい企業行動調査)によれば、環境関連の費用や投資額を他と区別して集計している企業は回答企業558社のうち29.7%であり、また、集計している内容は公害防止投資関係及び廃棄物処理費が中心であって経費把握の努力は現状では限られたものであった。この背景としては、特に、最近、企業の収益改善に資するものとして欧米で注目を集めている生産工程の低負荷化などを含めた幅広い意味での環境保全経費については、集計の範囲や手法が企業にとっては明確ではないということがあると考えられる。前述の環境庁調査では、環境保全のための費用集計に当たって、「一定のルールを定めて各社共通の物差しを作る」ことについて意見を聞いているが、回答企業全体の合計85%が良いこととする一方、このうち8割は「企業の実態に合わせ各企業が自主的に判断するべき」と考えており、企業の活動実態の複雑さが経費把握を困難にさせ、意欲をそいでいることがうかがわれる。また、自社の環境保全経費を積極的に開示し、環境への取組を国民にアピールするような諸外国で見られる動きについては、「大いに結構であり、日本の企業も取り入れるべきだ」とする回答が、全体の36.7%と高い一方、「各企業に公平なルールができるまでは自粛すべきだ」とする回答もほぼ同じ率の34.9%あった(第2-3-9図)。この調査結果からすると、現在、企業は、自社の取組状況に自信を持っており情報の公開にも積極的な企業と、環境保全経費の額から取組状況について画一的に批判されるのは好ましくないと考えている企業の2つにわけることができる。もとより、企業の規模や事業内容は千差万別であり、環境保全経費の大小からその企業の環境保全への取組状況が類推されるものではない。しかし、環境保全経費を明確に把握していてこそ、社内的にも、社会全体としても、費用効果的な環境対策が実行できるのである。しかし、費用把握の現状から見ると、多くの企業の対策は、未だ他律的であって、自主的な判断に基づくものとはなっていないとも言えよう。環境保全経費については、国際的に検討されている環境資源勘定の重要な一項目に位置づけられていることもあり、その把握と活用に向けた一層の努力が期待されている。
以上のとおり、企業が現在取り組んでいる課題、今後取り組むべき課題は多い。こうした取組の状況に対し企業の自己評価はどうなっているだろうか。前述の(社)社会経済生産性本部の調査によると、地球規模の環境問題への取組の自己評価について、「積極的に取り組んでいる」と回答した企業は15.6%、「まあ積極的に取り組んでいる」と回答した企業が42.1%で、この2者を積極派とすると、積極派が6割を超えていたが、一方、「あまり積極的に取り組んでいない」が30.1%、「取り組んでいない」が4.3%あった。「あまり積極的に取り組んでいない」と「取り組んでいない」を合わせて消極派とすると、消極派は4割弱であった(第2-3-10図)。これを、資本金別に見てみると、資本金が100億円以上の大企業では積極派が7割を超えているのに対し、資本金が100億円未満では逆に消極派が多くなっている。この調査では、回答企業のうち資本金が100億円未満の企業が53%と過半数を占めており、この調査結果は、環境問題の取組への自己評価で消極派が過半数を占めていることを示している(第2-3-11図)。また、環境庁が実施した平成5年度環境にやさしい企業行動調査によると、具体的な目標を設定している企業は全体の39.8%で、平成5年度中に設定する予定の企業8.2%と合わせ48.0%であったが、売上規模別に見ると、売上高が低い企業ほど設定している割合は低かった(第2-3-12図)。大阪府が平成4年度に実施したアンケート調査(対象は大阪工業会所属の企業から無作為に抽出した1000社、回収率は49.4%)によると、環境保全に対する専門組織又は対応部局を設置し、担当者を配置している企業は、回答企業全体の20.8%であった(第2-3-13図)。一方環境庁の実施した平成5年度環境にやさしい企業行動調査によると、環境問題担当組織を既に設置している企業は回答企業の63.3%であり、平成5年度中に設置予定2.0%と合わせ65.3%となっていた(第2-3-14図)。大阪府の調査でも、環境庁の調査でも、回答企業の業種による偏りはなく、この調査結果の差異は、環境庁の調査が上場企業を対象としたものであり、回答企業のうち従業員数が1001人以上の企業が73.2%と大企業からの回答が多かったのに対し、大阪府の調査では、回答企業のうち従業員数が1000人以上の企業が22.7%であり、環境庁の調査に比べ規模の小さい企業の回答が多かったためと考えられる。こうした調査から、企業の環境保全対策は、大企業では進みつつあるが、企業の規模が小さくなるほど消極的になっていることが示唆される。我々の経済社会を環境への負荷の少ない持続的発展が可能な経済社会に変革して行くためには、一部の大企業だけでなく、製品の生産、流通、廃棄にかかわるあらゆる企業が積極的に取り組んでいく必要がある。我が国の中小企業は、例えば、従業員数は全産業の約8割を占め、製造業の出荷額では約5割、小売業の年間販売額は8割弱を占めるなど(第2-3-15図)、日本経済において大きな地位を占めており、中小企業の動向が与える影響は大きなものがある。これは、環境保全の観点からも例外ではない。しかし、環境に配慮した事業活動への取組については、上述のとおり、大企業に比べ中小企業の取組はやや遅れている面があると言え、環境への負荷の少ない持続可能な経済社会の構築に向けて、政府による様々な支援策を活用しつつ、大企業はもちろん中小企業においても積極的に取組を進めていく必要があると言える。
以上、本項では、今後企業においてさらなる自主的な取組が求められている点について考察を加えてきたが、こうした取組は個々の企業にとって決して負担の増加につながることばかりではないと考えられる。例えば、米国では、近年、生産工程を低負荷型のものに変える取組が積極的に進められているが、米国環境保護庁の資料では、事例研究として、こうした取組が個々の企業へ与える経済的な効果について、低環境負荷型の技術を専門とする公益的なシンクタンクによる、様々な企業の取組についての横断的な分析を紹介している。この分析では、中身や規模を異にする全米27の化学プラントを代表例として選び、そこで、産業活動をその根本から低負荷型のものに変えていくことに向けて最近始められた181の取組事例を分析している。この結果によれば、そうした取組の3分の2は6ヶ月以下の準備期間で実行できたものであり、4分の1の事例では取組に資本費用を要しなかったという。資本投下を要したものも含め、全体の3分の2の事例では、投下費用は6ヶ月で回収された。さらに、これらのうち記録のある62の取組の合計の利益(従来あった費用の節約額など)は、年額ベースで21百万ドル(邦貨換算約22億円)に達したという。
一般に何らかの取組を行う場合、比較的に費用対効果の優れた対策から順次実施していくのが通例であり、したがって、初期の対策は経済的に引き合うものである傾向がある。この点を割り引いて考えても、以上の事例の優れた経済性は際立っている。環境負荷をそもそも生まないことに向けた取組がこのように経済的に引き合うことが多いのは、次のような理由からだとされている。すなわち、処理に費用の掛かる廃物の量そのものが減少すること(事例研究では、5割から8割の削減が行われているとのこと)、第2に、これに伴い、労働衛生も向上し、近隣への迷惑や危険も減り、これらに付随して従来発生していた諸費用が減ること、第3に、新たに工程に投入される原材料も減って、原料費が節約されること、といった様々な経済的利点があるからであるという。さらに、長期的に見れば、費用が節約される一方で、環境保全的な企業、環境保全的な製品が消費者に支持され、売上が高まることも期待できる。
この米国での事例研究に見るように、環境対策は、個々の企業のベースでみても、単なる負担ばかりではなく、環境対策の実施が無駄を省く契機となることにより、また、廃棄物処理費用や原材料購入費の節約につながることにより、企業の収益の改善に寄与する場合も多々あるといえる。しかし、環境対策の実施が個別の企業として合理的なものであったとしても、現実には、多くの企業で実施されてはいない。そこには、本節で見てきたように、個々の企業の中に環境対策に対し知らず知らずのうちに消極的になってしまう事情があるほか、企業の取組を促進させる消費者の支援、社会的環境などが現状では必ずしもうまく整備されていないということもある。環境への負荷の少ない持続可能な経済社会の構築に向けて、今後、こうした障害が克服される必要があるとともに、企業としても自主的な努力を積極的に推進していくことが望まれている。