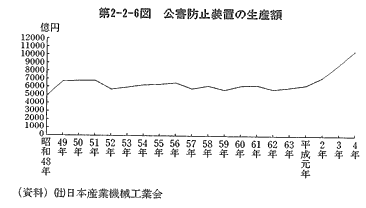
2 エコビジネス(環境関連産業)
今日の環境問題は、規模の点において、オゾン層の破壊や熱帯林の減少など地球的規模をもち、その対象となる問題も、従来の大気汚染、水質汚濁、騒音といった問題のみならず、地球温暖化問題や廃棄物問題などへ裾野が広がってきている。さらに、前項で見たとおり、産業構造が環境保全型に変革していく中で、環境コンサルタントや金融サービスなどのソフトの分野での取組も拡大しつつある。また、国民の環境へのニーズも、従来の公害の防止といったマイナスの影響の抑制・排除から、快適な環境(アメニティ)の維持、自然とのふれあいの確保といったより積極的な環境への働きかけへと変化しつつある。我が国では、かつての産業公害を克服する過程で、大気汚染防止装置、排水浄化装置などの公害防止装置を中心に公害防止技術の開発が進み、今日、公害防止設備の生産額は1兆1124億円の市場規模を持つに至っている(第2-2-6図)。産業公害の激化に対応して、企業が公害防止のために新たに投資した資金は、その企業にとっては費用であったが、公害防止装置産業の側からみれば新たな需要であり、新規産業分野の形成につながったのである。これは、今日の環境問題でも同様であり、環境問題の質的な変化、空間的な拡大と、環境保全ニーズの多様化は、新たな需要を満たす産業の成長を促すことにつながる。ここでは、新たな産業として成長しつつあるエコビジネスについて、その概況を見てみよう。
(1) エコビジネスの動向
エコビジネスは、環境への負荷の軽減に資する商品・サービスを提供したり、様々な社会経済活動を環境保全型のものに変革させるうえで役立つ技術やシステム等を提供するようなビジネスなどを中心とする幅広い概念であり、あらゆる産業分野にまたがる横断的な商品・サービスを提供する産業分野と言うことができるであろう。環境問題の質的な変化、空間的な範囲の拡大や環境保全ニーズの多様化に伴う対象分野の拡大により、エコビジネスもその範囲と規模を拡大しつつある。エコビジネスについての定義や分類方法などは未だ確立されていないが、ここでは、エコビジネスを便宜的に?環境負荷を低減させる装置、?環境への負荷の少ない製品、?環境保全に資するサービスの提供、?社会基盤の整備等の4つの分野に分類してみた(第2-2-1表)。
? 環境負荷を低減させる装置
環境負荷を低減させる装置には、主として物を生産する際に排出されるSOxやNOxなどの環境への負荷を低減させる公害防止装置及び技術、二酸化炭素固定化・処分技術、コージェネレーションなどのようにエネルギー効率の向上に資する省エネ技術、水力発電装置や風力発電装置など再生利用可能な自然エネルギーによる発電システムなどがある。
我が国の排煙脱硫・脱硝装置などの大気汚染防止装置及び技術は、厳しい排ガス規制に対応してきた経験から世界でも最高水準との評価を得ている。排煙脱硫・脱硝技術は酸性雨対策としても重要であり、日本に比べ酸性雨の被害が深刻な欧米諸国や、工業化の進展に伴い化石エネルギーの使用量が増えている中国をはじめとする中進国・開発途上国への技術輸出が進められている。
温室効果ガスの代表的物質である二酸化炭素については、製造工程で排出した二酸化炭素を固定化・分解する技術の開発が進められている。二酸化炭素を分離する技術としては、アミン液を用いた化学吸収法や高分子膜などを用いた膜分離法などの研究が進められており、低コスト化に向け積極的な取り組みがなされている。また、固定化・処分技術については、藻を利用して光合成により固定化しようとする技術やメタノールを合成する技術などが研究されている。
オゾン層保護の観点から国際的に全廃に向けて取組が進められている特定フロン関連の技術としては、自動車や冷蔵庫などの冷媒用CFCや半導体の洗浄用CFCの回収・再利用技術や代替フロンへの切り替えが実用化されている。さらに、純水を利用した洗浄装置が開発されており、CFCに代替する洗浄技術の一つとして普及しつつある。
エネルギー効率の向上に資する省エネ装置及び技術としては、燃料電池やコージェネレーションシステム、スーパーヒートポンプなどがある。燃料電池は、石油、天然ガス、メタノールなどの原料や燃料から水素を作り出し、これを空気中の酸素などと反応させて電力を得るシステムである。従来の化石燃料の燃焼による発電システムに比べ、NOx、SOxなどの大気汚染物質をほとんど排出しないなどの利点があり、現在実用化に向け、リン酸型、溶融炭酸塩型、固体電解質型、固体高分子型の4方式の研究開発が進められている。特に、リン酸型は技術面では実用レベルに達しており、低コスト化へ向けた取組が積極的に進められている。
コージェネレーションシステムは、熱電併給システムとも呼ばれており、エンジンやガスタービン、燃料電池などによって発電をするのと同時に、その排熱を給湯や暖房に利用するシステムのことで、エネルギー効率の大幅な向上と二酸化炭素排出削減効果がある。コージェネレーションシステムは、電力供給に関わる一連の制度面の整備、小型で経済性の高いシステムの開発、燃料電池などの要素技術の開発などを背景に、近年急速に普及しつつあるが、技術面でも高効率化に積極的に取り組まれており、今後とも一層の普及が見込まれている。
ヒートポンプは、そのままでは利用しにくい低い温度の熱を、圧力の変化や化学反応、吸収などの方法により、有効に利用できる高い温度の熱に変換する技術である。排熱利用であるため大気汚染物質の排出がない、投入エネルギーよりも大きなエネルギーを得ることができる、冷房にも暖房にも利用できることなどの利点により、近年急速に普及しつつある。家庭用や自動車用のエアコンであれば現状の技術水準で十分であるが、最高出力温度が120度程度であり、産業用としては高温ヒートポンプの開発と効率の向上が必要である。そこでスーパーヒートポンプとして、従来の2倍程度の高い効率をもつ高効率型と最高出力温度が300度近い高温出力型の2種類が開発されつつある。
無尽蔵な自然エネルギーによる発電システムとしては、風力発電システム、水力発電システム、地熱発電システム、太陽光などの新エネルギーによる発電システムがあり、出力の安定化や制御方法、コスト削減などの課題に向け積極的な研究が続けられている。
このほか、廃棄物処理が大きな問題となっている中で、廃棄物を有効利用するごみ発電システムも開発、実用化されており、清掃工場などに設置されつつある。また、アルミやガラスなどの再利用可能な資源を有効活用するための再資源化装置も普及しつつある。
? 環境への負荷の少ない製品
この分野には、まず現在流通している商品を再利用することにより省資源につながり、かつ廃棄物の減量化に資するリサイクル製品や、現在一般的に流通している商品に代替されることで、環境への負荷を軽減するような商品などがある。また、家庭などで利用することにより省エネにつながる太陽熱や太陽光利用機器もある。こうした商品の例としては、エコマーク商品のようにエコラベルが付与されて、他の商品と差別化が図られているものがある。
廃棄物の増大が社会的な問題となっている中、有用な資源を廃棄物から取り出し、再生資源として利用するリサイクル技術の開発も積極的に行われている。アルミ罐やスチール罐、ガラス屑(カレット)、古紙などのリサイクル技術は確立しており、回収率の向上と需要の開拓などによる再生資源価格の安定が課題となっている。プラスチックのリサイクルに関しては、もともと、素材の多様さ、製品の複雑化・合成化の進展、安価な材料費と再生コストの高さ、再生品の市場性・ニーズの問題などにより、廃プラスチックのリサイクルは非常に困難であるとされていた。しかし、近年、廃プラスチックの量の多さと処理の困難さが問題となり、リサイクルによる再利用の必要性が高まりつつある。こうした中、廃プラスチックの再利用技術が積極的に研究されている。特に、食品用のトレイやポリ袋、ペットボトルなどの容器・包装材については、回収ルートを確立し、洗剤容器や文具、プランター、再生トレイなどの二次製品として再利用する研究が進められている。一方で、プラスチックの回収効率は悪く、回収やリサイクルにかかるエネルギーを考えると、熱エネルギー源として再利用した方が効率的であるとする考え方もある。こうした観点から、廃プラスチックの油化、燃料化による焼却熱利用の研究も進められており、廃プラスチックからガソリンやナフサを生成する技術が開発されている。
現在のガソリン自動車やディーゼル自動車に比べ環境への負荷の少ない電気自動車やメタノール車、天然ガス自動車、ハイブリッド自動車などの低公害車の研究開発も進められている。
電気自動車は、エンジンの代わりにバッテリー(蓄電池)に蓄えた電気でモーターを回転させて走る自動車であり、排出ガスがなく、ガソリン車に比べエネルギー効率が高いなどの特徴がある。電気自動車については、蓄電池の性能向上、車体の軽量化などを図り、実用上問題のない十分な走行距離等の確保が目指されている。さらに、広範な普及が進むためには、生産コストの低下、維持費用の軽減などの経済性の向上も必要となっている。
メタノール車は、ガソリンや軽油の代わりにアルコールの一種であるメタノールを燃料とする自動車であり、ディーゼル車に比べてNOx排出量が少なく、黒煙も発生しないなど大気汚染物質の排出が少ないという特徴がある。こうしたことから、積極的な技術開発が進められ、一部では実用されているが、更に一層のNOxの低減と燃費の向上、部品の耐久性の向上、エンジン始動時に発生する有害物質であるホルムアルデヒドの一層の低減などの改善が図られている。
天然ガス自動車は、圧縮した天然ガスを燃料として走る車で、ガソリンなどに比べて燃焼時の二酸化炭素の発生量が少ない、NOxの排出量が少ない、黒煙を排出しないなどの特徴がある。今後、ガス容器の軽量化や生産コストの低減、ガス充填スタンドの整備を図ることにより、広範な普及を目指す必要がある。
また、ハイブリッド自動車は、通常走行時はエンジンで走行し、停止・発進の際に余剰動力を発電機や油圧で回収・利用する自動車で、省エネルギー効果があるほか、NOxや黒煙の排出も低減されるという特徴がある。今後、普及を図る上での開発課題として、ハイブリッドシステムのコンパクト化等が挙げられる。
こうした低公害車については、ソーラーカーや水素自動車などの次世代自動車の開発も期待されている。
現在流通している商品に比べ環境への負荷の少ない商品の開発も進められている。例えば、廃棄されても土に還元せず長期間環境へ負荷を与えるプラスチックの代わりに、通常の使用段階では分解されずプラスチックの性質を保つが、使用後に埋め立てられると自然に生分解されて土に還元する生分解性プラスチックが研究されている。生分解性プラスチックとして研究されているのは、植物などの天然高分子を材料としたプラスチック、微生物によって作られ微生物によって分解されるプラスチック、でんぷんなどを混ぜて分解しやすくしたプラスチックなどであるが、いずれも製造コストが高いという課題が残されている。生分解性プラスチックは実用化に成功すれば市場規模は大きいと見込まれており、低コスト化に向けた取組が積極的に進められている。
有機スズ化合物は防除剤として優れた性質を持っているため、広く海中用塗料として用いられていたが、その毒性が問題となり、亜酸化銅系などの非スズ系の塗料が開発され、普及しつつある。
この他、洗剤や紙製品など様々な商品において、既存の商品と同等の性質や能力を保ちつつ、製造工程や使用、廃棄段階での環境への負荷の少ない商品が開発されている。こうした商品の一例としてエコマーク商品がある。エコマークは既存の商品等に比べ相対的に環境への負荷の少ない商品に付与されるマークで、消費者はエコマークの有無により購入の際の判断材料とすることができる。エコマーク事業は、(財)日本環境協会により平成元年より実施されているが、認定商品数は年々増加しており、平成5年12月末現在で、57品目2599商品が認定されている(第2-2-7図)。
省エネ対策という点では、家庭での省エネの促進も重要である。この観点からは、住宅の断熱化技術の向上、太陽熱・太陽光を利用するソーラーシステムの開発、省エネ家電の開発などが進められている。太陽熱・太陽光を利用するソーラーシステムについては、技術的には実用化されているが、高いコストが普及のネックとなっている。
? 環境保全に資するサービスの提供
環境保全への人々の関心が高まる中、各種の開発事業の実施に際し、その事業による環境汚染を未然に防止するために行われる環境影響評価(環境アセスメント)の実施件数は、近年増加してきている(第2-2-8図)。これは、地方公共団体における環境アセスメントの制度化の進展、各種開発事業の実施件数の動向等に左右されているものと考えられる。地方公共団体では、ここ数年環境アセスメント制度の新設、改正が相次いでおり、また、その対象事業も、政府が定めた「環境影響評価実施要綱」では国が関与する大規模な事業を対象としているが、地方公共団体では地域の実情等に応じてより小規模な事業やゴルフ場等のリゾート施設なども対象としている。このような地方公共団体の取組等を背景として、環境アセスメントは今後とも広範に実施されるものと考えられ、環境アセスメントに係る調査、予測及び評価を開発事業者から請負って行う事業は大きな成長が予測される。
廃棄物回収処理業では、従来事業規模の小さい中小・零細企業が中心となっていたが、近年、廃棄物問題への認識が高まる中、廃棄物処理や再資源化の新たな技術も開発され、廃棄物処理システムの計画、設置、運営を手掛け、地方公共団体と共同でリサイクル主体のごみ処理一貫工場の設置を推進するような総合的な廃棄物処理事業者も現れている。米国では、年商1兆円、従業員数6万2千人余りという大規模な廃棄物処理会社も誕生しており、我が国においても大資本の導入が進むものと見られる。
米国では、スーパーファンド法などにより、土壤汚染に対して積極的に対策がとられており、規制の強化に伴って土壤汚染の浄化ビジネスが急速に拡大しつつある。近年、我が国においても、特に市街地などの土壤が半導体の洗浄やドライクリーニングなどで用いられる有機塩素化合物等による汚染が判明する事例が増加している。こうした事態に対応し、主として米国などの汚染土壤浄化技術を導入しつつ総合的な土壤汚染対策事業を試みる企業が増えてきている。現段階では、重点はコンサルティングに置かれており、汚染浄化に先立った現状把握・調査事業が進められつつある。さらに、海外の先進的な浄化技術と組み合わせることにより、調査から浄化までの一貫体制を確立した企業も誕生しつつある。また、汚染浄化技術としては、低温加熱処理法、真空ポンプを使った汚染物質の抽出法、バクテリアで分解させる生物処理法、高電圧の電流により汚染土壤をガラス化する溶融固化法などが研究されている。
様々な産業分野での環境保全に向けた取組が進展するのに伴い、省エネやリサイクルの動向、環境監査のノウハウ、土壤や地下水の浄化技術などの新事業に関する情報を提供するサービスが見られつつある。環境監査については、企業の環境保全に向けた取組が、理念の確立から実行の段階に移行するにつれ、企業活動を環境管理の面からチェックするものとしてニーズが高まりつつある。こうしたニーズに対応して、環境保全に先進的に取り組んできた企業や、欧米の実例に詳しい環境コンサルタントなどが、環境監査等のノウハウを提供しようとする動きも現れており、今後の成長分野として大いに期待されているところである。
環境保全意識の高まりを受けて、旅行を通じて環境保護や自然保護に対する理解を深めようとするツアーも、近年、増加しつつある。このようなツアーは、参加者に環境問題についての認識を高めてもらうことを第一においており、専門家が同行して講義を行ったり、実際に現地でのボランティア活動に加わったりするものである。最近の例としては、環境関連の国際会議に参加できるツアーや、出発前にあらかじめ現地の自然環境や環境問題について講義を受けることのできる自然志向ツアーなどがあり、また、熱帯諸国で植林を実施するツアーなどもある。
環境問題への取組の一つとして注目を浴びている環境教育も、ビジネスマンを対象とした通信教育や、企業において環境学習室を設けるなどビジネスに取り込まれている例もある。
消費者の環境保全意識の高まりを背景として、環境関連の金融商品も増大・多様化している。具体例を挙げると、第一に、公益信託は、従来、教育助成、国際研究協力への助成を主としてきたが、近年の環境問題への関心の高まりから、都市・自然環境の整備・保全を目的とした公益信託の取扱いが増えつつある。第二に、環境保全活動を実施するNGO等に利子・配当の一部などの資金を提供するサービスを組み込んだ金融商品も多数誕生している。こうしたボランティア型金融商品は、定期預金、普通預金等の預金口座を利用したものから、自然環境保全関係の社会貢献型信託のように信託口座を利用したものまで多岐にわたっている。また、カード会社でもカードの利用額の一定割合相当額をカード会社自らが環境保全団体へ寄付するサービスを付帯したカードが誕生している。第三に、保険分野においても環境汚染に起因して被保険者が負担した損害を担保する環境汚染賠償責任保険が誕生している。このように、環境関連の金融商品は金融サービスにおいて一分野を形成しつつある。
? 社会基盤の整備等
この分野には、公共部門において実施されている下水道整備事業、公園整備事業、廃棄物処理施設整備事業、環境への負荷の低減に資する鉄道の整備などの社会資本の整備、及び民間における地域冷暖房システムの導入や排水の再処理水や雨水などを利用する施設の設置、省エネ型ビルの建設など、直接生産工程や商品の環境負荷の低減に資するものではないが、省エネや省資源により環境保全効果のある設備や装置の設置などが含まれる。
近年、大量生産、大量消費、大量廃棄型の経済社会構造が定着する中、廃棄物は増大の一途をたどっており、廃プラスチックの増加に対応して高い燃焼温度に耐え得る焼却施設の整備、前述のごみ発電システムの併設など、技術の進歩に応じて廃棄物処理施設の整備が進められている。
我が国の下水道普及率は平成4年度(1992年度)で47%と、諸外国に比べ整備が遅れている状況にある(第2-2-2表)。下水道の整備は、生活排水による河川などへの水質汚濁負荷削減に資するものであり、生活排水による河川や湖沼、閉鎖性水域の有機汚濁が大きな問題の一つとなっている中、今後とも一層推進される必要がある。
近年、身近な自然が失われていく中、国民の自然とのふれあいに対するニーズが高まりつつあり、自然とのふれあいの場の確保の重要性が注目されている。自然とのふれあいの場については、優れた自然環境を有する国立・国定公園等における園地、自然観察路、野営場、公衆トイレなどの基幹施設の整備や、「長距離自然歩道」や「環境と文化のむら、ふるさといきものふれあいの里」などの身近な自然とふれあう施設等の整備が進められており、今後一層の整備の充実が期待される。
また、都市公園の整備についても、人口一人当りの面積では、例えば東京23区でみると2.6?/人であるのに対し、イギリスのロンドンでは25.6?/人、米国のニューヨークで23.0m
2
/人と、諸外国に比べ整備が遅れている(第2-2-2表)。都市公園は、都市における貴重な緑地であり、潤いのある都市景観の形成、ヒートアイランド現象の緩和、野鳥や小動物等の生息地、住民の身近な自然とのふれあいの場などの重要な役割を担っている。人々の間で自然とのふれあいの場の確保を求めるニーズが強い中、都市における身近な自然とのふれあいの場の確保は重要であり、都市公園の整備は今後とも積極的に推進されるべき施策といえる。
道路事業に際し、自然環境との調和や自然の再生を図るための構造・工法を取り込んだエコロードの整備も進められている。
さらに、河川・港湾等において、親しみがあり、やすらげる水辺環境を整備することは、レクリエーション活動や自然観察など身近に自然とふれあうことのできる場の提供につながり、生活に潤いを与えるものである。こうした観点から、親水公園や散策路の整備などの水域環境整備事業は一層推進されることとなろう。さらに、河川・港湾整備事業に際し、できるだけ多くの自然を残そうとする多自然型工法の研究も行われている。
森林は、人々にやすらぎを与え、自然とふれあう場を提供し、良質な水を安定的に供給する機能を有するほか、二酸化炭素を吸収・固定するなど重要な役割を担っている。さらに、道路や工場付近に樹木が植えられることにより、緩衝地帯としての役割も果たすこととなる。こうした観点から、森林の多面的機能を十全に発揮させるための治山事業、造林事業等による適正な森林整備、沿道緑化事業などが積極的に進められている。民間部門においても、特に都市部において残された貴重なスペースを有効に活用するという観点から、ビルの屋上部分を緑化するという取組が見られる。この背景には、軽量な土壤の開発や緑化防水システムなどの技術開発がある。都市部における緑の増加は、ヒートアイランド現象の防止や大気汚染の緩和に効果があると考えられており、今後一層進められていくものと思われる。
さらに、民間部門において、環境への負荷の少ない都市構造への取組の一環として、設計当初から省エネの観点を組み込んだビルの建設やエネルギーの有効活用のために地域冷暖房システムを導入したり、資源の有効利用として下水・産業排水の再生水や雨水などの雑用水を、生活用水の中で低水質でもよい用途(トイレ用水や散水などの雑用系用途)に使用するシステムを取り入れたりする事例が見られる。舗装地の多い都市部では、雨が大量に排水溝に流れ込み、河川が急激に増水する場合が見られるが、透水性舗装をはじめとする雨水浸透施設の設置により、こうした急激な増水を防ぐとともに、地下水のかん養に効果がある。
こうした環境への負荷の少ない都市構造への取組は今後とも様々な技術開発が進んで行くであろうと予想される。
以上のとおり、新たな産業分野としてのエコビジネスについては、様々なビジネスや事業が見られるが、既に実施されているビジネスや実用化されている技術があり、また数年後には実用化されると考えられる技術もある。こうしたエコビジネスについては、今後、大きく成長するであろうと予測されており、例えば米国では、1993年(平成5年)11月に環境技術輸出戦略を発表しているが、その中で、環境技術市場は大きく成長する可能性を秘めており、世界の環境技術の市場は現在は2000億ドルから3000億ドル(約22兆円から約33兆円)であるが、2000年(平成12年)までには6000億ドル(約66兆円)に成長するであろうと予測している。
我が国のエコビジネス市場については、様々な推計がなされているが、例えばOECDの分析(1992年)によれば、1990年から2000年までの年平均成長率は6.7%と試算している。環境庁の試算では、?環境負荷を低減させる装置等、?環境への負荷の少ない製品、?環境保全に資するサービスの提供、?社会基盤整備等の4分野合計で、2000年までの10年間の年平均成長率は約8%、2000年から2010年の10年間の年平均成長率は約7.8%になるであろうと推計されている。
なお、環境庁の試算によれば、上記4分野において、定量的に把握できたエコビジネスの1990年(平成2年)の時点における市場規模は約6兆円となっている。
こうした数値はあくまで推計であるが、今日の企業や消費者の環境保全への意識の高まりを背景として産業活動の環境保全型への変革は活発化しており、エコビジネスに対する需要は高まりつつある。かつて、我が国において自動車による大気汚染防止のニーズが高まり、官民を挙げて取り組んだ結果、日本製の自動車が公害を克服した上で、世界で圧倒的な競争力を持つことができた経緯については、平成3年度の本報告書で分析しているが、エコビジネスという新しい産業分野が、今後成長していくためには、企業による継続的な環境投資や技術開発などの積極的な取組と政府による適切な支援が必要であり、さらに、消費者においても環境に配慮した消費行動を取ることにより企業が事業活動に環境への配慮を組み込むことを促進させる必要がある。各主体が積極的に協力して取り組むことによってエコビジネスの成長が促されるが、エコビジネスの成長は産業界の環境保全型産業活動への変革を促進し、環境負荷の少ない持続的発展が可能な経済社会の構築につながっていくのである。