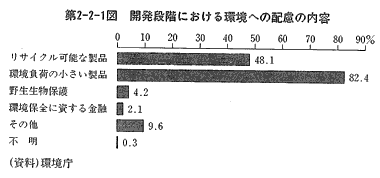
1 我が国の産業界の取組
持続可能な経済社会の構築という理念が一般的になる中、産業界の環境保全型産業構造への変革に向けた取組は、脱硫・脱硝装置の設置などといったパイプエンド的な取組や省資源・省エネルギーの推進だけではなく、個々の製品の環境保全への問題点を明確に認識し、素材、生産工程、製品内容、廃棄時のリサイクルの促進などあらゆる段階での対応を図るという方向に向いつつある。環境庁が実施した調査によれば、環境にやさしい企業行動として技術開発・製品開発段階で実施することとして、環境負荷の小さい製品設計が82.4%、リサイクル可能な製品設計が48.1%とそれぞれ平成4年度の調査での54.4%、39.9%から大きく伸びていた(第2-2-1図)。製造段階では、廃棄物の減量化が72.6%(4年度は62.7%)、省エネ・省資源が62.1%(同50.9%)、廃棄物の低公害化・無公害化が61.9%(同49.3%)と、いずれも大きく伸びている(第2-2-2図)。また、取引の相手について環境問題がないかを事前にチェックしていると回答した企業が62.5%(平成4年度は34.8%)と、これも大幅に増加している(第2-2-3図)。さらに、企業が、経営方針などで定めた環境保全に関する理念を実現して行くためには、売上高や利益などと同様、目標を定めて計画的に着実に努力していく必要があるが、理念だけで行動が伴わなくては、実効があがらず、環境に配慮した企業行動の実現は困難である。こうした点について、環境庁が実施した平成5年度環境にやさしい企業行動調査によると、経営方針及び目標を達成するための具体的な行動計画を作成している企業は、全体の36.7%、平成5年度中に作成する予定の企業が10.9%で、合わせて半数弱の47.6%が作成している。作成時期は、平成4年度が25.4%、5年度が55.6%で、平成4年頃から経営法神の制定や目標の設定に合わせて作成されつつある状況にある(第2-2-4図)。こうした調査結果からも分かるとおり我が国の企業も環境保全に向けて多面的な取組を推進しつつあるといえる。
以下では、建設業、製造業、小売業、運輸業、サービス業、農林水産業を例に、環境にやさしい企業への変革に向けた先進的な企業の努力事例を中心に、それぞれの産業分野で特徴的な環境問題への対応を見てみよう。
ア. 建設業
建設業においては、特に建設廃棄物や建設発生土などの建設副産物の処理が課題となっている。特に、平成3年に施行された「再生資源の利用の促進に関する法律」(リサイクル法)により、土砂、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、木材が指定副産物に指定されたことにより、建設副産物の処理・再利用が積極的に取り組まれている。例えば、平成元年に建設業者282社が共同で建設廃棄物処理会社を設立し、廃棄物の選別、再資源化、最終処分を行うこととしている。この他、ある大手建設業者では、建設廃棄物の専門処理業者が処理施設を建設する際に技術、資金の面から支援し、建設廃棄物の再利用を促進しようと試みるなどの事例が見られる。さらに、環境管理の面については、ある建設業者では、自然環境の保全、資源とリサイクル、エネルギーの有効利用と削減について行動指針を策定し、その中で、開発と自然環境のあり方、廃棄物の削減とリサイクル、エネルギー消費量の削減などについてガイドラインを示している。その上で、推進体制の整備、評価報告の推進、海外での対応について取組体制の整備を進めることとしている。
イ. 製造業
製造業では、地球温暖化問題などに対応するための省エネルギーをはじめ、生産工程で洗浄剤や発泡剤として使用するCFCやトリクロロエタンの廃止、製品・部品のリサイクルの促進、廃棄物として処理される際の環境への負荷の低減など様々な課題がある。こうした課題に対して、製造業における環境にやさしい企業への変革という観点から、先進的な企業では、設計段階において製品が廃棄物として処理される際に、可能な限りリサイクルができ、最も環境への負荷が少ないような商品設計を行い、極力環境にやさしい素材を使用するよう努める動きが見られる。また、生産工程においては、環境に配慮した生産技術の導入や環境への負荷の少ない原材料の使用などによるエコファクトリー化により大気や水質への環境負荷を極力減らす努力を実施し、さらに、企業全体の環境保全対策を実効あるものとするべく環境管理を積極的に推進している。
例えば、生産工程におけるCFCやトリクロロエタンの削減については、ある電機メーカーでは、全社横断的な環境対策についての組織を設置し、この環境保全対策組織が中心となって平成元年(1989年)に削減計画を策定し、実行に移している。この削減計画に基づき、CFCについては既に全廃しており、また、トリクロロエタンについても、6年度(1994年度)に使用量をゼロにするという目標を立てており、国際規制を大きく前倒しして削減に取り組んでいる(第2-2-5図)。
また、環境管理体制の整備については、ある電気機械メーカーでは、海外の関係会社も含むグループ各社に適用される環境基本方針を策定し、その中で企業活動のあらゆる面で地球環境保全に配慮して行動するとして、省資源、省エネルギー、リサイクル、廃棄物の減量化に企業活動の全ての領域で取り組むこと、環境監査を実施し、自主管理の維持向上に努めること、環境に関する社会活動により社会に貢献すること、社員の環境に対する意識向上を図るため、教育、広報活動等を行うこと、環境管理の状況等について必要に応じて公開することなどを定めている。さらに、この基本方針に基づき、廃棄物や製品の再資源化などについて目標値を定め、管理体制の確立、事業活動における環境配慮、製品・技術開発の推進などについて具体的な推進策を策定している。
ウ. 小売業
小売業では、販売時を中心とした包装の適正化、減量化対策、ビン、缶などの容器のリサイクルの促進などが、省資源の観点に加え、廃棄物の増大による処分場不足問題などから重要な課題となっており、これらに対する取組は消費者と直接接することなどから早い時期から積極的に行われている。包装の適正化については、簡易包装や包装材の見直しが行われている。リサイクル問題については、消費者の意識の高まりも受け、大手チェーンストアやスーパーにおいて牛乳パック、各種飲料ビン、アルミ缶等の店舗回収が行われているなど、立地状況などの店舗特性に合わせた取組が広く行われている。
エ. 運輸業
運輸業界では、特に都市圏の窒素酸化物汚染問題に対応してトラック等のディーゼルエンジンからの排ガスが問題となっている。この点については、電気自動車、メタノール車等の低公害車の導入や、公共交通機関の利用の促進、輸送効率の向上などによる運輸過程における環境負荷の削減が課題となっているが、こうした問題に対応するためには、自動車メーカーとの協力が必要となっている。例えば、ある運輸メーカーでは、従来より電気自動車を試験的に運行していたが、さらに自動車メーカーと協力して実用性を高めた電気自動車を開発し、宅配便用に投入して実用化に向けた研究を行っている。この他、鉄道業界においても、運送効率の向上を目指し、アルミ合金を用いた軽量・低騒音・省エネ型の車両が実用化されている。
オ. サービス業
サービス業は、従来あまり環境問題に直接関係があるとは考えられていなかったが、今日の環境問題では我々の広範な経済社会活動が大きな要因になっているとの認識が高まるにつれ、環境問題への積極的な取組が見られるようになった。例えば、金融業界では、環境保全に貢献する活動を行っているNGOに資金を提供する仕組みを付加した金融商品を取り扱う機関が増えており、また、信販業界でも、カード会社がカードの利用額から一定の比率を環境保全活動を実施している団体へ寄付する企業が現れている。また、企業の環境管理、環境監査、環境報告書などへの関心の高まりを受け、これらの点について情報提供、システム設計などを行う環境コンサルタント業も芽生えつつある。さらに、旅行業界においても、環境問題への意識の高まりを受け、自然とのふれあいや環境保全に貢献するボランティア活動を目的とする旅行など、環境をテーマにしたツアーが登場しつつある。
カ. 農林水産業
持続可能な開発という概念がもともと水産資源の利用方法についての研究から生み出されたように、生産力の基礎を自然の物質循環の中に置いている農林水産業は持続可能性を基本とする産業と言うことができる。さらに、農業は、緑地の確保や水田による水質浄化、地下水かん養といった環境保全機能も有している。しかし、今日の農林水産業は、抱えている問題も多い。例えば、農業では、一部地域において、化学肥料の過剰な施用、農薬の不適切な使用や不適切な家畜ふん尿の処理が環境に悪影響を及ぼす場合が生じている。また、森林は、木材の供給源という役割の他、水源のかん養や生態系の保全、さらには二酸化炭素の吸収・固定など様々な環境保全効果を持つ。森林の持続可能な利用には適切な管理が必要であるが、山村の過疎化、林業従事者の減少・高齢化等から適正な管理が不十分な森林が増え、森林の持続可能な利用の阻害要因となる可能性がある。水産資源は、我が国にとって重要な食料供給源であるが、底魚類を中心とする資源量の減少が懸念されている。また、船底や漁網の防汚剤として使われていた有機スズ化合物による海洋の汚染が問題となっている。
こうした課題に対し、農業では、農薬や化学肥料などの資材の投入量の削減やより生態系に調和した農業システムの開発等により持続可能な環境保全型の農業推進へ向けた取組が進められつつある。例えば、水田において除草剤を蒔く代わりに合鴨をはなして雑草を食べさせるなど、農薬に頼らない米作りなどの事例も見られる。また、水産業においても、養殖技術の開発による水産資源の保護や有機スズ化合物の代わりに非スズ系の塗料を用いるなど化学物質による環境負荷低減に向けた取組がなされている。
また、持続可能な農林水産業の実現には、生産者だけでなく消費者をはじめとする様々な主体の協力も必要であるが、こうした観点からの取組の例としては、第一次産業を中心に生産者、市民団体、消費者、流通業者などの事業者が協力して、「森と海と大地を守る」をテーマとして展示会が開催され、さらにネットワークが形成されるなど様々な主体が協力して環境にやさしい農林水産業を実現しようとする動きも見られる。