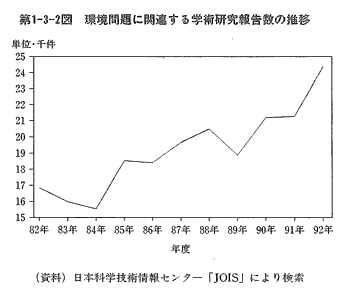
2 環境にやさしい生活文化の定着と発展に向けて
人々の環境に対する認識の変化に支えられ、我が国においても、新しい環境に関する規範である「環境基本法」が制定された。人々の環境観の変化と新しい規範の成立は環境にやさしい生活文化の形成の第一歩であるが、生活文化はその時代、その地域の社会的経済的条件によっても大きく左右されるものであり、こうした社会的経済的条件についても考えていく必要がある。過去の文化の例でも、環境の持続的な利用を行っていたケースの背景には、日常生活の場と自然とが一体化していて自らの行動が環境に与える影響やその影響が自分の生活に跳ね返ってくるという相互関連が把握しやすかったこと、江戸時代のリサイクルのように経済的に見合っていたことなど様々な条件がある。こうしたことから、環境にやさしい生活文化が人々の間に定着していくためには、人々が容易に環境にやさしい行動をとることができるよう様々な社会的経済的条件が整備されていく必要があろう。そのために、今後に求められる社会の仕組みを考えてみたい。
(1) 環境に関する知見の充実等
環境に大きな負荷をかけて営まれている現在の生活や経済活動を環境にやさしいものに変えていくことが求められている中、今日の環境問題や人間活動と環境との関わりは複雑で今後解明すべき点も多い。このため、環境の状況や人間活動との関わりについてよく知り、人と環境との関わり方について考えていく必要がある。こうしたことから、環境の状況や環境と関わりのある様々な経済社会活動の状況についてモニタリングや調査を通じて的確に把握していくことが求められている。
また、こうした環境の状況や人間活動との関わりに関する情報を、我々の判断材料として分かりやすく把握するため「環境指標」の活用が求められている。例えば、我々は直接大気汚染の状況を目で見て把握できないが、大気汚染物質の濃度を計測し、基準値と比較することによって、大気の汚染状況を理解することができる。また、ホタルなど特定の生物の分布の変化を追うことにより、地域の自然の変化の状況を時間を追って把握することができる。このように計測の結果に意味付けを行い把握するという指標化の作業は、環境の状況を把握するために従来より行われてきたが、近年では、このような環境の状況を把握するための指標に加え、人間の諸活動と環境との関わりを把握するための指標の研究も進められている。OECDにおいては、経済活動全体と環境との関わりを把握するための指標や交通、エネルギー、農業など各部門の活動と環境との関わりを把握し、その部門の意志決定に環境への配慮を盛り込むための指標が研究されている。こうした環境指標を用いることにより、直接目に見えない環境への影響を身近なものとして把握し、また環境全体の状況と人間の諸活動とを総合的に評価することが可能となる。環境指標は人々に環境の状況や人間活動との関わりを伝え、判断材料とするために欠かせないものであり、今後も分析手法の整備を進めるとともに、その内容を充実させていくことが求められている。
こうした状況把握とともに、環境と人間との関わりについて学問や研究が深められていくことが期待される。今日、環境に関わりのある学問は、自然科学分野にとどまらず、経済学、法学、文学、哲学など多様な分野にわたり、大学における環境に関する講座も平成4年現在、国立大学で61大学101学科、公立大学で2大学2学科に上っており、環境に関する学術研究論文の数も著しく増加している(第1-3-2図)。個々の分野からそれぞれ研究が深められていくことはもちろん重要だが、環境と人間との関わりは様々な側面を持っているため、全体を一つのアプローチで把握することは難しい。近年、人間と環境との総合的な関係を把握するための「環境学」も提唱されている。また、分野横断的なプロジェクト研究も関係省庁の研究予算の下で進められている。こうした学際的、総合的なアプローチの発展も期待される。
また、リサイクルのための技術等環境保全のための技術開発の振興が求められるとともに、技術自体も環境にやさしいものへと変革していくことが望まれる。平成3年に世界資源研究所が今後の技術革新のあり方に関するシンポジウムを開催するなど近年こうした議論が活発になっているが、今後議論がさらに深められていくことが期待される。
(2) 環境に関する知見の普及と環境保全活動の支援
今日の我々の生活では、生活排水が遠くの川や海を汚染するなど環境負荷が与えられる場所と環境への影響が生じる場所が離れていたり、地球温暖化のように影響が出てくる時期が時間的に離れていたりすると、その影響を直接的に目でみて把握することができないため、自らの行動と環境との関わりや環境影響の深刻さを実感することが難しい。こうしたことから、環境と人間活動に関わる様々な情報が、広く人々に提供されることが人々の環境に対する意識を高め、環境に配慮した行動に結び付けていくために必要であり、環境基本法においても、環境の保全に関する必要な情報の適切な提供が位置づけられたところである。
環境庁では、従来より環境白書を策定するとともに環境保全に関する各種パンフレット等を作成、配布している。平成6年2月には、国立環境研究所環境情報センターと連携して、民間情報を含めた広範な環境情報源情報を「環境情報ガイド」として公表するなど環境情報を整備し、国民に提供するための取組を行っている。また、行政からの情報提供とともに、住民からも情報提供を行うことができるような住民参加型の情報提供システムも構築され始めている。福井県においては、パソコン通信を利用した環境情報ネットワークシステム「みどりネット」を整備しており、住民が環境に関する各種刊行物、シンポジウムなどの行事案内、県内の大気汚染等の測定結果等の情報を入手できるようにするとともに、住民からの環境保全活動に関する情報も書き込むことができるようになっている。今後は環境情報の充実を図るとともに、提供方法についても国民と行政が協力して利用しやすいシステムを構築していくことが求められる。
また、かつて環境との関わり方についての知恵やルールが親から子へ、子から孫へと伝えられてきたように、人々に環境との関わりについて深い理解と認識を持ち、環境に配慮した生活や行動を行うことができるようにするため環境教育が重要である。将来の世代を担う子供達に対する環境教育とともに、今日の環境問題は一人一人の自主的な取組が大きな力を持つことから、社会のすべての人が参加できるような生涯教育としても実施されることが求められている。地方公共団体においても、様々な環境保全活動のリーダーとなる人材の育成、環境学習センターなどの環境保全活動促進のための拠点の整備に向けた取組が始められており、環境庁としても、こうした地方公共団体の取組に対する支援を行っている。また、環境保全団体によっても、広範な国民に対し、啓発や様々な活動への参加機会への提供等が行われている。しかし、我が国の環境保全団体の状況を見てみると、その活動は近年活発になってきているものの、ニッセイ基礎研究所の調査によれば活動基盤が他の民間団体に比べてもかなり弱く、年間予算100万円未満の団体が約6割以上を占め、専従有給スタッフがいない環境保全団体が8割近くに上るなど(第1-3-3図)、今後の活動を展開していく上で多くの問題を抱えており、これらの活動に対する様々な支援が求められている。こうした環境保全団体の地球環境保全のための活動を支援するため、平成5年5月に地球環境基金が環境事業団に設置され、平成5年度の助成事業として104件、総額約4億円の助成案件が決定されたほか、情報提供や人材の育成といった多様な支援が行われることとなっている。
さらに国民の自主的な取組が政府の施策に反映されるという機会を設けることも求められている。地球サミットに報告した国別報告書やアジェンダ21国別行動計画については、広く国民の意見を取り入れるための努力を行ってきたが、環境問題はあらゆる人々に関わる問題であり、今後もこうした国民の参加を取り入れていくことが求められよう。
(3) 経済システムの変革
価格メカニズムなどの経済システムは、消費や投資といった人々の経済行動を大きく左右している。今日の経済システムでは、環境の価値の適切な評価の難しさもあり、価格メカニズムに反映されていないため、環境に配慮した行動も、配慮しない行動もコストが同じであったり、環境にやさしい行動の方が高いコストがかかったりするため、こうした行動を躊躇する例も見られる。例えば、ごみ処理については、一般に地方公共団体が税によって行っており、そのためごみをたくさん出す人とごみ減量の努力をした人の負担に差がない場合が多い。また、再生紙の方がバージンパルプから作られた紙より高いケースがあるが、これは人々が再生紙の購入をためらう一つの要因になっている。
今日の生活がこうした価格メカニズムに大きく左右されていることを考えると、環境への負荷の大きい行動には環境に対するコストが十分に検討されて適切に反映され、環境にやさしい行動には経済的にメリットが与えられるような経済システムが整備されることが、人々の行動を促すために有効であろう。こうした経済システムを作るための手段の一つとして、第3章で見るように環境にやさしい行動にインセンテイブを与える補助金や、環境への負荷が大きい行動に対するデイスインセンテイブを与える税・課徴金といった経済的手段があるが、後者については環境の保全上の支障の防止に係る効果、我が国の経済に与える影響等を調査、研究し、その措置が必要な場合には国民の理解と協力を得るよう努めるとともに、その措置が地球環境保全の施策に係るものである時は、その効果が確保されるために国際的な連携に配慮することが求められている。
(4) 社会システムや社会資本の整備等
環境にやさしい行動をしたいという意識は人々の間に広まってきているが、実際に行動しようとしても、一人の力では解決することのできない困難な問題もある。消費者と企業との協力がなければ進まないリサイクルや夜型の生活が定着した社会での朝型の生活の実践など、社会ぐるみの取組がないと実践が難しい問題については、これを社会ルール化することやその実施を容易にする様々な支援が求められている。例えば、朝型の生活については、欧米諸国では、日照時間を有効に使うため、夏季の間に時計を標準時より1時間進めるサマータイムが広く実施されている。我が国においても、昭和23年から26年まで実施されていたが、近年、エネルギーの有効利用や余暇の拡大のためサマータイム制度を再評価していこうという動きも見られ、国民ぐるみのライフスタイルの見直しの一つの形として導入について検討が進められている。
また、人々の環境に配慮した行動を支える社会資本や都市構造そのものの変革等ハード面の整備も求められている。都市における水や物質、エネルギーの生態系循環を再生する「エコポリス」が提唱され、環境庁ではその具体化に向けた地方公共団体の計画づくりへの補助を行っている。建設省では市町村における都市環境計画の策定をモデル的に先導するため、環境共生モデル都市(エコシティ)に対する都市環境計画作成補助、施設整備補助等を平成5年度から実施している。また、省エネルギー化、自然エネルギーの活用等により地球環境に十分配慮した住宅市街地形成の促進を図るため、「環境共生住宅市街地モデル事業」を実施している。
環境にやさしいライフスタイルの変革を支える社会資本の整備の一つとして、個々人が自動車に過度に依存しない生活ができるよう、鉄道等の公共交通機関の整備等が求められており、先進各国においても様々な取組が進められている。ドイツのエルランゲン市では自転車道路の整備や貸し自転車事業等の自転車利用促進対策を進め、1974年(昭和49年)から1980年(昭和55年)の間に、交通手段全体に占める自転車利用率は14.1%から25.5%に増加し、自家用車の利用は40.6%から34.5%に減少した。フライブルグ市では公共用交通機関の利用の促進のため、割安な「環境定期券」を発行している。オランダでは、アムステルダム、グローニンゲン等の都市で公共交通機関への誘導や自転車利用の促進等の政策がとられている。我が国においても、鉄道等軌道系システムの整備、バスサービスの改善、バスレーンや自転車道路の整備等の道路事業に関する地域モーダルミックス推進施策が進められている。
環境保全に資するこうした社会資本の整備については我が国では遅れている面もある。下水道普及率はイギリスでは96%(平成2年)、ドイツでは86%(平成2年)に達している一方、我が国では47%(平成4年)に止まっており、一人当たり都市公園の面積もロンドンで25.6?(昭和57年)、ニューヨークで23.0?(昭和63年)であるのに対して、東京23区では2.6?(平成3年)に止まっており、環境保全に資する社会資本の充実が求められている。また、人々が自然とふれあい、心豊かな生活文化を築いていくために、自然環境を適正に整備し、健全な利用を進める自然公園における遊歩道や自然観察施設、大都市における都市公園、環境と共生する港湾(エコポート)等の社会資本の整備も求められている。
人々の環境に対する意識の高まりとこうした社会的経済的条件の整備により、環境にやさしい生活文化が人々の間に定着し、発展していくことが期待される。環境にやさしい生活文化は現在の大量消費、大量廃棄型の生活文化を見直し、物質的な制約はあるかもしれないが、心の面では、季節ごとに自然とのふれあいを楽しむように感性豊かな文化としていくことができよう。また、地域のコミュニティ活動や企業者と消費者のネットワークなど人と人との関わりをより豊かにするものでもあろう。こうした環境にやさしい生活文化を構築し、次の世代に伝えていくことができるかどうか、我々の今後の取組にかかっている。