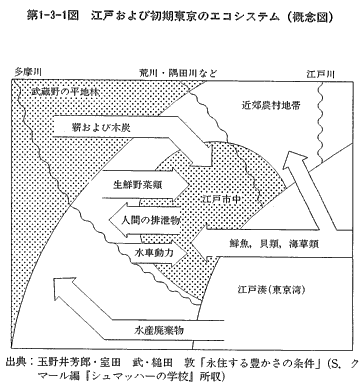
1 環境にやさしい生活文化の意義
第2節では、環境に配慮した消費行動やレジャー活動等の個別の実践例を見てきたが、近年、こうした動きについて「環境にやさしい」というキーワードがよく使われる。同様の表現はドイツでは「Umweltfreundlich」、英語では「Environment-friendly」、フランスでは「Respectueuxdel'environnement」という言葉で人々に広く知られている。我が国で使われる「やさしい」とは、大和言葉の「痩す」を起源としていて、痩せる程に自省する人が初めて成し得る他者への思いやりを示す言葉であり、「環境にやさしい」という言葉には自らの行動がその生存基盤である環境に大きな影響を与えていることへの深い自省が表われているとも考えられよう。今日の我々の生活は、環境に対するこうした自省も十分になされないまま、大量に資源を消費し、大量に不用物を排出するものとなってきたが、今後はこうしたやさしさが生活様式、行動様式に組み込まれ、人々の間で伝播され、共有され、足元からの生活文化として定着していくことが求められている。
この際、忘れてはならないのは、生活文化はその時代、その地域の人にとっては当たり前のように思われているが、その時代、その地域によって異なっており、その背後にある人々のものの考え方や意識、自然的社会的条件に大きく影響されている点である。生活文化の一要素である生活規範と人々の意識との関係を見てみると、欧州諸国では、再利用できないビンに対する課徴金や使用禁止等のルールも定めている例が多いが、環境に影響を与える商品の使用を避けようという意識の高さがこうした規範を支えていると言われている。その一方で、今日の我が国においては、環境保全のために時間や手間をかけたがらない人も多く、再利用ビンの利用も減少してきている。また、人々の意識は生活文化の一つの要素である技術や機械の発展の方向にも大きな影響を与えている。身近な例でいえば、野菜の色や形、虫による食害の有無等に過度にこだわる消費者の志向は、虫による食害のまったくない野菜や色形のよい野菜の生産を促す要因になっている。何時でも手軽に飲料等が買えることから消費者に自動販売機は広く利用されており、我が国では自動販売機は約250万台、約15世帯に1台の割合で設置されている。こうした生活文化のありようは、人々の意識だけでなく、自然と生活とが密接していたり、環境にやさしい行動が経済的に合理的であったりするなど自然的社会的条件によっても変化してくるため、環境にやさしい生活文化の基盤となるこうした条件についても考えていくことが重要となる。こうしたことから、ここでは、環境にやさしい生活文化について、その背後にある人々の環境に対する意識や自然的社会的条件を軸に考えてみたい。
(1) 過去の生活文化、外国の伝統的生活文化
現代日本に生きる我々の多くは環境にやさしい生活文化とは言えない大量消費、大量廃棄型の生活文化の中で生きている。我々は、現代日本の生活文化が高度で豊かなもので、それゆえに普遍性をもっていると思いがちであり、環境にやさしい文化はあたかもこれから構築される目新しいもののように考えられがちである。
しかしながら、過去にも、また、現在も、現代日本の生活文化と違ったいろいろな生活文化がある。こうした中で、環境にやさしい生活文化は決して目新しいものではなく、人類がこれまで経験してきた生活文化や地域に伝えられてきた民俗、各国で伝統的に伝えられてきた生活文化の中にも、その要素を見つけることができる。前に見たように、現在の我々の生活様式、行動様式が環境に大きな負荷を与え、人類の存続をも脅かすおそれも生じてきている今日、我々はもう一度こうした生活文化の価値を見直していく必要性があるのではないだろうか。我々は、これらの文化から学ぶことにより、人類の歴史の中で、環境にやさしい文化が決して実現可能性の乏しいものではないという確信を得ることができるし、また、今日にも通じる実践的な知恵や着眼点を見いだすことができる。いくつかの事例を通して、まず先人達の環境との係わり方や考え方を見てみたい。
最初に我々が経験してきた文化として、近代化が進む以前の日本の様子を江戸時代及び現在にまで伝えられてきた民俗に着目して見てみよう。
我々が認識しておかなければならないのは、現在の我々の生活を基準に考えると、江戸時代は約230年に及ぶ鎖国体制の中で利用できる資源も限られているなど生活物資も少なく、封建体制の下で職業等に関する自由の制約もあった点である。自然の災害も厳しく、3年に一度の不作、30年に一度の小飢饉、50年に一度の大飢饉といわれたように周期的に人々を襲う飢饉や水害によって人々は苦しめられていた。こうした厳しい自然環境条件、社会経済条件の中で、人々が環境とどのようにつきあってきたのか、いくつかの事例を見てみよう。
最初に、物質消費について見てみよう。江戸時代は現代に比べればものが少なく、使えるものは徹底的に再利用、再生利用され、そのための様々な商売が成り立っていた。まず、ものが壊れても修繕して使うことが根付いており、煙管を直す羅字屋、錠前直し、算盤直し、鍋や釜の穴あきを直すイカケ屋、壊れた陶器を直す焼継屋などの修繕屋業が成立していた。また、使えなくなったものについては、紙屑は漉返紙に、ローソクの屑は集めてローソクに、薪や炭などから出る灰は肥料や酒のろ過やアクぬきに、金属も専門の業者が集めて再生利用した。江戸が当時では世界有数の大都市でありながら、このようにものの修理、リサイクルが徹底していた背景には、鎖国政策により基本的に外から資源が入ってこず、また排出物も外に持ち出せない閉じた世界であったことが考えられる。このように資源が有限であったために、大切に有効利用され、様々なリサイクル業が成り立ち、人々は経済的にも得になるという理由で使用済みのものをリサイクルに出していたのであろう。今日我々が生きている地球も閉じた世界である点は同じであり、物を大切に使い回していくことの必要性は共通している。
人間活動から排出される不用物のゆくえはどうだっただろうか。糞尿は買い取られて田畑の肥料となり、食物の生産に役立てられる。生活排水については、水をきれいに使うための様々な掟が守られた上で、最終的に海に流れ込み、魚介類や海草の栄養源として利用されるといったように、人間にとっての不用物は生物の相互依存関係の中で、有意義に利用されていたといえる(第1-3-1図)。水の利用にあたってのルールは比較的最近まで、慣習として伝えられ、守られてきた地域がある。琵琶湖湖畔のある村では、水汲みの時間と洗濯の時間や場所を分けるなど、皆が川の水を気持ちよく使うことができるように様々な配慮がなされていた。下のものやオムツは直接川では洗わずにたらいで洗い、洗い水は便所に入れて肥料として利用し、台所や風呂水は貯水層に溜めてから畑のかん水などに使用していたが、これは水を汚さないという意味とともに、肥料として使えるものは徹底して使うという意識があった。川にものを捨てたり、糞尿を流したりすることはタブーによって禁じられていた。
また、生物資源とのつきあい方を見てみよう。獣や漁業資源については、その枯渇が、狩猟者や漁民にとって自らの死活問題となることから、自然資源の保存、利用の仕方について多くのルールがあった。例えば、熊狩については、繁殖期の熊の捕獲を避けるため、寒中の熊狩を禁じる習慣や、子持ちの熊の捕獲を禁じるタブーが東北地方のいわゆるマタギ集落で伝えられていた。漁業資源との関わりを見てみると、新潟県北部ではサケを水神からの授かりものと考え、サケが産卵最盛期に入る時期以降は禁漁とする規則が伝説として守られていた地域がある。北海道のアイヌの人々は、海や川から得られる食物は神からの恵みと考え、クマやキツネなどとも共有すべきものとして、取り尽くさず他の生物の取り分を残しておくという狩猟採集習慣があったと言われている。森林資源については、手つかずのまま残された例として、地域社会のタブーや御神木として残されたり、寺社仏閣のまわりの鎮守の森として守られてきた例が各地に見られる。明治期になると、南方熊楠はこうした鎮守の森が減少することに対して、「土崩れ山崩れ、洪水風害をもって常時となす」おそれがあることを指摘し、その保護を訴えた。
農業などの生産活動のために、自然を改変し、利用していく営みの中でも、自然の有限性、生態を理解した上で利用していく方法が見つけられていた。例えば、農耕を営む人々の生活と密接な関わりをもった二次林の利用である。いわゆる里山の森林は、かんがい水を維持し、水田の肥料とする下草や落ち葉また燃料となる薪を確保する役割を果たしており、地域の住民はこれらの恵みを共有するとともに、下草刈りなど様々な作業を分担して行っていた。地域共同体全員の利用や次世代の利用を守るため、自然資源を保全し、里山の利用にあたっては、利用時期や人数の制限、一人当たりが採取できる量など入り会い上のきまりがあった。里山は人に恵みをもたらすと同時に、明るい林床を好む植物を繁殖させ、それらを食料とする野生鳥獣が集まるなど様々な生物に生息場所を提供し、人間と多様な生物が互いに恵みを与えあう共生の場でもあった。
その地域の自然条件をうまく踏まえた農地管理方法も模索された。沖繩では土壤侵食によって赤土が川や海に流出しやすく、海洋生態系に影響を与えるという懸念が指摘されているが、18世紀に記された琉球の農業指導者蔡温の「農務帳」では、山間の傾斜地の草木を刈払って開墾し、山肌を出したままにしておくと荒れ土が落ちてしまうため、これを禁ずるとともに、土壤流出を防ぐため等高線に沿って横溝を多く掘ったり、水がたまる場所を短い間隔で設けたりして泥や水が一カ所に集中して流れないようにするなどの工夫が記されている。
木を植えることによって、漁業資源を確保するということも行われた。これは、「魚つき林」と呼ばれており、水面に対する森林の蔭影、投影、魚類等に対する養分の補給、土砂流出の防止等の作用により魚類の棲息と繁殖を助ける役割をもつ森林である。海岸に檜(アオモリヒバ)の密林があったためにあわびが豊富にとれた下北半島では「檜の枝にあわびができる」という諺もあり、人々が海と陸の生態系のつながりをよく知り、活用していたことが分かる。こうした海と陸の関係を一つ続きのものととらえる考え方は、沖繩では近年まで「山がはげると海もはげる」、「陸がだめになると海もだめになる」という言い伝えとして残っている。こうした自然資源の利用に当たっては、自然のメカニズムをよく知り、その性質に合わせた技術が結局有効であることが長い経験の中で理解されていた。
また、季節ごとに自然とふれあう余暇活動も盛んであった。江戸は当時世界有数の大都市であったが、江戸名所花暦には、300箇所余りの江戸の花の名所があげられている。また、江戸の町には約1000の寺社が抱える豊かな寺社林があり、武家屋敷では自然風景を模した庭園がつくられ、住民も園芸に熱を入れるといったように身近な緑化も盛んに行われていた。天保年間(1830〜1843年)の江戸の街全体の緑被地率は全体で約43%、また、江戸城を中心とした緑被地率もほぼ同じという試算もあり、市街地全体に緑が分布していたといえよう。こうした園芸の技術は、当時の世界では非常に高い水準にあり、来日した外国人を驚かせている。
こうした江戸時代あるいはそれ以前からの環境とのつきあい方は、現在でも地域の民俗として伝えられ、守られているところもある。
次に、世界の伝統的な文化の中で、環境との共生を成し得てきた様々な文化を見てみたい。
東南アジアなどで伝統的な暮らしを守る人々の間で引き継がれてきた伝統的な焼畑農業は、自然の循環サイクルにうまく適合しているものであった。伝統的な焼畑農業では、熱帯林を焼き払って耕作を行った後、地力及び植生の回復力が落ちないうちに耕作を放棄する。そして、数十年の歳月を経て回復した二次林を再び焼き払って利用する、という植物遷移のサイクルに合わせた利用が行われていた。ボルネオ島中央部では、現在でもおよそ30年のサイクルをもつ焼畑農業が行われている例も見られる。また、伝統的な焼畑に利用する森林は、原生林あるいは回復途中にある森林を使うことは少なく、回復した二次林を対象とすることが多いと言われている(第1-3-1表)。これは、長い時間をかけて営まれる自然の遷移のサイクルに人間活動が合わせた利用の形態であり、自然のサイクルとともに生きる共生の形とも言える。しかし、近年では人口の急増を背景に、このような長期的視点に立った持続的利用形態を持たない焼畑農業が急増しており、熱帯林の減少を引き起こす一つの原因となっている。
漁業資源の管理の面でも様々な知恵がある。東インドネシアの島々の中には、ナマコなどサンゴ礁の海産物資源を管理するために、一定期間の禁漁時期を設けたり、海浜をいくつかの区域に分割し、その1区分を1年おきに禁漁区域とするサシという制度が人々に実践されている例がある。
カナダのイヌイットやアマゾンのいくつかの民族を始めとする狩猟採集によって生活を維持している多くの人々の間では、狩猟採集の対象となる動植物を始めあらゆる生き物と人間とが同等に霊魂を持ち、獲物を粗末に扱うことを避けるという考えがあった。アマゾンの民族の中には、過剰な狩猟採集が人間に報復として病気をもたらすという考えもある。
これらの例に見られるように、伝統的な暮らしを続ける人々は、自然とともに生きる様々な知恵や手法を身につけている。それは持続的な利用のために意識してルールとして守られている場合もあれば、偶発的に生み出されたものあるいは本来は宗教的な目的など別の理由であったものが実は持続的な利用に役に立っていたという場合もある。いずれにせよ、こうした人々は自然の豊かさや肥沃な土地を生活の基盤としており、地域の資源を持続可能な方法で利用するということが、経験から学んだ自衛手段となっている。子孫も同じ場所で暮らすという意識をもっているため、土地に対しても長期的な視野を持ちやすい。こうした人々はその土地の自然についてすぐれた生態学的知識を日々の生活の中で身につけており、それを慣習や神話、タブーの中に織り込んで、親から子へと引き継いできた。こうした生態学的知識から、森林や草原、農地、漁場、野生生物を有効に持続的に利用するために様々な管理手法(スチュワードシップ)を持っている(第1-3-2表)。
伝統的な暮らしを続ける民族の力を現代の自然資源の管理に生かすような政策もとられている。フィリピンでは、1982年(昭和57年)から、特定の地域について行政の森林部門と先住民族共同体など地域住民が共同で森林を管理する政策がとられている。森林の所有権は国家に属しているが、森林地域の住民共同体と政府の環境自然資源局が「森林共同管理協定」を結び、住民共同体がその森林地域を借り受け、森林を管理するとともに、林産物を利用する権利を得るものである。1990年(平成2年)現在約4万4千haが対象地となっており、13の森林共同管理協定が結ばれているが、その内2つの共同体を除くすべての共同体に先住民族が含まれている。この手法は、先住民族などの地域共同体にとっては居住地域が認められるメリットがあり、また、政府にも少ない行政コストで広大な面積の森林を管理し環境を保全することができるというメリットがある。アジア太平洋地域の文化問題、社会経済上の緒問題を長年研究している米国の東西センターの調査によれば、こうした森林を地域共同体で管理する手法は、フィリピンだけでなくインドやタイでも行われている。
先人達や世界の伝統的な暮らしを続ける民族の知恵をいくつか見てきたが、先人達の暮らしは、現在の我々の暮らしを基準に考えると利便性に欠けることは否定できないし、現代日本に生きる我々が昔のような生活に戻ることも困難である。しかしながら、先人達の知恵の中には、現代に生きる我々が見落としてきた重大な要素がいくつかあり、今日の社会が学ぶべき点もある。
第一に、経験と観察から環境をよく知り、総合的に把握していた点である。自然資源の管理や農用地の管理の例でも見たが、人々は山と川と海の環境を結び付けて考えるなど自然の循環や生態系のメカニズムを生活の中で感じとり、環境を総合的に把握していた。山、川、海といった要素ごとにバラバラの対策をとるよりも、海の環境を守るために山を守るといったいわば流域の総合的な管理により効果が増加することを知っていたのである。このように環境をひとまとまりのものとして総合的に把握する視点は、環境問題が相互に絡み合ったものとなっている今日にも生かされる視点であろう。
第二に、自然と共生しながら利用していく環境観を持っていた点である。人々は長い経験と観察から自然の生態について豊富な知識や知恵を持ち、自然の再生能力や浄化能力の限界も考慮し、自然のサイクルにあわせて利用を図ってきた。里山の利用や先住民の持続的な焼畑農業にみたように、それぞれの地域の生態系のルールを理解し、その一員として自然のサイクルに参加するという形で、人間からの養分の提供など自然の側にも便益をもたらすとともに、自然からの恵みをより豊かに享受するという共生形態を持っていた。先人達が守ってきた(1)自然のサイクルに合わせた長い時間をかけて、(2)適正に管理し、(3)自然資源を使い尽くさずストックを残しながら、(4)感謝の気持ちをこめて、(5)必要なものを必要なだけ適切に使うという共生の精神は、将来の世代も含め多くの人が環境の恵みを分かちあっていくために、改めて学ぶところが大きい。無論、今日の社会では、様々な技術が生み出されており、公害防止技術のように環境保全面から大きな役割を果たしてきたものも多い。しかしながら、人間のつくりだした技術だけで、生態系の微妙な均衡の上に成り立つ有限な環境を将来にわたって保持しようとすることには自ら限界があり、こうした先人達の自然観、世界観が今後の参考になるところが大きい。こうした自然感や世界観について、わが国の国際日本文化研究センターなど様々な研究機関でも研究が進められている。個々人の価値観は個々人が選択するべきものだが、環境と人とが共生していくための新しい哲学や理論の発展は今後大いに期待されるところである。
また、環境観や環境に対する意識は、単に思想的な背景だけでなく、社会条件、生活条件によるところが大きいと考えられる。例えば、生活の場と自然とが密着しており、自然資源を枯渇させたり、回復不可能なダメージを与えたりすることは、自らのあるいは自らの子孫に影響や被害を及ぼすことが分かりやすかったために必然的に環境を守っていたと考えられる。言い換えれば、環境へ負荷を与えることが、自らにあるいは将来の世代にどのような影響をおよぼすかという情報を身をもって把握していたという状況にあった。しかし、今日では、川とのつきあいにしても、上水道等の完備により人々の生活が川水利用から離れてくると、川との関わりが薄れ、様々なタブーも忘れられる傾向にある。また、江戸時代に見たように、資源の有効利用は、資源がもったいないという意識とともに、様々なリサイクル業が成り立つ経済的条件が成立していた点は重要であろう。環境観や環境に対する意識が、情報や経済性といった社会条件や生活条件によって変わってくることを考えれば、国民が環境に対する意識を深めていくために、情報提供や経済性の確保等社会条件、生活条件の整備を行っていくことが重要となろう。
第三に、環境保全の担い手として、地域の共同体全員が参加していた点である。自然の恵みは地域全体のものであり、地域全体でそれを守るという意識があった。与えられた地域の自然環境の中で、その環境に依存して永続性をもって暮らすために、タブーや慣習等環境との関わりに関するルールを設け、地域共同体で山の手入れや漁業管理などを行っていた。このように地域の共同体が主体となって取り組むメリットは、彼等が最もよく地域の生態系をよく理解しているため適切な管理を行うことができるといった点や、地域の人間であればその土地の自然資源と永続的に付き合っていくために自然資源をとり尽くすことをしないといったことがある。また、こうした作業を共同で行うことによって、地域の共同体の中のつながりを豊かにすることができる。このようなことから、地域共同体が主体となって積極的に土地管理や環境管理に参加していくことの重要性は、現代にも通じるものがあるだろう。
(2) 人間と環境をめぐる認識の高まり
今日我々の多くが享受している豊かな生活文化は、他方で資源の大量消費、不用物の大量排出という側面をもっており、環境に大きな負荷を与えている。こうした生活文化も、あたかも大量消費や大量廃棄が美徳であるかのような、我々の認識に大きく影響されていると言える。しかしながら、こうした生活文化が普遍的なものではなく、過去には、また、世界の中には、環境と共生する環境観をもった文化が存在していることも前に見たとおりである。我々の生活文化の背後にも、ようやく環境と人との係わりに関する新たな認識の変化が生まれてきており、近年それを生活全体あるいは社会全体の規範へと高めてきた。ここでは、そのような動きを見てみたい。
1960年代から1970年代にかけて、飛躍的な経済成長を遂げた先進諸国において地域的・局所的な公害が大きな問題となる一方、開発途上国の間では、貧困からの脱却が急務となっていた。このような状況で、1972年(昭和47年)にストックホルムで、国連人間環境会議が開催された。しかし、経済成長の帰結として発生した公害が深刻化し、その対策に悩む先進工業諸国と、貧困の克服のためこれから経済成長を進めようとしていた開発途上国との間での公害をめぐる認識の対立は厳しかった。環境保全を進めて行くためにストックホルム宣言という合意と行動の枠組みは形成されたものの、その後、先進国においては大量消費、大量廃棄型のライフスタイルや経済活動が拡大され、また途上国においては、貧困から脱却するためにはまず開発を行うことが先決で、環境への配慮を行う余裕はないという主張で開発が進められることが多かった。
こうした中、環境と人との係わりに関する認識は様々な出来事をきっかけとして変化していく。まず、1972年(昭和47年)に発表された「成長の限界」(ローマクラブの報告)、1980年(昭和55年)に発表された「西暦2000年の地球」(アメリカ合衆国政府特別調査報告)を始め、深刻な予測が相次いで発表され、資源・環境の制約による成長の限界を明かにし、世界の人々に大きな衝撃を与えることとなった。人間の活動が拡大すると、地球の資源再生能力や汚染の浄化能力といった様々な限界に突き当たり、人間と地球の将来に重大な危機が訪れるのではないかという懸念が1960年代後半ごろから示されていたが、環境が有限であるという認識は次第に人々に広まっていった。また、宇宙開発の時代に入り、人々が宇宙からの地球をその目でとらえることができるようになると、地球環境の有限性という認識は視覚的にも人々に強く印象づけられることとなった。
また、様々な地球環境問題が顕在化するにつれ、人々の環境に対する考え方は徐々に変化してきた。例えば、1974年(昭和49年)にアメリカの学者によって、スプレーや冷蔵庫の冷媒など日常生活で使われているクロロフルオロカーボン(CFC、いわゆるフロンの一種)がオゾン層を破壊するという問題が発表され、改めて人々に自らの生活が地球の環境に責任があることを認識させることになった。また、どの国から排出されたCFCであれオゾン層に影響を与えるとともに、オゾン層が壊れるとその被害は世界中に及ぶ、また現在の世代だけでなく、将来の世代にも影響が及ぶという事態は、人々に人類は運命共同体であり、将来の世代とも環境を共有しているのだという認識をもたらす一つのきっかけとなった。
さらに、人間活動の拡大による野生生物種の生息区域の破壊や悪化、乱獲、侵入種の影響等により、野生生物種の絶滅がかつてないスピードで進んでいることが明らかになってくると、生物種の生物資源としての利用可能性が減少するといった面だけでなく、野生生物と人間との交流といった非消費的利用価値を見直す動きや、地球上の多用な生物種が相互に依存しあい有機的に連携を保っているという地球生態系への認識を高めることとなった。また、分子生物学の発達により、我々人間の遺伝子には、他の生物種の遺伝子と共通のものが多いことが分かると、人間が他の生物種に超越したものではないということが科学的にも裏付けられ、人間も他の生物と同様に地球生態系の一員であることが広く認識されるようになった。
このように個々の問題から、環境の有限性、現在の世代と将来の世代の共有とすべての主体の責任、地球生態系の一員としての認識といった環境と人間との係わりに関する新たな認識が生まれてきたが、こうした動きを受けて、国際社会では、人間社会全体の新たな行動原則が作り出されてきた。それが「持続可能な開発」という行動原則であり、有限な環境の中で、将来の世代の利益を確保しながら、現在の世代のニーズを確保していくことが今後の社会が目指すべき方向として打ち出されたのである。この概念を一般的に定着させたのは「環境と開発に関する世界委員会」(WCED)が1987(昭和62年)年に公表した報告書「我ら共有の未来」(OurCommon Future)である。「持続可能な開発」の概念は、さらに1992年(平成4年)6月にブラジルのリオデジャネイロで開催された「環境と開発に関する国連会議(地球サミット)」で全世界の行動原則へと具体化された。
地球サミットでは、持続可能な開発を実現するための行動原則である「環境と開発に関するリオ宣言」、同宣言を踏まえた21世紀に向けた具体的な行動計画として多様な分野ごとの取組や企業、NGO等主要な行動主体の役割強化等をまとめた「アジェンダ21」等が採択された。これを受けて、世界各国で、持続可能な開発を実現するための取組の開始、さらなる強化が進めらている。
さらに、環境と人間との係わりに関する新たな認識を反映した人間の生活行動全般を律する規範として「環境倫理」を構築しようという考え方も出てきている。アメリカの環境保全運動は環境倫理の構築に大きな役割を果たしたと言われており、開発により原生自然が失われていく中、19世紀半ばから自然保護のための様々な考え方が提唱された。その中で、環境倫理を定型化したともいわれるアメリカの野生生物生態学者アルド・レオポルドは、国立公園の管理、狩猟用鳥獣の個体数の観察など自然管理の実務的な経験を踏まえて、「土地の倫理(LandEthics)」を提唱している。「土地の倫理」は、人間、土壤、水、植物、動物を共同体の一員として考え、人間を含めた共同体の個々の構成員は自分自身が生存するために他の構成員と相互依存関係にあり、構成員は共同体の健全性に対する責任を持っていると考える。様々な生物は、人間にとって資源として利用できるといった経済的利益がなくとも、共同体の安定性を高めるために存続する必要性があることを指摘した。価値判断の基準として「それが生物共同体の統治、安定、美を保つ傾向にあるならば、正しい。反対の方向にあれば間違っている」という尺度を提案している。その後、環境倫理に関しては現在世代が未来の世代の生存の可能性を保証する責任があるという世代間倫理の考え方や有限な地球生態系と人間活動の関係等種々の論点について議論が深められている。
環境倫理については、我が国においても様々な検討が進められている。環境庁の「環境と文化に関する懇談会」では、人文、社会、自然の各科学の第一人者、さらには産業界、労働界、民間団体などから幅広い参加を得て、広く環境と文化について検討を行い、平成3年4月に報告書「環境にやさしい文化の創造を目指して」が提出された。同報告書では、環境倫理の実践のための3つの道しるべとして、第一に有限で精妙な環境の背後にある自然の理にかなった行動を心がけること、第二に環境と人との絆を強めていくこと、第三に現在の世代や将来の世代、多様な生物達と環境を分かちあうようにすることを掲げている。これは、後にのべる環境基本法の3つの理念にも生かされている。
国際的にも、1991年(平成3年)10月に、国連環境計画(UNEP)、国際自然保護連合(IUCN)、世界自然保護基金(WWF)が発表した「新・世界環境保全戦略」では、持続可能な生活様式のための世界倫理が提案された。持続可能な生活様式のための世界倫理を構成する要素として、人間が現在の世代、将来の世代及び自然界とを結ぶ共同体の一部であるという認識、人間の基本的な人権の尊重、全ての生物の尊重、人間が自然に及ぼす影響への責任、資源利用の恩恵と代価の共有等が挙げられている。環境倫理はこれまでの経済性、効率性といった我々の価値判断の基準を環境の観点から考え直そうという一つの取組として、今後の発展が期待される。
(3) 認識の共有から新たな規範へ
環境と人との関わりをめぐる新たな認識は、今日では、考え方、ものの見方としては、企業や市民の間にも共通のものとなりつつある。
企業の間でも、人間と環境の関係についての認識は変化してきており、世界27カ国の経済人が参加しUNCEDに対する経済界からの見解をまとめた「持続可能な開発のための経済人会議(BSCD)宣言」の中で、地球上の全生命を支える環境を破壊することなく人間の基本的ニーズを満たすことが現在及び将来の世代が享受する生活の鍵となることを指摘し、政府、企業、社会の間の新しい協力関係の構築の必要性を述べている。また、我が国でも、平成3年4月の経団連地球環境憲章において、世界的規模で持続可能な発展を可能とする健全な環境を次代に引き継いで行かなければならないという決意が示されている。同年11月の経済同友会からの提言「地球温暖化問題への取組みー未来の世代のために今なすべきこと」の中では、人類が地球上に生きる生物種の一つであり、人類が地球の環境に何らかの形で依存し、自然の再生力の範囲内で生きているという認識を示し、企業への具体的な提言として「成長のみに価値を置く企業から、地球環境の保全に配慮した生活文化を消費者と一体となって築き上げていく企業へ」姿勢の転換を掲げている。
市民の立場でも、地球サミットと同時に世界187カ国7946団体のNGOが集まって開催した「グローバル・フォーラム」で採択された「地球憲章」において、前文で地球の保全と再生、資源の恵みの賢明で公平な分配、生態系のバランスと社会的、経済的、精神的に新たな価値観を達成するため責任を分かちあうことを掲げ、地球生態系の尊重、永続不可能な生産と消費パターンの変更、政策決定過程とその基準の透明性及びアクセスの確保等の原則が規定された。
また、現在の先進国の消費活動に対する反省として、「環境スペース」という概念がオランダの国際NGOから提唱されている。これは、将来の世代の資源利用の権利を侵さない範囲でどの程度のエネルギー、水、その他資源の利用や消費活動、そして環境汚染が許されるのか、一人一人の許容限度を計算し、具体的な数量を示したものである。例えば、2010年(平成22年)に70億人になると想定した地球の中で、すべての人が平等に資源を分配する場合には、例えばアルミニウムについては2010年に1人1年間当たり使用量は2kg(現在のオランダ国民使用量の約8割を削減)、木材については現在のオランダ国民使用量の約65%を削減することになるという試算を行っている。こうした環境スペースを算定した上で、資源を繰り返し使うよう消費行動を考え直そうという取組を提案している。
このように環境と人との関わりをめぐる新たな認識が共有されつつある中で、我が国でも平成5年11月19日、環境保全のための新たな規範が生まれた。第128回国会における環境基本法の全会一致による可決・成立を経ての公布である。環境保全のための規範は、環境保全の歴史の中で育まれ、変化してきた。環境基本法制定に至るまで、我が国における環境保全のための規範の変化を公害対策基本法(昭和42年)及び自然環境保全法(47年)にさかのぼって見てみたい。我が国においては、激甚な公害の発生や自然破壊の進行の中で制定された公害対策基本法、自然環境保全法に基づき、各般の公害防止対策、自然環境保全対策が進められてきた。公害対策基本法は、その法目的を公害対策の総合的推進を図り「国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全する」こととしている。同法は、公害を大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、地盤沈下、土壤汚染及び悪臭という7つの限定された事象から、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることと定義し、このような公害を防止するために事業者、国、地方公共団体、住民の責務を定めるとともに、排出規制等を始めとする各種の措置を講ずることを定めた。また、自然環境保全法においては、基本理念として、「自然環境の保全は、自然環境が人間の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることにかんがみ、広く国民がその恵沢を享受するとともに、将来の国民に自然環境を継承することができるよう適正に行わなければならない」と定めており、この基本理念の下、関係法令があいまって、自然環境の保全のための特定地域の行為規制等が行われることとなった。これらの法律に基づく対策は、激甚な産業公害や大規模な自然破壊に対して大きな効果をあげてきた。
公害対策基本法と自然環境保全法下の対策は、基本的には、環境に直接的に影響を与える行為を抑制しようとする発想によるものである。その意味で、警察的な取締りの考え方を背景としており、社会の各主体に求められる責務も、環境に著しい影響を与えるような特定の種類の行為を限定的に定めた上、これを行ってはならないとすることを中心とするものであった。このため、環境への負荷を与える日常生活の行動や一般の経済活動に配慮を求めるものではなかった。また、公害対策基本法では、主に国民の健康保護の観点から、種々の規制が定められていたため、将来世代の利益や国境を越えた地球的な利益を保護すべきことは明示的には要請されていなかった。
こうした中で、先に見たように地球環境問題が顕在化し、人類の生存基盤であるかけがえのない地球環境が損なわれるおそれが生じるとともに、人類の生存基盤である有限な環境を守り次の世代へと引き継いでいくことが課題となってきた。また、我が国においては、その後の経済的発展の中で、物質的にはより豊かになったものの、大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済活動が定着するとともに、人口や社会経済活動の都市への集中が一層進展してしまった。その中で、大都市における大気汚染や生活排水による水質汚濁等の都市・生活型公害等の改善は依然として進まなかった。また、廃棄物の量の増大による環境への負荷も増加していった。さらに、都市における身近な自然が減少しているのに対し、過疎地域を中心に農地、森林の有する環境保全能力の維持が困難な地域も出てきている。その一方で、人と環境とのきずなを強める自然とのふれあいや快適な環境(アメニティ)などへのニーズも高まってきた。
このような今日の環境問題に適切に対処し、環境の恵沢を現在及び将来の国民が享受していくためには、社会経済活動や国民のライフスタイルのあり方を含め、社会全体を環境への負荷の少ない持続的発展が可能なものに変えていくことが必要となってきた。これまでの環境政策の土台となっていた公害対策基本法及び自然環境保全法を2本の柱とする施策体系では不十分であるとして、環境保全に関する各般の施策を総合的・計画的に進めていく法的枠組みとして、環境基本法が制定された。
環境基本法では、環境の保全についての基本理念として、先にも触れたような人間と環境との関わりに関する認識の変化を踏まえ、環境の恵沢の享受と継承等、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等及び国際的協調による地球環境保全の積極的推進という3点を定めるとともに、国、地方公共団体、事業者及び国民の環境の保全に係る責務を明らかにしている。
環境の有限性、環境が生態系の微妙なバランスの下に成立していることを認識した上で、第1の理念では、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健康で文化的な生活に不可欠であること、環境負荷の増大により人類の存続基盤である環境が損なわれるおそれが生じてきていることを踏まえ、環境の保全が「現在及び将来の世代が恵み豊かな環境を享受するとともに人類の存続の基盤である環境が将来にわたって維持されるように適切に保全されなければならない。」という大本となる考え方を示している。
第2の理念では、環境問題が事業者や国民一人一人の日常の経済社会活動から発生しているという背景を踏まえ、環境への負荷の低減や環境保全行動がすべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われることによって、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的発展が可能な社会を構築していくことを掲げるとともに、科学的知見の充実の下に、環境保全上の支障が未然に防がれることを掲げている。
第3の理念は、我が国の能力を生かし、国際社会においてわが国の占める地位に応じて、世界各国と手を携えながら地球環境保全に積極的に取り組むとの基本姿勢を明らかにしている。
環境基本法では、以上の理念を踏まえ、環境基本計画の策定をはじめ、多様な基本的施策を規定している。環境基本法は、これから全ての主体が公平な役割分担の下、力をあわせて「環境負荷の少ない持続的発展が可能な経済社会」を構築していく必要があるという、従前の法体系にはない新たな環境保全の理念を示しているのである。政府としては、先ず、環境基本法を受けて展開すべき施策の大綱を示す環境基本計画を策定することとしているが、これにより新たな理念を支える施策の全体像が形を整えることになる。