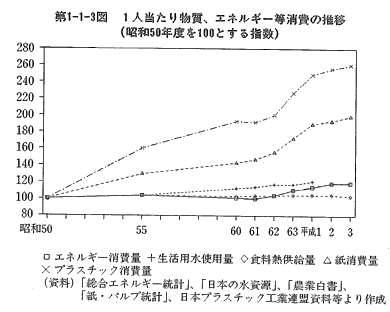
2 日常生活における行動と環境への負荷
(1) 物質消費とエネルギー消費
我々は日常生活において、大量の物質及びエネルギーを消費している。例えば、我が国の一人当たりの年間一次エネルギー消費量は石油換算で3.54トンであり、OECD諸国平均(4.81トン)の73.6%にとどまるものの、世界平均(1.52トン)の2倍以上にのぼっている。また、紙消費量は234.7kgで世界平均の44.5kgの5倍以上にのぼる。一人当たりのエネルギー消費量や紙、プラスチックなどの物質消費量は増大しており、特に好景気を反映して昭和61年以降の伸びが著しいが、最近では景気後退の影響から伸び率は鈍化している(第1-1-3図)。
物質の大量消費により我々の生活は便利で物質的に豊かなものになった。その一方で、物質の大量消費は、自然界からの資源採取量を増大させ、資源利用の持続可能性を失わせる恐れも生じさせる。また、我々が物質を消費するに伴って、間接的に商品の生産・流通、使用さらに廃棄の各段階で環境への負荷が生じている。昨年の環境白書でも取り上げた慶応義塾大学産業研究所の研究結果等から商品が消費者の手に届くまでの生産・流通段階で発生する二酸化炭素量を試算すると、家計からの支出が最も多い食料品については、肉1kg当たり0.8kg(炭素換算)、マグロ1kg当たり2.4kg、野菜1kg当たり0.2kg、塩1kg当たり1.1kgとなる。また、乗用車1台の生産・流通過程では、国立環境研究所の推計結果では、1695kg(炭素換算)の二酸化炭素が排出されている。さらに、我が国の海外への依存度が高まるにつれ、こうした生産段階での環境負荷が海外で生じるようになってきている。食料輸入について見れば、近年では、東南アジアでのエビの養殖に伴うマングローブ林の伐採や水質の悪化、地下水の汲み上げによる地盤沈下などの問題やバナナ栽培における大量の農薬使用による環境への影響といった問題も指摘されている。
次に、家庭におけるエネルギー使用について考えてみると、灯油や天然ガス、ガソリンといった化石燃料の燃焼に伴う二酸化炭素や窒素酸化物等の環境負荷のほか、電気の使用により火力発電所等から発生する二酸化炭素や窒素酸化物等の環境負荷が生じている。一人当たりの年間二酸化炭素排出量は平成3年度で2.61トン(炭素換算)であり、環境庁の試算によれば、昭和41年度の排出量の約2倍、10年前の昭和56年度からは14.5%増加している。一世帯当たりの日常生活のエネルギー等の使用に伴う二酸化炭素排出量の内訳を環境庁試算により、10年前と比較してみると、エネルギー源別では、ガソリン、電気の使用による二酸化炭素排出量の増加量が大きい。また、用途別に見てみると、電気機器等の動力や照明の使用、自動車の使用に伴う排出量の増加は著しく、それぞれ10年前から24%、39%増加しており、また、冷房使用に伴う排出量は50%増加していると試算される(第1-1-4図)。
家庭からの二酸化炭素排出量が増えている背景の一つには、家庭で使用される電気製品や自動車等エネルギーを消費する耐久消費財の大型化、高級化、大量普及がある。例えば電気製品については省エネルギー技術の発達によって一台一台のエネルギー消費量は第一次石油危機当時に比べかなり低下してきているが、近年は下げ止まり傾向にある(第1-1-5図)。その一方で、家庭への普及は著しく、例えば、冷蔵庫、エアコン、カラーテレビを2台以上所有している家庭も増加してきており、「一家に一台」から「一人に一台」といおう傾向が強まっている(第1-1-6図)。また、エネルギー使用量の多い大型のものや高性能のものが選好される傾向にある(第1-1-7図)。特に、こうした家電製品の大型志向、複数保有志向は所得階層が上がるほど、つまり暮らしに余裕ができるほど高まる傾向がある。国立環境研究所の調査では、高所得者世帯ほど冷蔵庫でも300l以上、テレビでは20インチ以上など大きな物が使用され、また、ビデオデッキなど常に電源をいれておくものが使用されるなど、エネルギー消費量が多くなることが示される(第1-1-8図)。一方、乗用車についても全体的に、大型で排気量の多いものが選好されている(第1-1-9図)。技術によって一台一台の機器から生ずる環境負荷量が削減されても、大量消費、大型・高級志向という我々のライフスタイルの選好によってその効果が打ち消され、全体としては二酸化炭素排出量が増大するパターンが出来上がっていると言える。
このような傾向は、消費者の嗜好にも影響されるが、様々な経済的な要因にも左右されている。乗用車について見れば、バブル期には実質可処分所得の伸びの高まり、資産価格の上昇による資産効果に支えられ、乗用車の購入も進み、排気量2000cc以上のいわゆる3ナンバー車の保有率が上昇するなど大型化が進んだ。また、税制改革による物品税廃止、自動車税の税率の見直し、自動車保険料率の軽減等によって相対価格が有利になるという要因も働いた。(社)日本自動車工業会の調査によれば、3ナンバー車に対して、税制改革で身近になったとする人は2500cc車については4割以上、3000cc車については3割以上となっている。
また、その他の背景としては、より快適な生活を求めてエネルギーを消費する耐久消費財の使用方法が変化している状況も見られる。(財)省エネルギーセンターの調査によれば、冷房温度の設定温度を28度以上にしていた家庭は平成4年度には48.3%、平成5年度には39.4%となっている。照明についても、インテリアデザイン的に螢光灯よりも電気消費量の多い電球が好まれたり、高齢化社会への対応、視環境の快適さを求めて明るい照明が多用されるなどの傾向がある。
(2) 廃棄
日常生活で不用とされたものはごみとして排出される。一人一日当たり排出量を見てみると、昭和61年の1,007gから平成3年には1,118gへと増加している。廃棄物の処理に当たっては、焼却過程における二酸化炭素、窒素酸化物の発生、埋立による自然の損失や最終処分場からの排水などの環境負荷が生じる。また、廃棄物の質も多様化しており、プラスチック等自然の中で分解されにくい物質が増加するとともに、家庭からのごみの中にもフロンを冷媒として使用している冷蔵庫、PCBを絶縁体として使用している家電製品や水銀電池等処分の方法によっては環境負荷を与える製品が含まれている。
次に、どのようなものが廃棄物として捨てられているのか、京都市における家庭ごみの組成調査の結果を参考に考えてみたい。京都市でもごみの排出量は増加しており、一人一日当たりの家庭ごみの排出量は、昭和56年度には551gだったものが平成4年度には622gになっている。ごみの内容を見てみると、厨芥類、紙類、プラスチック類の3種類で約8割を占めている。特に、近年消費量が増加している紙類、プラスチック類は、ごみとして排出される分も多く、昭和56年度に比べ、紙類の量は2割近く、プラスチック類の量は4割近くへと増加している。また、使用されていた用途別に見ると、食料品は約4割、容器・包装類は約2割を占めている。昭和56年度と平成4年度を比べると、容器・包装類の量は5%、商品だったものの量は6%、ダイレクトメール等広告に使われたものは4割以上、「時間と手間を節約できる便利な商品」の紙おむつや使い捨てライター等の使い捨て商品の量は8割近く増加している(第1-1-10図)。
厨芥類の内訳を見てみると、4割近くが食べ残しであり、14%の食品が手つかずのまま捨てられている。野菜や果物がそのまま捨てられている以外に、調理食品や加工食品類がパックされたまま捨てられているケースも多い。厨芥類の量は、昭和56年度に一人一日当たり262gだったものが、平成4年度には244gとやや減少しているが、調理済み食料の普及や外食化により調理くずの占める割合が59.8%から52.9%へと減少する一方、食べ残しは27.8%から37.5%へと上昇している(第1-1-1表)。
調査結果から見ると、家庭からのごみの内訳は、食べ残しの増加、商品の消費と廃棄サイクルの短期化、容器・包装類の増加といった我々の消費生活をそのまま反映したものとなっている。このようなライフスタイルから生じるごみの質、量の変化が環境への負荷を大きくする要因となっている。
(3) 水まわり
日常生活においては、台所、風呂、洗濯、水洗便所等で水が使用され、生活排水として排出されている。これらの排水中には、様々な有機物や栄養塩類が含まれており、海や河川、湖沼における有機汚濁や富栄養化を引き起こす原因の一つとなっている。生活排水による負荷は、これらの原因の大きな割合を占めている場合が多く、例えば東京湾について見れば、水域全体の汚濁負荷量(COD)に占める生活排水からの割合は69%(平成元年度)、また燐で見ると58%(平成元年度)を占めている。
日常生活からの水質汚濁負荷発生状況(BOD)を環境庁調査により見てみると、し尿が30%(BOD13g)、それ以外の生活雑排水が70%(BOD30g)となっている。し尿は衛生的な処理が法律上義務づけられており、直接環境中に排出されないため、家庭から直接に環境中に排出される実際の水質汚濁負荷量としては生活雑排水がはるかに大きくなっている。生活雑排水の中では、台所からの負荷が57%、風呂からが30%、洗濯等からが13%となっている。台所からの負荷が大きいのは、台所で使用、排出される調味量や油脂等に汚濁負荷量が大きい物が含まれているためである。これらを用いた食料品を直接排水口に流してしまうと水質に大きな汚濁負荷をかけることになる(第1-1-2表)。
また、風呂や洗濯からの水質への負荷は、洗剤やシャンプー等の要因がある。近年、清潔志向が高まっていると言われており、例えば、最近では、洗濯も「汚れたから」ではなく、「着用したから」という基準で行われる傾向が見られる(第1-1-11図)。またこうしたことから洗濯用洗剤の販売量も増加している(第1-1-12図)。
洗髪については、若い世代を中心に毎朝シャンプーする習慣が広がったこともあり、シャンプーの販売量は近年増加し、現在は横這いになっている。シャンプー1回(使用量12ml)のBOD負荷量は1.8gで、コンパクト洗剤(使用量25g)で1回洗濯をした時のBOD負荷量2.4gの4分の3に該当するという試算もある。清潔志向の高まりによって我々自身の生活はきれいになってきているものの、水質への負荷は増加しているといえる。
(4) 居住と交通手段の利用
都市における交通は、居住環境と人々のライフスタイルと密接不可分な関係にある。以下では、我が国における都市の土地利用の変化、それに伴う交通手段の選択の変化と環境への負荷について見てみたい。
我が国の居住の状況を見てみると、地価の高騰やモータリゼーションの進行に伴い、市街地の低密度拡散傾向が進んでいる。全国の人口集中地区(DID)について見てみると、昭和35年(1960年)には面積約3900km
2
、人口密度約10.6千人/km
2
だったものが、平成2年(1990年)には面積約11700km
2
、人口密度約6.7千人/km
2
と、30年間で面積が3倍に増加した一方、人口密度は約63%に低下している。市街地の低密度拡散傾向は、地域的に見れば地方中核都市で特に大きい(第1-1-3表)。このような市街地の拡散動向を地方中枢都市についてランドサットデータにより見たものが第1-1-13図である。
また、大都市圏について、昭和60年〜平成2年の人口増減率を距離帯別に見てみると、東京圏、大阪圏では0〜10km帯の人口が減少し、10〜20km帯の人口増加率がそれぞれの50km圏全体の増加率を下回っている。また、名古屋圏でも0〜10km帯の人口増加率が50km圏全体の増加率を下回っている。一方、最も人口増加率の高い距離帯は、東京圏が40〜50km帯、大阪圏が30〜40km帯、名古屋圏が20〜30km帯となっており、いずれの50km圏でも中心部の人口が減少ないし停滞し、周縁部において人口が増加する、いわゆるドーナッツ化現象が見られる。東京圏では、昭和50年代後半には、中心部の人口減少に歯止めがかかり、ドーナッツ化の進行が鈍化したが、バブル期の地価高騰を背景に60年〜平成2年に0〜10km帯の減少率が6.9%と再び大きく上昇している。大阪圏においても1980年代には鎮静化していた中心部の人口減少がバブル期に再び大きくなっており、地価の高騰が人口の郊外化を進めた様子がうかがえる。
このように郊外に居住する人の増加と相まって、利用交通機関も変化してきている。郊外部では、都市中心部に比べ公共交通機関のサービス水準が低いため、自動車交通の役割が相対的に大きくなる傾向が見られる。我が国では、昭和30年代半ばから自動車保有台数が増加しており、国際的に見ても、我が国の自動車普及率はアメリカには及ばないもののすでにヨーロッパ諸国とほぼ同じ水準に達している。この傾向は全国的に見られるが、公共交通機関のサービス水準の低い地方圏においてより一層進行している(第1-1-14図)。また、日常の生活でも、教育、医療、買い物、余暇活動等について自動車を利用する機械が増加している。自動車の一人ひとりの使用状況を見てみると、通勤・通学目的の利用が減少し、買い物・用足し、レジャー目的の利用が増加する傾向にある(第1-1-15図)。人口の郊外化とともに、道路交通の便利な郊外に大規模駐車場を設けたショッピングセンターが増加するなど、これらの活動も広域化、郊外化しており、自動車の利用に一層依存する結果となっている。我が国の場合ショッピングセンターは昭和40年代半ばまで中心商業地に立地していたが、道路交通、駐車場確保等の容易さ等から郊外化が進み、特にここ数年の郊外立地件数の伸びは急激で、平成3年度では7割強が郊外への立地となっている。
次に、自動車など我々が日常生活の中で用いる各種交通機関と環境との関わりを考えてみよう。自動車などの交通機関は、移動時間を短縮し、便利で快適な生活をもたらす一方で、走行中に騒音、振動といった環境影響を生じさせるとともに、燃料の燃焼にともなって、地球温暖化の原因となる二酸化炭素、呼吸器に影響を与えたり酸性雨の原因となる硫黄酸化物や窒素酸化物、光化学スモッグの原因となる窒素酸化物、炭化水素等を排出している。
運輸部門からの二酸化炭素排出量は、平成3年度には、我が国の排出量の全体の19.0%を占めている。同部門では過去からの増加傾向が続いており、環境庁の試算によれば、同部門全体で、前年度に比べ、2.6百万トン、対前年比4.5%の増加と、輸送量の増加率(対前年比2.5%)を上回る水準となり、二酸化炭素の排出量は引き続き増加している。
窒素酸化物、硫黄酸化物及び炭化水素については、規制の強化と技術開発により、同じ燃料を使用した同一クラスの自動車一台ごとの排出量は減少してきている。例えば、環境庁調査によれば、乗用車が時速15kmから25kmで1km走行する際の窒素酸化物排出量は、昭和48年の2.28gから平成2年には0.34gへと低減している。その一方で、先に見たように、自動車の普及は著しく、総走行距離も大幅に延びている(第1-1-16図)。窒素酸化物については、第4章第1節に見るように、自動車交通量全体の増加と、その中でのディーゼル車の比率の増加などが、自動車一台ごとの排出ガス浄化の効果を相殺し、東京特別区、横浜市や大阪市といった大都市圏総量規制地域では環境基準の達成状況は依然低い水準で推移している。ディーゼル車の増加の背景には、ディーゼル車の燃料の軽油がガソリンに比較して安価であるためなどの理由があり、平成5年3月には、貨物車ではディーゼル車が全体の70%以上を占めている。近年、オフロードタイプの四輪駆動車人気から、乗用車においてもディーゼル車は増加しており、平成5年には対前年比で13.4%増加している。
また、交通機関の利用は、その都市の規模と密接に関連しているが、地域の交通構造の特性を、3大都市圏、地方中枢都市、地方中核都市ごとに見てみよう。
首都交通圏、中京交通圏及び京阪神交通圏の大都市圏においては、高度の人口集積を背景として高速鉄道網の整備が進んでいるため、年間旅客輸送人員のおおよそ7割以上を高速鉄道が担っており、人流体系全体としては効率性が高いが、自家用乗用車による輸送人員の伸びが大きく、昭和50年(1975年)から平成3年(1991年)の間に各交通圏とも概ね2倍となっている。旅客の自動車と鉄道の分担率を見ても、同期間中に例えば首都交通圏では19%から30%まで増大している。
札幌市、仙台市、広島市、福岡市の地方中枢都市における通勤・通学時の利用交通手段について見てみると、鉄道・バス等の公共交通機関の占める割合は概ね30%前後、自家用車が概ね40%前後を占めており、公共交通機関のサービス水準の高い大都市圏と同サービス水準の低い地方圏との中間的な性格を有している。また、近年、札幌、仙台、福岡において地下鉄の運用開始ないし延伸が進んでいる(第1-1-17図)。
金沢、岡山等の地方中核都市における通勤・通学時の利用交通手段について見ると、公共交通機関の占める割合は、大都市圏や地方中枢都市に比べて相対的に低くなり、概ね15%前後であり、逆に自家用車の占める割合は高くなり40%から57%程度となっている。
(5) レジャー
近年、所得水準の向上、労働時間の減少に伴って、「自由時間」が生活の中での重要性を増している。総理府の「国民生活に関する世論調査」によれば、レジャーや余暇生活に今後の生活の力点を置きたいとする国民の割合が高くなってきている。
自由時間の使い方には様々なものがあるが、(財)余暇開発センターの調査によれば、最も参加希望率の高いレジャーは国内観光旅行(76.2%)であり、また、ピクニック、ハイキング、野外散歩といった自然とのふれあいを求めるものも40%の人が参加を希望している。オートキャンプ、スキーといったアウトドアでのレジャーやスポーツは、近年参加率が上昇しており、今後も伸びていくことが考えられる。
このように国民の求めるレジャーは自然を活動の場とするものが多く、自然とのふれあいによる豊かな人間性の形成、自然への理解の深まりなど得られる価値も大きい一方、適切に行われない場合には、レジャーのための施設の整備やレジャー活動そのものによる自然環境への影響も懸念される。リゾート開発については、国民の余暇意識の高まりと地方公共団体における地域振興への期待を踏まえ、バブル経済時のいわゆる金余り現象の中で多くの企業がリゾート産業へ出資したことから、昭和60年代以降次々とリゾート施設の整備が進んだ。リゾート開発は「良好な自然条件を有する土地」で行われることが多く、適切な環境配慮がなされない場合には、施設整備に伴う自然への影響も懸念された。例えば、林地のレジャー施設用地への転換が進んだが(第1-1-18図)、森林がゴルフ場に変わった場合を考えてみると、森林の持っていた水源かん養機能の減少(第1-1-19図)を始め、土壤保全、大気汚染物質の吸収、野生生物の生息地の提供といった環境保全に資する様々な機能を消失させ、あるいは減少させてしまうことが懸念される場合もある。
しかし、リゾート開発の中にはバブル期に過大な需要見込みに基づいて計画されたものもあり、バブル崩壊後、ゴルフ場開設数も減少しており(第1-1-20図)、計画中の事業から撤退するケースも多い。リゾート法上の基本構想に基づくリゾート開発・整備についても事業の中止、大幅な遅延が見られ、総務庁が行ったリゾートの開発・整備に関する調査では、昭和63年及び平成元年に基本構想の承認を受けた9県のうち、平成4年7月現在で基本構想に位置づけられたスポーツ施設やレクリエーション施設等の特定施設のうち83.3%は工事未着手となっている。環境配慮の観点からは、施設を整備する事業主体が自主的に環境影響評価を実施している場合もある一方、ゴルフ場の開発により、水道等の水量・水質に直接影響が及ぶとして隣接町から申し出のあった異議について、隣接町との協議が整わず、これが一因となって事業の見通しが立っていないものや、民間が設置する施設の整備に当たって、環境保全上の懸念から関係者との調整が進まず、事業着手に至っていないものもいくつかある。こうした中、地方公共団体においては、ゴルフ場やスキー場などのレジャー施設の環境影響評価のための要綱等の制定が相次ぎ、平成元年以降20以上の都道府県がこのような要綱等を制定している。
一方、自然の中でのレジャー活動については、国民のアウトドア志向が高まり、多くの人が参加する状況にある。特に、自然公園等自然の豊かな地域の利用者は年々増加しており、一方では従来から、休暇の取り易い特定の時期、一部の有名観光地に利用者が集中する傾向がある。例えば、本州最大の湿原を有する日光国立公園の尾瀬地域では、平成4年度には前年度より6.9%多い539,790人が入山した。入山者が集中するのは、水芭蕉の咲く6月、夏休みの時期であり、この3カ月に利用者の約7割が集中している。また、土曜日及び日曜日に利用者の5割以上が集中している。このような集中は、混雑のため快適な利用環境が阻害されるという問題の他に、自然環境にも様々な影響を及ぼす。生活排水の増加も、脆弱な湿原にとっては大きな負荷となり、植生の変化などの影響が生じているところもある。そのため、近年では各施設への合併処理浄化槽の設置や浄化槽処理水を更に湿原の外部まで搬送するパイプラインの整備が進められており、一部では供用を開始している。木道の整備率も低く利用マナーも徹底されていなかった時代には利用者の踏みつけにより湿原の植生が破壊され「裸地化」したところもある。こうした場所については、植生復元事業や利用者への自然利用に関する普及啓発、利用者のマナーの向上、利用規制などによってかなり植生が回復してきたところもあるがまだ完全ではない。
また、近年レジャー用に四輪駆動車やモーターボート等動力付きの乗り物の普及が進んでおり(第1-1-21、第1-1-22図)、自然の豊かな地域などでの利用が盛んになっている。動力付の乗り物による利用は、騒音の発生源となったり、植生の破壊や野生生物への脅威となるなど自然環境に影響を及ぼす例もみられる。このため、平成2年以降、国立公園又は国定公園の特別地域のうち環境庁長官が指定する区域において、自動車やモーターボート等の使用、航空機の着陸が規制されることとなり、平成5年度末までに18の国立・国定公園の26地域、136,680haを乗り入れ規制地域に指定し、パトロール等が行われている。