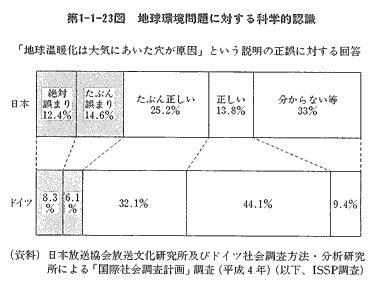
3 日常生活から生じる環境負荷に対する国民の意識
これまで見てきたように、我々のライフスタイルがより便利で快適なものになる一方で、家庭からの環境負荷はその量及び質の面で大きく変化してきた。物質やエネルギーの大量消費、大量廃棄に伴って環境負荷の量は増加し、また、家庭から排出されるごみの中にも水銀電池等有害化学物質を含んだものがあり環境負荷の質も影響力の大きいものとなってきている。こうした中、国民の間にも日常生活が環境に影響を与えているという認識が高まってきている。
ここでは、国民の環境保全意識と行動の実態について、ドイツ社会調査方法・分析研究所、国立環境研究所、日本放送協会放送文化研究所が実施した調査結果を見てみよう。
まず、環境問題に関する科学的な知識についてみると、我が国では、正しい知識を持っている人が多い一方、ドイツと比較するとわからないと答える人も多い(第1-1-23図)。関心のある人は知識を深めているのに対し、関心のない人は知らないという二極分化傾向が見られる。
また、日常生活に伴う環境負荷を減らしていくためには、我々自身が現在のライフスタイルを見直していく必要があるが、現在の生活を変える必要性についての認識は高まっており、生活を余り変えなくても、科学が環境問題を解決してくれるだろうという楽観論に対してはドイツと比較しても否定的な見方が強い(第1-1-24図)。
一方、認識と実際の行動状況を見てみると、例えば、自動車の排気ガスが環境にとって危険だと考えている人は多いが、自動車の運転を減らしている人は少ない(第1-1-25図)。また、家庭からの廃棄物を処理する場所の確保は最も深刻な問題の一つになると考えている人はかなり多いが、ドイツと比較するといつもリサイクルのための分別を心がけている人は少ない状況にある(第1-1-26図)。また、より積極的な講堂として、自ら環境保護団体に参加している人や、環境保護団体に寄付したことのある人はドイツと比較すると約半分程度に止まっている(第1-1-27図)。こうしたことから、我が国においては、環境問題に対する認識は高まってきており、現在のライフスタイルを変える必要性は分かっているものの、まだ認識と行動が一致していないという傾向が見られる。また、より積極的な行動については躊躇する人が多い。認識と行動の不一致については、第2節でさらに分析してみたい。