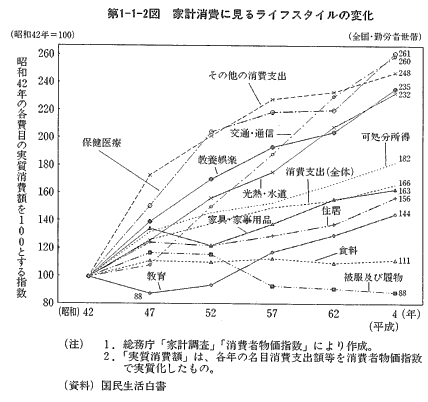
1 消費生活から見た生活行動様式の変化
今日までのライフスタイルの変化を知るため、この25年間の家庭における消費動向を見てみると、消費支出全体は25年前の約1.6倍に増加しており、特に、保険医療費及び交通・通信費は約2.6倍、教養・娯楽費及び光熱・水道費は約2.3倍、また、家具・家事用品への支出は約1.6倍と増加している(第1-1-2図)。特に自家用車の普及に伴う自動車関係費、耐久消費財の大型化・高級化に伴う支出の増加、エネルギー使用の増加に伴う光熱・水道費の増加など、国民の利便性の追求、快適志向がうかがわれる。また、教養・娯楽費の中では、宿泊・パック旅行の増加が著しく、国民の余暇志向の高まりが感じられる。
生活時間の使い方の変化を見てみると、まず労働時間については、平成元年4月から一部の職場を除いて労働時間の週44時間制が実施され、年間総労働時間は昭和63年の2111時間から平成3年には1958時間へと減少傾向にある。こうした労働時間の減少や家事の省力化に伴いテレビを見たり新聞を読んだり、レジャー活動を行ったりする自由時間が増加しており、日本放送協会の生活時間調査を基に昭和60年と平成2年の自由時間を比較すると、平日では3時間51分から4時間7分へ、土曜では4時間39分から5時間8分へ、日曜では6時間8分から6時間22分へと伸びてきている。
生活のリズムを見てみると、同調査によれば、夜11時過ぎまで起きている人は昭和55年には24%であったのが、平成2年には39%、夜12時過ぎまで起きている人は8%から13%へと増加し、夜型に変化してきている。
こうした生活の志向や習慣は、例えば利便性や快適性の追求により自動車利用が増加したり、自由時間の増加によりレジャー活動が活発化したり、生活リズムの夜型化により照明用エネルギーの使用量が増加したりするように、環境負荷と密接な関係を持っている。近年の生活の志向や習慣の変化により、環境への負荷がどのように変化してきたのか、以下ではより具体的に考えてみたい。