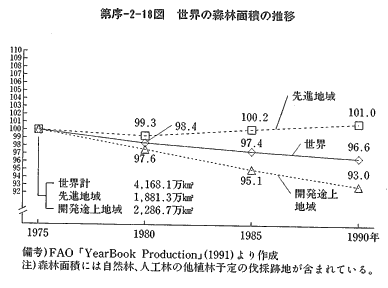
4 森林資源の循環等
(1) 世界の森林資源の現状と我が国への木材の流れ
森林資源は、地球上の熱収支、水収支に深い関わりを持ち、地球の環境を生物の生息に適した状態に保つとともに、野生生物に生息地を提供し、水源をかん養し、また、人間の生活に欠かせない木材を供給するなど多面的な価値を持つ自然資源である。森林資源は本来的には再生可能な資源であるが、この再生の過程は資源の循環になぞらえることができよう。ここでは、近年の経済社会活動の進展により特に熱帯林を中心に危ぶまれる森林資源の循環を考察するために、まず、世界の森林資源の現状と我が国への木材供給の流れを見てみたい。
世界の森林面積は1990年(平成2年)現在で約4,028万km
2
存在していると見積もられている。これは陸地面積の約3割に達する数字である。先進国には森林面積の約5割が存在し、うち9割が米国、カナダ、旧ソ連に存在している。他方、開発途上国に存在する森林は近東・極東555.9万km
2
、中南米892.8万km
2
、アフリカ635.1万km
2
、その他43.9万km
2
となっており、総計の2,127.7万km
2
は世界の森林の約5割強を占めている。近年、先進国では森林面積がほとんど変化していないのに対し、途上国ではその減少が著しい(第序-2-18図)。
熱帯林を保有する熱帯地域の開発途上国では、森林の持続可能な経営が確立されていないことにより森林の減少、劣化が進んでいると考えられている。詳しくは第4章で述べるが、FAO(国際食糧農業機関)の調査によれば、熱帯地域の開発途上国において1981年(昭和56年)から1990年(平成2年)の間、毎年15.4万km2の割合で熱帯林が減少している。これは、およそ我が国の国土面積の約4割、同じく森林面積の約6割に相当する面積である。熱帯地域での森林減少の原因については、?非伝統的な焼畑耕作、?過度の薪炭材採取、?不適切な商業伐採、?過放牧等が指摘されている。その背景には、人口増加、貧困、土地制度等の社会経済的な背景など様々な要因が指摘されている。湿潤熱帯で森林が消失する最大の原因は計画的・非計画的な農地の転用であり、持続的な農業の失敗が大量の荒廃地を生みだしたと考えられ、また、焼き畑や盗伐等の社会的障害も理由に挙げられる。また、熱帯林減少の過程において、市場性のある少数の財貨の獲得に集中し、森林の存立がもたらす様々な便益が低く評価されるとともに、森林伐採と多目的用途への転用の利益が誇張される反面、それに伴う社会的費用が無視されてきたといわれる。さらに、多くの途上国は、一次産品価格の低迷、貿易収支の悪化、累積債務の増大という問題を抱えているため、外貨獲得の手段として環境への適切な配慮がなされないまま資源開発を進めることが乱開発につながっている面があるとの指摘もある。
森林の「持続的」利用については、開発途上国の熱帯林に関してだけではなく、先進国の温・寒帯林においても問題になっている。米国北西部では、「絶滅のおそれのある種」に指定されたマダラフクロウの保護のため、国有林における立木販売を一時中止する判決が連邦地裁より出されている。ワシントン・オレゴン両州の国有林の1992年(平成4年)の伐採量は、1988年(昭和63年)と比較してそれぞれ約7割、6割減となっている。また、カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州ではここ数年過伐で推移してきたが、現在許容量の見直しが行われているところである。
次に、木材に関する我が国と世界との関わりについて、我が国の用材供給の現状について見ると、その供給量は丸太換算で10,849万m
3
であり、このうち約4分の3を外材に依存している(第序-2-19図)。地域別では、米国から3割弱、カナダから約1割、マレイシアから約1割、インドネシアから5%弱、この他オーストラリア、チリ等世界各地から木材を輸入している。
近年、産地国における自然保護の強化、また熱帯林の減少及び熱帯林産地国における加工産業の育成などによって、丸太輸入の減少、製材品、合板等木材製品輸入の増加という傾向が見られる。北米から輸入される米材については、米国からの輸入は平成元年を境に丸太・製材とも減少に転じている一方、カナダ産の製材輸入は、昭和59年以降増加傾向にある。東南アジア、オセアニアの熱帯林保有国からの熱帯材(南洋材)輸入は、1960年代はフィリピンを主要供給国としていたが、同国での資源の減少、国内加工産業の育成が進んだため、1971年(昭和46年)にはインドネシアがフィリピンに代わる最大の供給国となった。インドネシアでは、国内の合板産業を振興することもあって1985年(昭和60年)には丸太輸出が全面的に禁止され、1980年代後半には我が国熱帯林丸太輸入量のうちマレーシアのサバ、サラワク両州が90%程度を占めるようになった(第序-2-20図)。また、輸入南洋材の種別の推移について、丸太、製材、合板の輸入量を見てみると、1975年(昭和50年)にそれぞれ、1,750.7万m3、12.1万m3、3.6万?、であったものが、1991年(平成3年)には、1,016.8万m3、118.6万m3、43,352.9万?となっており、丸太から製材、合板へと輸入南洋材の種類が移行してきていることがわかる(第序-2-5表)。
(2) 環境への影響
森林の減少に伴って、地域レベルから地球レベルに至る環境への影響が懸念される。まず、一地域の木材資源への過重な依存は、適切な配慮がなされない場合には、地域的な環境悪化を招く可能性もあろう。木材・薪炭材等の資源の不足、洪水・渇水の発生等は、地域社会の安定的発展を阻害することも考えられる。また、地球規模での影響としては、生態系への影響が考えられる。生物種数がどのような影響を受けるかについての推定のうち、Reid & Miller(1989)では、FAOの森林資源評価による熱帯林減少の推計値と生物種数及び生息面積の関係を示すものとして用いられている「種−面積曲線」とを用いて、1990年から2020年までの間に、全世界の生物種の5%から15%が絶滅すると予測している。全世界の生物種数を未知のものも含めて約1000万と仮定すると、一日当たり50〜150の種が絶滅していることになる。
一方、森林の減少は土壤に対する劣化も引き起こす。森林減少が原因となって生じた土壤劣化の面積は、全世界で578億km
2
で全劣化面積の30%を占めている。森林減少による土壤劣化の要因としては、植生の被覆がなくなることによって表土が侵食されやすくなることが第一にあげられるが、新たな植被が定着した場合でも、栄養循環などの面で植生と土壤の間で平衡状態が確立されるまでの間に、土壤劣化が進行しやすい。
さらに、地球温暖化への影響も懸念されている。先進諸国では既に農耕地化が進み、森林面積の減少は少ないが、熱帯地域の開発途上国における急速な森林の減少によって、蓄積されていた大量の二酸化炭素が大気中に大量に放出され、地球温暖化を加速させる一因となっているとの指摘もある。また、森林は、注がれた太陽エネルギーの約3割を大気や土を暖めるために使い、7割を植物の葉から水を蒸散させるのに使うとされている。このような蒸散作用を通じて穏和な気候条件を作る働きが森林にはあるが、大規模な森林減少は、地球規模で気温、水のバランスにも影響を与えることが懸念される。IPCCによると年間約6億から26億トンの炭素が森林の減少により放出されており、これは、石油や石炭などの化石燃料の燃焼の放出量の30〜40%に相当するといわれている。
以上のような地球レベルでの森林減少による環境への影響の他、現在の木材の利用形態の中には環境への影響が懸念される一面もある。例えば、廃木材の排出は、ゴミ問題の原因の一つともなっている。また、紙ゴミの割合も近年増加している。廃木材については、平成2年度実績で657.3万トンの排出量があった。紙ゴミについては、重量ベースで見た時にそれほどの量とならない場合でも容積的に大きな割合を占めることに留意する必要があるが、廃木材の量に産業系の紙ゴミを加えると平成2年度実績で876.6万トンの排出量となっている。なお、一般廃棄物中の木くず、紙ゴミの量は明らかではないものの可燃ゴミ2,701.9万トンの約2〜3割程度を占めるものと考えられ、これらを合わせると木材に由来するゴミの量は千数百万トンに上ることが予想される。
(3) 森林の循環を確保する木材利用等に向けて
我が国は、世界の森林と深い関わりを持つ経済社会活動を行っており、熱帯林を始めとする世界の森林保全と持続可能な経営を達成するために世界の国々からより一層の貢献を求められているところである。
森林資源の循環を確保するためには、まず、第一に森林の保全と持続可能な経営を行うことが考えられる。これに関して、我が国の企業の中には、計画的な植林を行っている例も見られる。
第二としては、木材の有効利用を図ることにより、森林の循環の確保に貢献することもできよう。このような有効利用の一つとして、木材加工技術の推進が考えられよう。近年、熱帯産材の産出国では、これまでの付加価値の低い丸太という形態での輸出から、自国内で加工度を高めより付加価値の高い製品という形での輸出に構造を転換してきている現状にある。合板の製造技術に関しては、我が国の歩留まりが65%程度であるのに対して、途上国では50%程度であると言われており、加工技術水準の低い開発途上国に対して、関連する技術協力を行うことも有効であろう。また、間伐材や林地残材等の利用も含め、我が国における木材資源の有効活用といった取組を進めることも重要である。例えば、伐採された木材が焼却されたりして失われるまでの時間が長ければ、森林の樹木に生長する時間を与えることとなり、また木材を住宅資材等へ利用することにより伐採後も二酸化炭素を貯留し、地球温暖化の防止といった二酸化炭素の貯蔵といった観点からの有効性も期待できる。木材は、他の建築資材に比べ、生産に要するエネルギーは極めて少ない(例えば、人工乾燥製材は、鋼材、アルミニウムと比べて製造時の消費エネルギーがそれぞれ0.5%、0.1%である。)とともに、木造住宅においては炭素貯蔵量が大きいという利点を有する。我が国において木造住宅が固定する二酸化炭素量(炭素換算)については、約50kg/?との推計があり、これは、我が国の森林の材積の約2割、人工造林の約5割弱の蓄積に相当する。さらに、従来、単純に熱源としての利用に止まることの多かった廃木材についてもリサイクルにより有効に活用していくことは、環境への負荷を低減する上で有効であろう。例えば、合板の代替材としてのパーティクルボード、ファイバーボードへの再生利用や木炭の製造などが考えられる。木炭は外気に通じる多孔体構造をしており、吸着能力に優れているため、単に燃料としてではなく、汚水浄化にも利用できる。福岡県久山町では、これを全町の浄化槽に使用し、家庭排水のBODを10ppm以下に浄化することに成功している。また、木炭は土壤改良材として田畑に使われると作物の生育を助けるといった利点も有する。木タールについては、有効成分が医薬品として使用される他、タイヤへの添加剤などとしても用いられている。今後、こうした方面での木材の有効活用も進められよう。
廃木材のリサイクルを進める上での問題点としては、?建物解体における機械依存の高まり等による木くずのごみ化の進行、?原料としての木くずの供給不安定、?技術開発の立ち遅れ、?処理費用の負担を伴う再生資源の利用は処女資源より経済的に不利であること、?木材だけを区分することが困難なことなどが考えられる。これらの課題を解決し、リサイクルを進めるために、処女資源と再生資源が適切に配分利用される施策に加え、使用する側における積極的な協力など利用率向上を図ること等を検討することは有効であろう。
環境庁では、情報化の進展に伴う紙需要の増加に対処しつつ、紙の有効利用の重要性に鑑み、非木材繊維の活用という観点から「森林保全のためのケナフ等代替資源利用検討委員会」においてケナフ等のパルプ代替資源利用のための予備的な研究及び評価を行った。それによると、成長速度が速いことなどからケナフも紙の原料として有効であることが明らかとなった。紙を有効に利用し、使用した紙のリサイクルを進めるような努力に加え、今後このような原料の有効活用も重要であろう。