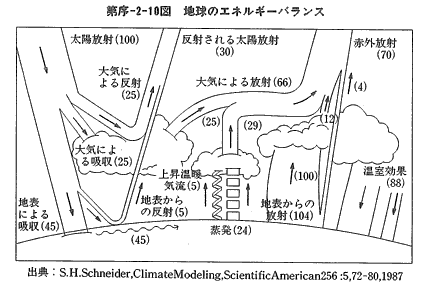
3 エネルギーの循環等
(1) エネルギー循環等と利用の概況
地球上では、太陽によりもたらされるエネルギー(入射太陽放射)、地球の持つ熱流、月による潮汐摩擦などによりエネルギーが複雑に関連して大きな流れをなしている。第序-2-10図は、地球に注がれる太陽エネルギー量を100とした時の、大気・地表系のエネルギー・バランスを示したものである。入射したエネルギーのうち30は雲などによって直接反射され、雲等を通過して地表面に吸収されるのは、約5割程度である。これに対して、地表から放射されたエネルギーは、雲等によってとらえられ、その大部分が地表に向かって再放射されていることがわかる。すなわち、大気、雲は太陽からの入射線は比較的簡単に通過させるが、地球からの熱放射はなかなか通さず地表に再放射して、地球を暖めている。このメカニズムにより、地球は生物の生存に適した温度に保たれている。一年間に太陽から地球に6.55×10^20(10の20乗)キロカロリーのエネルギーが降り注いでいると考えられている。また、全世界で一年間に消費するエネルギーは、約7.13×10^16(10の16乗)キロカロリーである。このようなエネルギー消費は地球の複雑で精妙なメカニズムに作用しているのである。では、現在のエネルギー消費の形態はどうなっているだろうか。
まず、世界の一次エネルギーの動向を把握するため化石燃料等の生産量及び消費量の動きをみてみよう。第序-2-11図は、各地域で生産される化石燃料が貿易を通じてどこから運ばれ、どこで消費されるかを算出したものである。1990年をみると、まず北米では、1906MTOE(石油換算百万トン)の一次エネルギーを生産し、2116MTOEの消費を行っている。人口一人当たりの消費量では、7.64TOE(石油換算トン)と群を抜いている。欧州では、2704MTOEの生産に対し、3099MTOEの消費を行い、一人当たり3.67TOEとやはりエネルギー消費は高水準にある。アフリカでは、511MTOEのエネルギーを生産し、219MTOEを消費しているが、一人当たりでは0.42TOEとさらにエネルギー消費の水準は低い。豪州では、170MTOEの生産に対して102MTOEの消費であり、一人当たりの消費量は5.1TOEと高水準である。中東は、962MTOEと生産水準は高いが消費は238MTOE、一人当たりでは1.82TOEとその水準はそれほど高くない。我が国は、69MTOEの生産に対して、428MTOEの消費と生産に比べ消費が圧倒的に大きく、人口一人当たりのエネルギー消費量は、3.45TOEと北米との比較では半分以下であるものの開発途上国に比べ依然高水準である。我が国を除いたアジア地域では、1146MTOEの生産に対して1173MTOEの消費、一人当たりでは0.43TOEである。図の矢印に従って化石燃料が行き来しているが、このように、エネルギーの生産と消費の間、また一人当たりの南北間の消費量には著しいかたよりがあることがわかる。
次に我が国のエネルギーの利用の状況をエネルギーフローでみてみたい(第序-2-12図)。我が国が輸入した燃料から発生させた熱の半分以上は未利用のまま環境中に捨てられている。エネルギーロスは、発電用では、62.5%、民生用では38.8%、運輸用では75%、産業用では40.6%となっている。一次投入エネルギーのうち有効に利用されているのは34%に過ぎず66%が排熱の形で直接環境中に捨てられている。この効率の低さは、高温に始まって常温の熱で終わる「熱」を有効に利用し尽くしていないことに原因を求めることができよう。例えば、ガソリン自動車などは、アイドリング状態なども勘案すると有効に活用されているのはエネルギーの20%以下であることや25℃の室温を得るために千数百度という熱を用い、排熱として出される数百度の熱を利用していないことなどによる。
(2) エネルギー利用に伴う環境問題
エネルギーの利用に伴って、各種の環境負荷が生じ、環境汚染問題を引き起こしている。化石燃料の燃焼は、様々な大気汚染物質を排出する可能性を持っている。我が国では、まず、石炭や石油の燃焼に伴い発生するばいじん(黒煙、すす)による大気汚染がエネルギー利用による環境問題として顕在化した。粒径が大きなばいじんは、降下ばいじんとして地上に降下し、その汚染状況は昭和30年代から40年代の前半にかけて深刻な状況にあった。また、粒径が10ミクロン以下のものは、気道又は肺胞に沈着して呼吸器に影響を及ぼす可能性があることから、浮遊粒子状物質として環境基準が定められているが、その達成状況は低い。石炭、石油等、硫黄分を含む化石燃料は、燃焼に伴い硫黄酸化物を発生する。1960年代に重化学工業を中心とする鉱工業活動がエネルギー消費を増大(10年間で3倍)させつつ急速に拡大したが、エネルギー需要増の大部分は石油であり、深刻な硫黄酸化物による大気汚染にみまわれた。また、高温燃焼による空気中の窒素ガスの酸化(燃焼)、燃料中の窒素分の燃焼により窒素酸化物が発生する。この他、燃料の不完全燃焼に伴い発生する一酸化炭素や、窒素酸化物及び炭化水素を原因とする光化学オキシダントによる大気汚染も、エネルギーの利用に伴い発生する地域的な大気汚染問題である。
化石燃料の燃焼等に伴って発生する硫黄酸化物、窒素酸化物は、酸性雨の原因物質の一つとされており、化石燃料の質と消費量とに密接に関係している。我が国では、被害は顕在化していないが(第4章参照)、今後、エネルギー需要の急増が見込まれる開発途上国でも被害の深刻化が懸念されている。
都市においては、エネルギーが高い密度で消費されている。これに加えて、都市の多くはアスファルト、コンクリート等の乾いた物質により覆われているため水分の蒸発による温度低下が望めず、また、緑地の場合は、蒸散により日射熱をほとんど蓄積しないのに対しアスファルト等は、日射熱を蓄積し、これを夜間に放出するため、夜間の気温低下を妨げる。この結果、都心部では郊外に比べて気温が高くなる現象が起こっている。(第4章参照)
地球温暖化は、人類の生存基盤を直接脅しかねない問題であり、その早急な対策が喫緊の課題である。地球温暖化現象は、温室効果ガスの排出や温室効果ガスである二酸化炭素の吸収源である森林の減少等様々な要因が絡み合って生じると考えられているが、人為的に排出される温室効果ガスの内、46%がエネルギー関連のものであるとの推計がある(第序-2-13図)。
(3) エネルギーの有効活用に向けて
エネルギーを有効に活用する上で、様々な観点からの方策が考えられるが、ここでは、エネルギー利用の無駄をなくすという観点から、未利用エネルギー、コージェネレーション・システム及びごみ発電について概観したい。
ア 未利用エネルギーの活用状況
都市域に供給されるエネルギーの多くが、最終的には、排熱として大気中、河川あるいは海水に放出される。こうしたエネルギーを有効に活用することも有益であろう。これらは、ごみ焼却施設、火力発電所、送変電施設、工場、下水処理場、地下鉄、地下街などさまざまな施設等から発生している。我が国では、都市ごみの焼却排熱、下水汚泥焼却排熱、下水及び下水処理水、地下鉄排熱、河川水等の利用が行われている(第序-2-3表)。
厳寒地の北欧等においては、暖房用の地域熱供給が重要な公益事業であり、未利用エネルギーが積極的に活用されている(第序-2-4表)。例えば、スウェーデン第二の都市であるイエテボリ市では、イエテボリエネルギー公社によるごみ排熱を利用した地域暖房が行われている。同市のごみ焼却プラント(年間ごみ処理量約30万トン)では欧州最大級の蒸気タービン発電機によって14,000kWの発電を行うと同時に、一部の蒸気を抽気して吸収ヒートポンプの熱源としている。吸収ヒートポンプによって排ガス処理用の40℃程度のスクラバー排熱を75℃〜115℃程度まで昇温し、地域暖房に供している。
また、米国では、夏の暑さと冬の寒さから地域冷暖房が発達している。ミッドランドコージェネレーション事業(MCV)は、アメリカ・ミシガン州ミッドランドの未完成の原子力発電所を再生し、コンバインドサイクルコージェネレーション発電所として運転するものである。設備の転換は1990年に終了し、12基の出力85MWのガスタービン発電機が、12基の蒸気熱回収器に排熱を供給し、蒸気供給側で集合され2台の蒸気タービンのいずれかにエネルギーを供給する。このような機器の組合せによって、1380MWの発電と近隣の化学品会社への蒸気供給、60MWの電気供給を可能とした。
今後は、高温の未利用エネルギー及び低温の未利用エネルギーについて、より積極的な活用が必要となろう。
イ コージェネレーション・システム
エネルギーを有効に活用するためには、熱を高温から低温まで効果的に利用することが必要である。例えば、これまでの通常の火力発電においては、発電だけの目的で燃料を焚き、熱機関を駆動して排熱は活用されなかった。一方、熱が必要な時には、ボイラを焚くというように2つの操作は独立で、並列的に行われた。高温の熱は熱機関で動力化し、温度を下げて排出された熱を熱として用いるといういわば直列的なエネルギーの利用が、熱エネルギーの合理的な使い方の第1歩である。このような方法で熱を利用をするものとしてコージェネレーション・システムがある。
コージェネレーション・システムとは、燃焼により発生する熱の高温部から発電などに用いられる動力を、また動力がつくられる際の排熱等から熱を同時に取り出すものであり、これにより熱需要と電力需要の適切な組み合わせが行われれば、一次エネルギーの70%から80%を利用することができるといわれている(第序-2-14図)。
熱を動力に変換する熱機関にもいろいろあり、高温部、中温部、低温部の熱をそれぞれの守備範囲とする3種類に大別される。熱のポテンシャルを高温から低温まで使いきるためには、それぞれの特長を生かして複合するのが望ましい。図のように、カスケード利用、すなわち複合した熱機関システムの適当の温度レベルのところから目的に応じた熱を抽出して、産業用プロセス、加熱、給湯・冷暖房などの熱としての用途に使うことを進めるべきであろう(第序-2-15図)。
コージェネレーションシステムではシステムの効率等を考慮すべき事項はあるものの、二酸化炭素を削減する効果もあり、これらの積極的な利用が望まれる。なお、NOxについても、一定の基準値を満たすシステムでは、在来型の系統からの買電とボイラで、電力と熱を供給するシステムに比べ、コージェネレーション・システムの方が総排出量が少なくなるという調査結果がある。
このように、コージェネレーション・システムはエネルギーの有効活用、CO2の排出削減の観点から極めて有効なシステムであり、今後の一層の普及が期待される。
ウ ゴミ発電
近年の廃棄物の形態は量の増大と質の多様化に特徴づけられるが、その適正な処理の確保とあわせ、排出量の抑制と再生利用の促進によるごみの減量化を促進する必要がある。減量化を図った上で、なお排出されるごみについては、最終処分としての埋立処分地の確保が困難になりつつあることからこれを焼却によって処理し、埋立の減容化を図るとともに焼却に伴って発生する余熱を積極的に回収し、有効利用する方向で、廃棄から利用への意識改革が必要な状況にあると考えられる。現在、ごみ焼却余熱を有効に活用しうるものとしてごみ発電がある。図に見るように紙、プラスチック等の増加といったごみ質の変化が、ごみ焼却時の発熱量の高カロリー化を招き、焼却炉の温度が上がり過ぎるため、一度に焼却できるゴミの量が減ることが懸念される(第序-2-16図、第序-2-17図)。
ごみの焼却による排ガスは900℃程度と温度が高いことから熱利用は容易で、かつ設備の定期検査時期を除いて安定供給されるという特徴を有しており、エネルギー利用の面から質の高い排ガスといえるため、これを積極的に活用していくことが望ましい。しかしながら、現状では燃焼ガス中の塩化水素などによるボイラチューブの腐食が懸念されるため、燃焼熱の利用は、低いレベルにとどまっている。現在のゴミ発電の状況については、ごみ焼却場は住宅地や業務用地と離れて立地している場合が多く、主に焼却施設内の給湯・暖房への排熱利用に限られていたが、隣接する温水プールや老人施設等の住民福祉施設への熱供給や発電に利用されるケースが増えつつある。4年度末現在、全国のごみ焼却施設のうち116カ所で発電を行っており、同年の最大発電出力は、約36万kwである。これらのごみ焼却施設のうち平成4年度末現在、56の施設において自家消費を越える電力を発生させており、これを売電している。
また、下水処理場との連携が図られている例もある。ごみ焼却場の排ガスからの発生蒸気又は発電電力を下水処理場で利用したり、ごみと下水汚泥ケーキの混合焼却による排熱を利用する事例も見受けられる。
現在、日本国内で行われているごみ発電は、前述のとおりごみ焼却施設から発生する蒸気が、その施設の特性から通常の火力発電所における発生蒸気よりも相当低温にならざるを得ないため発電効率は低く、ごみ焼却余熱が本当の意味で有効利用されているとは言い難い状況にある。したがって、発電効率を高め、より一層ごみ焼却余熱の有効利用が図られることが望まれる。ごみ発電の高効率化を図る方法としては、他の熱機関を利用してごみ焼却施設から発生する蒸気を高温化し、効率の高い蒸気タービン発電を行い、未利用エネルギーの活用を図るシステムが各種実用化しているところである。このような、他の熱機関を利用したごみ発電の高効率化のシステムを「スーパーごみ発電」と称している。このようなスーパーごみ発電の効果として、
(ア) 従来のごみ発電の発電効率が10〜15%であるのに対して、これを20〜25%に向上させることが可能である。
(イ) 現在、ごみ発電を実施していないごみ焼却施設にも外付けの形で事業展開が可能である。
(ウ) 熱源が二系統になるため、一方が定期点検等によりシステムダウンした場合でも、もう一方で最小限度の発電と熱の供給が可能である。
等が考えられるが、地方公共団体においてこのスーパーごみ発電を実施することにより、一層の未利用エネルギーの有効活用を図ることが可能となり、地球温暖化の防止の一助となるといえる。また、売電収入の活用により各地域における施策の積極的な展開が期待できる。