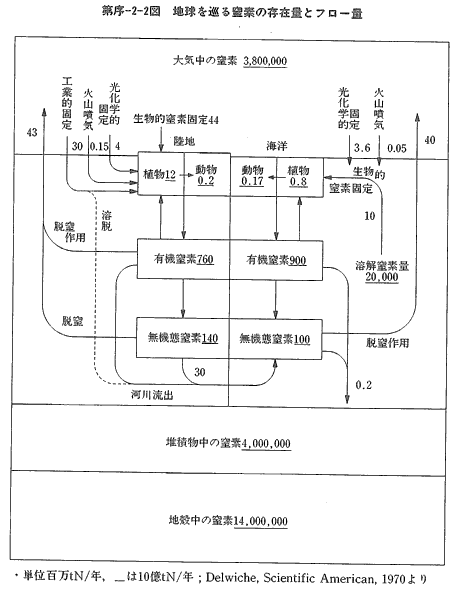
2 窒素の循環等
ここでは、まず窒素の循環を概観し、現在の循環の態様が我々の環境にどのような影響をもたらしているのかを明らかにしたい。窒素は、大気の主要成分として容積で78%をしめ、重量では、約3,800兆tが大気中に存在している。一方、地殼中には、約14,000兆tが存在する。この他、動植物の死骸等の堆積物中に4,000兆tが存在し、海水中に約20兆tが溶存しているものと考えられる(第序-2-2図)。
窒素は、タンパク質などの構成元素の一つとして生命現象を支えているが、その循環のシステムは自然界において長い時間をかけて成立したものであり、人類という生物もその延長上において生存が可能となっている。多くの生物は自ら大気中の窒素ガスを利用することはできず、ほとんどの植物は窒素がアンモニウム塩や硝酸塩などの化合物となることによって、これを利用することができるようになる。人類は、近代化以降、食糧増産のための化学肥料を考案し工業的な空中窒素固定を進めることができるようになった。生物により摂取された窒素は有機窒素に形を変え、生物から排泄される。また、生物が死んだ後に微生物によって再び無機窒素に分解されることが自然の窒素循環に見られる。窒素循環には様々な試算があるが、前出のデルウィッチによれば、生物自身による窒素固定量は、およそ5400万トン(陸上で4400万Nトン/年、海で1000万Nトン/年)、人類による工業的窒素固定は3000万トン/年であると推計されている。
まず、人類の主たる経済社会活動の場とその外部との窒素の循環をみよう。人間が使用している窒素を3つに大別して考えると、第一に、化石燃料があげられる。第二は、肥料を中心とする工業的固定、第三が衣食住、特に食料によるものとなる。これらの量的な割合は、それぞれおよそ4:2:1であると推計されている(第序-2-3図)。一方、我々が環境中に排出している窒素の量は、化石燃料の燃焼によるものが約6000万トン、廃棄物・肥料として約4700万トン、と推計され、総計で約1億700万トン/年の窒素を使用し、環境中に1億700万トン/年の窒素を排出していると考えられる。
窒素は、生態系の重要な構成元素であり、肥沃度等植物生産の重要な部分をなすとともに湖沼等の富栄養化の重要原因物質になっていることから、世界を巡るその収支がどうなっているかは、人間の生存基盤の現状を判断する重要な指標となる。
まず、国家間での貿易を通しての窒素の移動を1979年から81年にかけての食料貿易に代表させて概観したい。これによると、アメリカ大陸から世界各国に向けてきわめて多くの窒素が移動している傾向が見られる。また、アルゼンチン、フランス、オーストラリアなどは、アメリカの約1割前後の量を持ち出しているのに対し、タイからの持ち出し量は、その半分程度であることがわかる。穀物・畜肉による窒素輸出の多い国は、その分を補給しないと国土がやせ細ってしまう点に留意する必要がある。我が国は世界一の窒素輸入国で、旧ソ連を上回っている。ヨーロッパ各国やメキシコ、エジプトについて比較的輸入量が多いといえる(第序-2-4図)。次に土地への負荷という観点から単位面積当たりの窒素輸入量をみると(第序-2-5図)、日本、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、韓国等の国々で窒素の輸入量が多くなっている。我が国の窒素輸入量は、単位面積当たりでは130kg/haと世界的に見ても多量の窒素を輸入している。また、ノールウェー、デンマークなどでは、窒素の輸出が多い。
このように、窒素循環を国家間の視点でとらえると、それが極めて片寄りのあるものであることがわかる。
次に国内での窒素循環について見てみたい。窒素の流れは、産業活動とともに我々の食生活と深い関わりがある。第序-2-6図により、我が国における食生活に関連する窒素の流れを見ると、食料消費量の増大により窒素通過量が、昭和35年の89万トンから平成4年には176万トンと約2倍に増大していることがわかる。一国レベルでの窒素循環については、環境資源勘定の重要な構成要素の一つとなるマテリアルバランスに関する先駆的な研究事例として、オランダにおける研究を例にとって見てみたい(第序-2-7図)。窒素は、工業固定(肥料)、飼料や食料の輸入及び河川等により国土に流入する。これに対して、食料等の輸出、河川・海への排出などにより国土から流出していると考えられる。1990年にオランダでは、工業固定により3252百万kg、飼料輸入が424百万kg、河川から362百万kgなど総計4676百万kgが流入していると推計される。一方、流出分は、有機ないし無機窒素化合物輸出の2556百万kgをはじめ、食料輸出として402百万kg、また下水処理場等での窒素処理363百万kgなど総計3931百万kgとなるものと推計される。したがって差引で745百万kgが国土に蓄積されている勘定になる。以上のようなフローは環境と人間活動等との関わりを環境資源勘定の手法を活用して把握する上で極めて有効であるものと考えられるため、我が国においても今後の整備が望まれる。
(2) 循環の片寄りによる環境問題の発生
我々は、大気中の窒素を固定し肥料等として利用している他、化石燃料等の燃焼に伴って生じる窒素酸化物を環境中に放出している。前者は、大気中の窒素を生物に摂取させて自然の窒素循環に戻すことであり、後者は、窒素を窒素酸化物などの形態で大気中に放出することである。これに伴い、種々の環境問題が引き起こされているが、窒素循環が適正に行われなくなったことから環境への負荷が生じている例を見てみたい(第序-2-8図)。
例えば、化石燃料等を燃焼させることによる大気中への窒素酸化物の放出は、近年、特に大都市地域を中心とする窒素酸化物に係る大気汚染といった問題をもたらしている。1985年度(昭和60年度)の窒素酸化物の大都市地域における排出推計量を見ると東京都特別区等地域では、52.7千トン、横浜市等地域54.7千トン、大阪市等地域42.4千トンとなっている。その排出源別の寄与割合と推移について1983年度(昭和58年度)と1985年度、(昭和60年度)を比べると例えば東京都特別区等地域では、自動車等の移動発生源は、43.0千トンから38.2千トンへ、工場・事業場等の固定発生源は15.3千トンから14.5千トンへと推移している。また、我が国においては、1986年(昭和61年度)以降、それまで減少傾向にあった窒素酸化物の排出量が上昇傾向に転じている(第4章第1節)。
また、大気中に放出された窒素酸化物は、硫黄酸化物とともに、雲粒などに取り込まれて複雑な化学反応を繰り返し最終的には、強い酸性を示す降雨又は乾いた粒子状物質として降下する、いわゆる酸性雨の原因物質となっている。こうした酸性雨による影響は、ヨーロッパ、北米、中国等世界的な規模で発生している。スウェーデン、ノールウェー、カナダ等の湖沼では、魚が死滅するなどの影響が見られる(第4章第1節)。
自然林地の地下水中の硝酸性窒素濃度は、5mg/lを越えることはほとんどないとされ、高濃度の硝酸性窒素が見られる場合には、過剰な施肥、畜産排水や生活排水の土壤浸透処理など人間活動に起因することが考えられる。農地などに施用された窒素は、酸化されてその一部が硝酸となり、水の降下浸透に伴って下層に浸透する。その後、NO3-、NO2-、NH4+といった形態で地中や水中に存在し、地下水汚染の問題や湖沼、内湾といった閉鎖性水域等における富栄養化問題などの原因の一つとなっている。
施肥等の窒素負荷が地下水汚染を引き起こした例として岐阜県各務原市の硝酸性窒素汚染をみてみよう。同市では、昭和40年代の名古屋市のベッドタウン化により、大型住宅団地の造成が進んだ。この大型住宅団地への給水のため、ニンジンを主体とした園芸団地において水源の試掘を行ったところ、水道水質基準(10mg/l)を大幅に越える硝酸性窒素が検出された。硝酸性窒素は、嫌気的環境で亜硝酸性窒素を経て窒素ガス等に変わる。亜硝酸性窒素は、特に乳児にメトヘモグロビン血症(チアノーゼ症状)を引き起こすなどの影響から、水道水質基準が設定されている。各務原市の硝酸性窒素汚染は、専門家グループによる数年に及ぶ調査により肥料が原因であるとされた。農業団体も示された科学的根拠に理解を示し、行政、農業団体、生産者が相協力して施肥改善に取り組み始めた。施肥量を従来より30%減ずることにより、硝酸性窒素濃度20mg/l以上の高濃度汚染地域が縮小してきている。なお、にんじん生産についても、過繁茂生育が軽減され、病害虫の発生が減少したことにより、可販収量の増加等が見受けられ、同地域でのニンジン生産は結果的に収益性が15%増加したという好影響も見られた。
次に、東京湾流域における富栄養化を例にとり見てみたい。東京湾流域における窒素負荷は主として、生活排水、工場排水、その他(畜産排水、農耕地等)から発生していると考えられる。
東京湾流域では、特に1950年代以降に人口、家畜頭数の著しい増加が見られたが、宅地需要等を反映して水田及び畑地は減少している。第序1-2-1表は、東京湾流域において発生した総窒素負荷量の変遷である。これによると昭和54年度実績で364.9トン/日、59年度で334.4トン/日、平成元年度で319.5トン/日と近年ほぼ横ばいの状況で推移している。第序-2-9図は主として食物を中心に東京湾流域における窒素の流れを試算したものである。東京湾流域に生活する人間の食料として、流域外より295トン、流域内の農業生産より1日当たり45トンの窒素が供給され、我々の食生活を支えた後、生活廃棄物として319トン、農業より78トンの窒素が排出される。これらの窒素の一部は浄化処理されるものや自然の脱窒作用により大気中に返されるものがあるため、東京湾への窒素負荷量は、1日当たり人間よりの171トンを始めとして、約294トンと試算されている。この試算は、農業生産のリサイクル利用がないとの仮定で試算されていること、流域外から産業への窒素の流入が不明であることなどさらに検討を要する部分がある等の点に留意する必要がある。しかながら、全体として窒素流量の経年変化を見てみると、流域外からの流入量が大幅に増加している。また、1935年時点の東京湾への窒素流入は1日当たり64トンと1990年の約4分の1であるとされている。流域外からの流入量の増加した主要な原因は、東京圏への人口、産業の集中により、化石燃料の使用、食料の需要が集中したことによるものと考えられ、こうした社会的要因が窒素循環の片寄りを引き起こしている。
こうして、東京湾では流入する窒素負荷により富栄養化現象が生じ、利水障害などの影響が現れている。
また、一酸化二窒素が、自然発生源である海洋や土壤などのほか人為的発生源である化石燃料や薪等のバイオマスの燃焼、施肥農地などから発生している。前者は、脱窒と呼ばれる作用で、微生物により硝酸態又は亜硝酸態窒素がガス状の窒素(N2)か窒素酸化物(NO又はN2O)に還元される反応である。後者は、硝化作用であり、アンモニウム態窒素が硝酸態窒素に酸化される過程でN2Oが生成する現象である。
この一酸化二窒素は、100年程度のタイムスケールで見ると同量の二酸化炭素に比べ、約290倍の温室効果を持っていると考えられる。
一酸化二窒素の年間の総発生量は、4.4から10.5Tg(=10ug)の範囲であると推計されている。近年特にここ20〜30年の発生量の増加が著しく、窒素肥料を施用した土壤及びバイオマス燃焼には注目する必要がある。肥料から発生する一酸化二窒素の量は、0.01から2.2Tgと現段階では不正確であるが、先に見たように世界の窒素肥料の消費量は1960年頃から急速に伸びており(第1節)、窒素肥料のもつ環境への潜在的な負荷は増加していくものと予想される(第序-2-2表)。
(3) 窒素循環の適正化に向けて
これまで、地球規模から国内にいたる窒素の循環をみてきたが、様々な場面で著しい片寄りが生じ、肥料の過度の投与、自然の自浄能力を越えた窒素の排出等による局地的な遍在が起因して各種の環境問題が引き起こされていることが示された。
また、諸外国等においては、例えばスウェーデンでは、ボイラー等固定発生源からの窒素酸化物の排出を抑制するためにNOx排出課徴金の制度がある。また、ECでは「散在汚染源からの硝酸塩による汚染から、淡水、沿岸水、海水を保護することに関する指令」を加盟国に提案している。これは、もし対策をとらなければ硝酸濃度が一定の基準を越える可能性がある表面淡水または地下水等の水質保全上問題のある地域を「脆弱な地帯」として指定し、有機・無機窒素肥料の使用制限等の対策を講じようとするものである。また、イギリスでは政府が「硝酸塩感受性地帯」においては「水質保全のための優良農法ガイド」を作成し、農家に提供している。農家がこれにより不利益を被った場合には、一般財源からの所得補償を受けることができるとしている。外国の中には、肥料、化石燃料の生産・消費などに経済的な手法を講じている例もある。我が国においては、降水量に恵まれ、急峻な地形が多く、森林面積が国土の7割近くを占めるといった自然条件から、これらの手法を単純に適用することは不適切であろうが、例えば、物質循環型産業としての特質を持つ農業分野においても、施肥基準の見直し、土壤生育診断による効率的な施肥等環境保全型農業を推進する必要がある。
このように、窒素及びその化合物の局地的な遍在等に起因する環境負荷を低減するため、それらの循環全体を視野に入れた各種の対策を検討することが有効であろう。