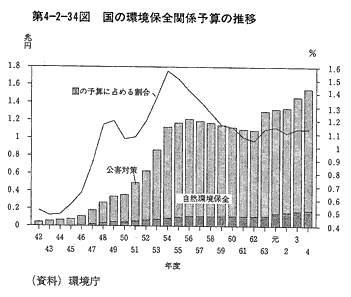
4 政府
環境問題は、あるがままの市場経済のメカニズムでは解決されない問題、いわゆる「市場の失敗」の典型例の一つと言われる。このため、政府の役割が不可欠となっている。
政府は、国全体として環境保全を進めていくために、これまでも様々な機能を果たしてきた。我が国では、戦前において「工場法」等により公害の規制を行っていた経緯があるが、昭和30年代より各種の公害規制法律の制定が始まり、特に、42年の「公害対策基本法」及び47年の「自然環境保全法」により、政府が一体となった整合的体系的な環境対策が始まった。政府では、環境基準を設定して公害対策の目標を示したり、自然環境保全基本方針により自然環境保全施策の基木的方向を示すとともに、各種環境保全法今等の制度を立案し、これらに基づき規制等の措置を的確に実施すること、自らの活動についても環境への配慮を十分行っていくこと、民間の自由な活動では十分になし得ないような環境の保全に資する施設整備やサービスについては、公共事業としてこれを進めていくこと、また、基礎的な調査研究や技術開発を推進していくこと等の、政府に課せられた重要な役割に取り組んできている。さらに、私的に解決の難しい公害に係る紛争や被害の補償に関しても、公害苦情への対応、都道府県や公害等調整委員会における調停、あるいは汚染原因者の民事責任を踏まえた行政上の補償制度による公害健康被害者の迅速、公正な救済等が行われてきた。また、環境情報の普及や環境教育によって国民各層の意識を啓発し、民間における自主的な取組を促していくことも、政府の重要な機能である。政府が環境保全に関連して行っているこれらの対策の予算の推移は第4-2-34図に示すとおりであり、近年、政府予算全体に占める割合は横ばいであるものの、総額は増加傾向にある(内訳については第2部第1章第1節を参照)。
環境問題の時間的、空間的な広がりや、その発生原因の複雑化などの今日の状況に対処するため、既に本節の1から3までに見たとおり、社会の各方面から政府の取組に一層の充実が求められるようになっている。ここでは、重要度を増しつつある、政府のいくつかの役割を取り上げて見よう。
(1) 理念や望ましい環境の在り方の提示
環境のもたらす恵みは多様なものであり、極めて多数の、さらに立場を異にする人々が環境を利用している上、それぞれの人による利用の仕方も多種多様にわたっている。このため、こうした多種多様な利用のされ方が適切なものとなるように調節することが必要となる。環境基準については、人の健康や生活環境の保全が図られるように、維持されることが望ましい環境の水準として定められ、この基準の確保に向け排出規制等の各種の施策を行っていくこととされている。また、水質の生活環境項目に係る環境基準や騒音の環境基準の類型区分のように、環境利用の目的や利用のされ方などに応じた環境の在り方が示されているものもある。例えば水質の生活環境項目については、自然探勝や上水道といった環境利用の目的、浄水操作法や水産業の対象種などのような環境利用のされ方などに応じた類型の区分がなされている。特に、第3章でみたように、環境に期待される恵みは、単に現在世代の健康を守るという限りのもので良いのではなく、将来世代にも継承される必要があり、まだ、環境に国境がないことを考えれば、広く地球全体で分かち合う必要のあるものである。広く国民が尊重する環境上の目標の設定は、今後とも政府の重要な役割である。
(2) 計画的な取組の推進
既に第2章において論じたように、地球温暖化問題や廃棄物の増加の問題など、我々が直面している環境問題の多くは、広範で相互に結びついた各種の経済社会活動が全体として原因となって発生している。第1節で様々な事例について見てきたように、これら問題の解決には、社会のそれぞれの主体が共通の認識の下に、中・長期的視点に立ちつつ、多種多様な対策に協力して取り組んでいくことが確保されなければならない。このためには、政府においては、目指すべき望ましい環境像について国民のコンセンサスを築き、また、環境政策の基本的な方針や計画を国民に明らかにし、これを通じ、あらゆる主体による自主的、積極的な取組を効果的に全体として促すことが必要である。また、環境問題に係わる経済政策等様々な政策領域に環境保全の視点を十分織り込んでいくことも重要であり、このような観点から、例えば平成4年6月に閣議決定された長期経済計画「生活大国5か年計画」においては、環境と調和した内需主導型の経済構造を定着させることを政策運営の基本方向とし、地球環境問題への頁献、環境と調和した経済社会の構築、環境と調和した簡素なライフスタイルの実現を図っていくことが盛り込まれた。
海外についてみると、環境に関する国の計画を定めて対策の総合的な推進を図っている国々がみられる。オランダ政府は、1989年(平成元年)に「国家環境政策計画」(NEPP)を作成、公表した。同計画は、地球環境問題を含めオランダ内外のあらゆる環境問題に対する同国政府の政策を掲げたものである。2010年(平成22年)までの長期を見通しつつ、計画期間を1994年(平成6年)までとして政策理念と目標を明らかにするとともに、その達成のための各種の規制強化、研究・技術開発、財政投融資、税制改正、国民に対する普及・啓発等各般にわたる詳細な施策をまとめている。さらに、1990年(平成2年)には、同計画の中でより急ぐべき政策を示したNEPPプラスを作成している。また、カナダにおいては、1990年(平成2年)に審議会の検討、国民からのヒアリング、各種団体の意見等を広く踏まえて「グリーンプラン」を作成した。この計画は、大気・水・土壌の保全、再生可能資源の保全、生態系の保全、地球環境保全等の分野について、1990年代に達成すべき目標、政府の取るべき施策をまとめている。なお、カナダでは、政府は、対策の優先度の変化が適切に反映されるよう、毎年計画をフォローアップすることとしている。その他の先進国首脳会議参加国(G7国)においても、米国を除き、政府レベルの環境上の計画が立てられている(第4-2-4表)。
我が国においても、平成5年3月に第126国会に提出された環境基本法案において、環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱等を内容とする環境基本計画を政府において策定する旨の規定が置かれている。
(3) 民間における活動の促進、誘導
現在の環境問題の態様を見ると、かつての公害問題のように特定の種類の大規模な事業活動を中心とするものから、工場から事務所や家庭に至るまでの活動が広いものが中心的な課題となってきている。このような中で環境の保全を図っていくためには、社会の様々な主体が行っているあらゆる経済社会活動に環境への配慮が適切に組み込まれた社会を構築していかなければならない。このような方向を実現するための政府からの社会の諸活動への働きかけの在り方としては、第1節に収めた各事例に見てきたとおり、現在までの基本的な法制に基づく法体系が主要な対策手法として位置づけている規制的手法のみでは不十分であり、それに加えて、社会の様々な主体に自主的、積極的な環境の保全への取組を促すための多様な働きかけなどを適切に組み合わせていくことが必要である。
社会における環境保全活動への取組を助長していくためには、国民や事業者に対し、現在の環境の状況や様々な活動と環境との関わりについて適切に認識してもらうことがまずもってその基礎となる。このための広報活動や環境教育、情報提供を充実させていくことが政府の任務としても重要である。また、民間の自発的な活動を、その自主性を尊重しつつ促進していくことも重要であり、このため、参考となるような活動の指針を示したり、望ましい取組事例や期待される効果などの幅広い情報を提供していくことも必要である。こうしたことを踏まえ、前述した環境基本法案も民間活動の促進に関連する規定が置かれたところである。
平成4年度には、例えば、環境庁では「環境にやさしい企業行動指針」を産業界の専門家や学識経験者の参加を得て作成し、環境にやさしい行動を取ろうとしている企業の判断の参考として提供した。また、通商産業省では、各企業が環境のための行動計画(ボランタリー・プラン)を自主的に作成するよう呼びかけを行った。
様々な活動が複雑にからみあった社会を全体として環境の保全が図られたものとしていくことや、将来の環境劣化を防ぎ、持続可能性を高めることのようにその実現のための対策努力の配分や段取りが多様に存在する場合には、これまでの主要な対策手法であった一律的な禁止のような規制的手法にとどまらず、問題の態様などに応じ、多様な方策を取っていくことが有効である。
このような方策として、国際的に導入が広がっているものに、市場の活力を生かせる利点を持つ経済的手法がある。地球サミットで採択されたリオ宣言の原則16においても「各国当局は、汚染者負担原則を考慮にいれつつ、公益に対し適切な配慮を払い、かつ、国際貿易や国際投資を歪曲することなく、環境コストの内部化及び経済的措置の利用を促進するよう努力しなければならない」とされた。OECDにおいては、1991年(平成3年)の「環境政策における経済的手段の利用に関するOECD理事会勧告」の中で、経済的手法として、?課徴金及び税、?排出権の市場での売買、?デポジット(預り金)制度及び?資金援助(補助金等)を挙げ、各国の社会経済的状況を考慮しつつ利用することを勧告した。さらに、このような趣旨から、1993年(平成5年)3月には、租税委員会と環境政策委員会が合同で設置した税制と環境に関する作業部会の報告書を公表した。
各国の経済的手法に関する状況を見ると、上記の?に掲げる資金援助が産業公害対策の促進策として利用されている事例が見られる。我が国においても、最新排出ガス規制適合車に関する優遇税制を設けるなど、詳しくは、第2部第1章第2節4に紹介するように、様々な助成措置が講じられている。
また、?から?に掲げるような、環境への負荷を与える行為に何らかの経済的負担を課して、こうした行為を自主的に抑制させていく手法に関しては、フランス、ドイツでは1960年代より排水課徴金が活用されていたが、前述したような新たな態様の環境問題にも対処するため、最近、その導入が広がっている(第4-2-5表)。例えば、デンマークでは、1992年(平成4年)5月から、既に取組をみせているスウェーデン、ノルウェー、フィンランド、オランダに続いて、二酸化炭素排出の削減に着目した税制を導入した。また、アメリカにおいては、1990年(平成2年)の大気保全法の改正により、酸性雨対策として二酸化硫黄を削減するために排出権売買の仕組みが導入されたが、1993年(平成5年)3月から実際に市場において排出権の取引が開始され、その動向が注目されている。デポジット制については、飲科容器を対象にして古くから各地で行われている。ドイツにおいては、「廃棄物の回避及び管理法」に基づく「包装廃棄物回避に関する政令」により、運搬用や販売用の包装の引き取りを事業者に義務付けている。また、この政令では、再利用できない飲料容器、洗剤及び洗浄剤や塗料容器へのデポジットを課している。以上の引取りやデポジットの義務は、事業者が参加した収集システムが整備され、一定の回収率を達成している場合は免除されることから、民間会社デュアル・システム・ドイチュラント(DSD)が設立され、包装物回収を行っており、これに加盟している企業は600社以上に及んでいる。
我が国においても、前述の環境基本法案において、このような施策に関する規定が置かれている。この規定では、必要かつ適正な経済的助成措置を環境の保全上の支障を防止するための経済的措置の1つとして位置づけるとともに、新に経済的負担措置について規定している。経済的負担措置については、まず、このような施策が、有効性を期待され、国際的にも推奨されているということを明らかにしている。次に、このような措置が国民に負担を求めるものであることから、その措置の効果、経済に与える影響等を適切に調査し及び研究する必要があるとしている。そして、そうした調査・研究を踏まえ、個別の措置の必要がある場合には、国民の理解と協力を得るように努めるとしている。さらに、その措置が地球環境保全のためのもの、例えば、地球温暖化等の課題に対処する措置であるときは、国際的な連携に配慮して行うとしている。以上のような考え方に沿って、今後とも、内外の研究成果や実例等を参考に調査研究を行っていくことが必要である。
(4) 国際的な取組の推進
環境問題の原因と影響が国境を越えた広がりを見せる中で、その解決には、それぞれの国における取組に加え、各国のより一層協調した取組が強く求められるようになってきている。また、開発途上国においては、深刻な環境問題に既に直面している一方で、その対策のための資金、人材、技術等が極めて不足し、また、法制度及び行政の実施体制も不備であるため、先進諸国の積極的な援助が国際的に求められている。こうした援助は、第3章第3節でみたとおり、いわば地球全体の安全保障という側面もあり、先進国と開発途上国との共通だが差異のある責任に留意しつつ、地球的なパートナーシップの精神の下で積極的に進めていくことが先の地球サミットで国際的に合意された。
我が国においては、既に第4章第1節において見たように、地球環境保全に関する様々な国内対策を実施してきており、また、第4-2-6表に掲げる各種の環境関係国際条約に加入し、国際的に共通した対策を行ってきている。さらに、地球環境問題に関する広範にわたる対策を、関係行政機関の緊密な連絡を確保しつつ、効果的かつ総合的に推進するため、平成元年5月、「地球環境保全に関する関係閣僚会議」を設置し、第1回の会合において、我が国が講じるべき施策の基本的方向として、地球環境保全のための国際的な枠組みづくりに積極的に参加すること等6項目を申し合わせ、これに沿って諸施策を推進している。また、元年7月には、地球環境問題への政府内の円滑な対応を図るため、地球環境問題担当大臣を設け、以後、歴代の環境庁長官をこれに任命している。地球環境問題担当大臣においては、政府各省庁の地球環境関係予算の取りまとめなどを行っている。
平成4年には、4月に環境と開発に関する国連会議(地球サミット)事務局が主催して、「地球環境賢人会議」(地球環境と開発への資金供給に関する著名人会議)が東京で開かれ、我が国政府もこの開催に協力したが、その成果(東京宣言)は、その後の地球サミットにおける資金問題についての国際合意の方向づけを行うものとなった。我が国は、この東京宣言を4月の開発途上国環境大臣会合(クアラルンプール)や5月の先進国環境大臣会合(ボン)において紹介し、地球環境を守るための資金問題についての国際合意を促すなど、大きな国際貢献を果たした。また、5月には、第6回の地球環境保全に関する関係閣僚会議が開催され、地球サミットの成功に向けた我が国の取組を盛った「地球サミットを控えた我が国の取組について」を了承した。さらに、地球サミットに提出された宮沢総理大臣の演説では、効果的かつ効率的なメカニズムができること等を前提とした国際開発協会(IDA)や世界銀行等の運営する地球環境ファシリティ(GEF)ヘの積極的協力といった多国間の環境協力の方針を明らかにし、また、我が国の環境関係の政府開発援助を1992年度(平成4年度)からの5年間の累計で9,000億円から1兆円を目途として大幅に拡充・強化する方針を明らかにした。この方針を受け、4年6月に閣議決定した「政府開発援助大綱」においても、「環境保全の達成を目指しつつ、地球規模での持続可能な開発が進められるよう努める」ことを我が国の開発援助の基本理念に盛り込んだところである。さらに、10月には、1990年のヒューストンサミットで我が国が誘致を提唱したUNEP国際環境技術センターが大阪市及び滋賀県に開設された。これは、開発途上国等に環境にやさしい技術を移転することを目的として、研修、コンサルティング等を行うものである。このほか、10月には、地球サミットのフォローアップの一環として、北東アジアの環境に関して意見交換、情報交換を行うことを目的に、「第1回環日本海環境協力会議」を環境庁及び新潟県の主催により開催した。
我が国の具体的な環境国際援助には、他の国際援助と同様、無償の資金協力・技術協力、有償資金協力があるが、その推移は第4-2-35図のとおりであり、近年、その拡大傾向が著しい。環境援助の内容、定義は援助実施国によって異なり、その国際比較は困難だが、我が国の環境援助額は主な援助国の中で最大規模のものと言えよう。また、政府べ一スの国際環境協力に加え、地球市民としての民間の草の根の国際環境協力を官民が一体となって促進することとし、このため、5年2月には、環境事業団に地球環境基金を置くことなどを内容とする環境事業団法改正案を国会に提出した。
平成5年3月に国会提出された環境基本法案においては、地球的な視点や国際的な取組がますます重要になっていることにかんがみ、環境政策の理念の一つとして国際的協調による地球環境保全の積極的推進を掲げ、地球環境保全及び開発途上地域の環境保全等に関する国際協力の推進、その実施のための人材育成、情報収集・整理分析、監視・観測・調査研究等及び地方公共団体や民間の地球環境保全等に関する国際協力の活動の促進、並びに国の行う国際協力における環境配慮や民間の海外事業活動における環境配慮の促進を具体的な政策として掲げている。法律において国際環境協力の理念や内容を明定した例は先進諸国にも乏しく、地球サミットの成果を受けた政府の取組として世界に先駆けたものとなっている。
(5) 基礎的な調査研究
地球温暖化問題にみられるように今日の環境問題には、そのメカニズムや影響等について解明すべき点が多いものがあり、環境の状況の観測・監視、調査研究、先駆的な技術の開発等を積極的に進めていく必要がある。しかし、このような基礎的な科学技術の分野については企業の採算べ一スでの対応は困難である。また、特に地球環境保全については、関連する学問分野が広範であり、さらに研究対象が国際的に広がっているため、学際的、国際的に研究を実施し、その成果を施策に適切に反映させる必要がある。このようなことから、政府が積極的にその推進を図っていくことが欠かせない。例えば、二酸化炭素の地球全体での吸収・放出の収支に関して、まだ知られていない吸収源(ミッシングシンク)が存在しており、地球温暖化の将来予測を行う際にも大きな問題となっているため、ミッシングシンクの解明を含めた地球全体の炭素循環に関する研究等を関係機関が協力して進めている。国立環境研究所に平成2年に設置された「地球環境研究センター」においては、研究支援や研究者の交流等を行っている。
また、環境と経済との統合という観点から、社会科学的な調査研究の重要性も高まっている。例えば、環境負荷の少ない持続可能な経済社会を作り上げていく上で、経済政策の分野での環境に配慮した意思決定に資するべく環境と経済を総合的に評価しうる指標の重要性が国際的に認識されるようになっている。環境汚染や自然資源の枯渇・劣化を考慮しながら、長期的な発展のあるべき方向を探る指標体系、すなわち「環境資源勘定」や国民経済計算体系(SNA)における「環境・経済統合勘定」を整備することが求められるようになってきた。このような政策の検討や意思決定の基盤となる情報を提供するための研究の推進も重要である。今までにも、国連統計局、OECD、世界銀行、世界資源研究所等において各種の勘定体系の検討やこれに基づく試算がなされてきており、ノルウェー、フランス、オランダにおいては、実際に環境資源勘定を作成する試みが行われている。ノルウェー政府では、1975年から、様々な環境の要素を物量単位で表した環境資源勘定の研究を開始した。これは、環境資源をフローとして生産に消費されてしまう「物的資源」(鉱物資源、生物学的資源、太陽光や水力などの流入資源)と、生産の過程で資源の質は変化するが消費されるものではない「環境資源」(大気、水、土壤等)に分類して勘定体系を構成している(第4-2-7表)。「物的資源」の勘定は、エネルギー、いくつかの鉱物資源、魚、森林について作成されており、それぞれについて、全体の保有量とある期間のその変化と原因がまとめられている。「環境資源」の勘定は、土地利用と大気中への排出に関するものがあり、土地利用については土地の利用区分と土地の質がまとめられている。大気中への排出については、汚染物質の排出状況とその発生源がまとめられている。この勘定体系は、将来の資源利用の予測と計画に活用されている。また、国連では1993年に国民経済計算体系(SNA)を改訂して、環境・経済統合勘定を含めることを決めた。現在、そのハンドブックを作成中である。我が国においても、環境庁、経済企画庁及び農林水産省の各研究機関において、SEEAの手法等を検討するための研究を含め、環境資源勘定の確立を図るとともに、国民経済計算体系に環境・経済統合勘定を付加する手法等を検討するための研究が進められているところである。
環境基本法案においても、国は、上記のような環境保全に関する科学技術の振興を図るものとし、試験研究の体制の整備、研究開発の推進等の措置を講ずると規定されている。
(6) 制度、行政運営の改善
政府における取組に当たっては、以上のような具体的な施策の企画、立案、推進に力を入れていくべきことはもちろんであるが、さらに制度、体制を改善、整備し、これを不断に見直し、あるいは行政の運営をより適切にしていくことが求められる。政府においては、第3章第3節でみたように、地球環境時代にふさわしい環境の保全のための施策の新たな枠組みとなる「環境基本法案」を国会に提出したところである。以下では、これまでに行われてきた環境行政について、その在り方の改善のためにどのような作業が行われてきたかに関し、臨時行政改革推進審議会と行政監察を例にして振り返ってみよう。
行政改革の推進のため、昭和56年に臨時行政調査会が設置され、その後2次にわたり臨時行政改革推進審議会(行革審)が設置されてきた。現在は、平成2年10月に設置された行革審(第3次)において、臨時行政調査会及び先行の2次にわたる行革審の答申等を受けて講じられる行政制度や行政運営の改善に関する施策に係る重要事項について調査審議が行われている。この中で、3年12月に出された「国際化対応・国民生活重視の行政改革に関する第2次答申」においては、地球環境保全に関する行政の在り方が取り上げられ、地球環境問題に関する基本方針等の策定、環境庁の企画立案・総合調整機能の発揮等の地球環境問題に対応できる体制の整備及び国際協力の推進等が提言された。
また、行政監察は、全政府的立場から行政の評価を行うものであり、具体的なテーマを設定し、行政の実態と問題点を実証的に調査、分析し、その結果に基づいた改善方策を各省庁に勧告することにより、制度・施策、組織、運営の全般にわたって行政の改革、改善を推進することを目的として行われる。その勧告や勧告に応じて講じられた措置は全て公表されるが、これまでの勧告のうち、環境保全に関連するものとしては、昭和46年度の「公害対策に関する行政監察」や47年度の「自然保護に関する行政監察」をはじめとして、第4-2-8表に示すようなものがある。
最近行われた行政監察を兄ると、まず、平成2年度に勧告された「湖沼の環境保全に関する調査」においては、「湖沼水質保全特別措置法」に基づく指定地域内における生活排水対策を抜本的に充実するため、各種水質保全事業の実施に係る関係省庁、関係都道府県間の一層密接な連携を図るべきことや、湖沼水質保全計画の内容を充実、強化することを検討するべきことなどが勧告された。これを受けた環境庁等では、情報及び意見の交換を行うために指定湖沼関係省庁連絡会議を設け、連絡を密にすることをはじめとして、生活排水対策を充実するための対応を進めている。また、3年度及び4年度に第2期の湖沼水質保全計画を作成した琵琶湖等7湖沼において、汚濁負荷量規制の対象項目として、従来からのCODに加え、窒素、燐を加えるなど富栄養化防止対策を拡充しており、湖沼水質保全計画の充実・強化に努めている。
次に、4年度には「野生動植物の保護等に関する調査」の結果に基づく勧告が行われた。この中では、自然環境保全基礎調査について、調査対象種の範囲の拡大等調査内容を充実し、野生動植物の生息・生育状況等を一層的確に把握するべきこと、絶滅のおそれのある野生動植物の種の生息・生育地の保全等を促進するため、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づく生息地等保護区を指定するほか、「自然環境保全法」等に基づく特別地区等の指定等に際して、絶滅のおそれのある野生動植物の保存に配慮すること、絶滅のおそれのある種について適切かつ計画的に保護・増殖事業を推進することなどが勧告された。
環境問題が広範な分野に関係を有するようになるにつれ、環境保全に関わる行政の複雑、多様化が進んでおり、こうした行政監察などの結果を踏まえた行政の改善が重要になっている。
このほか、環境行政に関する一般からの苦情、陳情に対しては、地方公共団体の環境行政部局においても対応されているが、政府においても全国の総務庁の地方支分部局である管区行政監察局等に配置されている調査官等が、環境庁長官の指揮監督の下で環境庁の所管行政に関する相談業務を行っているとともに、環境庁本庁においても、相談係を設けて国民一般からの陳情を受け付け、行政の改善に役立てている。ちなみに、4年度に環境庁本庁が受理した陳情等の件数は119件となっている。