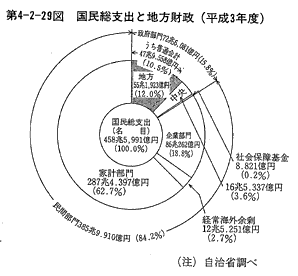
3 地方公共団体の取組
環境問題は、その原因が企業や国民一人ひとりが地域において日常行う活動から生じるものであり、その解決策としても地域的な取組が欠かせない。こうした地域の取組の要となると期待されているのが地方公共団体である。地方公共団体が営む財政活動や公共事業などの経済活動は国民総支出の12%に相当する(第4-2-29図)。このように地方公共団体自体、環境と深い関わりを持っている。さらに、住民の安全、健康及び福祉を保持することを責務とする地方公共団体には、住民の福祉に深く関係する地域の環境保全に関し、重要な役割が期待され、環境問題の解決に大きな責任を負っているといえる。この項では、地方公共団体が果たす役割と他の主体との協力の動向について見ることとする。
(1) 地方公共団体が果たしてきた先駆的役割
行政部門が講じる公害対策、自然保護対策の歴史を振り返ってみると、住民の意向や要望を受けた地方公共団体が地域で真っ先にこれらに取り組んできたことが分かる。地方公共団体は、地域の問題として様々な公害問題や生活環境の悪化、自然破壊の問題に直面し、自らの力でこれらの地域的課題に対処しなければならなかった。昭和24年の東京都の「工場公害防止条例」を始めとして、多くの地方公共団体で国の公害法制の整備に先駆けて公害防止条例が制定されたのを始め、27年には島根県が地元工場と公害防止協定を結び、その後多くの地方公共団体でこの手法が取り入れていったように先駆的な取り組みが数多くみられた。一方、自然保護に関しても30年代から条例による県立自然公園などの指定が盛んに行われ、45年には北海道で、良好な自然環境を保全する必要のある地区を指定し、不適切な事業行為等については知事が助言、勧告する制度も盛り込まれた自然保護条例が制定されるなど、自然保護に総合的に取り組んでいくための施策が各地で行われた。行政組織の面からみても、昭和30年代以降、公害専門部課が設置されるようになり、専門の組織の下で公害防止への本格的な取組が始まった(第4-2-30図)。
また、50年代には、環境影響評価の面においても、国の制度の整備に先駆けて、川崎市等の地方公共団体において、環境影響評価の条例や要綱が定められるなど先駆的な取組も見られた。
その後、国においては、42年の「公害対策基本法」の制定、45年のいわゆる「公害国会」において公害関係法が抜本的に整備されたのに加え、47年には「自然環境保全法」が制定された。これらの新しい法律の成立を契機として、地方公共団体の活力と地域の自然的、社会的条件に応じた独自の取組とを活かすような制度的枠組みが積極的に位置づけられた(第4-2-2表)。こうした国、地方を通じた制度の整備に加えて、各地の事業者の努力、市民の公害防止や自然環境保全に向けた根強い活動等もあり、地方公共団体の先駆的な取組により開始された環境施策は定着していき、急速に激化した産業公害を克服し、自然環境を保全していくのに大きな効果をあげた。
(2) 新しい役割を担いつつある地方公共団体
近年においては、従来型の公害に対する方法、すなわち環境に大きな負荷を与える施設や行為を個別的に列挙し、これを規制するという対症療法的な施策だけでは対応しきれない問題、あるいは健康の保護に直ちに結びつかないものの重要な環境の劣化が生じるといった問題が多く出てきている。いわゆる地球環境問題や都市・生活型公害がその典型である。それらの問題は、その原因が経済社会に根ざし、原因となるものも極めて多岐にわたる場合が多く、根本的に新しい対応が地方公共団体にも求められるようになってきている。
地方公共団体の中には、このような新たな問題に対し、先駆的な活動を行っている団体も出てきている。特に、条例は、憲法の「地方自治の本旨」を受け、国の立法に相当する自主立法であり、その制定は地方公共団体のみが果たせる役割である。住民に進んで努力を払うことを求めたり、適切でない行為を行った時に罰則を課すことによって実現され得る法益を、住民の総意として目指す上で条例は不可欠の手段である。条例に着目して、地方公共団体の環境施策の新しい動きを見てみよう。
空き缶の散乱については、国においても各種法律に基づくもの、その他の種々の対策を講じてきたところであるが、第1章第1節の8に見たとおり、その散乱状況には顕著な改善が見られない。このような中、福岡県の北野町や和歌山市では、平成4年、ごみの投げ捨てを防止するために、投げ捨て行為への罰則付きの条例を制定した。北野町の条例では、空き缶、たばこの吸殻等の投げ捨てに対して、町民、旅行者を問わず3万円以下の罰金を課すほか、自動販売機の設置事業者に対しても空き缶等の回収容器の設置を求め、自動販売機の設置の届出等を怠った場合、罰全を課すこととされている。住民と事業者の双方に相当厳しい努力を求める内容となっている。ごみの投げ捨てに対する罰則に関しては、かねてより「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)、「道路交通法」等に罰則を含む規定があり、不法投棄の取締りが行われており、また、散乱空き缶等を含め廃棄物を清掃、回収し、自らの土地の清潔を保持することを求める規定が「廃棄物処理法」にある。こうしたことを踏まえ、これらの条例は、国の法律とは直接競合しない環境の積極的な美化、清潔で美しいまちづくりを目的とし、法律による罰則との矛盾、競合を避けようとしており、ごみの投棄に直罰を設ける例や罰則の適用に当たって、適用地域を指定する例がある。北野町等のほか、山形県の最上町や福岡都市圏22市町村などでも類似の条例の制定に取り組んでいる。空き缶投げ捨てのように全国一律の対応が難しい問題について、地域の特性に即し、また、地域の合意と責任の下で強力に対処しようとする動きが広まりつつある。
また、滋賀県においては、平成4年に琵琶湖の生態系保全を目的に「滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例」が制定された。ヨシ群落は、魚類、鳥類の生息、繁殖の場としても重要で、湖岸の浸食を防止したり、水質の保全などにも役立つとともに、すだれ等の材料として利用されるなど多面的な効用を持つ有用な資源である。この条例は、琵琶湖及びその周辺のヨシ群落を積極的に保全し、その多様な機能を発揮させることにより、琵琶湖の環境保全を図ることを目的としている。具体的には、保全が必要なヨシ群落が生えている場所やヨシを増やすべき場所を「ヨシ群落保全区域」に指定し、その改変には許可が必要とすることなどにより、ヨシの保全や増殖に努めることとしている。県や市町村のヨシ等の刈取、植栽清掃等の事業だけでなく、地域住民や事業者の積極的な参加と協力を得て、対策を進めていこうとするものである。本条例は、湖岸のヨシについてその環境に関する多面的な機能を軸として、対策への広い参加と参加を通じた意識啓発とをともに進めようとする総合的な試みである。
このほか、岡山県美星町では、美しい星空を守り、天体観測等に関し、良好な環境を創出するため、水平以上に光がもれないようにするなど屋外照明施設の設置に係る基準を定めるなどを内容とする条例を制定している。滋賀県の条例も美星町の条例も地域独自の環境資源に着目して、その保全を地域のルールにまで高めていった点で特色ある事例といえよう。
地方公共団体は、条例の制定や施行以外にも、いろいろな工夫を活かし、積極的に取り組んでいる。そのための予算も増加する傾向にあり、国の補助を受けず、都道府県の自らの発案で行っている施策や事業に限ってみても、第4-2-31図のとおり、平成3年度には、約4,000億円に達している。ちなみに、平成4年度において都道府県及び政令指定都市が最重点を置いて実施した施策や事業は第4-2-3表のとおりである。ここには、多様性に富み創意工夫のある施策が多く見られる。なお、これら最重点施策の合計の原資の内訳を見ると国費20.3%、地方費79.7%となっている。
(3) 進展を見せる地球環境保全施策
第4-2-3表に掲げる施策等には、地球環境に係わるものも見られる。このように、地球環境保全の問題も、地方公共団体が従来からの公害施策、自然保護の分野に加えて、積極的に取り組んでいる問題の一つとなっている。我が国国内の地方公共団体も地球の一部を占めており、地球環境問題の解決のためには、その地域に住む住民一人ひとりが自らの住む地域において環境に負荷の少ない生活、行動をすることが望まれている。特に、我が国の経済力は大きく、地方公共団体のレベルでみても、その経済力は優に外国一国分のGDPに匹敵するところも少なくなく、それだけに地球環境に与える影響も大きい(第4-2-32図)。加えて、地方公共団体には、地球環境にやさしい地域環境づくりに地域のリーダーとして主体的な役割を果たすことが国際的にも期待されている。
平成4年6月、世界約180カ国が参加して行われた地球サミットにおいては、環境と開発に関する広範な問題が議論され、その成果が21世紀への行動計画である「アジェンダ21」に集約された。その中の第28章には地方自治体の役割が掲げられている。そこでは、「目標」として「1996年までにほとんどの自治体は、地域住民と意見交換を行い『ローカル・アジェンダ21』について合意を形成すべきである」とし、地域における環境のための行動計画の作成を促している。「アジェンダ21」において、地域レベルの行動計画である「ローカル・アジェンダ21」の策定を求めることは、地球サミットの準備過程で検討されてきたものであり、1992年(平成4年)2月にベルリンでNGO等も参加して開催された自治体の環境政策の推進についての専門家会合が採択したベルリン宣言の中でも「ローカル・アジェンダ21」の提案がなされており、また、地球サミット直前にブラジルのクリティバで開催された「世界都市フォーラム」における「クリティバ・コミットメント」の中でも策定の方針が示されている。国際的にも地方自治体のリーダーシップの発揮が求められているとも言える。
我が国の地方公共団体の地球環境問題への取組を見てみよう。環境庁が4年10月に全国の47都道府県及び12政令指定都市を対象に行った調査によって、地方公共団体が地球環境の保全に積極的に取り組んでいる様子を知ることができる。同調査によれば、地球環境保全の視点を盛り込んだ環境基本条例を川崎市と熊本県が既に制定しているほか、他に複数の団体で同様の条例案の検討がなされている。また、地球環境保全の祝点を盛り込んだ計国、方針・指針の策定については、さらに多くの団体が取り組んでいる。東京都等で、各種の地球環境問題に取り組むための「地球環境保全行動計画」が策定されているほか、地域環境の望ましい在り方を明らかにし、その実現のための諸施策を総合的に実施することを目指して取り組まれている「環境管理計画」の中に、地球環境保全の理念や施策を盛り込むこともいくつかの都道府県で試みられている。
また、地球環境問題に対処する組織については、7割近い41団体で庁内推進組織を設置しており、さらに愛知県等11団体では庁外推進組織が設置されている。
地球環境保全の具体的な施策・事業としては、地球環境に配慮したまちづくり・地域づくりを進めたり、ライフスタイルや住民・企業の取組に対する支援・誘導のための施策、地球環境保全に関する調査・研究、国際環境協力等が行われている。これらの活動ごとの件数は、第4-2-33図のとおりである。
これらのうち、地方公共団体自身が国際環境協力に取り組む事例として、北九州市を見ると、同市では、公害克服の過程で蓄積した経験、技術を活用し、市や産業界が出資する(財)北九州国際技術協力協会に多数の環境研修コースを設け、国際協力事業団事業による海外からの多くの研修員を受け入れている。同時に、技術協力にも力を入れており、官民の専門家の途上国への派遣などを通じ、公害防止技術の移転を図っている。研修の受け入れや技術協力に当たっては、自治体が取り組むだけではなく、多くの企業、大学が実習の場所を提供し、市民も研修員の家庭滞在を受け入れるなど、行政、企業、市民がそれぞれの能力、特質を活かして国際環境協力に貢献を続けている。こうしたコミュニティぐるみの取組は、地球サミットにおいても評価され、「国連地方白治体表彰」の対象となった。
目を世界に転じると、地域から地球環境保全を目指して取り組んでいる地方公共団体が数多く出てきている。前述の国連地方自治体表彰では、我が国の北九州市とともに、アンカラ(トルコ)、オースチン(アメリカ)、ブラワヨ(ジンバブエ)、カイロ(エジプト)、クリティバ(ブラジル)、レスター(イギリス)、メキシコシティ(メキシコ)、ザールブリュッケン(ドイツ)、ストレステム郡(デンマーク)、ザドリベ(カナダ)、スラバヤ(インドネシア)の12都市が表彰を受けている。
さらに、地方公共団体が国際的なネットワークを作り、協力し合っていこうとする動きが始まっている。「国際環境自治体会議」(ICLEI)は、1990年(平成2年)の9月に国連が開催した「持続的な未来のための世界会議」において、42カ国、200以上の自治体の参加によって設立された組織で、グローバルな問題に対し、ローカルな主体が連帯して取り組むことを標傍している。現在の環境問題は、地球全体の社会経済システムを環境への負荷の少ないものとしていくよう具体的な行動を進める段階になっており、従来であれば地域固有の問題に地域限りで対応することが多かった地方公共団体は、こうした世界共通の課題に直面することとなった。共通の課題を抱えた各国の地方公共団体が国際的な交流を図り、知恵の交換などの協力を進めることは、意義のあることである。現在、ICLEIでは、都市の二酸化炭素排出削減プログラムや環境自治体のための国際データベースづくり等のプロジェクトを行っている。我が国でも、平成5年3月末現在、山梨県、北九州市がICLEIに加盟しており、他の団体においても加盟の検討がなされている。また、ICLEIでは、アジア太平洋事務局となる団体を公募しているところであり、現在、我が国の地方公共団体もこれに応募しているところである。
(4) 地方公共団体の一層の取組に必要な理解と協力
以上見てきたように、環境に与える負荷の少ない社会の構築のためには、地方公共団体も他の様々な主体と積極的に協力し合って努力することが不可欠である。しかしながら、地方公共団体は、その施策や事業において様々な困難を抱えている。例えば、平成3年に(財)地方自治協会が、地球環境保全に取り組むに当たっての問題点について地方公共団体に行った調査によれば、具体的な施策の実施においては、財源の確保、情報・技術、あるいは関連する企業の対応、専門的な人材の確保等が問題点として指摘されている。地方公共団体の抱える困難の克服には、幅広い関係者の協力が必要である。
国との関係においては、現在、環境保全に関する多くの権限が地方公共団体に委任されており、国と地方公共団体の適切な連携は、環境行政の推進を図る上で不可欠である。特に、環境問題は地域ごとに特性が異なり、きめ細かな施策が求められていることもあり、各分野における国の施策を地域の実状を踏まえて整合的に実施していく上では地方公共団体は事実として大きな役割を担っている。他方、地方公共団体が環境保全施策を進めていく上では、国全体の制度づくりを所管する国の積極的な協力を得ることが必要である。
住民との関係においては、地域住民の自治として、地域住民のための行政を行うことが第一の使命とされる地方公共団体にとって、環境の保全への住民の協力を得ることは必要不可欠である。住民も自らの選んだ代表者が組織する地方公共団体からの助力なくしては、環境保全の責任を円滑に果していくことはできない。また、企業との関係においても、企業は地域経済、社会に大きな影響力を持つ主体であり、企業との協力なしには地域環境政策の進展は望めないであろう。幸い、我が国の場合、企業と地方公共団体が直接に公害防止協定を結ぶなどして公害対策を行ってきた歴史もあり、今後も良好な協力関係が続くことが望まれる。
平成5年3月に国会に提出された環境基本法案においても、公害対策基本法以来の国と地方の関係を従来どおり継承することとし、国の施策に準じた施策その他のその地域の実状に応じた環境保全のために必要な施策を策定し、実施するという環境保全上の積極的な役割を地方公共団体が、果たすことを規定している。さらに、地方公共団体は、自らの地域で地球環境対策を推進することが期待されている。同法案は、地球環境保全等に関する国際協力を推進する上で、地方公共団体が果たす役割が重要なものであることを明示し、このことを踏まえ、国において地方公共団体の行う地球環境保全等に関する国際協力のための活動の促進を図るため必要な配置を講ずるように努めることを規定したところである。
地方公共団体に対しては、国内から国外にまで広がるに至った環境保全のネットワークの欠かせないメンバーとしての役割を十分に果たせるよう適切な理解と協力が強く望まれる。