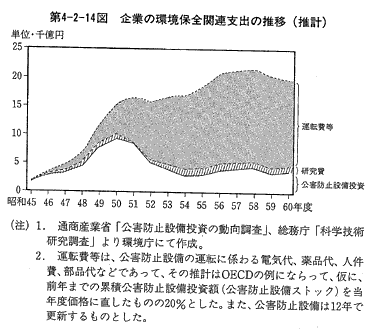
2 企業
第2章第2節で見てきたように、国民経済の各部門の中でも、生産部門が環境に与える影響は決して小さいものではない。その生産部門の主要な担い手である企業には、環境への負荷の少ない持続可能な社会を築く上で大きな期待が寄せられている。ここでは、企業の行う環境保全への取組の現状や動向について、こうした取組の障害となっている事情も含め広く概観してみよう。
(1) 企業の環境に対するかつての取組と今日の取組の違い
我が国で多くの企業が公害対策に本格的に取り組み始めたと言えるのは、産業公害が問題になり始めた昭和40年代からである。この時期には、悪化する産業公害に対し、社会の厳しい目が向けられ、企業の社会的責任が問われた。40年代後半から企業の公害防止投資支出などは急速に増加した(第4-2-14図)。政府においては、42年に「公害対策基本法」を制定し、事業者の公害防止の責務を明確化し、様々な公害関係法令を整備していったほか、46年6月には「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」を制定し、同年7月には環境庁を設置して、公害規制の一元的な立案や運用を始めるなど、官民を通じた体制の整備を進めていった。こうした責任の明確化や体制の整備もあって、激甚な産業公害は徐々に改善され、企業の公害対策もいわば定着していった。
しかし、近年、地球環境問題や都市・生活型公害に直面する中で、企業には従来からの産業公害対策とは違った取組が求められるようになってきている。従来の産業公害では、工場周辺の住民の健康保護といった明確な目標があり、健康に危害を与える物質は自社の製造課程で生じ、煙突なり排水口を経て周辺の環境に出ていくので、住民の健康保護のためになすべきことは技術的には明確であった。また、どの程度の公害対策を施すべきかについても、例えば、法令に基づく排出基準や立地する地域の公害防止協定といった企業の外部からの要請を遵守することが基本であった。他方、地球温暖化の主因である二酸化炭素の排出抑制といった問題では、将来世代の、それも全地球的な環境の保護が目的となり、二酸化炭素排出削減のための手段は、無数にあるものの特定の製造プロセスの改善といった決め手を欠いており、むしろ全社的なきめ細やかな対応をシステムとしてつなぎ合わせていくような対応策が求められる。さらに、対策の程度についても、我が国の二酸化炭素排出量についての目標はあるが、個々の企業の具体的な対策については、企業の自主的な判断に委ねられている。他方、地球環境への関心の高まりに伴い、国民の注目は企業にも向けられており、対策の実行は避けて通れないものとなっている。
(2) 環境にやさしい企業行動の内容
こうしたことから、企業では、自主的な対応を迫られることになり、各企業で多彩な取組が進められるようになった。このような取組がどのようなものであるかについては、例えば、平成3年4月に作られた経団連の「地球環境憲章」が参考となる。この憲章は、世界の「良き企業市民」として、社会からの共感を得て、持続的発展の可能な環境保全型社会の実現に向かう新たな経済社会システムの構築のために、企業が環境問題に真剣に取り組むことを促したものであり、4年5月の経団連の調査では、7割以上の企業が同憲章を活用して、環境問題への取組を強化している。その中で会員企業に推奨されている取組は、概ね第4-2-1表のようになり、きわめて広汎多岐にわたっている。これらの取組の実施状況に関し、環境庁が一部、二部上場企業を対象に平成4年に行ったアンケート調査(第2回「環境にやさしい企業行動調査」、回答率25.4%)の結果は次のとおりであった。まず、企業の業務のうち、環境配慮の対象となっているものをその種別ごとに見ると、通常の業務については約78%の企業で、また、廃棄に係わる業務については、約66%の企業でそれぞれ何らかの環境配慮が行われていた。これに対して、企業活動のいわば上流に位置する資源採取に係わる業務については、事業活動が直接資源採取と関係する企業は少ないこともあって、約13%の企業で対応を行っているに過ぎなかった(第4-2-15図)。
また、企業の環境保全経費(投資額ではなく、年々の経費。ただし、その範囲は企業により異なる。)については、製造業(回答企業75社)に限ると、売上高比0.7%が平均であったが、環境に係わる経費を集計していない企業も多かった。
(3) 環境保全組織
企業の行う環境保全業務は、製造過程での公害対策はもとより、相当大量の業務となっている上に、企業内の各組織が担当する各種の業務においても環境への配慮が行われており、その全体は複雑でかつ大量なものとなっている。こうしたことから、企業では環境保全自体を業務とする組織を設けつつある。
前述の環境庁アンケート調査の結果によると、企業内に環境対策組織が設置されたのは、地球環境問題が注目されるようになってきた平成2年以降が最も多い。また、40年代後半に公害対策部署が設けられていた製造業においても、公害問題だけでなく地球環境問題等を合めた環境問題全般を扱う部署に改組された例も多くなっている(第4-2-16図)。また、事業活動が環境に負荷を与える割合が多いと思われる第二次産業以外においても、環境保全業務を担当する部署を設置する企業が増えてきた。
以下では、これらの環境保全部署の果たしている役割などを見てみよう。
ア 環境対策と企業の目標との関係
多数の人々が共に働く企業においては、多数の互いに矛盾する可能性のある希望や期待を整理して、共通の目的に統合し、これに向かって様々な活動を行っていくようにすることが、組織として活動していく上では不可欠のことである。特に、企業にとって、環境対策は直接的な利益を生み出すものではなく、近時の不況期においては企業にとっての負担感は小さいものではない。このような厳しい状況の中で環境に配慮した行動を取っていくためには、個々の企業の目指すべき目的の中に環境保全が位置づけられていること、あるいは環境に関する特別の経営方針が確立されていることが重要である。前述のアンケート調査の結果では、全体で35%の企業で環境に関する方針を制定しており、さらに製造業に限ってみれば45%と半数近くの企業が何らかの方針を制定している(第4-2-17図)。また、この調査によれば、これらの方針は環境を専門に担当する部署によって起草されたり、内容が決められたりすることが多い。
イ 全業組織内の環境担当部署の位置
企業の組織の中で、環境担当部署はどのように位置づけられているかを、同じアンケート調査により見ると、環境担当部署は、「社長直属の機関」、「総務・管埋部門の一部」、「企画部門の一部」とされているところが併せて50%以上を占めている。なお、他のあり方としては、製造部門や営業部門の一部というライン組織として機能しているものが17%あった(第4-2-18図)。このように、環境担当部署については、いわゆる本社組織の一部となっているところが多く、スタッフ組織として機能し、ライン組織の行うものも含めて社内の環境対策を統括している事例が多いと言える。また、環境担当部署の長について見ると、社長・会長も含めて取締役以上が約3分の2を占めている。以上のことからみても、企業の内部においては環境保全は、全社的にまた、経営のトップレベルで推進すべきものとされていると考えられる。
しかし、組織の大きさを見ると、環境担当部署の専任スタッフは過半数の企業で10人以下となっており、企業内における組織としては決して大きなものではない(第4-2-19図)。
ウ 企業の意思決定への環境担当部署の関与
次に、環境担当部署が企業内の意思決定にどのように影響力を有しているのかを見ると、企業全体の経営全般にわたる方針や長期計画の策定に対しては、環境担当部署が何らかの影響力を有していると回答した企業は36%に過ぎず、他にも、主な設備投資の決定や年間生産計画の策定、新製品生産の是非といった項目については、環境担当部署が有する影響力はいずれも小さいという結果になっている。環境担当部署が大きな影響力を有する項目は、環境保全予算の決定や環境保全関連費用の支出、環境対策実施状況のチェックといった環境に直接関係する項目に限られているという結果になっている(第4-2-20図)。なお、アンケート調査に表れてはいないものの、設備投資等を行う際に、環境担当部署の同意が必須となっている企業もあり、環境担当部署の関与も大きくなりつつあり、変化しつつある過程にあるといえよう。
エ 環境保全部署と他の部署との調整
環境対策のように非収益的な活動に関しては、環境担当部署と他の部署と見解の相違が生じる可能性があり、このような場合の意思決定に際して関係部署間の調整の仕組みを用意しておく必要がある。こうしたことから、稟議書の中に環境担当部署がチェックする欄を設けて環境配慮を行うなどの工夫も見られるようになってきている。
オ 環境保全活動を担保する仕組み
また、企業の活動を環境に配慮したものにするためには、環境保全に関する方針の履行状況、実際に行われる活動の環境負荷を点検するシステムも重要である。企業の中には、環境に関する取組について自主的に内部監査を行っているところも増えてきている。一般に環境監査と呼ばれ、1991年(平成3年)に国際商業会議所(ICC)等の主催の環境管理に関する世界産業会議で採択されたロッテルダム憲章や経団連地球環境憲章等にもその理念が盛り込まれている。産業界の専門家の協力を得て、環境庁が企業の環境保全に関する取組の参考となるよう取りまとめた「環境にやさしい企業行動指針」の中においては、環境監査について、環境管理システムの有効性を点検するための監査計画を作成した上、可能な限り、対象となる活動分野の関係者から影響を受けない、専門知識を有する者によって実施し、監査の結果は、環境担当役員その他の責任者に報告する、と表現されている。アンケート調査では、環境監査を実施している企業は33%であり、特に製造業においては、46%の企業で既に実施されている(第4-2-21図)。監査結果の公表等の問題を抱えているものの、企業の中においては、環境保全部署の設置、環境に関する方針・計画の策定、そして、その実施状況についての点検といった一連の環境保全に関するシステムヘの試行が進んで、いると言えよう。
(4) 企業の海外事業展開と環境問題
我が国企業は活発に事業の海外展開を図っている。このような中、1992年(平成4年)の7月、マレーシアの日系企業が環境問題についての裁判において、環境汚染に対する住民の不安を理由に、操業停止の判決を受けたが、このことに伴い、日系企業の海外進出と環境の問題についての国民の関心がにわかに高まった。日系企業と言えども、所在国の法律の下に設立された独立した法人であり、これら企業に適用される法律は日本法ではなくその所在国の法律である。こうしたことから、我が国の国内並の環境保全的な行動を海外日系企業に義務づけることはできない事情がある。経験も技術も有する日系企業が環境の観点から模範的な行動を示すことを多くの国民が期待する一方、特定の事例についてのみ現地の状況が伝えられるだけで国民の不安がかえって増幅されかねない事情にある。
このようなことも踏まえつつ、環境庁では、海外進出の中でも途上国への進出を取り上げ、在外日系企業の環境保全への取組に関して調査し、実態を把握するべく、日系企業の立地が多いタイとインドネシアを事例として、同地に立地している日系企業のうち433社にアンケート調査を行った(回答率19%)。以下、これら2カ国の事例についての調査結果をもとに海外日系企業の環境保全への取組を見よう。
ア 立地の段階での環境配慮
回答企業全体の約7割が立地に当たり環境上の問題は生じなかったと回答しており、何らかの問題が生じたと答えた企業は23%であった。52%の企業が現地政府の定めるアセスメント手続きがあると回答しており、46%が自主的な調査を含め立地に際し何らかの環境アセスメントを実施している。環境調査の結果、計画や設計の変更、対策の強化を行った企業はアセスメントを行った企業の17%であった。アセスメントを行わなかったとの回答が28%、無回答が11%あるが、環境への影響が元来乏しいため、環境アセスメントの必要性に欠ける業態での立地が考えられる点や回答企業全体の27%が、我が国においてもアセスメント手続きが普及していなかった20年以上前に現地に立地した点を考慮することが必要である(第4-2-22図)。
イ 操業上の環境対策
前述の「環境にやさしい企業行動調査」では、企業の海外進出の理由を聞いているが、途上国の環境規制が緩いことを理由にしたものはわずかであり、進出企業が環境規制に対し消極的と決めつけることはできない(第4-2-23図)。実態面を見ると、タイ、インドネシアヘの進出企業についての調査では、回答企業の全体の77%が現地の環境保全法規等について承知しており、現地法人または本社として環境管埋の方針等を持っている企業は71%であった。実施している環境対策の目標については、現地国の基準に合わせた企業が61%と最も多く、次いで現地国基準以上の自社基準13%、日本国内の水準13%であった。なお、現地の基準が日本国の基準より必ずしも緩いものとは限らない点に留意を要する。62%の企業が汚染物質排出量の測定を実施しており、公害防止管埋者等の公害対策組織ないし環境保全の責任者を置いている企業も66%あった。
ウ 環境対策を進める上での課題
環境保全に関する現地政府との関係については、全体の約9割が今までトラブルは無かったと回答しているが、同時に43%がいつかトラブルに巻き込まれるのではないかと将来への懸念を表明している。トラブルの内容としては、改善指導の内容、排水基準等の突然の変更、技術の違いによる測定値の相違があげられている。なお、自社以外の他の企業、特に地元企業については、環境上のトラブルを抱えているとの印象を多くの企業が持っている(第4-2-24図)。合弁相手や地元住民、市民団体との関係については、87%が環境上の問題で意見の違いが生じた経験は無いと回答し、関係は概ね良好であるが、前述の「環境にやさしい企業行動調査」において、海外進出時の環境対策上の困難については、「合弁相手先等の環境認識が低い」と回答した企業が44%と最も多くなっており、合弁相手先の環境保全意識を高めていくことも、重要な課題であるといえる。
また、環境対策関係の支出の負担感については、現在は軽いが将来は心配である、との回答が59%と最も多く、今後規制が厳しくなった際等に負担が増すことの懸念が見られる。以上のとおり、これらの事例では、多くの日系企業はその環境対策に自信を持ちつつも、進出先国の環境対策の確立期に当たるため、強化されつつある規制への対応に若干の不安を持っている状況にあると考えられる。海外進出企業の環境対策の一層の対策の充実のための方策を問うた質間には、現地政府から進出先企業への支援策の強化、現地国民の環境意識の高まり、廃棄物処理業者等の現地の環境関係業者の能力向上等、現地国側の方策を求める回答が合計で81%を占め、多数であった(第4-2-25図)。
(5) 環境分野での社会貢献
企業は、自らの活動に係る汚染物質の排出を削減するなど、環境への負荷を少なくすることを自らの責務とし、進んで果たすよう努める必要がある。このことは当然として、さらに、社会の一員として、国民一人ひとりが行うのと同じように、事業との直接の関係がなくとも社会への貢献を積極的に進めることが企業には期待される。こうした社会貢献活動については、経団連においても「1%クラブ」を提唱し、経常利益の1%を社会貢献に当てようと働きかけている。2年度における社会貢献活動全般に関する企業寄付総額も5,491億円(42億ドル相当)にのぼり、米国の59億ドルには及ばないものの我が国の企業の社会貢献に対する最近の積極的な姿勢が伺える。
環境分野においても社会貢献活動が進みつつある。環境庁の前述のアンケート調査を見ても67%の企業が「地域活動への参加」、「環境に関する基金・団体への支援」等の形で活動を行っている(第4-2-26図)。経団連が平成3年に会員企業を対象に実施した調査においても、138件の環境に関する社会貢献が行われたことが報告されているし、関経連が行った調査においても、社会貢献の重点分野として、環境保全があげられている(第4-2-27図)。
企業の社会的貢献は、量的な面だけでなく、質的な面でも深まりつつある。例えば、企業が地域社会、市民とのパートナーシップの下、一つの事業に貢献するグラウンドワーク事業も社会貢献活動の一つである。グラウンドワークの活動は、イギリスで1968年(昭和43年)の終わりからの歴史を有する。その内容は、前節の6で見たとおりであるが、我が国においても、このパートナーシップ方式の活動が関心を集めており、静岡県三島市と長野県塩尻市・山形村が我が国最初の実験地区とされ、英国のグラウンドワーク事業団の協力を得て日本版のグラウンドワーク事業の実践活動が始まりつつある。
資金力だけでなく、企業の持つ様々な長所、例えば、優秀な人材、幅広い取引関係、豊富な資材などを活用した企業ならではの形の社会への貢献については、このグラウンドワーク活動に見るとおり、大きな発展の可能性があると考えられる。例えば、4年9月に設立された経団連「自然保護基金」は、我が国の産業界として、途上国におけるNGOの自然保護活動を支援するとともに、内外の環境市民団体を通じて、国内の人材育成を推進することを目的としている。企業の環境分野の社会貢献が深まるに伴い、国民や地方公共団体、政府の側でも人材等各種の手法を用いた企業の社会貢献をより円滑に進めるための受け皿や枠組みの整備が必要となろう。
(6) 持続可能な社会における企業の一層の役割の発揮に向けて
以上見てきたように、企業の環境保全への取組は拡大してきているが、その努力が報われ、息永いものとなっていくためには、努力した企業が製品の消費者や国民から正当に評価され、支持されることが必要である。ちなみに、消費者の評価に関し、環境保全型の商品を扱っている企業の評価を取り上げてみると、第4-2-28図のとおりであり、むしろ率直な評価が寄せられている状況にある。企業は、その生み出す製品やサービスを通じて消費者等にアピールすべきなことはもちろん、さらに、宣伝、広報、情報開示といった努力も行い、積極的に国民の支持を勝ち得ていくことができよう。また、消費者の側には、企業の努力になお一層の関心を払い、それを応援していく主体性が期待される。
企業の環境保全努力は、個々の企業にとっては直ちに利益にはつながらない費用負担増を意味し、決して容易なものではない。しかし、この努力は、個々の企業の健全な存続のために不可欠なものである。さらに、我が国の厳しい公害対策の際に経験したように、企業の費用増、ひいては製品の価格増に伴う国民経済の冷却効果は、個々の企業の公害防止設備等への投資等によりもたらされる経済拡大効果と相殺され得る性格のものであり、経済をマクロに見れば、より環境保全的な経済発展も十分に可能であって、国民経済全体の発展と企業の一層の環境保全努力とは決して矛層するものではないのである。政府においては、途上国政府における円滑な環境行政の整備に向けた支援を含め、析角の企業の創意工夫や努力を生かし、これを社会全体としての成果につなげていく枠組みの整備などを行うことが必要である。