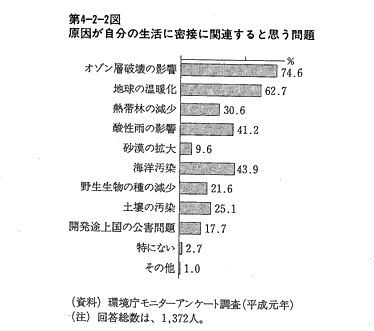
1 国民
第2章第1節に見たように、我が国では、国民の消費が国民総支出の約56%に相当する大きさとなっている。これから誘発される産業投資などを加えると、国民の消費が我が国の経済社会に与える影響はさらに大きなものとなる。国民の活動が全体として大きなものになるにつれ、国民と環境との関わりも密接になり、例えば、都市・生活型公害や地球温暖化に見られるように、国民一人ひとりの生活が環境問題の一つの原因となってきている。このことは第2章第1節で見たとおりである。このため、ライフスタイル自体を環境にやさしいものに変えていくなど、国民による積極的な取組が行われることが重要になってきている。
地球サミットで採択されたアジェンダ21においても、地球環境の保全のために、国、地方公共団体のみならず、国民やその団体の役割が重要であることが指摘されている。ここでは、環境保全へ向けての国民の役割と取組の現状を考えるとともに、国民が他の人々と協力し、あるいは外国の人々と協力し、環境保全に建設的に取り組んでいる草の根の市民活動について見てみることとする。
(1) 環境保全に関する国民の意識及び行動
近年の地球環境の悪化への不安や1992年(平成4年)6月に開催された地球サミットを契機として、環境に関する意識は急速に高まってきている。総理府が、5年2月に実施した世論調査で見ても、工場による大気汚染や水質汚濁の関心よりも生活排水やごみの増大などの生活に起因する問題や地球環境問題を中心に、国民の関心は年々高くなっている(第4-2-1図)。また、地球環境問題が、自らの生活に密接に関連していることについても、国民の多くが認識するようになっている(第4-2-2図)。
このような意識の変化は、国民の消費行動にも反映されてきており、日常生活において環境保全について心がけている人の割合は9割を超えている(第4-2-3図)。具体的には、環境に与える負荷の少ないエコマーク商品を約17%の人がこれを購入したことがあると答えている(第4-2-4図)。また、日常の商品の使用や廃棄といった段階においても、てんぷら油等を排水口から流さない、なるべくごみを出さないようにする、節電や節水に努める、リサイクル・分別収集に努めるなど、環境保全のための工夫や努力を行っている(第4-2-5図)。国民の意識は、環境の大切さや環境保全の意義を理解する段階を経て、今日では、自らの環境負荷を減らすべく実際に行動するレベルまで高まってきたと言えよう。
平成5年3月に国会に提出された環境基本法案においても、環境問題の背景、原因や、以上に述べたような国民一人ひとりの意識の高まりを踏まえて、環境に対する国民の責任がはっきりと位置づけられた。すなわち、同法案は基木理念として、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築するに当たって、「社会経済活動その他の活動による環境への負荷をできる限り低減することその他の環境の保全に関する行動がすべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われるようにすること」を掲げ、また、国民の責務として、「国民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない」ことや「基本理念にのっとり、環境の保全に自ら努めるとともに、国または、地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する」ことを規定した。
ア 自主的な環境保全努力を妨げる事情
国民が役割を分担し、環境の保全努力を自主的、積極的に担っていくことが期待されているが、国民の努力を促進し、それを円滑、効果的に成果につなげていくためには、いくつかの障害がある。例えば、環境庁が実施した調査によれば、環境保全活動については、現在、40%の人が、新たに始めたいという意向を持っているものの、どのような活動ができるかについての情報がない、活動を行う時間、仲間、資金がないという障害があり、意識の高まりほど活動が積極的に進まない状況にある(第4-2-6図)。NHKが行った生活時間調査を見ても、各種の社会参加活動に充てられている時問は日曜日でも平均わずか23分に過ぎない。
イ 政府等の取組
このような困難や障害を克服し、幅広い国民の参加と協力の下で一層効果的に環境の保全が進められていくよう、政府や地方公共団体、あるいは企業は様々な対策を始めている。政府においては、自然とふれあう活動を推進するための人材として、自然解説指導者(インタープリター)の育成を支援したり、都道府県が、住民に対し環境学習の機会を提供し、継続的な環境活動を促進するための拠点を整備する際の指針づくりを計画している。このほか、国土緑化推進運動等の支援を行っている。また、地域の環境保全活動を推進するものとしては、各都道府県に地域環境保全基金を設け、教材の作成、普及啓発行事の実施などの個別の事業の実施を支援している。
また、企業においても、社員が社会頁献活動をする際に、休職扱いとし経済的保障を与えたり、ボランティア休暇等の制度を設け、支援する動きも出てきている(第4-2-7図)。このような企業の動きを受けて、産業界としても、例えば、経団連では「地球環境憲章」において、世界の「良き企業市民」たるべく、従業員が環境保全活動に自主的に参加することを支援するよう努めることを企業の環境保全活動の一つに位置づけている。このように、様々な主体が環境保全活動を進めやすくするために支援を始めている。前述の環境基本法案においては、これらの国民各階各層の取組を一層進めるよう、環境の保全に関する教育、学習等や民間団体等の自発的な活動を促進するための措置を政策として明確に位置づけられており、今後は、新しい理念の下に、これらの措置が一層充実・強化されていくことが望まれる。
(2) 環境保全市民団体の抱える困難
国民一人ひとりが自身の行動を環境に負荷を与えないようにすることに加え、国民が互いに不足を補い、長所を活かして協力して活動することも考えられる。これは、国民の取組の成果を大いに高める可能性がある手法である。
我が国の環境保全に関する市民団体の活動を振り返ってみると、その歴史は古く、既に昭和初期には自然保護活動が全国的に展開されていた。現在、我が国最大規模の環境市民団体の一つである(財)日本野鳥の会は昭和9年に発足しているし、(財)日本自然保護協会も26年には誕生している。その後、高度成長期には産業公害に対する被害者の権利回復を要求する活動が盛んになり、国民に大きな反響を呼ぶところとなった。
また、生活排水やごみ問題といったいわゆる都市・生活型公害が顕在化してくると、自分たちのライフスタイルを見直していこうという実践型、提案型の市民活動が進められるようになり、近年では、地球環境問題についての認識の高まりとともに、活動規模も国際化し、地球的視野の広がりをもった活動を行う自主的組織(NGO(非政府団体))が増え始めている。他方、1980年代に、途上国の開発援助を目的に始まったNGO活動が、貧困と環境破壊が密接に結びついていることもあり、環境問題にも取り組んでいる。
環境市民団体の活動は、団体活動自体による大きな成果が期待されることのほか、団体による活動参加を通じた人材育成効果、さらには広範な国民に対する意識啓発にも効果を有するなど様々な意義を持つ。さらに、市民が地球市民として世界各地の人々と連帯して、開発途上国での環境保全活動に力を尽くす事例が出てきている。このような公益的民間団体による国際援助は、草の根レベルで地域社会に密着した事業を直接実施でき、ヒューマンニーズの高い事業にきめ細かい対応が可能であり、また、国、地方公共団体による対応でカバーしきれない分野での活動や住民の二一ズに迅速に対応した活動などを展開し得るという特色も併せ持っている。市民が国境を越えて助け合い、環境問題に取り組み始めたことに伴い、市民は、新しい形の協力関係を発展させていく必要に追られている。以下では、市民が結ぶ協力関係として最も困難なものと思われる国際協力を取り上げ、問題点とそれを克服する方向を考えてみよう。
環境市民団体の抱える第一の困難は、資金の不足である。我が国の市民団体による途上国における環境保全の活動を始めとする各種の国際協力の援助実績は、ODA総額に対する比率で1.9%、国民一人当たりの援助額では1.4ドルに過ぎず、どちらで見ても先進諸国の中でかなり低い状況にあり、その拡充が課題となっている(第4-2-8図)。
このように、我が国の環境市民団体による国際環境協力は諸外国に比較し、量的には必ずしも大きな実績をあげ得ていない。我が国の環境市民団体の現状に関する調査には、環境庁が、平成4年に661団体を対象に行ったアンケート調査がある。その結果によれば、地域を中心に活動している団体(地域型団体)の7割近くが常勤の有給スタッフがいない状況であり、20名以上の有給スタッフを持っている団体は、国際的に活動を行っている団体(国際型団体)でも2割程度に過ぎない。年間の予算を見ても100万円以下の収入しかない団体が地域型のものの6割にものぼっており、国際型団体においても、ほぼ半数の団体が5,000万円以下の収入に甘んじている(第4-2-9図)。これに対し、欧米の非政府団体は、我が国のそれとは異って、長い歴史を持っていることもあるが、100億円を超える予算や数百万の会員数を持つ環境市民団体も見られる(第4-2-10図)。我が国の公益的民間団体は、欧米諸国に比し、会員数も少なく、財政基盤もはるかに脆弱であるといわれているが、環境市民団体も例外ではない。
市民団体等の公益的民間団体の多くが資金不足を訴えているのは、我が国においては、社会貢献のための寄付の伝統が浅いこと、市民の独自の活動が真に評価されておらず国民の理解が不足していること、これまで市民団体と行政や産業界などの国民各界各層との対話が不足しがちであったこと、などの理由があげられる。我が国の場合、個人のうち納税申告を行ったものの寄付額は、国税庁の調査によれば、366億円(平成3年分)、企業による寄付は5,634億円(平成3年分、国税庁調査)であるが税制上の優遇措置のなお一層の活用が期待されるところである(第4-2-11図)。また、企業の寄付の理由として意識されていることの6割近くは他社からの要請であって(第4-2-12図)、必ずしも自主的な判断に基づいているわけではない。他方、外国の一例として米国を見ると、慈善事業や社会貢献についての長い伝統があること等、寄付を行いやすいような社会的環境があると言われ、1990年(平成2年)の個人寄付総額は1,018億ドル(12兆4,000億円強)、法人寄付総額は59億ドル(7,000億円強、いずれもAAFRC,GivingUSA 1991より)となっている。
資金以外にも環境市民団体の抱える課題は数多い。そのなかには、市民団体側の努力不足や認識の誤り、方法の未熟といったものもないとは言えない。これらの点の改善には市民団体自身の自助努力が期待されるが、このほか、これらの団体を取り巻く問題として、前述の市民団体へのアンケート調査によれば、全体の4割強の団体が「情報」が不足していると考えており、特に「環境保全活動の手段・方法に関する情報」が不足していると感じていることがある。また、人材についても6割近くの団体で不足感がある。さらに、我が国の環境市民活動は、資金の問題を始め、実践活動に必要な情報及び人材が不足しており、それが活動の阻害要因となっていると言える(第4-2-13図)。
(3) 環境市民団体への支援
政府としても、地球環境問題への関心が高まり、市民の自主的な活動を皆で支えなければならないという認識が広く受け入れられてきたことを踏まえ、活動に対する助成等を始めつつある。開発途上地域の環境保全活動に関しては、住民の福祉向上に役立つ市民団体の事業に対し、外務省において、平成元年度にNGO事業補助金制度を創設したのを始め、3年度からは郵政省において国際ボランティア貯金による援助事業が始められた。しかし、これらの仕組みは助成の対象を環境保全に限らない幅広いものとしていることもあり、環境市民団体の二一ズの増大、さらには多様化に応えきれなくなっている。
このような背景から、我が国の政府と民間が力を合わせ、民間団体による地球環境保全分野の活動を支援するための地球環境基金を環境事業団に設置することを内容とする環境事業団法改正法案が、5年2月、第126回国会に提出された。官民の力を合わせて市民レベルの国際環境協力を支援していこうという考えは、1992年(平成4年)6月に開かれた地球サミットでも示されたが、また、それに先立って、同年4月に東京で開かれ、地球環境を守る資金の問題についての世界の議論の方向付けを行って地球サミットに貢献した「地球環境賢人会議」においても示されたところである。地球環境基金は、地球環境賢人会議の際の提案をきっかけに検討が進められ、環境事業団法の改正によって具体化されたものである。本基金は途上国における環境市民団体の実践活動への支援はもちろん、環境事業団が自らこれらの団体の活動の進行に必要な調査研究、情報の提供、研修等を行うことにより、環境市民団体に対して幅広くきめ細かな支援を図ることが計画されている。
5年3月に国会に提出された環境基本法案においても、地球環境保全等に関する国際協力を推進する上で民間団体等によって、国際協力のための自発的な活動が行われることの重要性を明確にし、こうした活動の促進を図るため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めることが規定された。広く国民各層、さらには企業を含めた広範な参加・協調の下に、環境市民団体の国際協力活動に対する長期継続的な支援制度として本基金が充実され、環境市民団体の担う国際協力がますます優良なものとして発展していくことが期待されている。また、環境市民団体の活動の成果が豊かになることにより、国民の生活に慈善や貢献といった価値がなお一層定着し、我が国の社会が一層の道義的高さを獲得していくことも期待できよう。