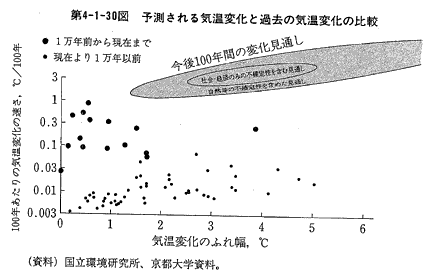
8 地球温暖化対策
地球温暖化は、主に石炭・石油等の化石燃科の燃焼等により、二酸化炭素等の温室効果ガスの大気中濃度が上昇し、地球規模の温度の上昇、気候の変動等が生じる問題である。
WMO(世界気象機関)等の組織する気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の報告書によれば、温室効果ガスの濃度が現在の増加率で推移した場合、地球全体の平均気温は2025年(平成37年)までに現在より約1℃、21世紀末前には3℃上昇することがあり得るとしており、この影響により海面水位は2030年(平成42年)までに約20cm、21世紀末までには65cmの上昇が予想されている。この温度上昇は、人類にとって未経験の変化である。過去90万年の間に地球の平均気温は最大で約5℃変化しているが、この変化は2万年程度をかけた非常にゆっくりとしたものであった。また100年に1度の割で非常に速く変化した時期も見られるが、その変化の幅は、0.5℃程度にとどまっている。一般的に過去の地球の気温変化は、変化の幅が大きい場合はゆっくりと変化し、変化速度が速い場合は少しの幅の中で変化してきた(第4-1-30図)。しかし、今後100年間の気温の変化の見通しは、変化の幅も速さも非常に大きく、我々は過去90万年に経験したことのない未知の環境変化を迎えようとしている。未来には、海面上昇、水収支の変化、突発的気象現象による災害、生態系の破壊、健康影響等、いろいろな被害発生のシナリオが描かれている。
地球温暖化は、各方面に甚大な影響を及ぼすことが予想されるため、被害が顕在化し取り返しがつかない事態が生じないよう、対策を今の段階から早急に進めることが、国際的にも合意されている。一方、対策を具体的に進める上での様々な問題点もある。以下では、地球温暖化対策を進める上での様々な困難が生まれやすい背景事情とそれらの克服策の方向を見てみよう。
(1) 地球温暖化対策を難しくしている事情
まず、地球温暖化では、原因とその結果の発生との間に大きな時間のずれがあり、人類に大きな影響が生じるおそれがあるのは将来のことである。例えば、温室効果ガスには大気中における寿命の長いものが多く、第4-1-31図にあるように、影響は累積的に生じる上、仮に温室効果ガスの濃度を現在の濃度に安定化したとしても、大きな地球のシステムの変化に要する時間、すなわち自然の反応の持つ遅れにより、温度上昇は容易には停止しない。しかも、海面上昇はさらに遅れて応答すると考えられている。現代世代は、環境資源を自由に使うことによって、経済的利益を得ているが、このことは将来世代の得るべき利益を先取りし、負の遺産を将来に残しているともいえる。しかし、将来世代には現代への発言をする機会はない。
地球温暖化の持つこうした影響面での時間的な広がりは、そのメカニズムの複雑さともあいまって、問題の認識を困難にしている。技術の開発や普及を含め、対策についても、いつ、どのような対策を取るべきかということについての合意を得ることを難しくしている。
また、特に二酸化炭素の排出は、エネルギーの利用と深く係わっており、このため、経済社会の在り方と密接な関係を有している。例えば、国立環境研究所の研究によれば、同じ人口規模であれば人口密度の高いコンパクトな都市が、また、都市が集中せず国土の中に適度に分散している方が、それぞれ二酸化炭素の排出が少ないことが報告されている(第4-1-32図及び第4-1-33図)。
さらに、利害や立場を異にした極めて多数の関係者に対策に参加してもらうことの困難がある。二酸化炭素は、上記に述べたとおり、日常の経済活動や国民生活から広く発生するものであり、対策を実施する際の対象範囲も極めて広範囲であって、それが及ぼす影響も大きいものと予想される。
特に、温暖化は地球規模で生じ、対策も全世界的に行われる必要があるため、利害や立場を異にした世界の各国の参加を得る必要がある。また、世界の国々の中には技術、費用等の面で有効な対策を取れない国もあるという問題もある。
(2) 地球温暖化対策の国際的な枠組みの整備と今後の課題
このような種々の事情のうち、世界各国の参加を得ることに関しては、1992年(平成4年)に大きな進展があった。すなわち、同年5月に、気候変動の問題に対処するための国際的な枠組みとなる「気候変動に関する国際連合枠組条約」(以下、気候変動枠組条約という。)が、コンセンサスにより採択されるところとなった。本条約の交渉会議は、1990年(平成2年)12月の第45回国連総会決議を受けて、国連事務局の下に設置され、翌年2月から外交交渉を開始していたものである。地球サミットにおいて本条約は署名のために開放され、期間中に我が国を含む155カ国が署名を行い、今後、多数の国による本条約の締結が期待される。
この条約交渉においては、前述した各国の利害の違い、立場の違いを反映した議論が行われた。まず、地球温暖化をめぐる責任論が途上国と先進国の間で繰り広げられた。途上国側が、これまでの温室効果ガスの排出についての先進国の責任を主張したのに対し、先進国側は、途上国からも一定量の二酸化炭素が排出されているとともに将来の排出が増大するとして、共通の責任を強調した。この結果、南北の意見等を踏まえ、共通だが差異のある責任と先進国による先導的役割が条約に規定された。
また、二酸化炭素排出抑制の先進国共通の目標設定については、EC、日本等が、概ね1990年(平成2年)レベルで2000年(平成12年)以降安定化することを先進国共通の目標として設定することを主張したのに対し、米国は科学的知見の不確実性、膨大な対策費用等の理由から反対した。このような対立を集約し、条約上は、先進締約国等は、温室効果ガスの排出を抑制すること等によって気候変動を緩和するための政策を採用し、これに沿った措置をとるとともに、これらの政策や措置等に関する情報を、温室効果ガスの排出量を1990年(平成2年)レベルに戻すという目的をもって、条約発効後半年以内に締約国会議に送付することとされた。
資金援助に関しては、途上国側が、先進国の義務的拠出による新規的かつ追加的な資金が必要であるとして新たな基金の創設を主張したのに対し、先進国は、世界銀行、国連環境計画及び国連開発計画により運営されている、地球環境ファシリティ(GEF)を条約に基づく資金メカニズムとすべきと主張した。その結果、条約の資金メカニズムを暫定的にGEFに委託する旨明記し、第1回締約国会議において、その暫定的措置をレビューし、GEFを継続的に利用すべきか否かを決定することで当面の決着が図られている。以上のほか、気候変動枠組条約では、締約国は、温室効果ガスの排出及び除去に関する自国の目録を作成し、締約国会議に通報すること、温室効果ガスの排出の抑制、減少又は防止に関する技術の開発等を促進し、これらについて協力すること、温室効果ガスの吸収源等の管理、保全等を促進し、これらについて協力することなどが定められている。本条約の仕組みは第4-1-34図に掲げるとおりである。このように、各国間の厳しい議論はあったものの、地球環境に係わるこれまでの条約の交渉と比較し、交渉の開始から1年半と極めて短い期間に条約が採択された(第4-1-35図)が、この点は特筆すべきであろう。その理由としては、地球温暖化は、人類全体に大きな影響を及ぼす重大な問題で、大気中の温室効果ガスの濃度を究極的には安定化させることが重要なことであるという点で世界各国が一致していたことがあり、また、地球サミットの開催に見られるように、地球環境を守るための国際的協調が今日までいろいろな機会に積み重ねられて、その必要性や実行可能性が広く各国に理解されていたこと、などがあげられよう。今後50カ国目の批准書等の寄託後90日目に条約が発効し、それから1年以内に第1回締約国会議が開かれることになっている。1993年(平成5年)3月31日現在、モーリシァス等の14の途上国及び米国、カナダ、オーストラリアの3先進国の合計17カ国が批准書等を寄託している。なお、我が国においても、平成5年3月、気候変動枠組条約の締結に係る国会承認を求める件が閣議決定されたところである。
今後は、本条約の速やかな発効を目指し、多数の国々の締結を求めて行くことが大切である。また、条約内容の早期の実行開始(プロンプト・スタート)についての幅広い国際合意を踏まえ、条約の実行上必要となる様々の事項について条約発効前からも準備を進めておくことが重要である。例えば、本条約に基づく政策や措置の立案やその効果予測などに係る事業を開始すること、GEFの活用のため、その充実や改善を図ることなどに世界の各国が取り組む必要がある。
(3) 地球温暖化対策をめぐる各国の動向
地球温暖化は、まさに地球規模の問題であり、国際的な協調を図りつつ、各国がそれぞれ努力することが必要である。以下では、他の先進諸国における地球温暖化防止に関する取組について見てみよう。
ア 世界の二酸化炭素排出状況
世界の二酸化炭素排出量については、第4-1-36図のとおりであり、世界中では年間およそ59.7億トン(炭素換算)の排出量になっていると推計されている。先進国が約半分のシェアを占め、残り半分を途上国と旧ソ連を含む旧社会主義国とで分けあっている。1971年(昭和46年)から1989年(平成元年)にかけての二酸化炭素排出量の推移について見ると、米国、日本といった先進国がマイナスか年率1%増程度の伸びであるのに対し、途上国や旧ソ連・東欧といった国々は軒並高い伸び率となっている。したがって、近年の排出増加量だけを取り出せば、途上国等が多くを占め、途上国と旧ソ連・東欧とを併せて増加量の8割以上を占めている。しかし、1人当たりの二酸化炭素排出量を見てみると、先進国の約3.3トン(炭素換算)、旧ソ連・東欧の約3.5トンに対し、途上国は約0.4トンに過ぎず、大きな差がある(第4-1-37図)。今後、途上国を中心に人口が増え続け、経済も発展していくことが予想されるが、有効な対策を講じることができなければ、二酸化炭素の排出量も大幅に増加することが避けられない。このため、1人当たり排出量の大きな先進諸国が率先して二酸化炭素の排出抑制を進めることに加え、途上国における排出抑制に関し、実効ある措置を講じることが急務となっている。
イ 先進諸国の温暖化対策の動向
ヨーロッパでは、ECが、1990年(平成2年)10月の環境・エネルギー相合同理事会において、二酸化炭素排出目標を2000年(平成12年)に1990年(平成2年)レベルで安定化する方針を決定した。この方針を実施する戦略として、ECの執行機関であるEC委員会は、エネルギーの生産や消費に係わる各種基準の設定、強化を進める加盟各国の各種の対策とEC共通の炭素・エネルギー税の導入とを2本の柱として、排出量を安定化する戦略を立案している(第4-1-38図)。この炭素・エネルギー税をめぐっては、現在、EC内においても様々な議論がなされ、政治家レベルの検討が続けられている。こうした中、オランダでは、このECの戦略を先取りした各種の対策が進められている。同国政府は、1989年(平成元年)及び翌90年に国家環境政策計画を策定し、これに基づき、89〜90年の二酸化炭素排出量を基準とし、1995年(平成7年)に排出量を基準年次量に安定化させ、さらに、2000年(平成7年)には、3〜5%の削減を図ることを目標に、ECが検討中のものと同種の炭素・エネルギー税を既に導入し、これらを通じて省エネルギーを促進し、自動車利用や廃棄物拡大を抑制するなどの二酸化炭素排出削減に資する政策やその他の温室効果ガスあるいはその前駆物質の削減のための政策を幅広く進めている。
ドイツでは、1990年(平成2年)に設けられた関係各省のワーキンググループの検討に基づき、1987年(昭和62年)を基準年次として2005年(平成17年〉には、1987年の排出量を25〜30%削減することを、1991年(平成3年)、政府の方針として決定した。現在、この目標の達成を目指して、幅広い対策を講じつつある。
また、北欧諸国を中心としたEFTAにおいても、1990年(平成2年)の第2回世界気候会議に際し、2000年(平成12年)における1990年レベルでの排出量安定化の方針を表明している。EFTAの国々では、多くの国で二酸化炭素排出削減を狙いとした炭素税が導入されている。これらの国々のうち、最も早い時期に炭素税を導入するなど、各種の二酸化炭素排出抑制対策に積極的に取り組んでいるスウェーデンでは、炭素税のみによる二酸化炭素排出割減量は1999年(平成11年)時点で年間500〜1,000万トンと予想しており、これは1991年(平成3年)の排出量に比較し、約8〜16%に当たっている。
米国については、1993年(平成5年)1月に、ブッシュ共和党政権からクリントン民主党政権への政権交代があり、新政権は、早速、大統領府に環境政策局を設けたことに見られるように、環境問題にこれまでよりも踏み込んだ対応を行うものと予想されており、地球温暖化問題への対応についても、今後の動向が注目されている。
なお、主要先進国の地球温暖化対策の目標については第4-1-10表のとおりである。このほか、OECDでは、IPCC等と連携を図りつつ、気候変動枠組条約の実施のための検討を行っているほか、地球温暖化への対処も念頭に置きつつ、各種の経済的手段の一層の活用についての調査検討を進めている。
(4) 我が国の地球温暖化対策
ア 地球温暖化防止行動計画の実施
既に述べたように、地球温暖化対策を進めるに当たっては、将来を見通した取組、対策についてのコンセンサスづくり、技術の開発と普及、さらには多数の関係者の積極的な参画が重要である。このようなことから、広範な施策を整合的かつ着実に進めるための枠組みとして、目標を明らかにし、その実現のための各種施策を一覧的に掲げ、幅広い関係者に期待される役割を明らかにした計画を策定することが有効である。
我が国においては、平成2年のヒューストン・サミットにおける海部内閣総理大臣(当時)の発言を受け、同年10月に地球環境保全に関する関係閣僚会議において、「地球温暖化防止行動計画」を決定した。これは、地球温暖化対策を計画的総合的に推進していくための当面の政府の方針及び今後取り組んでいくべき実行可能な対策の全体像を明確にし、国民の理解と協力を得るとともに、国際的枠組みづくりに貢献していく上での基本的姿勢を明らかにしたものである。
本計画は、将来世代に良好な地球環境を引き継ぐことを我々の世代の責務とし、世界各国が協調して直ちに実施可能な対策から着実に推進していく必要があるとの基本的な認識を明らかにした上、そのために配慮すべき事項として、環境保全型社会の形成、経済の安定的発展との両立、国際的協調を掲げている。二酸化炭素排出量の目標としては、官民挙げての最大限の努力により、本行動計画に盛り込まれた広範な対策を実行可能なものから着実に推進し、1人当たり二酸化炭素排出量について、2000年(平成12年)以降概ね1990年(平成2年)レベルでの安定化を図ること、さらに革新的技術開発等が現在予測される以上に早期に大幅に進展することにより、二酸化炭素排出総量が2000年以降概ね1990年レベルで安定化するよう努めることなどの目標を定めている。
本計画には様々な施策が褐げられているが、実施されている施策としては、施設整備として、ヒートアイランド現象緩和のための公園の整備等による都市緑化、二酸化炭素排出量の比較的少ない公共輸送機関のための基盤整備等の温暖化防止にも資する公共事業が行われ、また、公共施設の省エネルギー化、郵政事業や地方公共団体における低公害車の率先的導入などが図られた。
一方、制度の整備としては、3年10月、紙、飲科水用の罐等のリサイクルの努力義務を事業者に課すなどの内容の「再生資源の利用の促進に関する法律」を制定した。さらに、平成5年3月に「エネルギー使用の合理化に関する法律」(省エネルギー法)が大幅に改正され、エネルギー使用合理化に関する国の基本方針を定める規定を新たに設けたほか、事業者の省エネルギー対策への取組を加速させるための措置が強化されるところとなった。
また、同法の改正に先立ち、3年8月、4年2月及び5年1月には、同法に基づく措置により、それぞれ建築物の断熱材の性能及び自動車の燃費の向上が図られた。また、民間事業者の自主的な省エネルギー、リサイクル等に関する事業活動等を支援するための「エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法」も、5年3月公布された。
さらに助成措置として、大陽光等の分散電源、断熱構造化、省エネ建築設備、コジェネレーション、コンバインドサイクル発電等の導入に対し、政府系金融機関による融資、税制上の特例措置等により支援を行っているほか、安全性の確保を前提とした原子力の開発利用の推進等二酸化炭素排出抑制のための様々な施策が実施されている。
これら以外にもメタンその他の温室効果ガス排出抑制対策、森林保全等による二酸化炭素の吸収源対策、科学的調査研究、観測・監視の推進、技術開発、普及啓発の分野において、各般の施策を実施している。
国際協力の分野では、世界が手を携えて、地球環境を守る取組を進めていくこととなるよう、途上国の人づくりへの支援や相手国にふさわしい技術の移転、さらには、国立環境研究所等による国際研究協力の推進など、我が国の環境保全のための技術やノウハウを活かした国際協力を行っている。
イ ニ酸化炭素の排出量の動向
我が国の平成3年度の二酸化炭素排出総量は、環境庁の試算によれば、炭素換算で、324百万トンであり(第4-1-39図)、一人当たりの排出量は2.61トンであった。温暖化防止行動計画の基準年次となる2年度の排出量は、それぞれ318百万トン、2.57トンであったのでそれぞれ1.9%、1.6%の増加である。
この増加の背景を近年の動向も踏まえつつ、部門別に見ると、次のとおりである。まず、産業部門については、概ね80年代半ば以降、若干の増加傾向にあり、3年度においては、同部門全体の排出量では横ばいである。しかし、その大部分を占める製造業全体の生産額当たりエネルギー消費原単位が、総合エネルギー統計等によれば、石油危機以来16年間趨勢的に低下していたのが、3年度には、はじめて反転悪化し、前年度に比べ1.5%の増となった。
運輸部門については、過去からの増加傾向が続いており、3年度には、同部門全体で、前年度に比べ、2.6百万トン、対前年度比4.5%の増と、輸送量の増加率(対前年度比2.5%)を上回る水準となり、二酸化炭素の排出量は引き続き増加している。さらに、民生部門においても、近年の増加傾向に大きな変化はなく、家庭系、事業所系ともに増加し、同部門全体で、二酸化炭素排出量は、3年度に、前年度に比べ2.5百万トン増大した。
(5) 地球温暖化問題の解決を目指した一層の協力に向けて
以上のとおり、我が国の二酸化炭素排出量は、3年度においても、全体として、近年の増加傾向を維持し続けており、今まで長い間改善を見せてきていた製造業のエネルギー消費原単位が増加に転ずるなど、いわゆる「バブル経済」の流れの中で、経済社会全体が二酸化炭素排出の方向へ動いてしまったことは否めない。
このような中で、今後、我が国として、地球温暖化問題への取組を効果的に進めていくに当たっては、新たに国際合意を見た気候変動枠組条約の早期実行に努めるとともに、地球温暖化防止行動計画のなお一層の具体化を図り、幅広い主体の参画とますますの積極的な協力を確保していくことが不可欠である。
温室効果ガス、なかんずく二酸化炭素が、今日のあらゆる経済社会活動や日常生活に関わりを持っていることを考慮すると、あらゆる主体が、党悟を新たにもう一層の取組を図る必要がある。こうした取組としては、大は国土の利用、都市構造の改善から、身近な日常の生活行動の見直しまで極めて幅広いものがある。例えばエネルギー利用について見れば、熱やエネルギーの生産サイドから最終需要サイドに至るすべての過程において、発電所、工場、住宅といった壁を越えて、それぞれの持つ長所を活かし、短所を補える総合的な取組を協調して進めることが求められる(第4-1-40図)。こうした取組は、単に特定の分野の技術的隘路の解決を通じてなし得るのではなく、様々な制度を含め、経済社会自体の在り方や我々のライフスタイルの在り方そのものを見直すことによって、はじめて実現し得るものである。