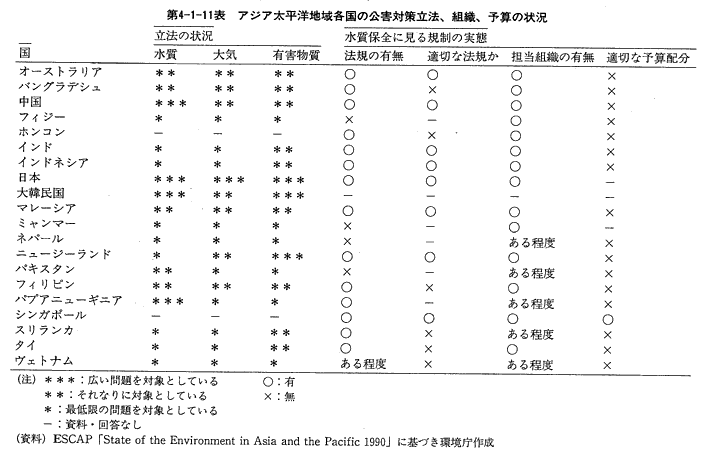
9 開発途上国の環境対策
今日、開発途上国の環境問題は、当該国限りの問題ではなく世界全体の関心事項となっている。経済が国際化し、原材料や製品、資金、サービスが自由に国境を越えて行きかうようになっている。このため、先進国等における経済活動のあり方が、貿易等を通じ、途上国における環境の利用のあり方に影響を与えたり、逆に途上国における環境の破壊、資源の枯渇が先進国等の活動に影響を与えることとなる。さらに地球温暖化のような地球環境問題については、先進国のみがいくら対策を行っても、これから経済活動を活発化する途上国においても適切な対策がとられなければ、世界全体として十分な効果をあげることが困難になる。こうした意味で途上国の環境対策は地球的な関心事となってきており、地球サミットにおいては、その最重要課題の一つになった。
昨年度の本年次報告では、開発途上園の環境問題の背景等について詳しく分析しているが、今年次の報告では、これを受けて、途上国での環境対策を広範な協力の下に進めていく上で中核的な意義を有する人の側面に着目し、問題点やその克服策を見ていく。
(1) 途上国の環境問題と途上国の環境保全政府組織の働き
途上国の直面する環境問題としては、第1章で見たとおり、一つには貧困が大きな原因となっている自然破壊、もう一つには急速な経済活動の活発化のもたらす歪みとしての公害、自然破壊が重要である。前者の例としては、貧しい農民が森林の開墾、畑地化を過剰に行うことにより、森林が破壊されることなどが挙げられる。後者としては、工業化や輸出向けの農林水産品の生産が急速に拡大し、これに環境対策が追いつかず、あるいは環境の改変や過剰な利用が行われることにより、水質汚濁や大気汚染、自然破壊が進行することがある。
途上国においても環境対策は途上国政府が中核となってそれを推進することが原則である。しかし途上国では政府の環境問題への取組の現状は必ずしも十分とはいえない状況にある。第4-1-11表は、アジア太平洋諸国における各種環境分野における法制度の整備状況と水質関連の環境保全制度及びその実施体制を示したものである。各種環境分野の法制度については、十分な範囲のものは多くないものの何らかの形では整備が進んできている。しかし、水質の例で見ると制度の実施体制は半数以上の国で十分なものとはいえず、さらに予算面では十分な配分がある国はほとんど見られない。これらの国においては法制度の整備は行われているものの、組織や資金など実態面ではまだまだ不足があるといえよう。環境対策技術移転を進めることや、その開発能力を向上させていくためには、その前提として、透明、公平かつ実際的な環境規制が実施されていることが重要である。このようなことからも途上国政府における環境対策能力の強化が必要となっている。
また、途上国政府自身の環境問題に対する姿勢により、環境問題の経過は大きく異なってくる。シンガポールと韓国を例にとって政府の役割の大きさを見てみよう。
シンガポール、韓国とも現在では開発途上国の地位から脱し、世界で最も急速に発展を遂げつつある国である。現在では、共に環境問題にも積極的に取り組んでいる。しかし、これまでの両国の環境に対する取組の経過には差が見られ、これが環境の状況に表れている。第4-1-41図は、シンガポール、韓国の大気汚染の状況である。シンガポールでは1980年(昭和55年)以来環境基準を超えていないのに対し、韓国ではようやく近年(1991年から)に至って基準を満足するようになっている。その間の両国のGDPの伸び及び環境対策の歩みの状況は第4-1-42図のとおりであり、シンガポールでは、1972年(昭和47年)に環境省が設立され、経済発展の初期から予防的に環境対策に取り組んできたのに対し、韓国は経済発展とともに環境が悪化し、その後経済発展のスピードが鈍る中で環境対策を進めることを余儀なくされてきている。持続可能な開発は、環境を保全しつつ経済発展を進めなくてはならないものである。両国はそれぞれ異った歴史的、社会的、経済的状況の中で取組を進めてきているが、シンガポールはその方向での取組に優れていたといえよう。
環境問題は、経済・社会政策の状況とも大きく係わっており、このため当該国の経済社会政策にも大きく影響を受ける。
途上国における森林減少・劣化や土壌流失、砂漠化といった自然資源の劣化は、貧困がその主な背景となっている。例えば、工業化が十分進んでおらず、農村の余剰労働力を十分吸収できない国においては、豊かな農地から締め出される貧しい農民が出現する。彼らは環境上脆弱な土地、例えば急傾斜の山地の森林を切り開き農地にしたり、乾燥しがちな土地で過剰耕作を行ったりする結果、森林の減少とそれによる土壌の流失、砂漠化を引き起こすことになる。
フィリピンでも森林の減少が深刻であるが、その原因として貧しい農民の流入による森林内での耕作地の拡大が指摘されている。第4-1-43図は、フィリピンにおける失業率と高地への移住の状況、森林地域における農地の割合を示したものである。特に1980年代(昭和50年代後半)に入る頃から森林の多い高地への移民が増え、同時に森林地域での耕地が増加していることが分かる。その理由としては、人口の増加にもかかわらず、土地所有制度との関係もあり、農業部門で農民を十分吸収できなかったこと、1980年代に入ってからの経済の停滞により、都市部でも労働力を十分に吸収できなかったことがあると指摘されている。
したがって、自然資源の劣化を防ぐためには、貧困を生じないような経済政策をとることが強く求められている。また、経済政策の運営に当たっては、開発による自然破壊や公害が生じないよう、その環境上の影響を考慮し、環境破壊を予防する政策を並行して進めることも重要である。こうした各種政策における環境への配慮は、地球サミットで合意された環境政策と経済政策の統合を進めるものである。
このような政策の統合の実現のためには、環境政策担当者のみならず、他の様々な政策担当者が自国の環境に配慮し、環境部局と十分連携をとって、政策を進めることが求められる。ここでも環境に関わる人々の能力向上が求められている。
(2) 途上国の人造り等への協力
ア 政府開発援助による協力
政府開発援助は、途上国が自ら行う取組について協力を行う重要な手段である。
我が国の政府べ一スでの環境協力は1980年代(昭和50年代後半)から進められてきており、その規模は近時急速に拡大している。平成元年6月の「地球環境保全に関する関係閣僚会議」では、開発途上国の環境保全に積極的に貢献するため、環境分野の政府開発援助の拡充、開発途上国の実情に応じた技術の開発・移転及び環境分野における人材の育成等に努めること、また政府開発援助等の実施に際しての環境配慮を強化することを申し合わせた。地球サミットでは、我が国は平成4年度からの5年間で環境分野の援助を9,000億円からl兆円を目途として大幅に拡充強化に努めることを表明した。環境分野の協力は実を結びつつあり、現在までにいくつかのプロジェクトについてその成果が現れてきている。
我が国が、フィリピンのパンタバンガンで1976年(昭和51年)から実施してきた林業協力についてその評価を見てみよう。この事業は、火入れによる畑地化、収奪的な牧草の再生方法による放牧によって草地、裸地化し、土砂の流失のおそれのあったパンタバンガンダム上流地域において、造林、治山、社会林業等の森林管理を行うことができるよう、森林保全、造成技術の開発、及び技術指導を行ったものである(第4-1-44図)。日本からは林野庁の職員を中心に延べ53名の長期専門家、及び91名の短期専門家の派遣が行われた。また、機材の供与や現地における経費の一部負担も行われ、16年間にわたる協力の結果、約8,000haに及ぶ森林が造成された。このほか、現地の人材開発にも力が入れられ、日本における46名の研修や現地での629名の研修が行われ、これらの人材の今後の活躍が期待されている。事業が終了する時点での報告書によると、この協力はフィリピン側、日本側の双方から高く評価されている。
一方、本プロジェクトは、森林、林業協力ブロジェクトの第1号として多くの教訓を与えた。その一つとして、地元住民の森林管理に対する責任感やインセンティブの付与がある。これは、植林地や試験林の一部が「山火事」によって失われており、今後この地域における森林の重要性についての普及活動が重要な課題にあげられている。ここでいう「山火事」は、不法な国有林における畑の開墾や牧草地の火入れ、またその延焼によるものが主である。地元住民は、森林を森林として維持するよりも、森林を耕作地等として活用し、食料や収入を得ることの方に関心が高く、その結果、折角の植林地に影響するような火入れを行っていたり、火入れの延焼により森林が失われたりする。森林の存在が地元住民に様々な利益を生むこと、そして逆に森林が失われれば、災害の拡大等住民の生活に影響を与えることについての認識が未だ低いことが指摘されよう。これは、森林に入り込んで生活の糧を得るしかない貧困や土地所有制度が解決されていないことがその背景にある。本プロジェクトにおいても、これらの課題に早くから取り組み、例えば、地域住民を取り込んだ森林造成(一部農作物も栽培する)を行う社会林業、住民参加による防火キャンペーン、植樹祭、リーフレットの配布等を実施しており、森林の重要性の啓発、高地農民の社会経済条件の改善が進められ、一定の成果を得ているが、後発の多くのプロジェクトにおいて、その経験を生かし、なお一層の充実を図っていくことが期待されている。
また、森林管理についての科学的、技術的側面だけではなく、例えば地域の状況、牧畜の状況といった森林管理に影響を及ぼす経済的、社会的な側面への対策を考えておくことも協力が成功するために必要と指摘している評価も見られる。
環境協力の最も重要な課題は、被援助国側が自立して環境管理を行うことができるようにすることである。そのためには、単に技術や資材を提供すればよいということではなく、まず現地の自然、社会、経済的背景を調査し、それを踏まえた必要な対策を取り込むとともに、その重要性を地域住民が理解できるよう啓発を進め、途上国自らが環境管埋に取り組めるよう人材の育成や体制を整備するといった、よりきめ細かな、専門的な協力を実現する必要がある。
イ 企業の取組
途上国へは先進国からの民間投資が行われ、また、多くの企業が進出し経済活動を行っている。このため、途上国の環境問題を考える際には、このような民間企業の活動の在り方も重要な位置を占めている。こうした企業活動は、途上国へ公害を輸出していると指摘されることがあるが、また一方で公害防止についての技術移転の担い手としても期待されてもいる。
環境庁がタイとインドネシアの在外日系企業を対象に行った調査(第4章第2節2参照)によると、環境対策の目標レベルは現地の基準としている企業が61.0%と大半を占め、日本国内の基準が13.4%、現地国基準以上の自社基準が13.4%となっており、概ね現地の基準が目標となっており、自主的な取組は必ずしも多くはない(第4-1-45図)。
別の調査によれば、現地での環境問題への取組に当たっての障害として、現地での環境対策に係る専門家・技術者が不足している(39.7%)、遵守するべき基準が不明確(25.8%)、環境対策に係る産業が未発達(22.3%)、環境対策に必要な資機材等の調達が困難(7.8%)、環境関連法制度が整備されていない(3.8%)等の回答が寄せられている。進出先の途上国においては環境対策を推進する上で、その前提となる基準のあいまいさ等の環境規制実施体制の不完全さや、人材、機材供給等の不足などが取組の障害になっていると、企業が受けとめていることが分かる。
また、環境への取組については自社と他の先進国からの進出企業、先進国以外からの進出企業、さらに地元企業を比べた場合、自社と同程度または自社の方が環境対策を円滑に進めていると考えている比率は、その他の先進国からの進出企業に対しては27.9%、先進国以外からの進出企業に対しては35.4%、地元企業に対しては54.9%となっており、特に地元企業において対応が相対的に進んでいないことが推測される(第4-1-12表)。地元資本の中小企業や古い施設を抱えた企業は、意識や資本、技術の面から環境対策に十分対処できていないでいることが見てとれる。他方、先進国からの進出企業は、資金、技術とも有しているか、それへのアクセスが容易であり、さらに公害輸出という進出元の先進国民の批判や、進出先国の地元の環境に対する意識の高まりに敏感であり、環境問題に対する取組に積極的であると見ることもできよう。途上国においては進出企業のみならず、地元企業の対策を充実させていくことが重要といえる。
しかしながら、一方で将来環境上のトラブルに巻き込まれるのではないかとの懸念を持っている日系進出企業は42.7%に達している。東南アジア諸国では、特に水質規制が急テンポで強化される傾向にあり、これに対応していく上での不安が表れているとも見ることができる。一方で、先進国企業の途上国への進出の環境上のメリットとして、途上国の環境保全技術を高め、能力を養うことに役立つかどうかについて相当役立っていると感じている企業が34.1%、今後役立っていくと感じている企業が45.1%あることも明らかになっている。技術力、資金力から見て外資系企業は、地元企業に比べ環境対策を進める上で有利である。海外進出企業にとっては、規制が強化されていく中でこれにいち早く対応することにより、途上国の民間企業の環境対策をリードしていく好機ともいえ、またそうした役割が期待されている。
(3) 途上国の自立のための支援
最初に見たように、途上国の環境の保全は世界が取り組むべき課題である。途上国の環境を守るためには途上国の政府の取組の強化が何よりも必要であり、さらに(2)アで述べたように、途上国の地元住民が環境を守ることの重要性を認識するとともに、自ら環境の適切な管理を行うことができるようになることが大切である。
先進国の我々が途上囲の環境問題の解決に協力するためには、こうした途上国の自助努力を支援することが重要であろう。人造り、行政の制度・組織等の対処能力強化(キャパシティ・ビルディング)が長期的に途上国の環境問題の解決に資すると考えられる。
我が国も、タイの環境研究研修センター、中国の日中友好環境保全センター、インドネシアの環境管埋センターに対する無償資金協力及び人造りのための技術協力を行ってきており、こうした協力を地道に続けていくことが必要である。
民間部門の人造りの協力として企業が研修を実施している例も多い。
また地域の人々の環境に対する意識の向上を進めつつ、これらの人々自身の環境への取組を支援しようとする非政府団体(NGO)の活動も活発化している。こうしたNGOの活動は地元住民と直接交流しながら進められるため、地元住民の二一ズを吸収し、住民とともに地域環境問題と対策の在り方について理解を深めながら取組を進めることができ、地域に根差したきめ細かな協力を実現することができる。こうした活動を支援するため、小規模無償資金協力やボランティア貯金、更には、外務省、農林水産省及び建設省によるNGO補助金制度が発足している。さらに環境事業団において環境関連のNGOの活動を支援すること等を内容とする環境事業団法改正法案が国会に提出されている。
環境を守るのは、最終的には額に汗して環境問題に取り組む一人一人の人間である。こうした人々が円滑に力を尽くせるようにするためには、現場を離れて暮らす人々にも果たすべき、それなりの役割があるといえよう。