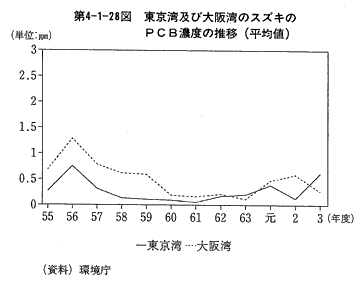
7 過去に使用された化学物質の対策
化学物質は我々の生活にとって欠かせない有用なものである反面、特に有害性を有するものについては、その取扱いを誤ると環境や人体に対して影響を与える可能性を有している。
これら有害性を有する化学物質については環境中に放出され、人の健康に被害が生じることのないように適切な対策を講じることが極めて重要になっている。こうした観点から、毒性や生体内への蓄積性を有する化学物質、例えば絶縁油等として利用されたPCB、殺虫剤として用いられたDDT、船底防汚剤として用いられたビス(トリブチルスズ)=オキシド等については、現在では製造、輸入、使用等が事実上禁止されている。
また、こうした有害性を有する化学物質による環境汚染やそれによる人への健康への被害を未然に防止するためには、予防的な取組を推進することも重要となっている。
ここでは、過去発生し、現在まで順次対策が進められてきた例として、PCB(ポリ塩化ビフェニールの略称)に関する経過と現状を見ることとする。
(1) PCBによる汚染の発生と対応
PCBは、ビフェニールの水素が塩素に置換した化合物の総称で、自然界には存在しない合成物質である。PCBは、水に不溶、有機薬剤に安定、不燃性、絶縁性が良いといった特性からその用途は多岐にわたっていた。最大の用途は、コンデンサやトランス用の絶縁油であり、また、熱交換器等の熱媒体、感庄複写紙等に用いられた。我が国においてPCBの生産が開始されたのは昭和29年であり、45年には年産11,000トン程度になったが、環境汚染問題が表面化した46年には6,800トン程度になり、47年には生産が中止されたが、この間累計で約59,000トンが生産された。また、輸入は同期間に累計で約1,100トン行われた。WHOの資科では、全世界で100万トン以上が生産されたと推定されている。
PCBは、その有用性から広く使用されていたが、1966年(昭和41年)以降、スウェーデン各地の魚類やワシを始め、世界各地の魚類や鳥類の体内からPCBが検出され、PCBが地球全体を汚染していることが明らかになってきた。我が国においても、43年に発生したカネミ油症事件によりPCBの毒性が大きな社会問題となった。これは、食用油の製造過程において熱媒体として使用されたPCBが混入し、健康被害を発生させた事件である。その後、46年になって、魚類、鳥類、土壌、底質、水中、さらには母乳等人体からもPCBが検出され、PCBによる汚染が大きな問題となった。
このような状況に対応し、政府は、47年に関係省庁からなる「PCB汚染対策推進会議」を設置し、生産・使用規制、回収・処理対策、環境基準等の設定、汚染土壌・汚泥対策等を進めることとした。具体的には、関係省庁の行政指導によりPCBの製造中止、回収等の指示がなされるとともに、48年に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」が制定され、PCBは同法に基づく特定化学物質(61年の法改正により、現在は第一種特定化学物質)に指定されて、原則、製造等が禁止された。
また、既に生産されたPCBやそれを含む製品については、回収・保管されることとなった。まず、液状PCBについては、製造業者に回収、保管、重電用変圧器等のPCB使用電気機器については、使用者において保管されることとされた。PCBを含む感圧複写紙については、メーカー、官公庁において回収・保管されたほか、処理体制が整うまでの間、それを保有する事業者において保管するよう指導がなされた。PCBを含むコンデンサーが部品として使用されている家庭電気製品については、自治体が廃棄物を収集する際にメーカーが部品を取り外して保管することとされた。
さらに、PCBやPCBを含む製品の排出・処分に関しては、排ガスについての暫定排出許容限界、排水についての水質汚濁防止法に基づく排水基準が定められており、また、廃棄物の最終処分に関して、あらかじめPCBについては焼却や除去を行うことや、PCBを含む汚泥については遮断型埋立てを行うことなどが定められている。
一方、環境汚染への対策として、暫定除去基準を超えるPCBによる底質の汚染が発見された78の水域のうち、平成3年7月末までに75カ所においてしゅんせつ等の浄化事業が完了している。
(2) PCBによる汚染の現状
以上のように、PCBについては昭和40年代末から50年代初めにかけて生産の中止、製品の回収体制の整備がなされ、また、環境の汚染を防止する措置が取られ、その後、汚染の除去事業や水質や生物に関する監視調査が続けられてきている。
現在のPCBに関する状況について、まず環境中の状況をみると、水質については、平成3年度の公共用水域水質調査結果で、全国で調査された3,823検体でPCBは検出されていない。一方、計20の海域、淡水域及び陸域において魚類、貝類及び鳥類を対象として行われている化学物質の生物モニタリングの結果を見ると、12地域の魚類、貝類及び鳥類からPCBが検出されている。また、東京湾と大阪湾のスズキの調査結果の経年推移(第4-1-28図)をみると、年々の変動はあるが、概ね横ばいの状況で推移している。このように、PCBは現在もなお広範な地域の環境中に残留している。
(3) PCBの処理の実績と保管等の現状
PCBを含む製品の保管状況についてみると、液状PCBについては、製造業者であった三菱モンサント化成四日市工場に約970トンが保管されている。鐘淵化学工業高砂工業所に保管されていた約5,500トンついては、次のとおり処分が行われた。まず、兵庫県及び高砂市の要請を受けて昭和60年に環境庁大気保全局に「液状廃PCB高温熱分解試験検討会」が設置され、当該高温熱分解試験の安全性の検討及び試験結果の評価等がなされた。これらの知見を踏まえ、62年から平成元年まで、兵庫県の指導監督の下、総合的な監視を行いつつ、事業者による高温熱分解処理が行われた。処理に当たって監視基準を、PCBの分解率は99.9999%以上、排ガス中のPCB濃度は0.01?/Nm
3
、排水や周辺環境のPCBは定量限界以下等としたが、これらはいずれも確保され、安全に処分されたことが確認されている。この時の国、兵庫県、高砂市、事業者及び地域住民の体制は第4-1-29図に示すとおりである。
PCBを含む機器については、(財)電気絶縁物処理協会の台帳によれば、全国の136,600の事業場において、335,300台のコンデンサーと33,300台のトランスが使用又は保管されている。このほか電力会社等にトランスやコンデンサーが一部保管され、また、家庭用電気製品から回収されたコンデンサーがメーカーに保管されている。また、PCB入りの感圧複写紙については、61年度の厚生省調査によれば、852トンが使用者において保管されている。
一方、一部の地方公共団体の行った調査によれば、PCB使用電気機器を保管しているとされる事業所の一部で機器の不明、紛失が伝えられている。このようなことから、処理体制が整備されるまでの間、より適切な保管体制の確保が強く求められるに至っている。
PCBの処理に関しては、47年の「PCB汚染対策推進会議」の決定で、二次汚染の防止等に留意した処理技術に関する研究を行い、関連事業者に処理方法について指導し、適正処理の徹底を図ることとされた。しかしながら、処理プラントの立地等に関して住民等の合意が得られないといった事情があり、一部を除き実施されていない状況にある。しかし、保管中のPCBについては、事故等による漏出や、不注意による紛失が汚染を生じさせることがないよう速やかに適切に処理、処分されることが望ましい。このため、事業者の処理責任を基本とした安全な処理、処分を目指して、国、地方公共団体、事業者、住民等が協力して冷静かつ合理的に取り組むことが強く求められる状況にある。環境汚染の未然防止の観点から、現在使用され、あるいは保管されているPCBが新たな汚染問題を引き起こさないよう、今後の的確な対応が求められている。