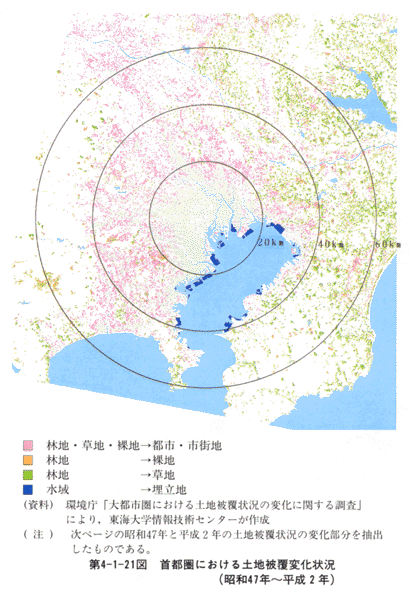
6 大都市圏の緑地や生物等の自然環境の保全
大都市圏の緑地や生物などの自然は国土全体の自然環境の一部であるとともに、住民に身近なものであって、その生活に重要な役割を果たしている。しかし、我が国の大都市圏では、これが急速に失われてきている。人口や経済活動の集中が続く東京、大阪などの大都市圏では、近郊地域での住宅開発や周辺でのゴルフ場開発などが進み、他方で森林や農地か減少し、これに伴って野生生物も減少してきた。これらの大都市圏は国土全体として見ても、人間活動の大きさに比較して自然に乏しい地域となっている。
緑地が失われていく状況を首都圏を例にとって見てみよう。第4-1-21図は、人工衛星画像の利用により、昭和47年から平成2年までの18年間の土地被覆の変化状況を解析したものである。この間に市街地化した地域、森林が失われた地域、埋め立てられた地域を抽出し図示している。これを見ると、既成市街地周辺の近郊地域では、住宅開発に伴い緑地の減少が進んでおり、特に都心から20km〜40kmの圏域での変化が顕著である。都心から南西の方向では多摩ニュータウンや港北ニュータウンの開発に伴う市街化が、また、東の方向では千葉ニュータウンの開発に伴う森林の減少が見て取れる。一方、より外側の40km〜60kmの圏域では、市街化やゴルフ場等の開発等による森林の減少が見られ、千葉県や埼玉県西部などで、森林が改変されているのが見て取れる。
こうした首都圏の土地被覆の改変状況を、国土数値情報を用いて定量的に解析し、東京60km圏内における昭和51年から平成元年(昭和62、63年のデータも含む)までの概ね13年間の変化を改変の前後のマトリックスとして示したのが第4-1-7表である。項目の分類方法が上記の人工衛星画像データと異なる点に注意を要するが、改変後の土地利用に着目すると、森林、農耕地、荒れ地等から市街地への改変量が大きいこと、また、次いで森林から荒れ地等への改変量が大きいことが分かる。前者は、宅地開発等に伴う市街化であり、また、後者はゴルフ場の開発による森林の改変などを表している。この13年間で森林の4.1%が荒れ地等に、3.0%が市街地に改変されており、また、農耕地の7.1%が市街地に改変されている。森林と農耕地の減少面積を合わせると合計は525km2となり、これは東京23区の面積に匹敵する。
以下では、大都市圏の自然の果たすべき重要な役割を概観した上で、保全のための課題や取組の方向を見てみよう。
(1) 大都市圏における自然生態系の重要性
ア 大都市圏の自然の効用
上記のように、大都市圏では、緑地などの身近な自然が失われてきているが、これらの自然がどのような役割を果たすものなのかを、いくつかの観点から考えてみよう。
まず、都市にある緑地の機能としては、従来から様々な効果が知られている。地下水や河川などの水源かん養機能、崖崩れなどの自然災害防止機能、粉塵吸着などの大気浄化機能、騒音緩和機能、地表気温低下などの気候緩和機能、快適な生活環境形成の機能、野外レクリエーションの場としての機能などである。
例えば、気候緩和機能について見れば、都市の緑地を増やすことにより、ヒートアイランド現象が緩和され、気温が低下することが知られている。この結果、冷房用のエネルギー需要が減少し、二酸化炭素排出を抑制することができる。また、植物自体も二酸化窒素等の汚染物質を吸収することも知られている。
また、快適な生活環境を形成する上でも、緑地は最も重要な位置を占めている。快適な生活環境づくりの上で重要と思うものについての世論調査の結果では、「豊かなみどり」が51.5%で首位、次いで「さわやかな空気」が38.0%で2位となっており、「美しいまちなみ」「レクリエーション施設」といった人工的なものより自然的な要素が重視されていることが分かる。
また、人と自然とのふれあいの機会を確保する上でも、大都市圏の自然環境の保全は重要である。自然への国民の渇望は高まっており、世論調査によれば、自然とふれあう機会を今以上に増やしたいと考えている国民は全国平均で63.1%、東京都区部では83.5%にも達している。自然とふれあう機会を増やすためには、日常接することができる身近な自然環境の保全が重要である。世論調査によれば、自然とふれあう機会を増やす方法としては「自宅や勤務先などの周辺に、身近な自然を残したり、増やしたりする」との回答が最も多くなっている(第4-1-22図)。
自然とのふれあいを確保することは、国民の二一ズに応えるために必要であるばかりではなく、自然教育の面から見ても重要である。自然と人間とが共に生きて行くためには、社会を構成する個人個人が、生態系の精妙な仕組みについて理解を深めるとともに、自然に対する豊かな感性を育み、自然との絆を深めることが重要であるが、これは、自然とのふれあいの中においてこそ獲得されるものである。ところが、大都市圏では緑地が減少し、それに伴って身近な野生生物も減少している。環境庁の調査によれば、ヒバリやホタルなどの身近な生き物が都市地域から次第に姿を消してきており、例えば、東京周辺でのヒバリの分布を見ると、練馬、田無、国立付近においては、昭和59年には見られたものが平成2年には見られなくなっている(第4-1-23図)。このようなことから、子供が、自然の中で遊んだりして生き物などとふれあう機会をほとんど持たないままに成長してしまうといったことが懸念されている(第4-1-24図)。こうしたことから、平成5年3月に国会に提出された環境基本法案でも、その第13条の施策の方針の一つとして、自然とのふれあいの増進を掲げているところである。
イ 生態系としての自然の必要性
さらに、大都市圏の自然の重要性を評価するには、個別的な機能の面に着目して、その量について評価するだけでなく、より包括的に自然を生態系としてとらえ、質的観点からその役割を考える必要もある。微妙な均衡の下で成り立っている自然生態系は、人類を含む全ての生物の生存基盤である。今日、人間の活動による環境への負荷によって、これが損なわれるおそれが生じてきている。こうしたことを防ぎ、恵み豊かな環境を将来にまで引き継いで行くためには、多様な自然環境を体系的に、また将来を見通して先取り的に保全していくことが重要となっている。このため、原生的で希少な自然環境だけでなく、身近な地域における自然をその特徴を生かして保全していく必要性がますます高まっているのである。
国民の意識においても、より自然に即した、多様な緑地が求められてきている。世論調査の結果では、日常生活の「みどり」に不満を持っている理由として、みどりの量が少ないことに次いで、「人工的過ぎて親しみが持てない」、「種類が少なく単調である」といった要因が挙げられている(第4-1-25図)。
緑地が減少を続け不足している大都市圏においては、緑地の絶対量を確保することや、これを住民が利用しやすい形で整備することは重要である。さらに、上記のような状況の中で、量的な面に加えて質の面をも重視し、生態系として健全な自然を確保していく必要性が高まっている。また、住民による緑地の利用に関しても、利用する機会を確保するだけでなく、これに加えて、野生生物とのふれあいを確保するなど、質的な面でも多様な自然とのふれあいを可能にしていくことが重要となっている。このため、自然の保全に当たっては、地域に広く生息、生育する種を大切にし、野生生物の生息・生育地としての条件を考慮するなど、生態系としての健全性を重視して、多様性に富んだ状態での保護・整備を行うことが重要となってきている。
土地の本未の生態系を重視した方法で自然環境が整備された例として、東京の明治神宮の森を挙げることができる。明治神宮は、大正4年から10年にかけて造成された人工の森である。4年に設置された明治神宮造営局は樹林造成の方針として、郷土の気候や土壌に適し、生態学的原則に基づき、天然更新によって森林を形成できる利点を持つ郷土樹種を中心とした常緑広葉樹林とすることを決めた。一部には、スギ、ヒノキ等の針葉樹林による荘重な樹林とすべきであるのと意見もあったが、造営局は、明治神宮の土地がスギには適さないことなどから、これを採用しなかった。ただし、常緑広葉樹の大木の移植は困難であったため、とりあえず、樹林の第1層にクロマツ、第2層にヒノキ、サワラの針葉樹類を植栽して形を整え、第3層に将来優占種となるべきスダジイ、カシ類、クスノキなど常緑広葉樹を多数植裁し、その後植林地を自然の遷移に委ねた。この結果、第一層のクロマツは暴風雨等により倒伏、枯損したものが多い一方、郷土樹種を中心とした常緑広葉樹は極めてよく成長し、25年後には外観はほぼ常緑広葉樹を主とする天然林に近く成長し、今日では、本来の自然植生そのものとは言えないまでも、その姿や生態系としての機能は残存自然林と見まがうばかりとなっている(第4-1-8表)。このように速やかに樹林が成長した要因としては、綿密な計画に基づき当初から森林生態系の原理にかなう樹種構成により植栽されたことに加え、樹林内の管理に当たって落葉、落枝を除去せずに土に返してきたことにより、地力が維持、改善され、土壌動物相が豊富になり、豊かな生態系が形成され、生態系の持つ生産力が活かされてきたことが挙げられる。土壌動物の多様さを、落棄、落枝を取り除いている日比谷公園との比較によって見てみると、同じクスの植生地の土壌動物の数は、日比谷公園が176頭なのに対して、明治神官が9,024頭と、約50倍にのぼっているとの調査結果がある。このようにして形成された明治神宮の森は、都市内の希少な自然として様々な機能を果たしている。例えば、活力の高い樹林と土壌により大気汚染の浄化が行われており、樹林内の二酸化硫黄濃度は外部に比べて顕著に低くなっている(第4-1-26図)。このように、明治神宮の森は、自然植生を考慮した形で自然環境を整備した結果、豊かな生態系が効率的に形成された例と言える。
以上のように、多様な種からなる系としての自然を一つの系として保全する趣旨から、5年3月に国会に提出された環境基本法案においても、その第13条に掲げる施策の方針として、生態系としての自然の保全を明確に位置づけているところである。
第4-1-26図 周辺市街地と都市林内部のSO2
(2) 大都市圏での自然環境の保全に伴う問題
大都市圏の自然は、現実には急速に減少を続けており、その保全を進めることが重要な課題となっている。
このため、国においても各種の制度を設け、地方公共団体と連携しつつ、その保全を図っているところである。大都市圏にある既存の自然環境の保全に係わる地域指定等の制度について見ても第4-1-9表のように様々なものがあり、有機的な系としての自然を保護、整備して行くには、これら各種の制度を総合的に活用していく必要がある。
しかし、大都市圏での自然の保全には様々な克服すべき問題がある。その背景として重要なのが土地所有権との関係である。自然環境の保全のためには、自然の存する土地の所有者に対して、その利用に何らかの制約を課すことが必要となる場合が多い。しかし、欧米諸国では一般に公共の利益が重視され、特段の補償なしでも土地利用規制による私権の制限が広く認められているのに比べて、我が国では一般に土地所有権の自由な行使がより尊重されており、公益のために土地利用を制約することが難しくなっている。緑地保全地区、自然公園、保安林等の地域指定に関しては、私権との調整のために、指定された土地の買い上げや、規制に伴う直接的、間接的な損失の補慣の制度が設けられているが、大都市圏においては、周辺地域に比べ、地価が高く土地所有形態も複雑な場合か多いこと等もあり、なかなか実績が上がらない。
その上、大都市圏での自然環境の保全は、人の健康にかかわるような火急の公共の利益の確保とは異なる点があり、法益と現制との均衡を考えると、強権的な規制には馴染みにくいものとされる傾向がある。このため、土地所有者をはじめ関係者の利害が調整できないことが対策の障害となる場合が多い。以下では、このような関係者のそれぞれの立場から見た課題について、具体的に見てみよう。
ア 土地所有者
土地所有者の立場から考えると、公共の利益の要請から所有地の自然環境を保全すると、個人としては不利益を被る可能性があることが問題となる。例えば、所有地を開発する機会がある場合、開発を控えて自然を維持すれば、得られたはずの利益を失うこともある。このため、所有地の自然を保護するためには、何らかの補償を求めることになる。また、自然保護のための何らかの地域指定を受けると、将来の土地転用の可能性が阻害されるため、地域指定を避けようとすることにもなる。なお、積極的に所有地の自然環境を保全したいとの意志を持っていた場合にも、相続の際に、前所有者の意向に反し、遺産分割等のため土地の転用が行われる場合もある。立木への固定資産税負担を避けるため木が切り倒される例もあるといわれている。
一方、所有地の自然を維持するためには、その土地の性質に応じて様々な管理が必要である。極力自然生態系に沿った手をかけない管理を検討する余地はあるものの、植生の状態や近隣との関係によって落葉かきや下草刈りからごみ拾いにいたる作業が必要となることが多く、この手間が自然の維持を断念させる要因ともなる。
このように、土地所有者の立場から見れば、自然の恩恵は広く周辺住民が受けるのに、そのための金銭面、労力面での負担を自分だけで背負うことは公正ではなく思われ、関係者に何らかの補償や協力を求める気持ちが生まれることになる。
イ 住民
住民の立場から見ると、周辺での自然の保全には総論として賛成するものの、自宅のすぐそばについては各論で反対するという傾向も見られる。例えば、自宅の近くでは、落葉が散乱してきたない、虫が発生する、日当りが悪くなる、屋根のトイに落葉がつまる、ごみが散乱しがちである、といったことを問題にしたり、また特に街路樹については、店の看板が見えなくなる、荷物の出し入れに不便になるといったことを問題にして、緑地の保全に反対したり、土地所有者や地方公共団体に対して、清掃等の管理の徹底を求める例が見られる。また、都市周辺の自然を享受する一方で、その管理には関心を払わず、逆にごみを捨てたり植物をむやみに採取したりする例もみられる。
ウ 地方公共団体
地方公共団体の立場からみると、地価の高さから、自然を保護、整備するための土地を買い上げによって確保することは財政上困難となってきている。このため、買い上げを伴わない地域指定などの方法によりこうした土地を確保せざるを得なくなっているが、このためには、公用制限に対する土地所有者の理解と協力が不可欠となる。また、街路樹、公園、都市内に残された樹林、里山など様々な地点の自然についてきめ細かな管理を行うには、地域住民や土地所有者の管理への協力と参加が不可欠である。このように、都市圏における自然環境の保全に関しては、土地所有者、住民、地方公共団体など様々な関係者が、それぞれの事情と利害を持っており、互いに他者の理解と協力なくしては、自然環境の保全を一層進めて行くことが困難な状況にある。
(3) 関係者の協力により進められる都市圏の自然環境の保全
様々な関係者が適切に役割分担をし、互いに協力して取り組むことにより、都市圏の自然を効果的に保全できる可能性がある。こうした例を、国外の先進的な事例に見てみよう。
イギリスのグラウンドワーク事業は、行政、市民、企業などが協力して身近な環境改善を進めるものである。政府と地方公共団体等の出資により各地域にグラウンドワークトラスト(事業所)が設立され、これが中核となって、様々な主体の参加と協力の下で、荒廃地の環境改善や自然環境の管理から、環境教育の推進に至るまでの様々な事業が実施される。例えば、工場が土地を提供し、市民の参加の下で利用方法を検討し、自然観察園として整備して、その管理は市民がボランティアで行う、といった事業が展開されている。中央には環境省やその関係機関である田園地域委員会によりグラウンドワーク事業団が設立されており、資金、ノウハウ等の提供を通じ各地のグラウンドワークトラストの設立及び運営を支援している。さらに、前述のとおり、民間企業も資金や資材、人材などをこの事業に提供してこれを支援しているが、こうした企業の自主的努力については、慈善事業への寄付として税制上の恩典が与えられているほか、環境を改善した地区にスポンサーとなった企業名が標示されるなど、その努力が報われる様々な工夫が凝らされている。また、グラウンドワーク事業は「行動のためのパートナーシップ(協力)」を基本理念としており、単に成果を完成させることよりも、様々な関係者の自主的な活動と協力関係を引き出していく過程を重視していることも一つの特色となっている。
ドイツでは、単に緑地の保全にとどまらず、ビオトープ(小生態系)という概念に沿って、動植物の生息・生育場所の体系的な保護や復元等が進められている。生態系の保全のために、希少な動植物はもちろん、それだけでなく身近に自然に分布している生き物と生息・生育環境をも保全の対象としており、連邦自然保護法に基づく「景域保全計画(ラントシャフト計画)」(第4-1-27図)により、郊外から市街の中心まで、池沼、河川、草原、森林などが様々な形でネットワーク化されている。具体的には、郊外の自然度の高い森林、池沼などがネットワークの核となるべく自然保護地域として保護され、また農地においても農道脇の空間の自然草地化などが図られる一方、市街地においては生態系を重視した都市公園、樹林地、空き地、個人の庭など大小様々なビオトープが設けられる。そして、郊外の森林や農地から市街地内への動物の移動空間として河川や道路が位置づけられ、河畔緑化、沿道緑化等が進められる。これらのビオトープ整備の基本として、野生種をできるだけ用いた多様な植栽と、自然状態に近づけた粗放的な管理が重祝されている。ドイツのこの事例は、自然を系として見る視点から施策が組み立てられ、そのための技術が開発されていることが特色となっている。
また、こうしたビオトープの保全にあたっては、様々な関係者の協力が不可欠である。例えば、農地周辺の自然環境の保全は農家と行政との話し合いにより進められており、中庭、壁面、屋上等の緑化は、行政や自然保護団体の働きかけに呼応した市民の協力により実施されている。さらに、行政部内に関しては、連邦自然保護法に関係官庁の自然保護官庁への協力義務が規定されており、これに沿って、各分野の施策で自然環境の保全を実現するため、自然保護・公園緑地部局を中核とした横断的な行政各部局の推進体制が整えられている。こうして、行政、市民、農家などの各主体に協力関係が仕組まれ、都市域の生態系の保全が進められている。横断的な性格を持つ生態系を守っていく上では、行政施策も各種の施策から成る系、システムとして運用されるべきであるとの教訓を与えるものである。
これらの事例から学べるように、身近な自然環境を豊かに保全するには、行政、住民、土地所有者等の関係者が協力して取り組みながら、生態系としての健全性を重視しつつ、その体系的な保全を図ることが重要である。行政においては、様々な行政部門を通じて体系的、総合的に自然環境の保全を進めるとともに、住民や土地所有者の協力のための枠組みを提供し、住民においては、庭などの小空間にまで及ぶ自主的な緑化を進めるとともに公共的な自然地域の管理に参加し、土地所有者においては公用制限にも協力しつつ自然地域の保全に努める、といった形で、各主体が協力しつつそれぞれの立場で努力することにより、身近な自然環境を保全し、社会としての効用を増加させることができるのである。
さらにに様々な関係者が協力して身近な自然環境の保全を進めることは、自然の重要性とこれを互いに協力して守ることの必要性を社会により広く認識させることを通じて、身近な自然環境の保全にとどまらず、大都市圏や我が国全体の自然の減少を食い止めることに、間接的ではあるがより根源から役立っていくであろう。