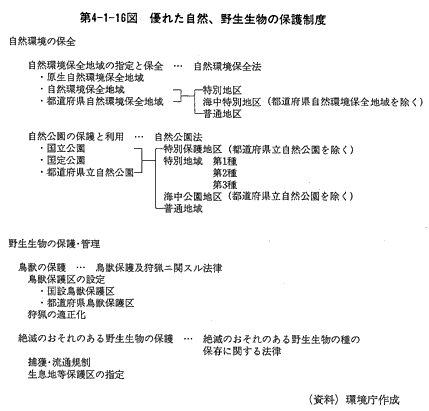
5 優れた自然や野生生物の保護対策
優れた自然はそこから直接収入を得ることができるものではないが、生態系の健全性の維持や、国民と自然とのふれあいの場の確保などの観点からは、高い公益を有している。しかし、このような高い公益の実現のための取組はなお充実の必要がある。
(1) 優れた自然や野生生物の保護のための制度
優れた自然や貴重な野生生物の保護に対して国民は高い価値を置いている。平成3年度において総理府の行った世論調査によれば、自然保護について「人間が生活していくために最も重要なこと」とする人の割合は、36.1%、「人間社会との調和を図りながら進めていくこと」とする人の割合は、58.5%であり、「開発の妨げになるなど不要なこと」と回答した人はわずか0.7%に過ぎない。さらに昭和61年の調査との比較を行うと、「人間が生活していくためにもっとも重要なこと」とする人が28.5%から36.1%に増加している半面、「人間社会との調和を図りながら進めていくこと」とする人の割合が63.3%から58.5%に減少しており、自然保護を重要と考える人々の数も増え、その意識も強まっていると見ることができる。
我が国における優れた生態系や野生生物の保護のための対策は、自然環境保全法、自然公園法、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律、鳥獣保護及狩猟二関スル法律等に基づき、指定区域内における行為規制、捕獲・採取の規制、取引の規制、輸出入の管理等が体系的に講じられており(第4-1-16図)、また森林法に基づく保安林制度による保護が図られている。
優れた自然や野生生物を保護するためには、個々の自然の要素や野生生物を保護するだけではなく、生態系の保全に配慮しつつ、まとまりのある自然や野生生物の生息・生育環境を保全することが有効であり、その面から地域指定による面的な保護措置がとられている。これまでも優れた自然については、自然環境保全地域、自然公園等の保護措置がとられており、これら指定地域は国土総面積の14.34%を占めている(自然環境保全地域0.23%、自然公園14.11%)。このほか、国有林における保護林、保安林、天然記念物等の制度や地方自治体の独自の条例等に基づく制度によっても保護がなされている。また野生生物の保護については、鳥獣保護区制度が鳥獣保護法の下に設けられている。さらに、絶滅のおそれのある野生動植物については、平成5年4月1日に施行される「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」により、体系的な保護施策が講じられている。すなわち、国内で絶滅のおそれのある種を「国内希少野生動植物種」として定め、捕獲、譲渡し等及び輸出入の規制を行うほか、生息地等保護区の指定によりその生息地等の保護を図り、さらに、必要に応じ、保護増殖のための事業を行うこととしている。さらに、これまで「絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律」及び「特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律」により、その譲渡等が規制されてきたワシントン条約附属書I掲載種及び二国間の渡り鳥等保護条約に基づき通報された種を「国際希少野生動植物種」として定め、引き続き、譲渡し等及び輸出入の規制措置を講じている(第4-1-17図)。
(2) 保護を進める上での役割分担の現状と課題
優れた自然や野生生物の保護はこのように国民からその必要性を理解され、高い価値を付与されており、保護体制が整備されている。一方、この優れた自然や野生生物の保護は、当該地域が住民の生活の場であることから、ややもすると、地域住民の利益と、国民全体の利益との対立の問題にもなりやすいものである。
自然性が高い地域やクマ、カモシカなどの大型野生動物が生息している地域は、第1章2節でみたように、山地、半島部、島嶼部に多い。一方、こうした地域では、林業や農業などが生業となっている度合いが高い。しかも、過疎が進んでいる場合が多い地域でもある。こうした活動との調整が具体的な保護を進める上で課題となる。
野生動物による植林苗木や農作物への被害を例に取り考えてみよう。例えば、「鹿児島県のツル及びその渡来地」は国の天然記念物に指定されており、また国設鳥獣保護区ともなっている。永年にわたる保護対策の結果、ツルの飛来数は平成2年には1万羽近くにまで回復した。しかし、この地区では増加したツルによる農作物への被害が見られ、関係町村による食害対策事業が行われているものの、依然被害は終息していない。渡り鳥については、近年その飛来数が増加しているが、その飛来地が特定の地域に集中することがあり、同様に渡り鳥の集中による農林水産業への被害も目立つことが懸念されている。獣類による被害も生じており、例えば、カモシカについては、一部地域において植林の若芽を食べるなどの被害が生じ、個体数調整として環境庁、文化庁、林野庁二庁の合意に基づき、毎年1,000頭程度の捕獲が行なわれている。平成2年度における鳥獣による被害は農作物で24万9,000ha、林業で7,500ha、において生じているとされている。(第4-1-5表)。
現在、こうした食害等に対しては、保護棚、防護棚を設けたり、有害鳥獣として許可を得て駆除を行ったり、より効果的な防除方法の開発所究が行なわれている。また、適正な頭数での生存を維持するための個体数の調整、すなわち捕殺も行なわれている。なお、野生生物の生息数を正確に把握することは、現在のところなお困難なものがあり、生息状況を把握し、これに基づき、より一層適切な駆除、捕殺を行なうことが求められている。
野生生物による農業、林業への被害のほかに、保護地区の指定も調整を要する問題である。総務庁が4年に実施した「絶滅のおそれのある野生動植物の保護対策の現状と課題」に関する行政監察によると、保護地区の指定は、開発行為が規制され、地価が下がるといった理由で地元住民から必ずしも歓迎されていない。例えば原生自然環境保全地域、自然環境保全地域及び都道府県自然環境保全地域の面積は近年ほとんど増えていず(第4-1-18図:なお、監察の後の同年7月に白神山地自然環境保全地域(14,043ha)が追加された)、都道府県自然環境保全地域については、指定されていない都道府県が3団体、昭和50年代前半以来追加指定のない都道府県が21団体ある。また都道府県自然環境保全地域の指定を計画したものの、関係者の同意が得られないため、長期にわたって指定できない地域がいくつか見られると指摘されている。また、自然公園のうち、規制の厳しい特別保護地区や特別地域の指定についても、長期間を要するなど、区域の拡大や規制強化ができない状況となっているものがあることが指摘されている。
野生生物の保護、優れた自然の保護は、国民的に重要なこととして認識されており、国民全体としての将来世代に対する責任ともなっている。一方で、野生生物や優れた自然の保護のための措置、特に地域指定による規制措置は、開発の障害となったり、地価が下がったりと様々な不都合を地域住民にもたらす場合がある。特に、日本では保護の必要な土地に民有地が多く合まれているため、こうした利害の調整がさらに深刻となっており、保護のための負担が過疎地住民等に集中しているとの認識が見られる。前述の世論調査においては、国民全体の場合と農林業従事者の場合との間では、自然保護についての認識に若干の差があることが読み取れる(第4-1-6表)。
現実に野生生物保護、自然保護のためにどれだけの対策がとられているかを見てみよう。第4-1-19図は、国の自然保護関係予算と、国民一人当たりの支出額を表したものである。一人当たりの支出としては年間約1300円となっている。また、第4-1-20図は、地方公共団体の自然保護担当者の数を示しているが、地方公共団体の自然保護担当職員の数は公害関係職員の約4分の1程度にとどまる。自然保護対策の充実を求める声、自然保護に関する様々な利害調整の訴えと、それに応えるべき行政の体制との間には落差がある状況にある。
一方、野生生物や自然の豊かな地域は、過疎化に悩まされていること等から、野生生物の保護、自然保護といった負担に応えられなくなっている。国土庁の調査によれば、いわゆる中山間地域の市町村では、人口の減少、高齢化に直面しており、地域社会の活力が低下し、田畑や山林の管理に支障が出てきていることが指摘されている。野生生物の被害が深刻であることの原因の一つには、地域社会の活力が失われ、こうした被害を防止する労力に耐えられなくなってきているという背景もあると指摘されている。例えば、駆除に従事する狩猟免許保有者は近年減少し、しかもその高齢化が進みつつあり、駆除が必要となってもその能力を有する従事者を容易には確保できない事態が起こり始めている。
(3) 優れた自然、貴重な野生生物の保護のためのより適切な責任分担に向けた取組
優れた自然環境、貴重な野生生物の保護のための責任分担のための試みがいくつか行われている。
ヨーロッパの先進諸外国は、日本ほど生態系が豊かではない国も多く、野生生物の保護は伝統的農法の保護という形でも取り組まれている。能率を追求する農法では、伝統的な農法で利用されてきた生け垣や採草地を残しておくことは経営的に不利なため、こうしたものは減少していく傾向にあるが、生態系の保全、野生生物保護等の観点からは、こうした生け垣や採草地は重要であることが分かってきた。このため、例えば、イギリスでは1987年(昭和62年)から、「環境上影響を受けやすい地域制度(ESA)」を発足させ、指定された地域内の農家が、経済効率性は劣るが、野生生物の生息には有利な伝統的な農法を継続する場合、自然保護の専門家からのカウンセリング等とともに、補助金が受けられることになった。同年には9地域、1989年(平成元年)までに10地域が指定され、総面積合計74万haに及んでいる。これは、野生生物の保護というコストを負担する農家に対し、国民全体がそのコストの一部を分かちあおうとする試みといえよう。
貴重な自然、野生生物の保護が地域の人々の負担となるのではなく、生活の向上のために役立つ存在となることが理想的である。この観点から、自然や野生生物を損なうことなく、むしろそれらを挺子に地域の活性化を図ろうとする例も多く見られる。エコツーリズムはその典型例であり、地域の自然やそれと一体になった地域文化を生かした地域おこしの手法の一つと考えられる。地域の自然やこれに根ざす文化は、地域の人々にとっての誇りであり、貴重な資源である。こうした誇りや資源を失うことなく地域社会の活力を取り戻すことが重要である。
地域住民のかかる取り組みが実を結ぶためには、国民一般の側もこれに応えるような努力が必要である。例えば、休暇に、豊かな自然のある場所まで自ら足を運び、自然を損なわないような方法で自然とできる限り直にふれあうことに国民がより高い価値を置くことなどによって、こうした形での地域活性化策が、より導入されやすくなることが予想される。
また、自然とのふれあいの方法、保護と利用との間のバランスをとる手法等は今後なお検討していく必要もあるし、また地域の特性に応じ変えていく必要もある。こうした手法の開発、普及には、NGO等の地域住民の外の存在の協力も重要であろう。NGOにより、保護増殖活動、人の生活と野生生物との棲み分けや共存を目指す活動が行われている例も諸外国では見られるし、我が国でも起こりつつある。
山村、農村の地域住民は、本来最もその地域の自然環境、野生生物に通じており、これまでこうした野生生物や自然環境と共存する生活を通じて保護を担ってきた人々でもある。その文化も自然や野生生物と密接に結び付いてきた。一方で、優れた自然や野生生物の保護に対しては、国民は高い価値を置くようになってきている。平成4年3月に国会に提出された環境基本法案においては、その理念に環境の恵みの持続的な享受が掲げられ、施策の策定や実施の方針として、生態系、生物種の多様性の確保が掲げられたところである。こうした理念等が国民の規範として明定されることを受けて、新しい目で、地域住民と国民一般が適切にかつ公正に、それぞれの長所をいかし、役割を分担していくことが必要である。