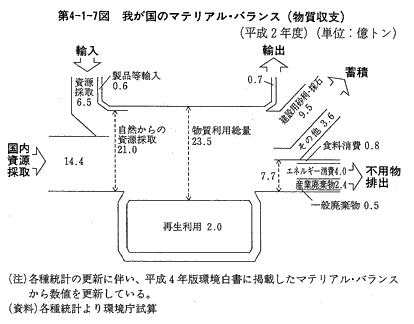
4 環境負荷低減のためのリサイクル
我が国では、様々な物質の利用量が増大するのに伴って、ごみをはじめとして環境への負荷が増加している。このため、これを減らすための一つの手段として、リサイクルの推進が重要な課題となっている。ここでは、我が国の物質利用量の動向を眺めた後で、リサイクルの現状と課題について、紙を例として見てみよう。
(1) 増加し続ける物質利用量と高まるリサイクルの必要性
我が国は、その経済活動に伴い、自然界から鉱物資源や生物資源などの資源を大量に採取し、利用した後、排水、排気ガス、ごみなどの不用物として再び自然界に排出している。こうした物質利用の状況を把握するために、我が国の経済活動に係わる物質の流れを総合的に計算した物質収支(マテリアル、バランス)を見てみよう。平成2年度には、国内外で合わせて約21億トンの資源が採取され、約6千万トンの輸入製品等と合わせて、合計で約21億6千万トンの物質が新たに我が国の経済活動に投入された。この結果、約7億7千万トンの不用物が排出され、約7千万トンの製品が輸出され、残り約13億1千万トンは建築物や耐久消費財として蓄積された。再生資源として再び投入に回されたのは約2億トンであった(第4-1-7図)。我が国の物質の利用量は増加を続けており、そのうち資源採取量と不用物排出量について経年変化を見ると、2年度の資源採取量は20年前の約1.4倍、不用物排出量は同じく約1.7倍となっている(第4-1-8図)。
人間の活動は、このように自然界から資源を採取し、再び自然界に不用物として排出することにより成り立っている。自然の生態系には、「動物の死骸を微生物が分解し、それを養分として植物が育ち、それをまた動物が食べる」といった図式に代表される循環のシステムがある。人間の資源採取と不用物排出の量と質が自然の生態系の循環に完全に適合したものである場合には、排出物はこの循環のシステムにより再び資源に転換されるため、環境汚染も資源の枯渇も起こらない。しかし、産業革命以降には、採取と排出が量的にも質的にも地域の自然の循環の能力を大きく越えてしまったため、地域的な環境問題が発生するようになった。その後、人間の経済活動は、資源供給源と不用物排出先を次々に新たな自然環境の中に求めるという方法で維持、拡大されてきた。しかし、経済規模の拡大に応じて採取と排出の量が飛躍的に増大する中で、こうした方法も地球の自然の有限性という限界に近づき、地球規模で資源の枯渇や種の絶減、不用物の蓄積による環境の悪化といった問題が生じてきた。このように、今日の環境問題は、本質に帰って考えれば、資源採取と不用物排出の量と質が自然の循環の容量を越えてしまったために生じたものと言える。上記の物質収支に見るように、我が国の経済活動に伴う資源採取量と不用物排出量は一貫して増え続けており、これによる環境への負荷は増加し続けている。こうした中で、我が国の経済を環境への負荷の小さなものとして行くためには、資源の採取と不用物の排出の質を自然の生態系に適合したものとしていくとともに、それらの量そのものを減らすことことが必要である。このため、具体的には、有用性の低い物資や無駄なエネルギーの消費を減らすこと、持続可能な形で生物資源や自然エネルギーの利用を進めること、自然環境中に不用物を排出する場合は、無害かつ極力分解可能な形で行うことなどの取組が必要である。
リサイクルもまた、このための有効な手段である。不用物を再び資源としてリサイクルすることにより、人間の活動の系の中で物質を循環させることができるため、必要な消費を確保しつつ、自然界からの資源採取と自然界への不用物排出を減らすことができるのである。
しかし、リサイクルを行うに当たって、排出された不用物から再生可能な資源を回収する営みのみを強調することは、大量消費、大量リサイクルの陥穽におちいる可能性がある。リサイクルを進める環境保全上の目的は、社会全体の環境への負荷を低減することにあり、不用物のリサイクルだけでなく、不用物になる前の、製品の生産、流通の段階から、不用物の量の少ない製品生産や商品の品揃えに努め、包装のあり方を見直すなどの努力を促進する必要がある。
また、不用物のリサイクルを進めるに当たっては、リサイクルによって廃棄物の発生が抑えられ生産工程でのエネルギー消費が節約されるとともに天然資源の投入が抑えられる一方、追加的なエネルギーが必要となるなど環境への負荷の増大要因をも伴うところである。リサイクルによって全体としての環境への負荷が適切に低減されるように、リサイクルの環境保全上の効果に関する科学的知見を一層充実させていくことが必要である。
リサイクルは、こうした前提の下で、環境への負荷を減らす有効な手段であり、一層推進していくことが必要である。現在、紙、ビン、缶、古繊維などの消費財や各種の産業廃棄物についてリサイクルが進められている。
リサイクルがどのような状況にあるかは、物品ごとに異なる点も多いが、再生資源価格が低迷し、これに伴ってリサイクルを支えている再生資源業者が不振に陥っていることが、共通して問題となっている。再生資源業者に対するアンケート調査の結果によると、経営上の問題としては、「再生資源価格が安く、経営が成り立たない」、「回収や分別作業が多くなり、経費がかかりすぎる」などの項目が挙げられており(第4-1-9図)、また、リサイクルを推進して行くための方策としては、「自治体が価格補償等を行い、価格の安定を図る」、「一般家庭や事業所に逆有償の慣習を持たせ、回収コストを補填する」、「回収業者も自治体のゴミ回収業務に参加し、回収したゴミの分別・再生利用ができるような仕組みをつくる」といった項目が挙げられている(第4-1-10図)。これらは、リサイクルのためのコストを再生資源業者だけで支えきれなくなっているため、地方公共団体や住民などとその負担を分かち合う必要があるという業者の認識を表しているといえる。このように、様々な物品に共通した課題として、リサイクルのあい路を解決するには、例えば再生資源業者の営業努力といったような、一部の関係者の個別的な努力ではなく、リサイクルを進めるための役割を様々な関係者が適切に分担し、互いに協力していくことが必要となっている。
ここでは、こうしたリサイクルの現状と課題を実例に即して具体的に考えるため、国民に身近な紙のリサイクルを例に取り上げてみる。
(2) 紙のリサイクルの現状と課題
ア 紙の生産・消費に伴う環境負荷とリサイクルの意義
我が国の紙の生産量と消費量は、平成3年までの数年間は急激に増加し、これに伴って、原料である木材の消費量が増加するとともに、廃棄される紙の量が増加してきた。しかし、平成4年には景気後退により11年ぶりに前年を下回り、これに伴い原料木材の消費量も減少している(第4-1-11図)。
製紙原料用の木材(パルプ材と呼ばれる)のうち輸入材の割合は57%(平成4年)であるが、この輸入先の大半は先進国である。また、パルプ材には、上質の原木はほとんど使われておらず、製材等の用途に向かない低質材や製材残材などが中心となっている。しかし、我が国の木材消費量の約40%が製紙原料として用いられていることを考えれば、減少が懸念されている世界全体の森林の保全のためには、製紙原料用の木材の消費量をいたずらに増加させることなく、持続可能な管理の下にある森林からの供給に移行していくことが望ましい。これは、森林資源に依存している地域の健全な発展のためにも重要である。
また、紙ごみの増加は、ごみ全体の増加の主要な要因となっており、例えば、東京都区部では、2年度までの4年間のごみ増加量の約80%が紙ごみの増加によるものである。さらに、紙ごみの増加は、プラスチック類とともに、ごみの発熱量を上昇させ、焼却炉の稼働率を低下させる原因となっている。このように紙ごみは、ごみの量自体の増加と、焼却炉の稼働率を低下させることの両面を通じて、埋め立て処分されるごみの量の増加の要因の1つとなっている。こうした点から、紙ごみを含めた廃棄物の減量化が急務となっている。
このように、紙については、処女原料使用量と廃棄量の双方を極力減らすことが求められており、このためには、まず紙の無駄な消費を減らすとともに、消費した分についてはリサイクルを進めることが必要となっている。
紙のリサイクルの効果は、紙ごみの量を減少させることと、原料である木材の使用量を減少させることにとどまらず、エネルギー使用量を節減する効果もある。環境庁の試算によれば、パルプ製造段階では、古紙を原料とする場合のエネルギー使用用量は処女資源を原料とする場合の約4分の1で済み、具体的にはパルプ1トン当たり約254万9000kcal(原油換算約280の省エネルギー効果がある。一方、輸送過程では古紙の方が余分なエネルギーを消費するが、製造段階の省エネルギー効果に比較すればわずかな量である。こうしたエネルギー使用量の節減に伴い、二酸化炭素や窒素酸化物などの大気環境への負荷も削減される。
一方、紙のリサイクルは、水質への負荷量にも影響を与える可能性がある。第4-1-4表は、木材チップから製造した機械パルプ及び晒化学パルプと新聞古紙を原料とした晒脱墨パルプについて、製造コストとCOD発生量を比較したものである。COD発生量について見ると、古紙を原料としたパルプは、機械パルプよりは少ないものの、晒化学パルプよりは多くなっており、中でも白色度の高いものほど多くなっている。現在ではバージンパルプの主力は晒化学パルプであるため、古紙の利用の拡大により、COD発生量が増えてしまう可能性がある。このため、紙のリサイクルの推進に当たっては、排水処理に十分留意する必要があるとともに、紙の質についても、いたずらに白色度の高いものを求めるのではなく、用途に応じ、可能な限り白色度の低い紙を用いて行くことが必要である。また、電力費、薬品費についても、白色度の高いものほど高くなっており、エネルギーや化学薬品の使用を通じて発生する環境負荷を減らす意味でも、できるだけ白色度の低い紙の利用が望ましい。
このように、紙のリサイクルは、総じて環境負荷を低減する効果を持っており、一層推進していくことが必要である。以下、我が国の紙のリサイクルのこれまでの歩みと現状を概観し、今後の一層のリサイクルを進めていくための課題を考えていく。
イ 我が国における紙のリサイクルの状況
まず、我が国の紙のリサイクルの状況を国際的に比較してみると(第4-1-12図)、我が国は、リサイクルの最も進んだ国の一つとなっており、古紙回収率は、先進諸国の中ではオランダに次ぐ水準となっている。これまでの変化を見てみると、我が国のリサイクルは従来から高水準にある一方、ドイツ、米国などいくつかの国では、1980年代後半(昭和60年頃)から、環境保全、特に都市ごみ問題の観点からリサイクルが進む傾向が見られ、我が国の水準に近づいている国もある。
次に、我が国のこれまでの歩みを見てみる。第4-1-13図に見られるように、昭和50年前後の石油危機のころから、我が国の古紙利用率と古紙回収率はともに上昇してきた。これは、輸入チップの価格高騰を背景として、国産資源であり、より安価で安定的に供給されるという経済的なメリットを持つ古紙を、紙・パルプ産業が積極的に利用したことによるものである。
その後、60年代に入ると、従来より古紙混入率の低いOA用紙の需要が拡大したことに加え、円高の影響などから輸入チップの価格も低位で安定していたため、古紙利用率の上昇が停滞した。また、紙の輸入量が増加したこと、円高の影響などから古紙の輸入量が増加したこと、国内の古紙引き取り価格が低で安定したこと、使用が急増したOA用紙の回収が進まなかったことなどから、古紙回収率は低下傾向をたどり、62年からは回収率が利用率を下回るようになった。
しかし、63年頃になると、新たに環境保全の観点からリサイクルの意義が見直され、古紙の分別回収や再生紙の積極的な利用が各方面で広がり、回収率、利用率は再び上昇を始めた。製紙メーカーでも、平成2年に日本製紙連合会が「リサイクル55計画」を打ち出し、向こう5年間で古紙利用率を55%まで引き上げることを目標に掲げた。平成3年には再生資源の利用の促進に関する法律が制定され、この法律に基づき、紙製造業が再生資源の利用を進めるべき「特定業種」に指定されるとともに、古紙の利用率を平成6年度までに55%に向上させることが公的な目標として定められた。こうした取組の中で、平成3年度には、古紙利用率は52.3%、古紙回収率は50.9%に達し、回収率は、過去のピークである昭和59年の水準にまで回復した。
このように、近年の取組の中で紙のリサイクルは進んできているが、その現状を見ると様々な課題がある。現在最大の問題となっているのは、古紙の需要の伸び悩みである。景気の減速により紙の生産の伸びが鈍化する中では、古紙の回収が進んでも、製紙メーカーの側での製紙原料である古紙の需要が伸び悩み、古紙の価格が低下している。このため、古紙回収業者は、在庫も増加する傾向にあり、経営環境が悪化している。(第4-1-14図)。
回収面を見ると、集団回収や地方公共団体による分別回収は進められているものの、従来回収システムが確立していなかったオフィスの古紙の回収はまだ十分進んでおらず、一方、古紙回収業者の経営環境の悪化から、既存の回収ルートも弱体化していくおそれがある。このように、紙のリサイクルの一層の推進のためには、利用、回収の両面の課題を解決していく必要がある。
ウ 紙のリサイクル推進のための課題
上記のような利用面、回収面での課題とその解決の方向をより具体的に考えるため、古紙回収業者、製紙メーカー、消費者のそれぞれの立場で何が問題となっており、何が必要とされているかを見て行こう。
(ア) 回収業者から見た問題
古紙回収業者は、古紙を回収し、蓄え、品質を整え、再び資源として製紙メーカーに納入するという重要な役割を担っている。これまで、我が国のリサイクルは回収業者に支えられていた部分が大きく、今後の一層の推進のためには、回収業が健全に営まれることが肝要である。しかし、現在、古紙の需給バランスが崩れ、古紙価格が低迷し、業者の在庫も増加傾向にある。しかし、自治体や住民により古紙の分別回収が進められると、回収業者としては、これに協力して古紙を引き取らざるを得ず、こうした板挾みの中で業者の経営環境は悪化している。このため、回収業者の立場からは、古紙の需要拡大による経営環境の改善が緊急の課題となっており、製紙メーカーによる古紙利用の拡大や、各消費者による古紙配合率の高い製品の利用、特に大口消費者や公的主体による一層の利用が求められている。
一方、古紙の回収面については、最近では、複合素材も含め紙の種類が増えたため、回収業者の分別作業の負担が増加しており、これを節減するため、消費者の段階での分別の徹底が望まれている。
(イ) 製紙メーカーから見た問題
我が国の古紙利用率は、現在、主要製紙国の中で既に最も高い水準にあるが、製紙メーカーでは古紙利用が進められており、主要製紙国同様、これがさらに上昇する傾向にある。しかし、国内の古紙の利用は古紙の回収を下回り、古紙の需給バランスが崩れている。市場経済の中で営利企業として活動している製紙メーカーの立場からは、需要のない製品を製造することはできないため、より一層の古紙利用を進めるには、消費者による再生紙や古紙配合率の高い製品の需要が伸びることが求められている。
また、古紙の購入についても、メーカーの立場からは、品質、コストの面で原料としてメリットがあることが利用の条件であり、より安価で、かつ品質の高い古紙の供給が求められている。
(ウ) 消費者から見た問題
消費者については、古紙の利用の面では、品質や見栄えの点から古紙の配合率の少ない製品を求めたり、環境への負荷の高い白色度の高い製品やリサイクルしにくい複合素材を使った製品を求める傾向がみられる。紙の品種毎に、生産量に対する古紙消費量の割合を示す古紙消費原単位を見てみると、例えば、衛生用紙(ティッシュペーパー、タオル用紙、トイレットペーパー等)は従来から原単位が高かったが、近年急速に低下してきた(第4-1-15図)。これは、最近の高級品指向の中でバージンパルプを使ったトイレットペーパー等の各種の衛生用紙製品のシェアが増加していることが原因となっている。消費者の立場から見れば、環境保全上望ましい製品に関する情報やそうした製品を買える機会が不足している場合、環境の観点を考慮せずに使いやすい製品や見栄えのよい製品を選びがちになる傾向がある。このため、環境負荷の少ない製品が選びやすくなるよう、生産者によるこうした製品の品質向上やより一層の価格低下の努力が望まれる。また、生産者や流通業者などが、こうした製品の品揃えや情報提供を充実するとともに、環境負荷の大きな製品の宣伝、販売が過剰にならないよう留意することが求められている。
(エ)オフィスなどの事業者から見た問題
オフィスなどの事業者を見ると、再生紙の利用はまだ十分には進んでいない。OA用紙などへのいわゆる再生紙の利用は平成元年ごろから広がってきたが、再生紙の方が若干価格が高いことや、白色度の低い再生紙を低級品と見る考え方がまだ残っていることが、一層の利用拡大の障害となっている。このため、紙の生産量の約57%を占める印刷・情報用紙の原単位は、徐々に上昇してきているものの、依然として低い水準にある(第4-1-15図)。事業者の立場からは、より品質の高い再生紙の低価格での供給を望む気持ちが生まれることになる。
回収面については、分別回収に取組む事業者が増えてきているものの、いまだにオフィスからの回収は他の分野よりも遅れている。この原因としては、簡単に参加できるような既存の回収システムが確立されていないこと、市街地中心部に立地するオフィスでは古紙を蓄える場所が確保しにくいこと、機密文書の取扱が難しいことなどがあり、事業者の立場からは、こうした事情に対応した回収ルートが整備されることが望まれる。
エ 今後の取組の方向
これまで、紙を例にとってリサイクルの現状と課題を見てきたが、そこには、冒頭に述べたような、様々な物品のリサイクルに共通する課題が表れている。リサイクルに関連するそれぞれの主体の立場から見てみると、単独では解決できず、他の主体による取組も同時に求められる問題が多いことが分かる。リサイクルは、社会全体としては必要かつ有益であるが、現在の経済社会の枠組みの中で、各主体が自分の利益に従い最小限の責任だけを果たしている限り、こうした課題が克服できず、リサイクルは進まないことになる。社会全体の利益のために一層リサイクルを推進するには、各自が自主的に取組を進めることにより自然に互いの協力が可能となるような、適切な役割分担が必要となっている。
また、各主体の適切な役割分担を実現するには、自主的な取組だけに全てを委ねるのではなく、公的にこれを促進するような枠組みが必要となる部分もある。こうした観点から、国においては、平成3年に再生資源の利用の促進に関する法律を制定し、これに基づき古紙利用率の目標を定めて製紙メーカーの古紙利用の拡大を促進するなど、リサイクルされる物品の種類に応じた措置を講じている。また、再生紙やリ夕一ナブルびんといったリサイクルに役立つ商品を含め、環境保全に役立つ商品であることを表示することにより消費者の利用を促す仕組みとして(財)日本環境協会によりエコマーク事業が、また再生紙に関する同様の仕組みとして(財)古紙再生促進センターによりグリーンマーク事業が実施されている。一部の物品については、諸外国や我が国の一部でデポジット制度が設けられているなど、種々の枠組みが考えられるところであるが、適切な制度的な枠組みと各主体の自主的な取組とが相まって、関係者の協力の下でリサイクルが推進されることが求められている。5年3月に第126回国会に提出された環境基本法案においても、こうした趣旨から、事業者において再生資源等を利用するよう努めること、国においては、再生資源等の利用が促進されるように必要な措置を講ずることや、事業者、国民、あるいは民間団体等が自発的に行う再生資源に係る回収活動が促進されるよう必要な措置を講ずることなどが規定されたところである。