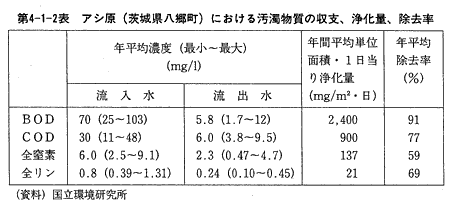
3 閉鎖性水域の水質保全
内湾、内海、湖沼等の閉鎖性水域は、我々に身近な水環境、自然環境であり、我々の生活に様々な恵みを与えている。しかし、一方では、汚濁が進行しやすいという特性を持っているため、その保全への取組が欠かせない環境である。ここでは、閉鎖性水域の汚濁の原因、必要な対策と社会の各主体の関係について見ることとする。
(1) 閉鎖性水域の持つ恵み
内湾、内海、湖沼等の持つ恵みたついてみると、まず、漁業、レクリエーション等の場として我々の暮らしに様々な恵みを与えている。東京湾、伊勢湾、瀬戸内海における主要な水浴場利用者総数は平成3年度に延べ1580万人となっている(平成4年度主要水浴場水質調査)。漁業についてみると、海面漁業、海面養殖を合わせた平成2年の実績は、東京湾では約8万トンの漁獲、約269億円の売上げ、伊勢湾では約15万トンの漁獲、487億円の売上げ、瀬戸内海では約74万トンの漁獲、約2749億円の売上げがあった(一部外部の水域の漁獲を含む)。湖沼においては、淡水の供給機能も重要であり、上水道、農業用水、工業用水として幅広く利用されている。上水道の取水量のうち、湖沼(ダム湖を含む)からのものが3割を超えている。さらに、閉鎖性水域は、優れた景観、水鳥等の飛来地、あるいは多様な生物の生息する干潟等自然環境としても貴重な地域を含むものも多く、また、干潟や湖岸の自然環境は、水質浄化機能についても評価されている。生活排水が流入するアシ原で、その水質浄化機能を測定した調査によれば、BOD、COD、窒素及び燐について、いずれも大きく削減されていることが示されている(第4-1-2表)。
(2) 閉鎖性水域の汚濁の状況と原因
一方では、我々は、このような水域を排水の放流先として人間活動からの不要物の処分にも利用している。自然の水域は、水質の浄化機能を有しており、その能力の範囲内では、人間活動からの環境負荷を浄化するという恵みを与えてくれる。しかし、汚濁物質の流入が過剰になることによって、浄化機能が損なわれ、ひいては閉鎖性水域の持つその他の価値も失われることになる。特に閉鎖性水域は、水の交換が悪く流入した物質が滞留しやすいことに加え、窒素、燐等の栄養塩の流入の増大により、藻類等の増殖に伴い水質が累進的に悪化するという富栄養化の現象が生じるため、汚濁に弱い面を持っている。このため、河川やその他の海域に比べて有機汚濁に関する環境基準の達成率が低い現状にあり、例えば湖招についてみると平成3年度の環境基準達成率は42.3%(COD)であり河川の75.4%(BOD)に比べて低く、また、東京湾では63%(COD、以下同じ)、伊勢湾では59%などと全海域の80.2%に比べ低い状況にある。
東京湾等の広域の閉鎖性海域や主要な湖沼においては、後背地に人口が集中し、経済活動も活発であり、このような活動の集中が汚濁の原因となっている。水質総量規制の対象となっている、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海の規制対象地域の人口は、平成元年で約6,500万人であり、「湖沼水質保全特別措置法」(湖沼法)に基づく9つの指定湖沼に水が流入する指定地域の人口も400万人を超えている。さらに、現在問題となっている汚濁原因はCODで計られるような有機物質や、富栄養化の原因となる窒素、燐等であるが、これらは、工場排水はもちろんのこと、生活排水、畜産業、水産養殖、農地や市街地からの流出など様々な原因から発生するものである。湖沼法の指定湖沼である霞ヶ浦と手賀沼について、排出源別負荷割合を見ると第4-1-6図のとおりであり、いずれも生活系が大きな割合を占めているが、様々な活動を含む広い集水域を持つ霞ヶ浦では多様な発生源が関わっており、都市化した地域にある手賀沼では生活系の負荷が特に高い割合を占めているという特徴がある。
(3) 水質保全対策と様々な主体に求められる役割
閉鎖性水域の水質保全を図っていくためには、まず、汚濁物質が発生、流出する集水域の全体で適切な対策を講じることが必要となる。この際、影響を与えている各種発生源それぞれにおいて対策が進められる必要がある。集水域で活動している様々な主体には、以下のような取組が期待される。
行政には、その規模、能力、事業者や住民との関わりに応じて、対策の枠組みをまとめ、多様な主体による多様な対策を適切に推進していくための方向付けが求められる。このため、都道府県における海域の総量削減計画や湖沼水質保全計画、市町村における生活排水対策推進計画等の計画策定、推進が重要である。また、自らも、水質保全のための地域特性に応じた生活排水処理施設の整備や、導水、しゅんせつ等の公共事業の推進が求められる。さらに、民間における対策の適正化や支援、促進を図っていくことが必要である。
平成2年の「水質汚濁防止法」(水濁法)の改正により、特に生活排水対策の実施の推進が必要な地域を都道府県知事が「生活排水対策重点地域」に指定し、その地域の市町村が生活排水対策推進計画を策定して、対策の推進を図る制度が取り入れられたが、この計画は、閉鎖性水域の保全においても大きな役割が期待される。第4-1-3表は、霞ヶ浦の集水域にある土浦市が、市内河川の水質を改善するとともに、霞ケ浦の水質改善にも寄与することを目的として策定した生活排水対策椎進計画の概要(計画目標)であり、各種施設の整備、直接浄化事業等による総合的な対策の推進が図られている。
集水域の事業者については、各種規制基準を遵守するとともに、できるだけ汚濁負荷が少ない形の活動を行うよう配慮していくことが期待される。工場、事業場については、水濁法や各県の上乗せ条例による排水基準の遵守、さらに、海域の総量規制地域においては総量規制基準、湖沼法の指定地域については汚濁負荷量基準の遵守が求められる。
畜産業については、規模に応じ、排水規則や、湖沼法指定地域においては管理に関する基準が課せられている。農地に関しても、営農の実情に即し、施肥法の適正化や田面水の適正管理が期待される。また、養殖漁業についても、湖沼法においては、管理に関する規制が課されている。
集水域の住民には、汚濁発生源の中で生活排水が高い割合を占めていることにかんがみ、生活排水の負荷の削減に進んで取り組むことが求められる。生活排水処理施設の普及に関しても、各家庭の排水の下水道への接続工事、合併処理浄化槽の設置等のような個人の負担が必要となるものもある。このような対応についても積極的な取組が期待されるとともに、その促進のための公的な支援措置も重要であろう。また、生活排水は、日常的な気配りで汚濁が削減できる部分もあり、各家庭における取組が期待される。平成5年2月に行われた環境保全に関する世論調査の結果から、毎日の暮らしの中で環境保全のために行っている工夫や努力についての質間の回答をみると「てんぷら油や食べかすを排水口から流さない」としている者が61.9%であり、水質保全への気配りへの関心の高さがうかがわれる。しかし、一方では、「浄化槽法」に基づき義務付けられている浄化槽の水質検査の実施率をみると平成3年度では10.5%と極めて低く、これへの取組も進められているが、各家庭からの排水の適切な処理について住民自身も含めた各方面の一層の配慮が求められる。
このように、それぞれの主体が汚濁負荷削減のための努力を行うことに加え、内湾、湖沼等の環境を共有の財産という認識を高め、沿岸、湖岸の清掃や、市街地からの汚濁流入を減らすための水路の清掃等についても、行政、事業者及び住民が協力して取り組んでいくことが期待される。
閉鎖性水域については、汚濁原因が広範で一般的な活動から発生するものであること、これらが集積して問題を引き起こしているという状況にあり、広範な者による取組が不可欠である。しかし、個々の者が与えている影響や個々の者による対策の効果が極めて見えにくいことから、広範な者による水質保全活動を推進していくには、水域とのふれあいの機会を増やしていくことや、海域や湖沼の与えてくれる恵みについて理解を深め、関心を高めていくための努力を欠かすことができない。このような努力の例として、霞ヶ浦において、茨域県では、湖辺にある霞ヶ浦ふれあいランドや水質調査や生物の観察ができる船舶を活用して、霞ヶ浦への親しみと水質浄化意識の高揚を図るための「霞ヶ浦ふれあい研修」を実施している。また、瀬戸内海では、瀬戸内海環境保全基本計画に基づき、関係府県、政令市において、海辺の教室や研修会、講習会等を実施している。