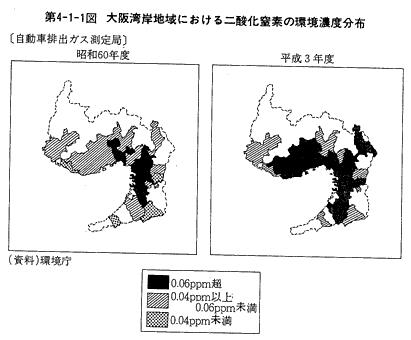
2 大都市における窒素酸化物大気汚染対策
大気汚染は、国民の健康保護に直結する問題であり、かねてよりその改善は環境行政の最重点の課題となってきた。しかし、窒素酸化物による大気汚染は、大都市を中心に汚染が改善されず、これまで各般の対策が講じられてきたが、なお、一層の努力を要する状況にある。ここでは、窒素酸化物の汚染の改善を困難にしている要因、必要な対策と社会の各主体との関係についてみることとする。
(1) 窒素酸化物による大気汚染の現状と原因
第1章でみたように、東京や大阪といった大都市圏では、近年、窒素酸化物による大気汚染の改善が進まず、かえって悪化傾向もみられ大きな問題となっている。環境基準の達成状況をみると、大都市圏にある、固定発生源に係る窒素酸化物の総量規制地域においては、一般環境大気測定局では約半数の測定局で、自動車排出ガス測定局では大多数の測定局でそれぞれ環境基準が達成されていない。また、達成されている測定局の比率は、近年では概して減少傾向にある。汚染地域の広がりについてみても、第4-1-1図の大阪湾岸地域の状況に示すように環境基準を超過している地域が拡大していく傾向が見られる。
窒素酸化物は、主として物の燃焼に伴って発生するため、その発生源は多岐に渡っている。発生源は、ボイラー等の固定発生源、自動車等の移動発生源に分けることができる。これらの発生源の寄与割合についてみると、大都市圏においては、自動車による排出の割合が高くなっている。また、環境庁の調査によれば、後述する自動車NOx法に基づく特定地域における二酸化窒素の発生源別排出負荷の割合をみると、自動車による排出割合が、東京周辺の特定地域では53.3%、大阪周辺の特定地域では53.9%と大きな部分を占めていると推計される(第4-1-2図)。
(2) 窒素酸化物対策の現状と方向
窒素酸化物に関する排出源対策をみると、まず、固定発生源に対しては、大気汚染防止法による排出規制が、昭和48年以来5次にわたり拡大されてきている。また、57年からは東京都特別区等地域、横浜市等地域及び大阪市等地域の3地域において総量規制が導入され、これにより固定発生源からの発生量は着実に削減されてきた。一方、自動車については、自動車一台ごとの、いわゆる単体規制が48年度以来逐次強化されてきており、現在、平成元年12月の中央公害対策審議会答申「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」に基づく規制強化が進められてきている。これまでの窒素酸化物に係る規制の強化の状況を、未規制時に対する現在の排出量で見ると、ガソリン・LPG車については、乗用車で1/10以下、トラック・バスの重量車で1/5となっている。ディーゼル車については、乗用車で1/5〜1/4に、直接噴射式のトラック・バス(車両総重量2.5トン超)で約2/5となっている。
このような規制の強化にもかかわらず、大気汚染が改善を示していないのは、全体としての自動車による排出量の削減が進まないことが原因となっている。これは、第4-1-3図に見るように、大都市を中心とした自動車交通量の増加や、ディーゼル車の比率の増加が、自動車一台ごとの排出ガス規制効果を打ち消していることによるものである。
自動車交通量の増加は、経済活動の増大や都市への集中の進行により交通量全体が増加してきていることに加え、各種交通機関の中で自動車が利用される比率が高まってきていることが大きな原因である。さらに、宅配便の利用や、在庫を減らし必要なものを必要な時に納入させるジャストインタイム方式の増加等の輸送形態の変化も自動車交通量を増加させる要因である。ディーゼル車は、ガソリン車よりも対策が技術的に難しく、これまで排出量削減がガソリン車に比べて遅れてきている。一方、ディーゼル車の燃科の軽油がガソリンに比較し安価である上、ディーゼル車の方が燃費等の経済性が良いこともあって、近年、貨物自動車を中心にディーゼル車の比率が高まりつつある。また、ディーゼルエンジンには直噴式と副室式があり、副室式の方が窒素酸化物排出量が少ないが、最近では、耐久性、燃費に優る直噴式の生産が増加している。また、トラック・バスの使用年数が伸び、最新規制適合車の代替に時間がかかっていることも一つの要因である。
(3) 自動車に関する対策の充実、強化
以上の状況から、自動車からの排出量全体を削減するための総合的な対策が必要とされている。
4年6月には、特に問題の大きい自動車による窒素酸化物の一層の削減を図るため、「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx)」が公布された。この法律は、自動車から排出される窒素酸化物による大気の汚染が著しい地域を政令で特定地域に指定し、この地域内で各種施策を総合的に講じようとするものであるが、この法律による特別の規制としては、特定地域を使用の本拠とするトラック、バス等に特定自動車排出基準を定め、基準に適合しない自動車には自動車検査証を返付しない等の措置を取ることにより、使用できる車種の規制を行う車種規制が定められている。また、製造業者、運輸業者等の事業者に対して、事業を所管する大臣が自動車使用の合理化等を促進するための指針を定めることとしている。法律の体系は第4-1-4図のとおりである。
この法律に基づいて、国は、特定地域において自動車排出窒素酸化物の総量の削減のために講じるべき施策に関する基本的事項等として、総量削減基本方針(以下「基本方針」という。)を定めている。基本方針は、特定地域において講じられる施策のマスタープランであり、?特定地域における自動車排出窒素酸化物の総量の削減に関する目標、?総量削減計画の策定に関する基本的事項及び特定地域における自動車排出窒素酸化物の総量の削減のための施策に関する基本的事項、?その他特定地域における自動車排出窒素酸化物の総量の削減に関する重要事項について定めたものである。
?の施策に関する基本的事項では、取るべき対策の内容が掲げられており、まず、自動車単体対策の強化、上記の各種規制、また、電気自動車、メタノール車等の低公害車の普及促進のための技術、燃科供給施設の整備等を進めることとしている。次に、輸送効率の向上、自動車交通量の軽減や効率の良い物流システムの整備等の物流対策、公共交通機関の整備、利便性の向上等による人流対策を進めることとしている。さらに、交通の分散や道路機能の分化を図るための環状道路やバイパス等の整備、交通渋滞の解消を図るための立体交差化等を進めること、また、適切な交通規制、駐車場の整備、駐車違反の効果的な排除等による交通流対策を推進することとしている。このほか、二酸化窒素濃度の高い交差点周辺部等の局地汚染対策や普及啓発活動の推進を図ることとしている。
特定地域に係る都道府県知事(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県)においては、総量削減基本方針に基づき、各都府県に係る特定地域について、自動車排出窒素酸化物の総量削減のための具体的な施策の実施計画である総量削減計画を策定していくこととなる。
このような措置を総合的に実施することにより、環境庁の行った試算によれば、特定地域全体で、第4-1-5図に示すように、現況(平成2年度)から3割強の自動車NOx総量の削減が図られ、これによって、特定地域においても概ね環境基準が達成されるものと考えている。
(4) 様々な主体に求められる協力した取組
以上のような対策を着実に推進し、窒素酸化物による汚染の改善を図っていくためには、自動車からの窒素酸化物の発生が、相互に依存し合っている社会の様々な主体の活動の全体から、また、都市や物流全体のあり方から生じているものであることにかんがみ、各主体がそれぞれの役割に応じ、相互に協カして排出量の削減に取り組んでいくことが強く求められる。
国においては、自動車排出ガスの削減目標の早期達成に向けた技術評価の継続的実施等による技術開発の促進や低公害車の開発、普及の促進等の措置を進めていくことが求められる。また、国や地方公共団体においては、公共的な施設整備も必要となる物流対策、人流対策、交通流対策に積極的に取り組んでいく必要がある。また、事業者や住民に対して、各種対策についての普及啓発を進め、その取組への協力を求めていくことも重要な意義を有する。
事業者においては、その業務と交通との関わりに応じて、窒素酸化物の削減に取り組むことが求められる。
まず、自動車の製造業者等は、1台当たりの自動車の排出ガスの低減に積極的に取り組むとともに、電気自動車、メタノール車等の低公害車の開発、普及を進めることが求められる。単体からの排出を低減させるためには、自動車の製造メーカーのみならず、関係する事業者の協力も必要とされよう。かつて、ガソリン車に対する対策が導入される際、当時のガソリンに含まれていた四エチル鉛が排出ガス浄化のための触媒に悪影響を与えることが指摘されたが、鉛の人体影響の問題もあって、燃料メーカーにおいてガソリンの無鉛化が図られることによって問題が解決された。ディーゼル車の窒素酸化物削減に関しても、軽油中の硫黄分の低減が求められており、そのための取組が進められている。
次に、製造業者や運輸業者には、営業用トラックの積極的活用、共同輸配送の推進、帰り荷の確保等による輸送効率の向上や、中長距離の物流拠点間の幹線輸送を中心とした鉄道・海運の積極的活用等適切な輸送機関の利用を進めていくことが求められる。このような対策の推進には、荷主や運輸事業者が連絡を密にして、協力して取り組むことが不可欠な条件である。首都圏の6都県市は、平成3年度の11月から1月の期問の毎週水曜日に、自動車の使用を10%以上抑制するよう事業者等に要請する冬期自動車交通量対策を実施し、合わせて効果把握のためのアンケート調査を実施した。この中で、この対策に協力できなかったと回答した事業所に対し、その理由を聞いた結果では、「生産活動上できなかった」とするものが60%であり、「取引先の指定がありできなかった」が51%であった(複数回答)。各事業者による積極的取組に加えて、事業者間の理解と協力が必要であることが認められる。
地域の住民についても、マイカー通勤をしている人がバスを利用すれば、バスの乗車定員が80人であると仮定すれば1台の定期バスで80台もの自家用車を減らすことができることとなり、公共交通機関を利用する等により、不要不急の自家用乗用車の利用を自粛することが期待される。また、自動車の選択についても、窒素酸化物の排出のより少ない自動車を選択するよう配慮することが期待される。
なお、固定発生源に関しても、近年、暖房の設定温度が上昇してきている傾向もあり、燃料等の使い方に配慮が求められる。環境庁及び関係各省庁においては、冬期に暖房温度の適正化等を内容とする「季節大気汚染暫定対策」を実施している。
民間における以上のような活動を促進していくためには、窒素酸化物問題についての理解を深め、対策への協力を促進していくための普及、啓発活動が重要である。一方、経済的な活動には、商品やサービスの価格がその決定要因として大きいため、環境保全の観点からは、経済的側面と環境との関係についても検討を加える必要がある。例えば、より排出量の少ない車種への代替を促進する税制が導入されているが、このような経済的な誘導措置も重要である。
二酸化窒素は、高濃度では人の健康に影響を及ぼす物質であり、環境基準の確保に向けて十分な対策が求められるが、自動車を中心とする個々の排出源は小さく、それらが集積して発生している問題であるため、個々の排出源に対する規制のみによっては、制度的にも枝術的にも対応に限界がある。さらに、窒素酸化物の排出が、自動車の利用等、通常の事業活動、生活の中から発生する問題であり、都市の構造や活動全体に関わっている問題であることがより解決が困難な原因となっている。このため、長期的、広域的な観点から、物流のあり方や都市構造について行政が基盤となる対策を進める中で、事業者から住民までが、それぞれの影響の程度や寄与の可能性に応じて、相互に協力しつつ、真に社会全体として取り組んでいくことが、唯一の解決への道といえよう。