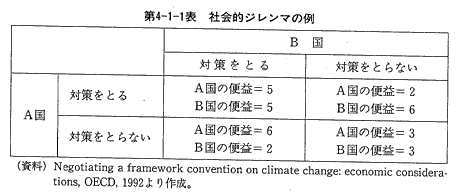
1 環境問題の解決を妨げるもの
第2章で見たように、消費活動も各種の生産活動も、互いに複雑な相互依存関係の網の目を作っており、そこから様々な環境負荷が生じている。一方、第3章で見たように、環境と共に生きる新しい理念、責任が発展してきている。しかし、個々の問題について、具体的に対策を講じていこうとするときには、資金の不足、技術の不足など様々な困難に行き当たる。ここでは、こうした困難が生まれやすい条件や背景事情のうち、各種の環境問題に共通的に見られるものをあげて見よう。
(1) 問題の認識を困難にしているもの
かつての典型的公害問題は、工場のような特定の発生源から出される排煙、排水、騒音等が周辺の環境に悪影響を与え、悪化した環境が人に被害を生じさせるという形のものであった。このような問題については、その発生源、影響及び因果関係が認識しやすく、また、住民が自らの生活への影響を実感することも容易であったため、問題の重要性やその所在が分かりやすく、対策実施を求める意見や行動も高まりやすかった。しかし、都市・生活型公害や地球環境問題に代表される今日の環境問題においては、その影響が実感しにくく、原因や因果関係が複雑になってきている。また、我々をとりまく、家庭や会社、地域社会、国内、現世代といった様々な枠は、具体的な行動に結びつくような意識の深まりを妨げる側面も有している。この点が、今日の環境問題の解決を困難にしている大きな要因と言えよう。
影響が実感しにくいことについて見ると、第1に、環境問題の空間的広がりが問題の認識、理解を困難にしている。国内でも、汚染源と影響が生じる場所が地理的に離れている場合には問題は実感しにくいし、さらに、開発途上国の問題など諸外国で生じている問題については、自らの生活との関わりが薄いために関心が高まりにくい面がある。第2に、地球温暖化、生物多様性の減少等のように、将来になって大きな影響を生じるという意味で原因と結果の間に時間的ずれがある問題については、現在に生きる世代の実感しにくい面がある。第3に、影響の性格について、有害物質による急性的な人体への影響の問題や騒音問題のように直接知覚される問題は、人々の注意を喚起しやすい。しかし、慢性的な影響をもたらす問題、生態系の破壊のように長期や超長期に様々な影響を及ぼす問題等は、実感しにくい問題である。
次に発生原因や因果関係の面でも、問題の認識が困難になってきている。これまでにも、有害化学物質の生物濃縮の問題のように科学的な知見の蓄積により初めて明らかになるような問題があったが、今日では、更に原因、因果関係が理解し難い問題が一層増えてきている。クロロフルオロカーボン(CFC)等によるオゾン層の破壊の問題も、当初は仮説が必ずしも受け入れられなかったが、南極のオゾンホールの発見や科学的知見の蓄積等が進んだことにより、CFC等によってオゾン層が破壊されていることが広く受け人れられるようになった。また、地球温暖化の程度とその原因物質に関しては、引き続き科学的知見の蓄積が求められている。原因が発生する地域と影響を受ける地域が遠く離れ、汚染物質が様々な環境要素の中を移動する酸性雨も因果関係の追求に難しい面がある問題である。このような、原因や因果関係が複雑でわかりにくい問題については、ひとつには、問題を引き起こしているということが認識されないままに、原因となる活動が続けられてしまうという危険がある。また、一般的に、科学的な議論を積み重ねて説明する必要があるような問題については、深い関心を持たない人々にとっては、理解しようとする意欲がわきにくく、意識を高めにくいという面がある。
以上のように、今日重要になってきている問題については、問題への対応を求める認識、意識がまず高まりにくい構造を持っているものが多い。従来の一過性の、いわばフローの汚染が中心であった問題とは異なり、今日の問題は、二酸化炭素の蓄積により地球全体の気候に影響を与える温暖化問題、熱帯林の破壊、酸性雨の影響による生態系の破壊の問題など、環境負荷が蓄積され生じる問題で、かつ、一旦影響が顕在化すると回復が困難であるという性格を持つ。このような問題については、人々がより深い認識を得ているか否かも対策の成否を決める大きな要素となる。
(2) 対策の実施を困難にしているもの
今日の環境問題について、対策の実施を難しくしている要因としては、環境影響の原因が、特定の限られた活動ではなくて、経済社会活動全体の中にあるような問題が増えていることがあげられる。また、環境への影響がより間接的になったり、長期的であることから、地域における生活や日常的な利便等が優先されがちであるという問題がある。
ア 環境負荷発生の機構の変化
再び従来型の環境問題についてみると、特定の生産活動からの排出により公害が生じる場合、その工場において排出を削減するための対策をとることで問題が解決できた。しかし、今日問題になっている、二酸化炭素の排出、窒素酸化物の排出、廃棄物のような問題については、広く日常的な経済社会活動に伴って生じるものであることから、特定の活動に関して対策をとる場合にはない多くの困難を生じる。
第2章でみたように、我々の消費活動や生産活動は、直接の影響だけでなく、産業の連関を通じて、間接的に様々な環境負荷をもたらしている。このような形の環境負荷については、単に直接排出する者に問題があるというだけでなく、全体としての活動が環境に影響を与えていると考えなければならない。様々な間接的な関連も考慮して、各種活動の中に適切、効率的に環境配慮を組み込んでいくことが課題となっている。
次に、このような排出については、個々の排出源の影響への寄与が、量的な面でも、有害性といった質的な面でも極めて小さいながらも、それが集積することにより影響を生じているという性格があり、個々の発生源が、直接人の健康に被害を及ぼすほどの影響を持つ従来型の発生源に比べて、これと同様の厳しい規則を導入することには困難が伴う。
また、規制措置では、産業の連関を通じ間接的に影響を与えるような行動までを対象にすることにも困難がある。さらに、あまりに排出源の多いものについては、規制措置は監視の困難性等から実効が上がりにくい。また、企業や住民においても、自らの活動の影響が、間接的で認識しにくかったり、自分が特別の活動を行っているわけではなく周囲の者と同じ程度の影響しか与えていないという場合においては、対策を実施しようとの動機も高まりにくいと言えよう。
以上のように、二酸化炭素に代表されるような環境負荷については、特別な活動に対する対応で成果を上げることは困難であり、従来の規制的な手法では解決しがたい面がある。
イ その他の便益との競合
人の健康に直接被害を及ぼすような公害、周辺の生活環境にまで重大な影響を及ぼす大規模な自然破壊のような問題については、その解決の社会的優先度が非常に高い。しかし、環境の恵みの中には、目に見えにくいものや長期的な観点から初めて意味を持つもの、また、便益が時間的空間的に離れたところで生じ、恵みを受ける者と対策が求められる者にずれがあるようなものがあり、このような恵みの保全については、他の便益や地域的な便益との間での競合を招く場合が生じる。
地球規模の環境問題では、地球温暖化における現在世代と将来世代との利益の比較や、生物多様性の保全における便益を受ける者と対策をとるべき途上国の負担がこのような問題を含む。また、国内の問題で見ても、農用地や工場跡地等の土壌汚染、休廃止鉱山の排水問題などは、汚染の事後的回復が技術的に難しいほか、便益を受ける者と損失をこうむる者との間に時間的ずれがある問題である。個人生活については、例えば、自家用車の利用、電気製品の使用、宅配便の利用といった便益とそれらが直接、間接に環境に与える影響をどう勘案するかという問題がある。都市への活動の集中に伴う経済的なメリットが優先され、同じ集中によって生じる窒素酸化物による汚染や水質汚濁の問題が解決されないという問題もある。また、優れた自然や野生生物の保護の問題についても、対策をとるべき地域においては、その必要性は全国的な観点からのものであるがためにかえって地元では特別に重要なものと意識されず、短期的な生産、生活の便益が優先されがちであるという問題がある。
地球環境問題のように、空間的、時間的拡がりを持つ問題や、関係者が多岐、多様にわたる日常的な経済、社会活動によって生じる問題により、便益間のバランスの問題、また、環境に影響を与える活動を行う者と影響を受ける者の違いや、守られた環境から便益を受ける者と、対策の負担を被る者のずれが従来の問題とは異なってきており、それが対策への取組を難しくしている。
(3) 求められる協カの難しさと社会的対応の必要
以上のように、各主体の活動が網の目のように関連した社会の中から発生している環境問題の解決のためには、社会の構成員が、一致協力して取り組むことが不可欠である。
まず、今後の環境問題への取組に当たっては、社会の各主体が自主的、積極的に、自らの活動を環境にやさしい方向に見直していくことや、環境保全のための様々な活動に参加していくことが期待される。このためには、(1)で述べたような実感の困難さの問題や、(2)アで述べた影響の実感の難しさに由来する問題の克服が必要となる。
次に、細かな機能分担により成り立っている現代の社会においては、個々の主体の対応にとどまらず、それが有機的に結びつき合った、環境にやさしい経済社会のシステムを作りあげていく必要がある。このためには、各主体がその機能に応じた役割を持ち、縦の協力体制を作ることが求められる。例えば、自動車交通量の低減のために物流の合理化を図ろうとすれば、荷主と運輸業者との緊密な協力が必要である。また、リサイクルシステムを作るには、消費者から回収、再生、再生品の利用までの流れを様々な主体の参加を得て確立する必要がある。このような協力を確保するためには、個人の判断を超えて、何らかの新たな社会的な仕組みが求められよう。
しかしながら、一方では、環境の持つ自由財的な性格が、このような協力の確保を困難にしている側面がある。
第1に、環境は占有できず、誰でも使用できるという性格から、個々の者が、他者への影響や個々の活動が集積して社会全体として環境へ及ぼす影響を考慮せず、自分の利益だけを考えて行動した場合、共有の財産である環境の長期的な恵みが損なわれてしまうという問題がある。このようなものとして、「共有地の悲劇」という例が引かれる。これは、かつてイギリスにおいては共有地を牧草地として利用する制度があったが、みなが競って放牧した結果、飼科となる草が食べ尽くされ、家畜は期待どおりに成長しなかったというものである。地球温暖化の問題、自然公園の過剰利用なども同様の側面があるといえよう。このような場合、環境の恵みが保たれる形で利用した方が、長期的には便益が大きいにもかかわらず、個々人の判断ではそれが達成できないこととなってしまうのである。
第2に、環境の便益は対策を行うものにも、行わないものにも等しく及ぶという性格がある。このことは、個々の者の環境影響への寄与が小さいことと合わせて、対策を実施せず便益にだけあずかろうというフリーライダーを生むおそれがある。例えば、不要不急の自家用自動車利用の自粛を行い、窒素酸化物の削減を図っている中で、自家用自動車を使い、きれいな大気の便益と合わせて自家用自動車を使う便益も得ようとするごとき行動である。競争の中で活動する企業にとっては、他企業に比べて多くの費用を費やせば収益が低下し、競争に遅れを取るおそれがあるため、対策の機運が鈍るおそれがある。ゲーム理論は、複数の者が、自分の利得は、各参加者の行動の決定全体で決まるという条件の下で、どのような行動を行い、どのような選択の結果が得られるのかを解析するものである。この中で、各参加者が協力して行動すればより高い利得が得られるにもかかわらず、他者の協力が期待できないと判断して個々に合理的な決定を行うと、それよりも利得が少ない状態で社会が安定してしまうという現象が「社会的ジレンマ」として表されている。例えば、世界が2か国にのみによってできていると仮定して、「社会的ジレンマ」の例を数値で示したものが第4-1-1表である。これは、A国とB国は、それぞれ、環境保全のため「対策をとる」か「対策をとらない」かの選択をし、自国と他国の選択に応じてそれぞれの国の便益が決まるというものである。自国で対策をとれば、その費用がかかり、また、自国や他国が対策をとらなければ、それにより生じる環境悪化に応じた損失を被ることになる。この場合、A国もB国もともに対策をとれば、それぞれの便益が5となるが、自国が対策をとっても相手国がとらない場合、自国の便益は2となってしまう。従って、相手国の協力が得られるという保証がない状態で、確実に期待できる便益をできるだけ大きくしようとすれば、両国とも対策をとらずにそれぞれ3の便益を得るという状態が生じてしまう。
以上のような問題点を乗り越えて、社会全体の協力を確保するためには、個々の者の意識面での変革や社会経済システムの変革が必要であり、それぞれの問題の性格に応じた様々な努力が求められよう。
まず、基盤として、環境を守るための新たな責任の考え方の枠組み、「環境倫理」ともいうべきものを確立し、社会に定着させていくための努力が求められる。これには、環境の状況や価値について明らかにするための調査研究を進め、その内容を広く普及させていくことも求められよう。次に、対策の実施を求めるルールや、対策をとることが経済的に不利にならないようにすることなどの社会的な枠組みの構築、公共的施設の整備により、個々の者の意識に頼るだけでなく、意識によらずとも結果として一致協力した取組が誘導されるようにすることが重要だろう。さらに、各主体の取組を助長していくための情報提供、技術提供、また資金協力などの支援策も積極的に求められるだろう。
2以下では、現在、解決が求められている様々な問題の中で、分野や性質が異なったいくつかのものを取り上げ、その解決が困難となっている原因、解決のため様々な主体に求められる役割と協力、そしてそれを可能にしていくための社会的な条件について見ることとする。