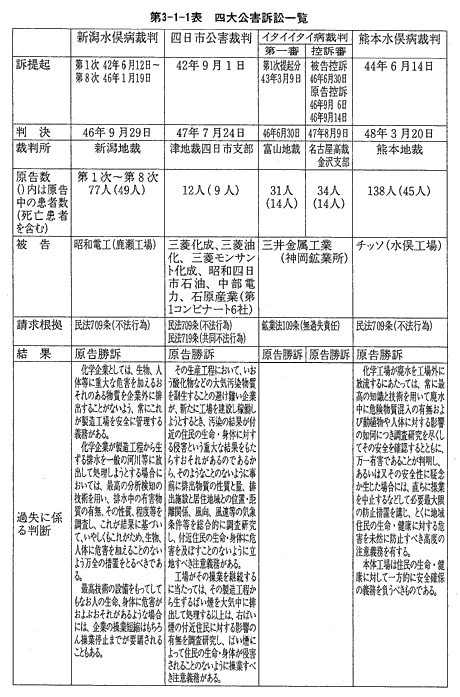
5 公害対策基本法及び自然環境保全法の制定後の制度の進展等
昭和42年の「公害対策基本法」の制定及び47年の「自然環境保全法」の制定以降、個別法等による環境保全制度の整備が次々と進むこととなった。ここでは、両法を柱として発展していった環境保全制度の主要な動きについてまとめたい。
(1) 規制等の充実・強化等
規制に関する枠組みの変化として第一に重要なことは、45年の「大気汚染防止法」の改正及び「水質汚濁防止法」の制定等により、以前の指定地域、指定水域制が廃止され、全国いずれの地域においても規制を実施することとなったことである。これにより問題の生じた地域に後追い的に対処するのではなく、公害問題が生じる前に対処する積極的な方向へと転換が図られた。
また、地方公共団体と国の権限分担も明確化され、地方公共団体は、国の施策に準じて施策を講じるとともに、当該地域の自然的、社会的条件に応じた施策を実施することが責務とされた。このようなことから、「大気汚染防止法」や「水質汚濁防止法」において、地方公共団体は、国の設定する全国一律の規制基準に加えた上乗せの一層厳しい規制を行う権限が規定された。また、自然環境保全に関しても、「自然公園法」や「自然環境保全法」の規定を根拠とした条例を定めることにより、都道府県立自然公園や都道府県自然環境保全地域の指定が進むこととなった。
規制対象も順次拡大されていった。昭和43年の「大気汚染防止法」により事業場のみならず自動車排ガスについても許容限度を定めることとなった。また、「大気汚染防止法」や「水質汚濁防止法」においては、規制対象施設が政令で定められているが、順次施設の追加がなされてきている。「水質汚濁防止法」の規制対象施設を見ると、製造業の施設のみならず飲食店等も対象に含まれるようになってきている。自然環境保全の分野でも、「自然公園法」及び同法施行令の改正により、国立公園・国定公園の普通地域での規制強化、公園利用のための事業施設からのゴルフ場の削除、車馬乗入れ規制等の追加等の規制の強化が行われたほか、「森林法」の改正により、林地開発許可制度が創設された。
規制の手法についても、問題の態様の変化を踏まえて、いくつかの進展があった。工場・事業場などが集中する等の条件から個別の排出基準のみでは環境基準の達成が困難と認められる地域や水域においては、汚染物質の総量を規制する手法として総量規制が導入された。この総量規制は、「大気汚染防止法」については昭和49年の改正で導入され、硫黄酸化物については49年から51年にかけて24の地域で開始され、窒素酸化物については東京都特別区等地域など3地域で57年から実施されている。また、「水質汚濁防止法」については53年に法改正がなされ、東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海の3地域で54年から実施されている。このほか、排出規制以外の形での規制も導入されており、工場立地については、大都市圏において「首都圏の既成市街地における工場等の制限に関する法律」等による工場の新規立地の抑制が行われている。また、平成2年に公布、施行された「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律」では、環境庁長官が指定する地域においてスパイクタイヤの使用を規制することとしている。また、平成4年に成立した「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」(自動車NOX法)では、トラック、バス等について、特定地域において、特別の排出基準に適合しない車両の使用をできなくすることとしており、東京や大阪の周辺が政令で特定地域に指定されている。
(2) 計画的対応の推進
大都市圏における窒素酸化物対策のように広域的な対応が必要な問題、湖沼の水質汚濁のように複雑な汚濁源に対して多様な対策が求められる問題などに対応するために、計画を策定し、これに基づき各種対策を総合的に講じる制度が設けられている。先にあげた「公害対策基本法」に基づく公害防止計画、「大気汚染防止法」や「水質汚濁防止法」に基づく総量削減計画もこのような計画制度である。このほか、昭和59年には「湖沼水質保全特別措置法」が制定され、水質環境基準の確保が緊要な湖沼を指定湖沼として措定し、都道府県知事が湖沼水質保全計画を策定し対策を取りまとめる制度が導入された。また、平成2年の「水質汚濁防止法」の改正により、生活排水対策の推進のため、都道府県知事が生活排水対策重点地域を指定し、当該地域の市町村が生活排水対策推進計画を定める制度が導入された。また、上述の自動車NOx法においても、総量削減計画を策定することが定められている。自然環境保全の分野では、昭和48年より、自然保護を基調とした国立公園等の公園計画の再検討を実施するほか、「森林法」改正により森林計画制度を充実する等、計画的対応の充実が図られてきた。
(3) 未然防止の推進
公害や自然環境の破壊は、いったん発生するとその対策には多大の費用と年月を要し、また完全な回復は期し難い。このため、環境問題の解決には、このような被害が生じないよう環境汚染を未然に防止することや、自然環境の保全を図ることが重要であり、この方向に沿った施策が展開されてきた。「大気汚染防止法」や「水質汚濁防止法」によって、指定地域制の規制を廃し、全国的に規制を行うこととしたことや、自然公園や保安林などの制度の適切な運用を図っていることは、このような考え方に見合うものである。
環境影響評価、いわゆる環境アセスメントは、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業の実施に際し、その環境影響について事前に十分に調査、予測、評価し、その結果を公表し、十分な環境保全手段を講じようとするものであり、環境汚染の未然防止のための重要な手法である。我が国においては、昭和47年に「各種公共事業に係る環境保全対策について」が閣議了解されて以来、「公有水面埋立法」等の個別法、各省庁の行政指導、地方公共団体の条例、要綱等により環境影響評価が行われてきた。さらに59年には「環境影響評価の実施について」の閣議決定を行い、国の関与する大規模な事業に関する統一的な環境影響評価を実施している。
また、環境や人体に悪影響を与える物質が製造されることを未然防止する制度も導入された。昭和46年には「農薬取締法」が改正され、農薬の登録申請に当たって農作物等への残留等に係るものにつき、登録を保留する場合に該当するかどうかの基準が設けられることとなった。また、PCB問題を契機として、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」が48年に制定され、新現の化学物質についての事前審査制度等が開始された。
(4) 事業者の責任の考え方の進展
公害防止等に係る制度が整備される以前には、公害による被害者が法的に損害賠償や対策を求めるためには、裁判に訴える以外に方法はなかった。「公害対策基本法」による事業者の責務に加えて、このような訴訟の判決を通じても事業者の汚染防止対策に関する責任が明らかにされてきた経過がある。
民事訴訟において、被告が責任を負うための要件の一つとして、汚染を引き起こした行為について故意又は過失があることが通常必要である。これは、過失がないと言えるためには、事業者にはどのような行動が求められるか、どのような責任を果たさなければならないのかという意味合いも持つため、損害賠償請求訴訟における過失の考え方を通じて、汚染に関する排出者の責任ということも明確になってきた。明治から大正にかけて裁判が行われたいわゆる大阪アルカリ事件における大審院判決では、会社が損害予防のために相当な設備を施した以上は、過失ありということができず、たまたま他人に損害が発生しても、損害賠償責任は間われないという判断が示された(ただし、この訴訟では、会社が相当の設備を設置していないとの判断がなされ、損害賠償が認められている。)。一方、昭和30年代以降における公害に関する訴訟判決により、責任に関する考え方にも進展がみられた。特に重要なのは、熊本水俣病裁判、四日市公害裁判等のいわゆる四大公害訴訟である(第3-1-1表)。例えば、熊本水俣病判決では「化学工場が廃水を工場外に放流するにあたっては、常に最高の知識と技術を用いて廃水中に危険物質混入の有無および動植物や人体に対する影響の如何につき調査研究を尽くしてその安全を確認するとともに、万一有害であることが判明し、あるいは又その安全性に疑念を生じた場合には、直ちに操業を中止するなどして必要最大限の防止措置を講じ、とくに地域住民の生命・健康に対する危害を未然に防止すべき高度の注意義務を有する」とされているように、これら判決を通じて事業者には被害が発生しないように十分な注意を行う義務があることが明確化された。
公害に関する訴訟を通じ、被害の補償や上のような責任に関する考え方が明確化されたが、一方では、原告の故意又は過失や損害との関係の立証が困難な場合も多く、被害者が極めて不利な立場に立ったり、裁判が長期化するなどの問題点も明らかになった。このようなことから、汚染被害の加害者が過失の有無にかかわらず損害賠償責任を果たすべきだという無過失損害賠償責任の考え方が強く主張されるようになった。これを受けて、昭和47年に「大気汚染防止法」及び「水質汚濁防止法」が改正され、有害物質が人の生命や身体を害した場合には、過失がなくとも損害賠償責任を認める考え方が位置づけられた。このほか、「大気汚染防止法」や「水質汚濁防止法」において、排出基準違反に対して直罰が課されるようになったことや、45年に「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」の制定により、公害により公衆の生命、身体への危険を生じさせる行為に対して刑事罰が課されることになったことによっても、事業者の責任が厳格化されることとなった。
(5) 健康被害補償、公害防止事業の制度化
我が国においては、四日市ぜんそくや水俣病にみられるように、公害による被害として著しい健康被害が生じた。当初において、これらの健康被害の救済は、制度的には民事訴訟等の手段により損害賠償を求めることしか道はなかった。四大公害裁判判決等を通じ、このような損害賠償も認められる例が出てきたが、一方では、民事訴訟による公害健康被害の救済は、その内容の複雑さから、迅速な解決が困難であること等も認識されるようになり、行政上の救済措置が求められるようになった。
このような制度として、まず制定されたのが昭和44年に成立した「公害に係る健康扱害の救済に関する特別措置法」である。この制度は、民事責任とは切り離した行政上の救済制度として構成されており、事業者からの拠出による納付金と公費を財源とし、法に規定する認定患者に対し、医療費、医療手当及び介護手当の給付を行うものであった。しかし、この法律は、公害健康被害の補償については根本的には民事的な解決が図られることを前提に、当面の緊急措置として医療費等の給付を行おうとするものであったため、過失利益に対する補償がなされない等給付の内容が限定されていた。
その後、前述の四日市公害訴訟判決が原告勝訴となり、法的因果関係の認定や被害者の過失利益の評価の方法についての判断が示されたことなどから、各界の大きな反響を呼び、行政上の補償制度の確立への期待が高まっていった。
こうして48年に「公害健康被害補償法」(公健法)が制定され、汚染原因者の負担により過失利益の補償等も行う民事責任を踏まえた行政上の損害賠償保障制度が整備された。この制度では、気管支ぜん息のように汚染原因物質と健康被害の因果関係の特定が困難な疾病の多発している第一種地域と、原因物質との因果関係が一般的に明らかな疾病が多発している第二種地域に応じて、被害者の認定や費用負担の方法が定められている。
なお、第一種地域については、現在の大気汚染は気管支ぜん息等の主たる原因をなすものとは考えられず、地域指定を継続することは民事責任を踏まえた本制度の趣旨を逸脱するとの中央公害対策審議会の答申に基づき、昭和62年に、第一種地域に関する新規認定の打ち切り、既被認定者への補償給付等の継続、健康被害予防事業の実施等を内容とする制度改正が行われた。この制度改正は63年に施行され、公健法は法律名を「公害健康被害の補償等に関する法律」に改正され、同法に基づき、健康被害の補償に加え、大気汚染による健康被害の予防のための施策も推進されることとなった。
水俣病に関しては、現在も、患者認定や被害発生に対する責任を巡り訴訟が提起されているような状況があるが、水俣病発生地域においては、水俣病と認定されない者に対しても、平成4年度より、発生地域における健康上の問題の軽減、解消を図るため、水俣病総合対策事業が開始された。
また、公害防止対策に関する費用負担制度についても整備が図られた。「公害対策基本法」において「事業者は、その事業活動による公害を防止するために国又は地方公共団体が実施する事業について、当該事業に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。」と定められたことを受け、45年に「公害防止事業費事業者負担法」が制定された。この制度により、緩衝緑地の設置、しゅんせつ事業、農用地の土壤汚染に係る客土事業などの公害防止に係る公共事業について、その原因となる事業活動を行う者に、原因となった程度に応じて費用を負担させることができることとなった。
一方、国際的に公害防止対策の費用に関する考え方を示したものとして、OECDによる汚染者負担原則が47年に示された。これは、希少な環境資源の合理的な利用を促進するとともに、国際貿易・投資における歪みを回避するためには、汚染防止対策の費用は汚染者が負担すべきであることを加盟各国に勧告したものである。我が国においては、各種公害規制やさらに健康被害補償や公害防止事業の費用負担が、この汚染者負担原則に適合する形で整備されてきたといえる。