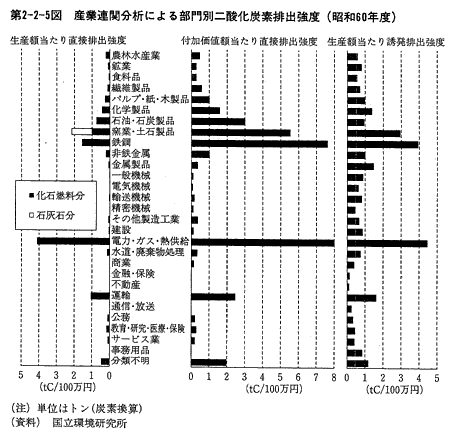
2 個別の生産活動から発生する環境負荷の大きさ
次に、より具体的に生産活動と環境との関系を見るために、二酸化炭素を例にとって、個々の生産活動に伴って発生する負荷の大きさを見ていこう。国立環境研究所が、産業連関表を用いて、生産活動の部門毎に二酸化炭素の排出量を分析した結果が第2-2-5図である。各部門から直接に排出される生産額100万円当たりの二酸化炭素量(以下、生産額当たり直接排出強度と呼ぶ)、付加価値100万円を生み出すために各部門から直接に排出される二酸化炭素量(以下、付加価値額当たり直接排出強度と呼ぶ)、生産額100万円の生産活動に伴い原材料の製造段階等も含めて直接、間接に排出される二酸化炭素排出の総量(以下、生産額当たり誘発排出強度と呼ぶ)の、3種類の値を比較している。なお、この産業連関表による部門分類は企業ではなく活動に着目した分類であり、例えば、実際の製造プロセスとしては一貫していても別々の部門に分類される活動があるなど、いわゆる産業分類とは若干異なる点があることに注意を要する。
この結果をみると、同じ額の生産を行うために排出される二酸化炭素の量は、生産活動の種類により大きく異なっていることが分かる。生産額当たり直接排出強度は、電力・ガス・熱供給が最も高く、ついで、鉄鋼、運輸、窯業・土石、石油・石炭製品などが高くなっており、概して、エネルギー供給、基礎素材、運輸といった分野の活動からの排出強度が高くなっている。付加価値額当たり直接排出強度では、排出強度の高い部門と低い部門の差がより拡大する傾向が見られる。しかし、これらの直接排出強度が高い活動から産出された財やサービスは、他の活動によって原材科などの形で消費されることになる。このため、原材科等の生産過程をも含めて考えた生産額当たり誘発排出強度を見ると、加工型の製造業や第3次産業などの生産活動に伴う排出量も大きくなっている。
環境への負荷には、大気汚染物質や水質汚濁物質から自然環境への負荷に至るまで様々な種類があり、生産活動と負荷の発生量との関係の様子は、負荷の種類により当然異なっているが、上記の分析結果から、一般に次のようなことが言えるであろう。すなわち、生産活動の種類により負荷の発生量は大きく異なるため、全体の負荷量を低減させる可能性が大きいものとしては、まず第1には発生量の大きい部門における取組が考えられる。しかし、各種の生産活動は独立しているものではなく、経済の網の目の中で相互に関連しながら営まれているため、負荷の量全体を減らすためには、直接に負荷を排出している部門だけではなく、原材科等の消費を通じて間接的に排出を誘発している部門での取組も求められるのである。こうした総合的な対策を促すことが、結局、経済の効率性を生かしつつ環境を守ることにつながっていくのである。