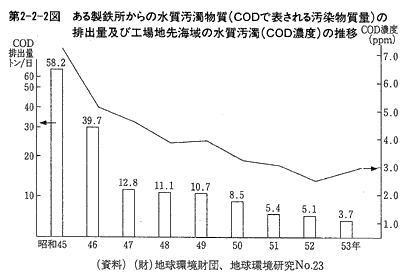
1 生産活動から発生する環境負荷の重要性
我が国は、高度経済成長期に、水俣病や四日市ぜんそくに代表されるような、健康被害をもたらす激しい公害を各地で経験した。これらの公害は、生産活動からの排煙、排水に起因するものであり、生産活動から発生する汚染物質をいかに減らしていくかが当時の課題であった。
こうした状況の中で、昭和40年代から、政府により環境基準の設定、排出規制の実施等の措置が取られ、これに対応して企業による技術開発、公害防止投資、生産工程の変更などの対策が進められた。その結果、生産活動からの汚染物質の排出量は減少し、周辺の環境汚染は改善されていった。第2-2-2図は、ある製鉄所からの水質汚濁負荷(COD)の排出量と周辺環境の水質汚濁の状況の推移を表しているが、工場からの排出量の削減に伴い、環境の汚染も大きく改善されていったことが分かる。
このように、生産活動に起因する産業公害の改善は進んだが、今日課題となっている環境問題について見ても、生産活動によりもたらされる環境への負荷は、いまなお重要な位置を占めている。第2-2-3図は、廃物の排出による各種の環境負荷について、発生源別に負荷割合を見たものである。二酸化炭素と廃棄物は全国の合計、窒素酸化物とCODは総量規制地域の合計である。これを見ると、負荷の種類により異なるが、生産活動から発生する環境負荷は4割弱から9割弱に達している。
国内の公害問題の中では、大都市地域の窒素酸化物等による大気汚染問題や、公共用水域の有機汚濁の問題の改善は依然として進んでいない。これらの問題は、いわゆる産業公害とは異なり、自動車からの排気ガスや家庭からの生活排水など、住民の消費生活に係わる負荷が比較的大きな比重を占めており、都市・生活型公害と呼ばれている。しかし、こうした問題においても、生産活動からの汚染物質の排出はなお主要な原因の一つとなっている。
個別の環境負荷の種類ごとに第2-2-3図に沿って見ていくと、窒素酸化物汚染については、工場からの発生量の割合は、減少してきてはいるものの、昭和60年で依然約39%に達している。また、約55%に及ぶ交通からの発生量のほとんどは自動車からの排出であるが、第2-2-4図の東京都区部の例に見られるように、その大半は貨物輸送など事業活動に関連する排出であり、広義の生産活動によるものである。
水質汚濁について見ると、総量規制地域(東京湾、伊勢湾、瀬戸内海)のCOD発生負荷量の合計では、産業排水による負荷の割合は、約36%である。また、その他として表示している約10%の中には、農業からの汚濁負荷も含まれており、これも生産活動に伴うものである。
このほか、二酸化炭素や廃棄物などの環境負荷の排出量について見てみても、生産活動からの排出の占める割合は大きく、窒素酸化物やCOD以上となっている。
二酸化炭素について見れば、産業部門と転換部門からの排出に産業廃棄物焼却分等を加えたものを生産活動からの排出と考えると、これは全体の約69%を占めている。さらに、交通(運輸部門)からの排出の一部は窒素酸化物の場合と同じく主として事業活動に従事するトラックからのものであること、消費からの排出の一部は業務用のオフィスからの排出であることを勘案すると、広義の生産活動からの排出はより大きな割合を占めることになる。
また、廃棄物の発生量では、廃棄物全体(し尿は除く)に占める産業廃棄物の割合は約89%にも達している。さらに、二酸化炭素の場合と同様、消費として表示した一搬廃棄物の中には、業務用のオフィスからのごみも含まれており、生産に関連する活動全体からの発生量を考えれば、これよりも大きな割合となる。ただし、廃棄物による環境への負荷は、廃棄物の性状やリサイクルされる割合などにも左右され、例えば一般廃棄物の資源化率は3.4%であるのに対し、産業廃棄物の再生利用率は41%に達している点に注意を要する。
一方、自然資源の利用に伴う自然環境への負荷について見れば、近年のいわゆるリゾートブームの中で開発による自然破壊が懸念されてきている。例えば、増加を続けるゴルフ場については、広域にわたる地形、植生の改変、野生生物を含む生態系や景観の変貌といった自然への影響が懸念されている。
このように、かつての激甚な産業公害が改善された今日でも、生産活動から発生している環境負荷は大きい。第1節で見たように、最終的に家計で消費される製品やサービスの生産に伴う環境負荷については、消費活動により誘発されているという考え方もできる。しかし、そうした負荷についても、直接排出しているのは生産者であり、また、様々な対策を行い、排出量を減らすことができる立場にあるのも生産者である。このように、生産活動と環境とは密接に関連している。
なお、生産活動に伴う環境問題の要因としては、環境負荷の発生量だけではなく、負荷の発生する場所も重要である。例えば、かつて工業地帯で深刻化した大気汚染や水質汚濁といった産業公害は工場の集中が一因であった。また、今日課題となっている大都市地域の窒素酸化物汚染は、大都市への経済活動の集中に伴う交通量の増加やディーゼル車の比率の増加が、自動車単体の排ガス規制の効果を相殺してしまっていることが重要な原因である。このように、環境問題の要因を考えるには、環境負荷の排出量だけの分析では不十分であり、その集中度合などの地域的分布も重要であることは忘れられてはならない。