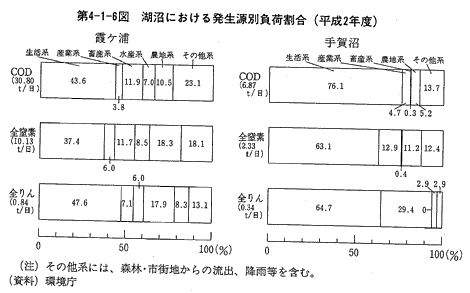
3 水質への負荷
次に消費生活に伴う水質への負荷を見てみよう。消費生活からは、直接に台所、ふろ、洗濯からの排水などの生活排水が発生している。我が国の水質については、高度経済成長期のような重金属等の有害物質による汚染は改善され、現在では有機汚濁が問題となっているが、こうした問題では、種々の負荷の中でも、生活排水による負荷が大きな割合を占めている場合が多い。例えば手賀沼と霞ケ浦について見れば、第4章第1節3の第4-1-6図に示されているように、水域全体の汚濁負荷量(COD)に占める生活排水からの負荷の割合は、それぞれ76%、44%となっており、大きな割合を占めている。
我々一人一人の日常の生活からどれだけの水質への汚濁負荷が発生しているかを見てみよう(第2-1-10図)。一人の一日の生活から直接に発生する汚濁負荷はBODで測って43gである。生活用水の使用量から計算すると、一人一日当たり、BOD濃度132?/の排水を325発生させていることになり、これを魚が住めるような水(BOD5?)に薄めるためには、浴槽約28杯分のきれいな水が必要となる計算になる。その内訳は、し尿が30%、それ以外の生活雑排水が70%となっているが、し尿は法律上直接環境中に排出することは許されず、衛生的な処理が義務づけられているため、家庭から直接に環境中に排出される実際の水質汚濁負荷としては生活雑排水がはるかに大きくなっている。生活雑排水の中では台所からの負荷が最も大きく、次いで、ふろ、洗濯の順になっている。
これらは、生活から直接発生している水質汚濁負荷の量であるが、家庭で消費される製品、例えば紙や加工食品など様々な製品の製造過程では産業排水として水質への負荷が発生している。これについても、消費生活に伴って誘発されるものと考えることができるが、これを含めると、消費生活に伴う水質への負荷の総量はより大きくなる。