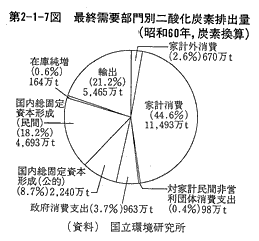
2 大気への負荷
消費生活に伴う大気への負荷について、ここでは国立環境研究所等が行った窒素酸化物(NOx)と二酸化炭素(CO2)に関する推計結果を取り上げる。
まず、これらの環境負荷の排出の原因として、家庭の消費生活がどれだけの比重を占めているのかを考えてみよう。国立環境研究所が環境分析用の産業連関表を作成して行った推計結果によると、昭和60年に我が国の家庭でのエネルギー消費により直接に排出された二酸化炭素の量は、排出量全体のうち約9%であり、一人当たりで見ると0.2t(炭素換算)となっている。しかし、家計で消費される財やサービスは、その生産、流通の過程でも二酸化炭素の排出を伴っており、直接排出される量に加えこうした間接的な排出量を含めた、消費に伴って誘発される排出量の合計(以下、誘発排出量と呼ぶ)を推計すると、二酸化炭素の総排出量の約45%にのぼり、一人当たりで見ると0.95t(炭素換算)とされている。これは、体積で考えれば約2000m
3
であり、25mのプール4杯分程度に相当することになる。なお、排出量の残りの部分は、民間企業による設備投資、政府による各種の事業や活動、輸出などに伴って誘発されている(第2-1-7図)。
次に具体的な消費の項目ごとに、国民一人1年間当たりと家計消費1万円当たりの二酸化炭素と窒素酸化物の誘発排出量を見てみよう(第2-1-8図)。慶應義塾大学産業研究所が(財)日本環境協会と共同で行った産業連関分析を用いた最新の推計結果によると、誘発排出量は項目により大きな差があり、二酸化炭素では、1年間の消費を通じて見れば電力消費とガソリンの消費によるものが格段に大きく、次いで灯油、都市ガス、LPGといった光熱関係の各種の項目が大きくなっている。また、個別の項目としては、医療、衣服、飲食店関係の消費からの誘発排出量も比較的大きくなっている。1万円分の消費当りの誘発排出量は、ガソリンと光熱関係の項目が大きくなっている。一方、窒素酸化物について見ても、ほぼ同様の傾向が見られる。これは、1つの推計例であり、今後更に分析手法の改善の余地があるが、我々が消費活動に伴う大気環境への負荷を減らそうと自ら努力する場合、どのようなものを控えることが効果的かを判断する一つの材料となりうるものであり、今後、こうした研究が、調査分析手法の改善が図られつつ、各方面で一層進められることが望まれる。
このように、我々の日常の消費生活に伴って大気環境への大きな負荷が発生しているが、消費生活のあり方を変える努力により、その負荷を減らすこともできる。国立環境研究所で、一般家庭の日常の対策により二酸化炭素排出量がどれだけ削減できるかを推計した結果が第2-1-9図である。これは、日常採りうる二酸化炭素排出削減行動のうち23種類について削減量を試算し、それぞれの行動の実行可能性を一般家庭に対するアンケートによって調査することにより、家庭での対策によりどれだけの排出削減が可能かを推計しようとしたものである。その結果、それぞれの行動を「取り入れられる」と回答した家庭がすべて実行した場合の全国での排出削減量は、総排出量の約2%に相当する約600万t(炭素換算)であり、「一部取り入れられる」と回答した家庭もすべて実行したと仮定すると、排出削減量は合計で、総排出量の約5%に相当する約1500万t(炭素換算)と椎計され、家庭での行動の変化によって削減できる排出量がかなりの大きさであるとされている。なお、この推計は排出削減量が推計可能であった23の行動についてのみ計算したものであり、その他の行動を加えた排出削除量の推計値はさらに大きいことになる。それぞれの行動項目について見てみると、最も効果の大きいのは「自家用車の燃費、排気量の考慮」、「自家用車の使用抑制」等の自家用車の使用に関する項目であり、他には「断熱に配慮した住宅を建てる」や「太陽熱温水器の使用」が大きくなっている。