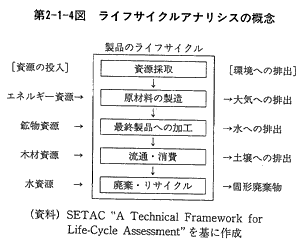
1 消費生活から直接的に生じる負荷と間接的に生じる負荷
我々の消費生活から発生する環境への負荷としては、まず第1に、生活に伴い直接的に発生するものが考えられる。例えば台所からの汚水、家庭で発生するごみ、自家用乗用車の使用による窒素酸化物や二酸化炭素の発生などである。しかし、こうした直接的な負荷にとどまらず、さらに、我々が種々の製品を購入することにより様々な負荷が間接的に誘発されている。すなわち消費者が購入する製品は、その原料を採取し、加工、製造し、さらに流通経路を通じて消費者の手元に届くまでの間に様々な環境負荷を発生させており、これらの負荷は、消費者がその製品を需要することにより誘発されていると考えることができるのである。消費活動に伴う環境への影響を考える際には、こうした間接的な影響についても考慮に入れる必要がある。
こうした視点から、様々な消費活動により誘発される環境負荷を定量的に評価しようとする場合、ライフサイクルアナリシス(商品の環境へのやさしさ度評価)の考え方が役立つ。ライフサイクルアナリシスは、個々の製品に着目し、原料採取から生産、流通、消費、廃棄に至る製品の一生(ライフサイクル)を通じて、製品が環境に及ぼす各種の負荷をできるだけ定量的に分析・評価しようとするものであって、製造事業者による製造プロセスや製品設計の改善、流通業者による商品の品揃えの変更、消費者による賢明な商品選択などを助け、これを通じて全体として環境負荷を低減することを目的としている(第2-1-4図)。
飲料容器を例にとって考えてみると、消費後にごみとして捨てられるという直接的な負荷に加え、間接的な負荷として、例えば、ガラス容器では原料であるけい砂の採掘時にその残渣が廃棄物として発生しており、アルミ缶では精錬時にエネルギーが比較的多量に用いられ大気環境への負荷を生じており、また、紙パックでは製紙時に水質汚濁負荷が発生している。また、リターナブル(繰り返し使用可能)のガラス容器は、ワンウェイ(使い捨て)のものと比べ、運搬距離が長いため大気への負荷がやや多い面もあるが、廃棄物の発生量は大幅に少なくなっている。このように、容器の種類に応じて消費に至る前の各段階でそれぞれ様々な負荷が発生している。ライフサイクルアナリシスを用いることにより、こうした負荷を総合的に評価、比較するための材料を得ることができる(第2-1-5図)。
ライフサイクルアナリシスに関する研究はヨーロッパ諸国や米国で進んでいる。例えば、オランダでは環境省の出資によりライデン大学環境科学センターがライフサイクルアナリシスの手法のマニュアルを作成しており、また、スイスでは、連邦内務省環境局が容器、包装材についてのライフサイクルアナリシスの手法と収集データの公表を行っている。このほか、米国、スウェーデン、デンマークなどで研究が進められている。我が国でも、近年、ライフサイクルアナリシスに関する調査研究が活発化している。例えば、エコマーク制度においては認定の要件に環境負荷の総合的な評価を組み込んで行くための検討が始められており、また、日本生活協同組合連合会においても商品にライフサイクルアナリシスを適用するための調査研究を進めている。
間接的に誘発されるものも含めて環境負荷を評価するには、産業連関表を用いる方法もある。これは、ライフサイクルアナリシスのように個別製品という切り口からではなく、産業部門という切り口から分析するものである。産業連関表は、経済学の基本的な分析の道具であって、様々な産業部門の間の複雑な相互依存関係を分析するために、各産業書部門から産出されたものが別の産業部門で中間財として使用されている様子をマトリックスの形で表したものである(第2-1-6図)。これを用いれば、例えば自動車の需要が増えたときに、それに伴って鉄鋼業や機械工業、ゴム製品工業など、様々な他の産業部門でどれだけ需要が増加するかが分析できる。産業連関表を応用して、産業部門別に環境負荷の発生量に関するデータを付け加えれば、ある産業部門から産出される製品やサービスを消費した場合に、中間投入物の生産段階も含め、直接、間接にどれだけの環境負荷が誘発されるかを分析することができる。
こうした産業連関表を用いた分析については、慶應義塾大学産業研究所において、二酸化炭素、硫黄酸化物、窒素酸化物についての研究が進められている。また、国立環境研究所において、二酸化炭素に加え、水質汚濁物質等についての研究も着手されている。
なお、消費活動からの環境への影響の程度を決める要因としては、負荷の発生量だけではなく、負荷の発生する場所も重要である。例えば、大都市における窒素酸化物等による大気汚染の問題では、大都市集中により自動車交通量が特定の地域で増加していることが大きな要因となっている。また、公共用水域の有機汚濁の問題では、限られた地域への人口の集中により生活排水、工場排水などの流入がその地域の自然の浄化能力を超えてしまっていることが重要な原因となってきた。このように、消費活動と環境との関係を考えるには、環境負荷の排出量だけの分析では不十分であり、その集中度合などの地域的分布も重要であることにも留意する必要がある。
また、消費活動に伴う環境への負荷としては、廃物の排出に伴うものだけでなく、レクリエーション活動など自然資源の利用に伴う自然環境への負荷も重要な問題であることは言うまでもない。
ここでは、我々一人一人の消費活動や生活からどれだけの環境負荷が発生しているかを定量的に考えるために、大気を中心に、水質、廃棄物の各分野について見ていこう。