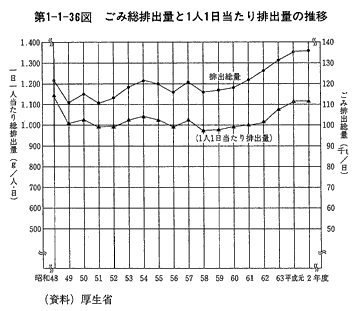
8 廃棄物
廃棄物は、人の活動から生じる固形状又は液状の不要物であって、不適正に処理された場合に汚染を生じさせる。このため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」にのっとって、焼却、脱水などによる中間処理を経て、適切な設備を施した最終処分場に埋め立てるなどによって処分される。
廃棄物には、事業活動に伴い排出される廃酸、廃アルカリ、廃油等や公害防止装置によって煙や汚水から集められたばいじん、汚泥などの産業廃棄物と、それ以外の家庭ごみなどを含む一般廃棄物とがある。廃棄物は適正処理のために施設の整備等多くの努力を要するが、近年、その量が増え、また、最終処分場も、自然環境保全との競合、地元住民の受け入れへの理解不足などのため新規の立地が困難となり、その容量の不足が目立ってきた。また、ヨーロッパなどにおいては環境を汚染する可能性のある有害な廃棄物が途上国に持ち込まれ、不適正に処分された事件があり、地球環境問題として有害廃棄物の越境移動に対する取組が求められている。
(1) 一般廃棄物
一般廃棄物のうち人の日常生活に伴って生じるごみの排出量は、平成2年度で約5,044万トン(元年度は約4,997万トン)であり、同じく一人当たりのごみ排出量は、約408.8kg(元年度は約406.6kg)で、ともに前年より増加している(第1-1-36図)。過去からの推移をみても、ごみの排出量は戦後の国民生活や社会活動の活発化に比例して一貫して増加しており、昭和48年のオイルショックの際に一時減少したが、その後また増加傾向にある。昭和60年度と比べてみても、総排出量は16.1%の増加、一人当たり排出量も13.6%増加している。また、生活の多様化を受けてごみの種類も増加しており、廃大型家庭用品など適正な処理の困難なごみが問題となっている。
廃棄物の処理については、その処理場、特に最終処分場の確保が困難であり、ごみ排出量の増加ともあいまって一般廃棄物最終処分場の残余容量は急速に減少している。特に、首都圏の東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県では、平成2年度のごみ最終処分量は我が国全体の24.5%を占めているが、最終処分場の残余容量は、新たな処分場が確保されないと1年持たないと見積られる(2年度の首都圏のごみ最終処分量412.2万トン、残余容量約387万トン、ごみの比重0.3にて算出)。このように、処分用地の確保が困難になっていく中で、ごみ排出量の削減、ごみの再資源化、再利用が緊急の課題となっている。このため、平成3年、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を改正し、また、「再生資源の利用の促進に関する法律」を制定して、再生資源の利用の促進に努めているところである。その詳細は第4章第1節4に記述したとおりである。
し尿の処分量は長年来着実に減少の傾向にあり、2年度は約3,621万キロリットル(元年度は約3,687万キロリットル)であった。これは、水洗化人口の増加による水洗トイレの普及などによるものである。なお、近年、公共用水域の水質汚濁防止の観点から、し尿処理施設からの排水に関心が高まり、COD、窒素、リンなどの高度な除去技術の開発が進められている。
以上のような収集されるごみ以外にも、環境中に不法に捨てられるごみも多い。全国で広く見られる問題の一つに、空き缶の散乱がある。我が国で平成3年1年間で発生した飲科用缶の空き缶は約309億個と推計され、前年(2年は約290億個)に比べ6.5%増となっている。これらの一部が環境中に散乱し、問題となっている。国や地方公共団体等では、空き缶散乱防止対策として様々な取組を行っているが、根本的解決には至っておらず、一層の取組が必要となっている(第1-1-11表)。
(2) 産業廃棄物
平成2年度における産業廃棄物の排出量は3億9,474万トンで(第1-1-12表)、平成2年度の家庭ごみ排出量の約8倍となっている。産業廃棄物の総排出量の伸びを見ると、昭和60年度比で26.4%増であり、これは同時期のGNPの伸びの26.3%とほぼ同じであり、経済の成長に伴って廃棄物の排出も増加していると言える。総排出量のうち、最終的には、約15,057万トンは再生利用され、最終処分量は約8,973万トンとなっている。排出量の内訳は、汚泥(43%)、家畜糞尿(20%)、建築廃材(14%)などである。産業廃棄物についての厚生省による5年に一度の調査によれば、昭和50年度以降では、汚泥が大きく増加する一方で、廃酸、廃アルカリが減少しており、平成2年度でも同様の傾向を示している。業種別の重量べ一スの排出量では、農業が最も多く、全体の20%を占め、ついで建設業、電気・ガス・熱供給・水道業などの順になっている。
産業廃棄物の処理や処分については廃棄物の処理及び清掃に関する法律によって様々な規制が行われ、その適正な処理、処分が図られている。排出された産業廃棄物のうち、中間処理による減量や再生利用に回るものを除いて、全体の23%、8,973万トンが最終処分されるが、最近では、最終処分場の確保が大きな問題となっている。特に首都圏における産業廃棄物最終処分場の残余容量は、元年度には1,036万m
3
しかなく、他県で処分している産業廃棄物も多い。こうした最終処分場の不足は、産業廃棄物の不法投棄の一因ともなっており、元年度では、建設工事から排出される建設廃材を中心として、不法投棄された産業廃棄物は全国で約87万トンにものぼっている(第1-1-37図)。諸外国の産業廃棄物の排出量については、統一的なデータがなく相互比較は困難だが、例えばOECD諸国全体で1980年代前半が年間約10億トン、中期が13億トン、1990年で15億トンと見積られている。
(3) 有害廃棄物の越境移動
有害廃棄物は、処理の費用の高い国から安い国ヘ、あるいは処理に伴う規制の厳しい国から緩い国へと移動されやすく、そのため、有害廃棄物の受け入れ国で適正な処理がなされない場合には、その国の生活環境や自然生態系に影響を及ぼしたりするおそれもある。
この問題の代表的な例としては、イタリアのセベソの農薬工場の爆発事故(1976年、昭和51年)により生じたダイオキシンに汚染された土壤が1982年(昭和57年)に行方不明となり、翌年フランスの小村で発見されたセベソ汚染土壤搬出事件が有名である。また、米国フィラデルフィアで有害な焼却灰1万4,000トンを積み込んだ船舶が、各国で受け入れを拒否され、2年余りも海上をさまよった上、インド洋で投棄したのではないかとされる事件なども発生している。
有害廃棄物の越境移動は、1980年代前半は例えばヨーロッパ内での移動といった範囲にとどまっていたが、80年代後半(昭和60年頃)になると有害廃棄物の移動範囲がアフリカや南米の国々に急速に広がり始めた。我が国においては、廃棄物中の有用物を回収するなどのため、有害な廃棄物が国際取引されている例がある。こうした地球規模での有害廃棄物の越境移動に対して、国連環境計画(UNEP)を中心に国際的なルール作りが検討され、1989年3月、スイスのバーゼルにおいて、「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」が作成された。
バーゼル条約は、1992年(平成4年)5月5日に発効し、我が国でも、平成4年(1992年)12月10日に「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」が制定され、条約への早期加入と国際的な枠組みの下での対策の実施に向けた努力が続けられている。