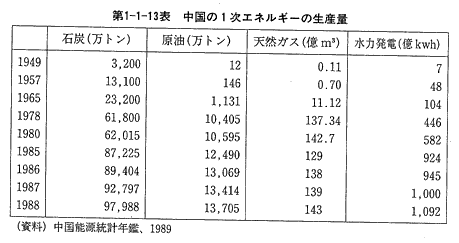
9 開発途上国の公害等
開発途上国・地域では、今日、公害をはじめとする様々な問題が生起しており、この中には、人類全体に影響を及ぼしかねないものも出てきている。他方、こうした問題を改善し、開発途上国が環境上健全な経済発展を遂げていくことは、相互依存を強める世界経済にとっても有益である。
後発開発途上国では、貧困や人口の増加が環境の破壊をもたらし、環境の破壊が貧困を加速させるという悪循環に陥っている。一方、開発途上国のうち、工業化が進み、経済が発展しつつある国々では、経済的発展を急ぐあまり環境保全の優先度が低かったり、環境対策が追いつかない場合が多く、工場等における公害防止対策が不十分なまま工業化が進展したり、社会資本が未整備なまま都市化が進展した結果、環境へ与える負荷が過大になり、大気汚染や水質汚濁など深刻な公害問題を招いている。さらに、東欧諸国や旧ソ連地域では、生産至上で環境保全への配慮を欠いた計画経済のもと、土壤汚染や水質汚濁など深刻な公害問題が生じていたことが明らかになった。こうした公害問題の中には、国境を越えて地球規模の汚染へと直接つながったり、それが各国それぞれで深刻化することにより、結果として国境を越える広域的な汚染に至っているものも出てきている。
我が国に関係の深いアジア諸国では、近年、急速に工業化が進み経済発展を成し遂げつつある国が多く見られるが、こうした国々では、これまで先進国が経験したような産業化に伴う公害問題が深刻化している。工業化の進展に伴い、工場等から排出される排ガスや排水、廃棄物などが増大しているにもかかわらず、環境対策の優先順位の低さや環境への配慮の欠如から、公害防止対策が追いつかず、硫黄酸化物などによる大気汚染や、廃棄物、重金属等の有害物質による水質汚濁や土壤汚染など、公害問題が深刻化している。また、公共交通機関や衛生設備などの社会資本の整備が十分でないまま、農村などからの人口流入などにより都市化が急速に進んでいるため、自動車から排出される汚染物質による大気汚染や、生活雑排水による水質汚濁など都市・生活型の公害も大きな間題となっている。なお、これらの国々では、依然として1次産品の輸出の経済に占める比重も高く、自然資源の保護が経済上も重要であるが、工業化・都市化による公害の深刻化が、こうした自然資源に悪影響を及ぼす事例もある。
ここでは、我が国と経済的にも、環境的にも関係の深い北東アジアを中心に、開発途上国の環境の現状を見てみる。
(1) 中国
中国は、およそ11億209万人の人口を擁し、1980年代後半(昭和60年代)は、平均の実質経済成長率で9%台の経済発展が進み、1980年(昭和55年)に2,678億ドルであったGNPが1989年(平成元年)には3,930億ドルへと約47%増加するなど、近年、大きな経済発展を遂げている。
ア 大気
こうした経済発展に伴いエネルギーの消費も1980年(昭和55年)に石油換算で387百万トンであったのが、1988年(昭和63年)には574百万トンヘと約48%増になるなど大きく増加している。中国ではエネルギー源の多くを国内から豊富に産出する石炭に頼っており(第1-1-13表)、石炭の燃焼に伴う硫黄酸化物やばいじんによる大気汚染が深刻な問題となっている。二酸化硫黄の中国全土の年平均値の推移を見ると、近年増加傾向にあったが、ここ数年は若干の増減はあるもののほぼ横ばいとなっている(第1-1-38図)。1990年(平成2年)の全国の年平均値は0.098?/m3(0.038ppmに相当)で、前年に比べ若干改善しているものの、依然として汚染レベルは高い。
こうした中国で排出される硫黄酸化物が、我が国の酸性雨と関係しているとの考えもあり、現在調査が進められている。
ばいじんについては、一般家庭で暖房用に多くの石炭を使う北部都市の方が汚染が著しく、降下ばいじん量は南部都市のほぼ3倍弱となっている。全国の年平均値の推移を見ると1980年代(昭和50年代後半)はほぼ横ばいであったが、1990年(平成2年)は19トン/km
2
・月と前年(全国平均で22トン/km
2
・月)より約14%改善している。浮遊粒子状物質も、やはり北部都市の方が汚染レベルは高く、年平均値の濃度は南部都市の約2倍となっている。全国の年平均値の推移では、わずかながら改善の傾向がみられる。窒素酸化物については、自動車の普及が進んでいないこともあり、それほど深刻ではないが、全国の年平均値では、ここ数年ほぼ横ばいで推移している。
中国では、環境基準を、一級基準、二級基準、三級基準の3つの地域に分けて設定している。1990年(平成2年)の各物質の全国の年平均値の環境基準との適合状況を見ると、二酸化硫貫、浮遊粒子状物質はいずれも居住地域に適用される二級基準を超えているが、窒素酸化物は二級基準に適合している。
イ 水質
中国の水質汚濁状況を見ると、河川の主な汚染物質は、有機物質及びアンモニア性窒素であり、そのほか、フェノール、シアン等による汚染も進んでいる。これらの物質の排出源は、主に工業排水と生活雑排水であり、工業排水の4割弱と生活雑排水の大半が処理されずに環境に排出されている。一方、鉛については、近年、汚染は減少傾向にある。
中国の6大河川についてみると、長江及びその支流では、水質は比較的良好であるが、近年、悪化の傾向にあり、主な汚染物質はアンモニア性窒素及びCOD、フェノール、カドミウムなどである(第1-1-14表)。6大河川のうち最も汚染が進んでいるのは、大遼河であり、主な汚染物質は、フェノール、アンモニア性窒素、CODなどである。
湖沼の水質汚濁では、特に都市周辺の湖沼の汚濁が目立っている。フェノールやBOD、水銀などによる汚染のほか、窒素や燐による富栄養化が進んでおり、また、工場排水による重金属や化学物質、有機性汚濁物質による汚染も進んでいる。貯水量10億m
3
の大型ダム湖である松花湖では、流域に鉱業、化学の工場が進出した結果、第1-1-15表のとおり、日本の霞が浦、北アメリカの湖沼と比べてみても、湖水の重金属汚染が進んでいる。
ウ 酸性雨
中国では、1983年(昭和58年)から84年(昭和59年)にかけて酸性雨調査(第1次)を実施したが、全国189都市・地区の調査結果では、そのうち45都市で酸性雨が観測された。中国の酸性雨の原因は主として硫黄酸化物によるものと考えられており、1989年(平成元年)の石炭燃料等の燃焼に伴う硫黄酸化物の排出量は1,565万トン/年(日本全国の排出量は約100万トン/年)と推計されている。中国産の石炭のうち、特に西南区の石炭中の硫黄分が高く、平均値は3.2%にも達している。中国の都市における酸性雨の観測結果は第1-1-16表のとおりであるが、降水中のpH値の平均値が4より小さい都市はすべて長江以南であった。
(2) 韓国
韓国は、人口約4,238万人を擁し、1989年(平成元年)のGNPは1,865億ドル、1985年(昭和60年)から1989年(平成元年)の経済成長率は年平均で10.5%であり、全体的に経済成長率の高いアジア諸国の中でも、ひときわ大きな経済成長を遂げつつある。
ア 大気
韓国では、近年の急速な経済発展に伴って、エネルギー消費量は、1980年(昭和55年)に石油換算で36百万トンであったのが、1988年(昭和63年)には約60百万トンになるなど大きく増加している。こうした中、特に大都市において、二酸化硫黄による大気汚染が大きな問題となり、環境省(当時は環境庁)では、1981年(昭和56年)以来、大都市においては低硫黄石油やLPGの使用を促進するなどの対策をとった結果、近年、韓国の大都市における硫黄酸化物による汚染は一部の都市を除き減少の傾向にある。しかし、依然としてWHOのガイドライン(年間平均値で40-60g/m
3
、0.015-0.023ppmに相当)を超えている都市もあり、汚染は深刻である(第1-1-17表)。なお、韓国等で排出される硫黄酸化物については、現在、環日本海における移流状況について調査が進められている。
全浮遊ふんじんによる汚染は、近年の経済の発展につれて増大した自動車交通や工場等からの排出を主因として、多くの大都市で深刻な問題となり、しばしば環境基準である150g/m
3
(年間平均値)を超えていた。これに対して、燃料の転換、固定排出源への規制強化などの対策を進めた結果、ここ数年大きく改善しているが、年間値はWHOのガイドライン(年間平均値で60-90g/m
3
)を超えており、汚染は深刻な状況にある(第1-1-18表)。
その他の大気汚染物質については、自動車などの発生源に対し、燃料の無鉛化、ディーゼルエンジンからの排出抑制対策などを進めた結果、窒素酸化物、オゾン、一酸化炭素などについては軽度な汚染にとどまっている。
イ 水質
韓国では、急速な工業化、都市化の進展により、工場等からの排水が大きく増加し、排水量の増加率は年20%にも上ったと伝えられている。こうした排水に含まれる重金属等や排水よる環境負荷の増大により、重金属汚染等が発生した。また、都市化の進展により、生活雑排水が増大しているが、処理施設の整備の遅れなどにより、排水処理が不十分で、有機物質による水質汚濁を引き起こしている。1989年(平成元年)の調査では、同国の下水量のうち処理されているのは約25%であった。また、同国のかなりの地域で水道水が重金属やその他の汚染物質で汚染されており、飲用に適さないことが分かった。
(3) フィリピン
フィリピンは、日本の南西約3,000kmに位置し、人口約6,010万人を擁し、1989年(平成元年)のGNPは428億ドルである。1985年(昭和60年)から1989年(平成元年)の経済成長率は年平均で5.0%で、現在、工業化を通じた経済発展への努力が続けられている。
ア 大気
フィリピンの中心的都市であるメトロマニラ地区では、大気汚染物質として、全浮遊粉じん、二酸化硫黄、一酸化炭素の測定が6局においてなされているが、1983年(昭和58年)から1986年(昭和61年)にかけて、測定機器の故障等により測定が中止されていた。1983年までの測定結果と測定再開後の測定結果を比べて見ると、全浮遊粉じんについては、1983年まで測定していた4局における測定値は、ほぼ横ばいで推移し、同国の環境基準を達成していた。しかし、測定再開後の測定値では、測定局のうち1983年以前も測定していた測定局2局において、エルミタ局で1982年(昭和57年)に93g/m
3
(年間平均値)であったのが、1988年(昭和63年)には207g/m
3
(年間平均値)となり、パサイ局でも1982年(昭和57年)に64g/m
3
(年間平均値)であったのが、1988年(昭和63年)は154g/m
3
(年間平均値)と、いずれも大帽に増加している(第1-1-19表)。1988年(昭和63年)から測定を開始した測定局のデータでは、翌89年の測定値は、ほとんどの測定局で悪化している。原因としては、特に都市部における自動車交通量の増加が挙げられている。
同様に二酸化硫黄について見てみると、1983年(昭和58年)までの測定結果に比較すると改善の傾向にあり、また、1988年及び89年(昭和63年及び平成元年)の測定でも、悪化の傾向は見られていない(第1-1-20表)。
イ 水質
フィリピンでは、1978年(昭和53年)に水質基準と排水基準を定め、1990年(平成2年)に改訂を行い、水質環境の維持を目指しているが、観測機器の故障などにより、環境監視体制の整備は進んでいない。1990年(平成2年)のメトロマニラ地区の4大河川の調査では、マリキナ川上流部を除く全ての河川において、DO、BODともに水質基準のクラスCを達成しておらず、舟運のみが可能な状態となっている。また、湖沼では、ラグナ湖は、面積900km
2
の東洋でも最大級の湖であるが、1986年(昭和61年)から1987年(昭和62年)にかけての調査によると、リン酸塩の濃度が高くなっており、富栄養化しつつある(第1-1-21表)。マニラ湾は、メトロマニラで発生した汚濁物質を最終的に受け入れており、マニラ湾の水質は、大腸菌群数で見ると、魚類等の水生生物の増殖・生育に適した水質を維持すべきクラスSCの基準値5,000MPN/100mlが達成できず、近年では、さらにメトロマニラ外の南部海岸でも同基準値を超過している。
これらの水質汚濁の原因は、人口の急増に社会資本の整備が追いつかず、生活雑排水等による水質への負荷が増大していること及び工場等からの排水の増大である。メトロマニラ地区の最大の河川であるパシグ川へのBOD負荷量の変遷を見ると、BOD負荷量は、1950年(昭和25年)頃から増加し始め、特に1970年頃(昭和45年)頃からBOD負荷量の増加が加速している。
(4) アジア地域のその他の国々
タイのバンコクでは、近年、特に公共交通機関などの社会資本が未整備のまま急速に都市化が進んだため、主として自動車を排出源とする大気汚染物質による大気汚染が深刻な問題となっている。バンコクでは、1980年(昭和55年)から1990年(平成2年)の約10年間に一酸化炭素の排出量は2倍に、浮遊粒子状物質の排出量は2倍以上に増加している(第1-1-22表)。次に、インドネシア全土における粉じん調査によると、ジャカルタ、バンドン、スラバヤなどの大都市及び産業活動を始めとする人為的活動が盛んな地域において粉じん濃度が高くなっている(第1-1-39図)。また、同国の主要河川では、近年、重金属による汚染が進んでおり、各地の河川で高濃度の重金属が検出されている。1981年(昭和56年)の調査では、特にスンタール川で複数の重金属が高濃度で検出されている。
以上のとおり、開発途上国・地域の中でも特にアジア地域では、工業化・都市化の進展に伴う環境の悪化が顕著であり、深刻な問題となっている。こうした国々に求められているのは、持続可能な開発の実現であり、我が国としてもこの問題の解決を支援するべく、経済発展の中で公害防止を図ってきた経験を生かし、様々な協カを行ってきている。開発途上国・地域での環境問題の解決を阻む要因と克服策等については、さらに第4章の第1節9で詳しく見たい。