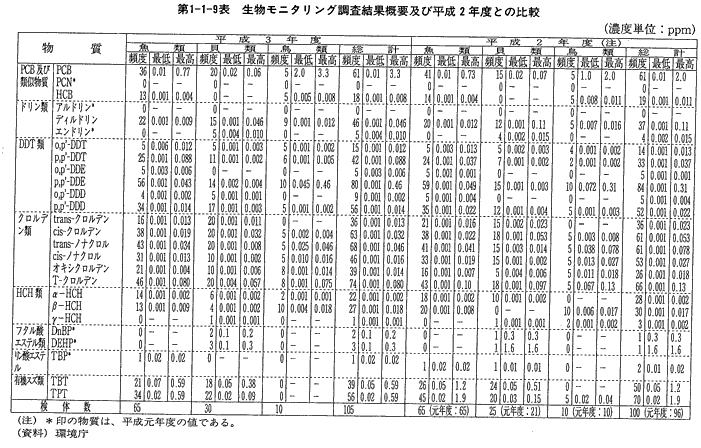
7 生物の汚染
汚染物質の中には、大気、水質、底質、土壌といった様々な環境の自然的構成要素間にまたがってその存在が確認されているものがあり、こうした環境要素に依存して生息している生物も汚染の可能性にさらされている。さらに、生物は、特定の有害重金属や化学物質を濃縮して蓄積し、水質、大気などに比べて、高いレベルの汚染を示すことが知られている。また、生物の測定値は、ある期間の汚染の蓄積状況の指標であって安定していることから、化学物質による生物の汚染レベルを測定すれば、人の健康や生態系に対して問題があると考えられる物質の環境中での挙動や汚染レベルの推移の把握、さらには、各種の公害対策の総合的な効果の把握など、多くの点で有意義なデータが得られる。
年ごとに順次異なる物質について魚類中の化学物質の蓄積状況を把握する化学物質環境安全性総点検調査では、3年度は、環境中に残留していると予想される24物質について調査を行ったが、エトロベンゼン、ピリジン、染科等に使われるo-ニトロアニソール、ナイロンの原料となる-カプロラクタムの4物質が検出された。今回のデータでは、検出頻度及び検出濃度などを勘案した結果、直ちに問題を示唆するものではなかった。
また、過去の化学物質環境安全性総点検調査などにおいて環境中から検出されたことがある化学物質のうち、特にその推移を監視する必要のあるものについては、環境汚染の経年監視を目的に魚類、貝類及び鳥類を指標生物とする生物モニタリングを行っており、3年度の調査によると、PCB、DDT、有機スズ化合物の一種であるトリブチルスズ化合物など24物質が魚介類、鳥類から検出された(第1-1-9表、第1-1-35図)。さらに、ダイオキシン類等の非意図的に生成する有害物質についても生物中の残留状況を調査しており、魚介類から検出されている(第1-1-10表)。これらの物質の汚染状況は、いずれも直ちに人の健康に被害を及ぼすとは考えられないが、今後とも引続きその汚染状況を監視していく必要がある。