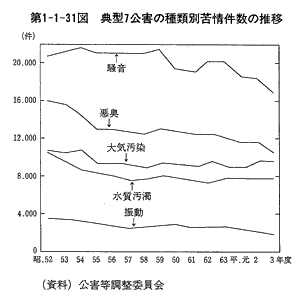
5 騒音、振動
騒音は日常生活に関係の深い問題であり、発生源の種類は、工場、建設作業、深夜営業、家庭生活、交通に伴う騒音など多様である。騒音は、例年、地方公共団体に寄せられる各種公害苦情のうちでも件数が最も多いものである(第1-1-31図)。騒音に係る苦情の件数は平成3年度には16,800件(2年度は19,018件)であり、ピークであった昭和48年度の7割程度まで減少している。これは、原因別苦情件数の約6割を占める工場等及び建設作業による騒音苦情が減少したためである。しかし、一方で家庭生活に伴う騒音苦情は、近年、件数は減少傾向にあるものの騒音苦情件数全体に占める割合は増えている。
騒音については、一般居住環境、自動車交通騒音、航空機騒音、新幹線鉄道騒音についてそれぞれ、地域の土地利用状況や時間帯に応じて類型分けされた環境基準が定められるとともに、工場・事業場騒音、建設作業騒音、自動車騒音(単体)についてそれぞれ規制基準等が定められ、様々な対策が取られている。
自動車交通騒音については、環境基準達成率は長期的には悪化の傾向にあり、平成3年の測定結果をみると全国の4,621地点のうち、朝、昼間、夕及び夜間の4時間帯すべてで環境基準を達成した地点はわずか13.6%(2年は13.3%)に過ぎず、逆に4時間帯すべてで環境基準を超過した地点は54.6%(2年は54.2%)であった。昭和62年から平成3年までの継続測定点1,077地点の測定結果では、3年の環境基準達成率は10.2%(2年は9.0%)と若干改善されたが、依然として低いレベルのまま推移している(第1-1-32図)。また、都道府県知事が都道府県公安委員会に対し、騒音規制法に基づき所要の措置を要請する際の基準である要請限度(環境基準より5-15dB(A)高い)との比較では、4時間帯すべてで要請限度以下であった測定点は全体の68.l%(2年度は69.0%)であった。なお、過去5年間の継続測定点(1,077地点)に限った要請限度との比較の経年変化をみると、4時間帯すべてが要請限度以下であった測定点の割合は、総じて年々減少しているが、3年は65.7%と2年(65.2%)よりわずかに改善している。
また、地域別の環境基準の達成状況は第1-1-33図のとおりであり、大都市域(東京23区及び11大政令市)の騒音環境はその他の地域に比べてかなり悪く、特に大都市域の環境基準達成率は7.3%ときわめて低い水準になっている。東京都での自動車道路沿道における騒音調査では、特に主要幹線道路を中心として、夜間においても、環境基準を達成していない沿道が見られ、また、一部では要請限度を超えている沿道も見られる(第1-1-34図)。
こうした自動車交通騒音に対しては、発生源対策として自動車騒音規制が実施され、順次強化されているが、都市化の進展、経済の拡大やその内容の変化に伴い自動車交通量が増加しており、規制強化の効果を相殺する方向にあり、今後とも総合的な対策が必要となっている。
航空機騒音については、低騒音機材の導入、空港周辺の整備等の対策が行われており、東京、大阪、福岡等の代表的な空港周辺において、環境基準制定当時に比べれば全般的に改善の傾向にあるものの、すべての地点で環境基準を達成している空港は少なく、なお引続き環境基準達成のための努力が必要となっている。
新幹線に起因する騒音については、従来よりの対策によりかなりの改善が認められるものの、環境基準の未達成の地域が依然としてかなり多く残されている。こうした地域のうち、東海道・山陽新幹線沿線は住宅密集地が連続する地域、東北・上越新幹線沿線は住宅が集合する地域において、75ホンを超える地域については、5年度末までに75ホン以下となるよう対策を講じているところである。
新幹線以外の在来鉄道においても、騒音、振動の苦情が寄せられており、特に津軽海峡線や瀬戸大橋線の開通に伴い、鉄道騒音問題が生じたため、各種対策が講じられている。
振動については、苦情件数の推移を見ると、近年、減少の傾向にあり、平成3年度は昭和51年度以降最小の2,207件であった。発生源別では、建設作業に係るものが最も多かった。