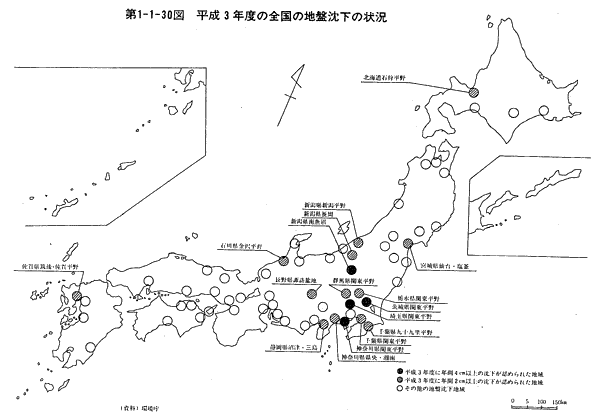
4 地盤沈下
地盤沈下は、主として地下水を過剰に採取することによって生じ、一旦沈下した地盤は元に戻らず建築物への被害などが発生する。古くは戦前から東京都江東区や大阪市西部で沈下がみられ、戦後の一時期の経済の停滞により一旦は鎮静化したものの、昭和40年代には全国的に発生し、年間20cmを超える激しい沈下も見られた。その後、地下水取水制限が行われるようになり、地盤沈下は鎮静化の方向に向かっているものの、一部では依然として著しい地盤沈下が続いている。平成3年度において年間2cm以上沈下した地域は17地域467km
2
(平成2年度は18地域360km
2
)であり、沈下面積は前年度より増加している(第1-1-30図)。一方、年間4cm以上の著しい地盤沈下が生じた地域は4地域6km2(平成2年度は5地域14km2)と減少している。地域別では、関東平野北部、千葉県九十九里平野、新潟県長岡、佐賀倶筑後、佐賀平野などの沈下が大きい。なお、全国の最大沈下地点は新潟県南魚沼地方で、沈下量は5.2cmであった。