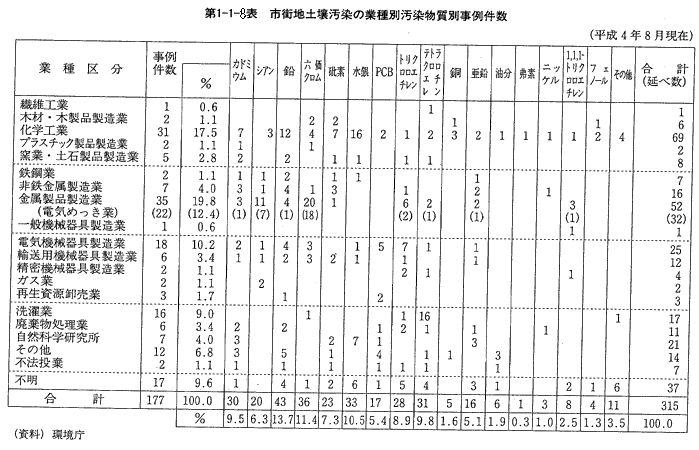
3 土壌
土壌は、生物の活動が深く関与して生成されるもので、環境の重要な構成要素となっており、生態系の維持に重要な機能を担っている。したがって、土壌が劣化し、このような土壤の機能が損なわれると、人をはじめとする生物の生存が脅かされたり、自然生態系の悪化をもたらすおそれもある。
土壌の劣化のうち土壌の汚染は、大気、水等を媒介として、排煙や排水中に含まれる重金属等の有害物質が土壌に蓄積し、長期間にわたり農作物や地下水等に悪影響を与える蓄積性の汚染である。農用地の土壤の汚染により、農作物の生育が悪くなったり、汚染された農作物により人の健康が損なわれたりすることがある。土壌汚染は、公害の中でも最も歴史の長いものの一つであり、明治時代の渡良瀬川流域の農用地汚染や、戦後の神通川流域などのカドミウム等による農用地汚染など、大きな公害問題を引き起こした。これを受けて、「水質汚濁防止法」等により、汚染の発生源での対策が行われていることに加えて、農用地については「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」に基づき、カドミウム、銅、ヒ素について基準値を設け、これを超えて汚染された農用地において客土等の対策事業を行うこととなっている。近年においては、新たに基準値以上の汚染が検出される地域は少なくなっている。客土等の対策事業の4年度末完了予定面積は、これまでの合計で4,600haであり、基準値以上検出面積(7,050ha)に対して進捗率は65.2%(平成3年度は63.5%)である。
農用地以外のいわゆる市街地土壌についても、都市再開発などに際して、工場や研究所の跡地で有害物質による汚染が明らかになる例が頻出している。こうした事態を受け、平成3年8月に農用地、非農用地を通ずる土壌汚染に係る環境基準がカドミウム等10物質について設定された。市街地土壌汚染事例としては、これまで地方公共団体等を通じ環境庁で把握しているもので177件ある(第1-1-8表)。これらの土壌汚染の汚染原因としては、製造施設等の破損に伴う漏出、廃棄物処理法施行前の工場の敷地内での廃棄物の不適正な埋立、汚染原因物の不適正な取扱等によるものが多くなっている。汚染源となった事業種では、化学工業(31件)、電気めっき業(22件)、電気機械器具製造業(18件)などが多いほか、学術研究機関(7件)、クリーニング業(16件)など多岐にわたっている。汚染物質は、六価クロム、水銀、鉛、カドミウムなどが多くなっているほか、トリクロロエチレンやテトラクロロエチレンによる汚染も多くみられる。
なお、諸外国の状況については、米国では、規制が緩かった時代の廃棄物最終処分場跡地の汚染や工場から漏出した有機溶剤等による土壤の汚染が問題となっており、幅広い責任者に対策を行わせ、あるいは、石油や化学品への課税により調達した基金で対策を行うスーパーファンド法などにより浄化を進めている。このほか、ドイツ、オランダ等の欧州諸国においても土壌汚染対策が積極的に進められている。また、東欧においては、ブルガリアで、金属工場に隣接した300km
2
が重金属により汚染されているのが発見されたり、ポーランドでは、オルクシやスラフコフの土壌から鉛とカドミウムが世界最高値で検出されるなど、工業地帯からの廃棄物の不適切な処理による汚染が問題となっている。
また、開発途上国では、過放牧や森林減少、不適正な農業活動により土壌劣化が生じており、大きな問題となっている。このように、世界的に見ると、土壌については、汚染のほかにも、その流亡や塩水遡上による塩性化といった問題が生じており、国際的な協力が求められている。