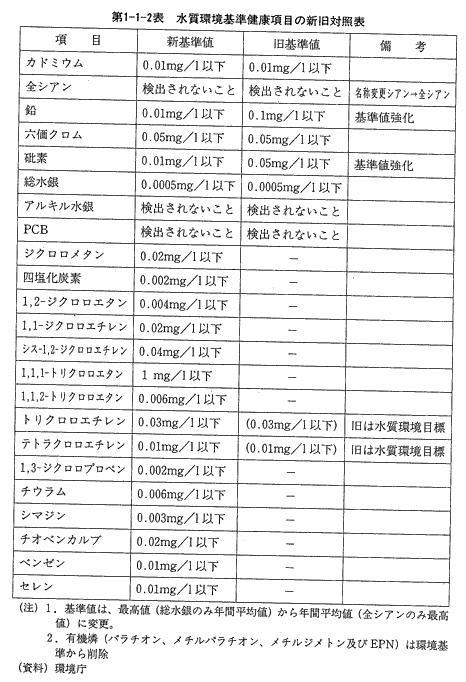
2 水質
水は、環境の重要な構成要素であり、地表から蒸発し、大気の流れによって移動し、雨や雪となって地表に戻るという大きな循環を繰り返している。この水の性状が人為の結果変化すると、人の健康や生活環境、自然生態系に大きな影響を与える場合が生じる。また、水の大循環は先に見た地球温暖化に深く関係している。
(1) 重金属、有害化学物質など
有害物質による海域や河川などの公共用水域等の汚濁を防止し、国民の健康の保護を図るため、我が国では、従来より水質環境基準健康項目(カドミウム、シアン、有機燐、鉛、クロム(六価)、ひ素、総水銀、アルキル水銀、PCBの9項目)について、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準値を設定している。こうした物質を摂取し、一定程度を超えて人体に蓄積した場合などに、様々な健康障害を引き起こすことがある。過去の例では、有機水銀(メチル水銀)による汚染によって水俣病が、カドミウムによる汚染によってイタイイタイ病が生じている。また、有機溶剤として広く使われているトリクロロエチレン、テトラクロロエチレンについては、平成元年4月に同じく健康保護の観点から、水質環境目標を設定した。これら環境基準等を達成、維持し、水質の汚濁やこれによる公害を防ぐため、「水質汚濁防止法」等による規制が行われており、また、水質の状況を監視するため、全国の公共用水域等について水質を継続的に測定している。
本質環境基準健康項目については、水道水質に関する基準の拡充・強化等の動きも踏まえ、5年3月の告示により、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等9項目の有機塩素系化合物、シマジン等4項目の農薬など合計15項目を新たに追加するとともに、有機燐を環境基準から削除して合計23項目とし(第1-1-2表)、5年度より公共用水域及び地下水の水質の監視や必要な施策を進める計画である。さらに、水質汚濁の未然防止の観点から、クロロホルム、トルエンなど25項目を要監視項目に指定し、継続的に水質測定を行って、その推移を把握するなど、将来の汚染に機動的に対処していくこととしている(第1-1-3表)。
3年度の公共用水域水質測定結果によると、健康項目全体の環境基準不適合率(調査総検体数に占める環境基準を超える検体数の割合をいう)は、0.02%(平成2年度は0.01%)と、近年ほぼ横ばいで推移している。環境基準不適合率は昭和46年度においては0.63%,47年度は0.28%であったが(第1-1-19図)、排水規制の強化・徹底や鉱害防止事業の実施などにより、現在では大幅に改善されている。また、トリクロロエチレン等従来の本質環境目標値を超える割合も、平成3年度は0.03%(2年度は0.04%)とほぼ横ばいで推移している。
水質汚濁防止法による規制が行われていない各種の化学物質についても環境汚染の未然防止の観点から、毎年異なる物質について水質中の残留状況について測定が行われている。3年度の調査(化学物質環境安全性総点検調査)では、土壤改良剤等に用いられるアクリルアミド、染料の生産等に使われるニトロベンゼンなど調査対象の24物質のうち、前記の2物質のほか、有機合成に使われるP-ニトロトルエン、有機合成用溶媒等に使われるN,N-ジメチルホルムアミド、薬品等に使われるピリジン、同じく薬品等に使われるトリエチルアミンの6物質が水質から検出されたが、検出頻度、検出濃度からみて直ちに問題となるものではないと考えられる。また、環境汚染の経年監視が必要と考えられる物質について継続的な調査(水質モニタリング)を行っているが、防虫剤等に用いられるジクロロベンゼン類等が前年度に引き続き検出されており、直ちに問題となる汚染レベルではないものの、今後ともモニタリングを継続することとしている。
昭和48年に制定された「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」による指定化学物質等についての本質中の残留状況の調査では、調査対象の合成原料として広く使われている1,2-ジクロロエタンなど5物質中、5物質すべてが検出されており、今後も引き続き調査して行くことが必要とされている。なお、船底塗料等に使われる有機スズ化合物等による汚染の状況は、使用抑制に関する指導の結果を受けて、横ばいまたはやや減少の傾向にある。
諸外国の主要河川の鉛及びカドミウムによる汚染状況の推移は第1-1-20図のとおりであり、多くの先進国で改善の傾向にある。しかし、一部の開発途上国では有害重金属により深刻な汚濁が指摘されている。
(2) 有機汚濁等
我が国では、生活環境に係わる水質については、河川において生物化学的酸素要求量(BOD)、水素イオン濃度(pH)、浮遊物質量(SS)、溶存酸素量(DO)、大腸菌群数の5項日、湖沼において化学的酸素要求量(COD)と河川と同じ4項目及び全窒素、全りんの計7項目、海域においてCOD、pH、DO、大腸菌群数、n-ヘキサン抽出物質(油分等)の計5項目の濃度等について、生活環境を保全する上で維持することが望ましい環境上の条件として環境基準が定められている。これらの生活環境項目については、水域の水道取水等の利水状況などを踏まえた類型が設けられており、水域の範囲ごとにそれぞれ該当する類型を指定することによって、各水域の特性を考慮した環境基準を設定する仕組みとなっている。
生活環境の保全に関する環境基準の達成状況については、水域の生活環境が有機物による汚濁により最も影響を受けることから、有機物による汚濁と関連の深い指標であるBOD(河川)又はCOD(湖沼、海域)を代表項目として、年間を通した評価を行うと次のとおりである。平成3年度の公共用水域水質測定によると、環境基準の達成状況(総調査水域数に占める環境基準を達成している水域の割合)は、河川で75.4%(2年度は73.l%)、湖沼で42.3%(同44.2%)、海域で80.2%(同77.6%)、全体で75.0%(同73.1%)であった(第1-1-21図)。また、湖沼における全窒素又は全りんの環境基準の達成率は31.3%(2年度は42.6%)であった。長期的な傾向を見ると、水質汚濁防止法による規制や同法に基づく都道府県の上乗せ規制により、河川では、昭和50年頃に50%前後であった達成率が徐々に改善してきている。また、海域の達成率は昭和58年度及び平成2年度を除けば、ほぼ80%程度で推移しているが、湖沼では依然として低い達成率で推移している。
湖沼、内海、内湾等の閉鎖性水域では、外部との水の交換が悪く汚濁物質が蓄積しやすいため、水質の改善や維持が難しい。また、湖沼においては、富栄養化の進行により、水道水の異臭味、漁業への影響、透明度の低下といった問題も生じており、水質改善対策が急務となっている。現在、「湖沼水質保全特別措置法」に基づき湖沼水質保全計画の策定されている琵琶湖、諏訪湖、霞ヶ浦など9湖沼について、同計画に基づき水質汚濁防止法による規制に加えた特別の対策が講じられているが、環境基準の達成には至っていない。
また、閉鎖性海域については、「水質汚濁防止法」、「瀬戸内海環境保全特別措置法」に基づき、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海について、CODに係る水質総量規制が実施されている。この3海域の環境基準(COD)の達成率を見ると、東京湾については、海域全体に比べ低水準で横ばいで推移しており、伊勢湾も若干改善の傾向はあるものの依然として低水準である(第1-1-22図)。瀬戸内海では全体としてはほぼ海域全体と同水準の達成状況であるが、大阪湾などは低水準で横ばいの状況にある。また、このような閉鎖性水域では、後背地である大都市から生活排水・産業排水などによって窒素、燐などの栄養塩類が流入し、富栄養化が進行している。このため、赤潮や青潮が発生し、漁業被害や悪臭、海水浴場の利用障害、海浜の汚染といった問題も生じている。なお、湖沼、内湾等の閉鎖性水域での対策の動向については、さらに第4章第1節3で詳しく見ている。
一部では汚濁の著しい都市内河川の状況は、近年、依然として改善が進んでいない(第1-1-23図)。これは、都市域の拡大等によりこれら河川への負荷が大きくなっているためであり、下水道整備のほか、地域の実情に応じ、合併処理浄化槽等の生活排水処理施設の一層の整備など生活排水対策が続けられている。
なお、3年度の調査では、我が国のBOD高濃度水域上位河川は第1-1-4表のとおりであり、主な汚濁原因は、第1位の揖保川は産業排水、第2位の不老川は生活排水、第3位の汐川は畜産排水となっている。
また、良質の飲料水を求める国民的二ーズが高まる一方で、水源地である湖沼の汚染の影響により、都市における水道水が悪臭を発する、いわゆるくさい水問題や、水道水中に含まれる有機物が殺菌に用いられる塩素と反応してトリハロメタンが生じる問題などが指摘されており、一層の対応が求められている。
先進諸国における主要河川、主要湖沼の過去20年間における水質の状況は、第1-1-24図のとおりであり、総体的には改善傾向にあるが、一部横ばいまたは悪化している河川・湖沼もある。
(3) 海洋
海洋は、陸上の汚染が水の働きにより移されて蓄積されるなど、汚染物質が最終的に行きつく場所となることが多い。広大な海洋ではあるが、その汚染が心配されるに至っている。
我が国の周辺海域で確認された海洋汚染の件数は平成4年度は846件であり、3年度の893件に比べ47件減少し、昭和46年に統計をとり始めて以来最も低い記録となった(第1-1-25図)。これは、総件数の約6割を占める油による汚染が527件から473件に低下したことによるが、一方で、廃棄物による汚染は、3年度の267件から4年度は287件と増加している。
「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」に基づき、廃棄物の海洋投棄は原則的に禁止され、特定の廃棄物に限りその性状に応じて定められた海域(例えば房総沖、四国沖、三陸沖、日本海)において、排出方法に関する基準に従った排出が認められている。海上保安庁が3年度に実施した排出海域周辺の汚染状況の調査によれば、油については従来とほぼ同様のレベルであり、PCB、重金属については減少の傾向にある。
また、3年度の浮遊性廃棄物調査では、浮遊廃棄物は日本近海、日本海南西部に比較的多く見られ、内容は発泡スチロール、その他の石油製品が多く、大きさ50cm未満のものがほとんどであった。海面に浮遊する廃棄物に関しては、海鳥や海獣などの海洋生物が、レジンペレット(プラスチックの原料になる細粒)やその他のプラスチック類を餌と間違えて摂食し障害を起こしたり、放棄された廃漁網、ロープ類に絡まって死亡したりするなどの影響が懸念されている。さらに、水産庁では、北太平洋において海洋廃棄物の分布状況を目視で調査する流失網分布実態調査を実施しているが、3年度の調査では、プラスチック類については、特に北緯30度から40度の間に東西に長く分布していた(第1-1-26図)。
海上保安庁が実施した調査によれば、廃油ボールの状況は、昭和50年代半ばから急激に減少しているが、漂流廃油ボールは南西諸島、本州南岸など主要なタンカー航路近辺で多く、漂着廃油ボールは、南西諸島、本州南岸、九州西岸で多く見られる。
海洋の油による汚染原因には、船舶からの故意及び取扱不注意により生じたものが大半を占め、ほかに海難事故によるものがあるが、海難事故による汚染は大規模な被害に結びつくことがある。平成4年12月に、ギリシャ船籍のタンカー「イージアンシー号」かスペイン沖で、5年1月には、リベリア船籍のタンカー「ブレア号」がイギリスで、また、同月にシンガポール船籍のタンカー「マースク・ナビケーター号」がインドネシア・スマトラ島沖で相次いで事故を起こし、多量の積載原油が流出した(第1-1-5表)。こうした流出原油は、自然環境中で分解されるまでに長い年月がかかり、海洋動植物など自然生態系に大きな影響を与える可能性が高い。幸い今回の一連の事故では、自然生態系への大きな被害は報告されていないが、1989年(平成元年)3月のアラスカ沖でのエクソン・バルディーズ号の座礁で約4万キロリットルの原油が流失した事故では、約3万羽の海鳥が死に、ニシン漁ができなくなるなど大きな被害が出た。このバルディーズ号事件を契機に、国際海事機関(IMO)でタンカー船体の二重化が合意され、1993年(5年)7月に発効する予定であるなど、船舶に対する汚染防止対策を中心に油汚染防止に向けた国際的取組が進展している。
(4) 底質
河川、湖沼、海域の底質には、様々な経路からもたらされた多くの種類の汚染物質が蓄積していることが考えられる。我が国ではかつての著しい産業公害の過程で、水銀を含むヘドロの汚染などが明らかになり、全国で合計約2,813万m
3
に及ぷ底質のしゅんせつが行われている。
化学物質環境安全性総点検調査では、底質中における化学物質の残留状況を把握することを目的に、毎年異なる化学物質について調査を実施している。平成3年度は、調査対象24物質のうち土壌改良剤等に使われるアクリルアミドなど7物質が検出された。しかし、検出濃度等を勘案すれば、特に問題を示唆するものではなかった。また、過去の化学物質環境安全性総点検調査などにおいて環境中にから検出されたことがある化学物質のうち、特にその推移を監祝する必要のあるものについては、環境汚染の経年監視を目的とする底質モニタリング調査を実施している。隅田川河口、大阪湾など18地区で20物質を対象に行った3年度のモ二タリングでは、ジクロロベンゼン類など20物質すべてが検出された。調査対象物質ごとの最高値が検出された地区をみると、洞海湾で7物質、大和川河口で6物質、隅田川河口で5物質、仙台湾及び信濃川河口で各1物質が最高値を示しており、閉鎖性の内湾部の汚染レベルが高いことが示唆される。
このほか、ダイオキシン類など、化学物質の合成過程、燃焼過程等で意図せずに生成される化学物質(非意図的生成化学物質)の環境残留性を把握するために、有害化学物質汚染実態追跡調査も実施されている。3年度の調査の結果、ダイオキシン類による一般環境の汚染状況は、現時点では、人の健康に被害を及ぼすとは考えられないが、低濃度とはいえ検出されており、今後とも引き続き監視することが必要な状況にある(第1-1-6表)。
(5) 地下水
地下水は良質・恒温な水資源として従来より高く評価され、現在でも都市用水の約3割は地下水に依存している。昭和50年代後半より、トリクロロエチレン等による地下水汚染が顕在化し、地下水汚染実態調査等により広範な汚染が判明した。このため、平成元年6月に「水質汚濁防止法」が改正され、有害物質を含む水の地下浸透を規制するとともに、国と地方自治体は地下水の常時監視を実施することになった。
3年度の概況調査(地域の全体的な地下水質の状況を把握するための地下水の水質調査)では、評価基準等を超過している井戸の割合は、六価クロムが0.03%、砒素0.1%、総水銀0.1%、トリクロロエチレン0.4%、テトラクロロエチレン0.7%であり、これ以外のシアン化合物やPCBなどについては基準を超過した井戸はみられなかった。このほか、汚染範囲を確認するための調査である汚染井戸周辺地区調査や、過去の汚染の継続的な監視等を行う定期モニタリング調査では、さらに高い汚染が見られている。評価基準等を超過した井戸には飲料用の井戸も含まれており、汚染対策が行われている。しかし、地下水は一度汚染が発生すると回復が困難である。例えば、昭和58年12月に、兵庫県太子町の一部の水源地でトリクロロエチレンが発見され、追跡調査したところ、同町内の地下水や一般家庭用井戸なども汚染されていることがわかった。汚染源は、同町内のIC製造エ場であったため、溶剤の切り替え、汚染土壌の客土などの対策をとったところ、水源地のトリクロロエチレン濃度は急激に下がり、その後も濃度は時間とともに低下していった。しかし、トリクロロエチレンの濃度が数百g/lまで下がると低下は止まり、2年後でもほぼ横ばいのままであった。また、汚染源の敷地内の井戸では、トリクロロエチレン濃度は5年後の63年でも約5,000g/lであり、汚染が発見された当時と変わっていない(第1-1-27図)。このように、地下水汚染については、新たな汚染を発生させないよう未然防止対策を徹底させる必要がある。
(6) 酸性雨
酸性雨は、工場や自動車などから排出された硫黄酸化物や窒素酸化物が大気中で複雑な化学反応により硫酸イオンや硝酸イオンに変化したものが溶け込んだpH5.6以下の雨のことで、強い酸性を示す場合もある。酸性雨の影響としては、酸性の雨や霧に直接さらされることによる樹木の衰退、土壌の酸性化による生態系や森林への影響、酸性雨の流入による湖や沼、河川の酸性化、これらの湖沼等の水生生物などの生態系への影響などのほか、特に大理石や金属でできている都市の建造物、文化財などへの影響もある。このように、酸性雨は、環境を構成する様々な要素に係わる複雑な問題となっている。
我が国では、酸性雨の現状と影響を調査するため、昭和58年から62年まで第1次酸性雨対策調査を実施した。その結果、年平均値でpH4.4〜5.5と欧米並の酸性雨が観測されたが、湖沼の水質では、ほとんどがpH7の中性付近に分布しており、土壌についても酸性化の傾向は見られなかった。しかし、酸性雨による生態系への影響などについては不明の点も多く、被害の未然防止を目的に昭和63年から平成4年までの計画で第2次酸性雨対策調査を実施した。4年3月に取りまとめられた中間報告によると、降雨の酸性度は欧米とほぼ同程度のレベルで推移しており、第1次調査から特に大きな変化はなかった(第1-1-28図)。また、酸性雨の植生への影響については、いくつかの調査地域で樹木の衰退が見られたが、酸性雨が原因であるかどうかはなお不明であった。現在のところ、我が国では、酸性雨による生態系への影響については顕在化していないと言えるが、酸性雨の陸水、土壌、植生などへの影響については明らかではなく、引続き調査・研究や環境の監視を実施し、必要に応じ対策が講じられるよう備えていく必要がある。
諸外国では、特にヨーロッパ、北米、中国大陸で酸性雨による深刻な被害が発生している。スウェーデンでは、約85,000ある湖沼のうち約15,000の湖沼は既に酸性化し、そのうち約4,500の湖沼では魚が死滅しており、カナダでも約4,000湖沼が生物の住めない湖と化している。さらに、硫黄酸化物や窒素酸化物、オゾンなど大気汚染物質が複合的に作用した結果と言われているが、ドイツのシュバルツバルト(黒い森)やカナダのオンタリオ州の楓など、それぞれの国を代表する森林で被害が深刻化しており、また、中国でも、四川省の我眉山の冷杉が衰退し、87%が被害を受けていると伝えられるなど、影響が顕在化している(第1-1-7表)。このほか、自然生態系以外でも、アテネのパルテノン神殿やローマの遺跡など貴重な文化財に酸性雨によると言われる影響が出ている。
酸性雨は、原因物質が大気に広く拡散する窒素酸化物や硫黄酸化物であることから、局地的な問題にとどまらず、国境を越えた国際的な問題となっている。酸性雨に対する国際的な取り組みは、被害の深刻な欧米で進んでおり、欧州では1985年(昭和60年)のヘルシンキ議定書により、また、北米では1991年(平成3年)に米国が大気浄化法(CleanAir Act)を改正し、抜本的な酸性雨対策として硫黄酸化物排出量の削減を開始するなど、関係各国は対策強化を進めている。一方、我が国の酸性雨にも、中国や北東アジア諸国の排出する硫黄酸化物や窒素酸化物が関係していることが考えられる。この点も踏まえ、これら原因物質の環日本海規模での移流の状況等について引き続き調査を行っていくとともに、これらの諸国が燃料の改善、燃焼効率の改善等を通じてその国に適した公害防止を実施できるよう協力し、酸性雨被害の発生の防止のために地域的な協力も行っていくほか、東アジアを中心とする地域におけるモニタリングネットワークの策定等国際協力を推進していく必要がある(第1-1-29図)。