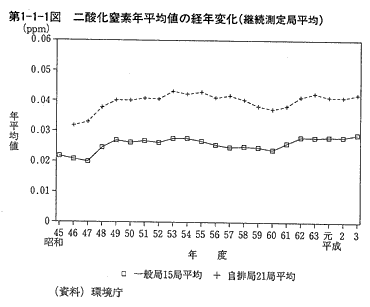
1 大気
人の活動の結果、大気中に様々な物質が排出され、大気の汚染が生じる場合がある。汚染された大気を人が呼吸すると様々な健康被害が生じるほか、大気中で物質が互いに反応して別の問題を生じたり、あるいは大気中の汚染物質が直接に、もしくは雨などを経由して地表の自然生態系に影響を与えたりするなど、大気の性状の変化は複雑な環境問題の原因となる場合がある。以下では、平成3年度の我が国内外の大気の状況を見る。
(1) 窒素酸化物
一酸化窒素(NO)、二酸化窒素(NO2)などの窒素酸化物(NOx)は主として化石燃料の燃焼によって生じ、その発生源としては工場のボイラーなどの固定発生源と自動車等の移動発生源がある。二酸化窒素は高濃度で呼吸器に好ましくない影響を及ぼすほか、酸性雨及び光化学大気汚染の原因物質となる。我が国では、対策の目標となる環境中の汚染物質濃度を示す環境基準を、窒素酸化物のうち二酸化窒素について、「1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内またはそれ以下であること」と昭和53年に定め(ppmは体積百万分率)、工場や個々の自動車などの発生源に対する各種の規制、汚染の著しい地域に限った工場、事業場の総排出量の規制、排出量の削減に資する各種の事業などの、諸外国に先駆けた強力な対策を行っている。
3年度における二酸化窒素の濃度は、一般的な大気汚染状況を把握するために設けられた一般環境大気測定局のうち昭和45年以来継続して測定を行っている15局の年平均値の平均で0.029ppm、道路周辺における大気汚染の状況を把握するために沿道に設置されている自動車排出ガス測定局のうち昭和46年度より継続して測定している21局では同じく0.042ppmであった(第1-1-1図)。これらはともに、2年度よりも悪化しており、特に一般環境大気測定局の年平均値では過去最悪となっている。昭和53年に基準値が改定された二酸化窒素の環境基準の達成期限は、原則として60年であるが、平成3年度においても、大都市を中心に環境基準は達成されていない。過去の傾向を見ると、一般環境大気測定局年平均値の平均で昭和53年度、54年度に0.028ppmを記録して以降、60年度までわずかながらも改善傾向にあったが、60年度の0.024ppmを底に悪化している。また、自動車排出ガス測定局の年平均値では、55年度に0.043ppmを記録して以降改善傾向にあったが、やはり60年度を底に悪化し、近年は、ほぼ横ばいとなっている。
環境庁では、全国8地域において、大気汚染の推移と学童のぜん息等呼吸器症状・疾患との関連性を調査したが、二酸化窒素の低汚染地域と比較し、高汚染地域ではぜん息様症状の新規発症率が高くなる傾向が見られ、環境基準を超える汚染については早急な改善が必要である。
全国における環境基準との対応状況をみると、全国の有効測定局(年間6,000時間以上測定を行った測定局)のうち環境基準の上限値0.06ppmを超える局は、一般環境大気測定局では、3年度は81局(2年度は87局)であり、全有効測定局に占める割合は6.4%(2年度は5.9%)であった。また、自動車排出ガス測定局では3年度は121局(2年度は112局)であり、全有効測定局に占める割合は37.2%(2年度は35.7%)であった(第1-1-2図)。工場等の固定発生源について総量規制制度が導入されている3地域(東京都特別区等地域、横浜市等地域、大阪市等地域)について環境基準の達成状況を見ると、一般環境大気測定局では未達成の局が測定局112局のうち59局(2年度は109局中59局)であり、自動車排出ガス測定局では72局中67局(2年度は72局中64局)であった。
窒素酸化物対策の課題や対策の方向は第4章第1節2に見るとおりであるが、環境基準を達成する上で削減が強く望まれていた自動車から排出される窒素酸化物については、4年6月に「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」(自動車NOx法)が制定され、これに基づき一層強力な対策が行われることとなった。自動車NOx法では、自動車の交通が集中し、これまでの措置では環境基準の達成が困難な地域を特定地域に指定し、特定地域においては、国が総量削減施策の基本方針を策定し、それに基づき都道府県が総量削減計画を策定、これに沿って様々な施策を行い、環境基準の達成を目指すものである。特に、排出量削減施策として使用車種規制を行い、窒素酸化物の排出の一層少ない車種への代替を提進する。この法律により、東京周辺地域など大都市における窒素酸化物汚染が着実に改善されていくことが期待されている。
諸外国についてみると、国連環境計画(UNEP)、世界保健機構(WHO)が日本の東京、アメリカのニュ-ヨークをはじめ世界の大都市20都市についてまとめた調査によれば、窒素酸化物による大気汚染は、これら20都市のうち、ロサンゼルス、メキシコ・シティ、モスクワ、サン・パウロの4都市で中程度の汚染であり、これらの都市ではWHO/EURO(欧州地域事務局)による大気質ガイドライン(1時間値で400g/m
3
、0.21ppmに相当)を超えていると報告されている(第1-1-3図)。欧米では、我が国よりも窒素酸化物対策が遅れたため、現在、その抜本的な強化に努めている。
(2) 二酸化硫黄
二酸化硫黄(SO2)は、硫黄分を含む石油、石炭等が燃焼することにより生じるが、呼吸器に悪影響を及ぼし、四日市ぜんそくなどのいわゆる公害病の原因物質であるほか、森林や湖沼などに影響を与える酸性雨の原因物質ともなる。
かつて我が国では、工業地帯を中心に、公害対策が不十分なまま化石燃料が多量に使われ、二酸化硫黄による著しい大気汚染が生じ、四日市ぜんそくなどの健康被害が発生した。その対策として、環境基準(1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること)を定めた昭和44年以来、順次強化されたばい煙発生施設ごとの排出量規制(K値規制)や、46年から規制が実施され、順次強化された燃料中の硫黄分の規制、49年から導入された地域を限っての工場ごとの排出総量の規制など、環境基準の達成に向けた様々な対策を実施した。世界に先駆けて実施されたこのような強力な硫黄酸化物低減対策とこれに対応した企業等の排煙脱硫装置の導入などの努力により、大気中の二酸化硫黄濃度は、昭和40年度から継続して測定している15局の一般環境大気測定局年平均値の平均で42年度にピークの0.059ppmであったのが61年度には0.010ppmと、著しく改善された。平成3年度は、一般環境大気測定局15局平均で0.011ppm、昭和48年度から継続して測定している自動車排出ガス測定局16局平均でも0.011ppmと良好な状態のまま推移している(第1-1-4図)。また、環境基準の達成率は、一般環境大気測定局で99.7%、自動車排出ガス測定局で98.6%となっている。
諸外国についてみると、OECD諸国では大幅に改善されているが、途上国や東欧諸国などで、特に工業化の著しい国々や硫黄分の多い化石燃料を使用している諸国では、特に大都市において二酸化硫黄濃度の状況は深刻なレベルにある。前述のUNEP、WHOの調査によれば、北京やメキシコ・シティ、ソウルで深刻な状況にあるほか、リオ・デ・ジャネイロ、上海で中程度の汚染であり、WHO欧州地域事務局のガイドライン(1時間値で350g/m
3
、0.12ppmに相当)を超えている(第1-1-5図)。
(3) 光化学オキシダント及び非メタン炭化水素
ア. 光化学オキシダント
光化学オキシダントは、窒素酸化物(NOx)と炭化水素類(HCS)とが太陽光の作用により反応(光化学反応)して二次的に生成されるオゾンなどの強い酸化力を持った物質である。光化学オキシダントは、いわゆる光化学スモッグの原因となり、粘膜への刺激、呼吸器への影響など人間の健康に悪影響を及ぼすほか、農作物など植物への影響も観察されている。また、オゾンは二酸化炭素よりもはるかに強力な温室効果を持っていると考えられている。炭化水素類で光化学オキシダントの原因となるのは光化学反応性に乏しいメタンを除いた各種の非メタン炭化水素であり、これらは二酸化窒素と同様自動車から排出されるほか、塗装工場、印刷工場等炭化水素類を成分とする溶剤を使用する工場、事業所からも排出される。これらの物質については、国、地方公共団体により排出抑制に向けた指導等が行われてきている。
光化学オキシダントについては、環境基準(1時間値が0.06ppm以下であること)が設定されているほか、「1時間値が0.12ppm以上で、気象条件からその状態が継続すると認められた場合」に光化学オキシダント注意報を発令し、屋外での運動を避けるなど健康披害を防ぐための各種措置を講じることとなっている。平成3年度において注意報以上の濃度が出現した1局当たりの平均日数は、昭和62年度からの継続測定局でみた場合、一般環境大気測定局で1.5日、自動車排出ガス測定局で0.2日と、平成2年度に比べていずれも減少した(第1-1-6図)。
諸外国についてみると、ヨーロッパでは、地上才ゾンの量は1世紀の間に2倍になったというデータもあるなど、窒素酸化物等の濃度の上昇に伴いオゾンレベルも高まっている。
イ. 非メタン炭化水素
非メタン炭化水素については、環境基準は設けられておらず、光化学スモッグの発生を防止するための濃度の指針(午前6時〜9時の3時間平均値が0.20ppmC〜0.31ppmC、ppmCとは各種の炭化水素に含まれる炭素量で換算した濃度)を定め、指針を確保するよう各種の対策を実施している。
一般環境大気測定局で昭和53年度から継続して測定している測定局(6局)の午前6時〜9時の平均値の年平均値の平均は、近年はわずかながら減少の傾向にあり、平成3年度は0.53ppmCで、前年度とほぼ同じであった。また、自動車排出ガス測定局では、昭和52年度から継続して測定している測定局(9局)の午前6時〜9時の平均値の年平均値の平均も、近年若干の減少傾向にあって、平成3年度も0.51ppmCと前年度に比べわずかながら減少している。
(4) 一酸化炭素
大気中の一酸化炭素(CO)は燃料の不完全燃焼により生じるもので、主として自動車がその発生源と考えられる。一酸化炭素は血液中のヘモグロビンと結合して、酸素を運搬する機能を阻害するなど人の健康に影響を与えるほか、温室効果ガスである大気中のメタンの寿命を長くすることが知られている。我が国では、昭和48年に環境基準(1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること)を設定するとともに、自動車の排出ガスの規制を行っている。
平成3年度における一酸化炭素濃度は、昭和46年度以来継続して測定を行っている一般環境大気測定局5局における年平均値の平均で0.7ppm、自動車排出ガス測定局のうち46年度以釆継続して測定を行っている測定局14局の年平均値の平均は、2.2ppmであった。過去からの推移を見ると、継続測定局の年平均値の平均が、一般環境大気測定局5局でおよそ2.1ppm、自動車排出ガス測定局でおよそ5.4ppmであった昭和40年代後半に比べ大きく改善し、環境基準も58年度に全国的に達成して以降、一貫して全ての測定局で達成している。
また、諸外国についてみると、前述のUNEP、WHOの調査によると、メキシコ・シティで深刻な状況にあるほか、カイロやジャカルタなど7都市で中程度の汚染であり、WHO欧州地域事務局のガイドライン(1時間値で30?/m
3
、26ppmに相当)を超えている。
(5) 浮遊粒子状物質等
浮遊粒子状物質(SPM)は、大気中に漂う粒子状の物質(大気エアロゾル)のうち粒径が10ミクロン以下の微小なものをいう。浮遊粒子状物質は、徴小なため大気中に長時間滞留し、肺や気管などに沈着して呼吸器に影響がある。浮遊粒子状物質の発生源は、工場、事業場のばい煙中のばいじん、ディーゼル自動車排出ガス中の黒煙等や、窒素酸化物や硫黄酸化物などのガス状物質が大気中で粒子状物質に変化したものなどのほかに、土壤の巻き上げなど自然界に起因するものがあるなど、その発生源は多種多様であるが、環境庁等の調査によれば、特にディーゼル車からの黒煙によるものが各地を通じて2〜4割を占めている。我が国では、昭和47年に環境基準(1時間値の1日平均値が0.10?/m
3
以下であり、かつ、1時間値が0.20?/m
3
以下であること)を設定するとともに、その達成に向け、工場、事業場や自動車の排出規制が行われている。
平成3年度における浮遊粒子状物質の濃度は、一般環境大気測定局のうち昭和49年度からの継続測定局40局の年平均値の平均で0.040?/m
3
であり、平成2年度(同0.041?/m
3
)に比べほぼ横ばい、自動車排出ガス測定局のうち昭和50年度からの継続測定局6局の年平均値の平均で0.054?/m
3
であり、平成2年度(同0.048?/m
3
)より悪化している(第1-1-7図)。環境基準の達成率では、一般環境大気測定局において2年度は43.1%(1,282局のうち552局)であったが、3年度は49.7%(1,348局のうち670局)であり、自動車排出ガス測定局では2年度は21.2%(156局のうち33局)であったが、3年度は30.l%(166局のうち50局)であり、依然低い水準で推移している。都道府県別では、特に東京を中心として首都圏での達成率が低い。
大気中の粒子状物質のうち、地表に降下してくるものを降下ばいじんと呼んでいる。3年度における状況は、長期間継続して測定を実施している測定点(16測定点)における年平均値の平均で3.5トン/km
2
/月と2年度の3.3トン/km
2
/月に比べてやや増加している。
一方、積雪・寒冷地などでは、降雪期に金属製のピンを装着したいわゆるスパイクタイヤが路面を引っかくことによって発生するスパイクタイヤ粉じんによる降下ばいじんが生じていた。これに対し、「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律」が制定され、3年4月より、環境庁長官の指定する地域において、スパイクタイヤの使用が禁止された。これらの対策の結果、観測を実施している札幌市や松本市などの各都市において、降下ばいじん量は著しい改善の傾向にある(第1-1-8図)。
このほか、国設測定局では、エアロゾル等の浮遊粉じん中の硝酸イオンや硫酸イオンなどの成分の測定を行っている。これらの測定結果の推移は図のとおりであり、際立った変化は見られない(第1-1-9図)。
諸外国における浮遊粒子状物質の状況は、UNEP、WHOの調査によれば、バンコクや北京など12都市で深刻な状況にあるほか、ブエノス・アイレス、ロサンゼルスなど5都市で中程度の汚染であると報告されている(第1-1-10図)。
(6) 成層圏オゾンとクロロフルオロカーボン(CFC)等
ア. 成層圏オゾン
成層圏には、オゾン(O3)を多く含むいわゆるオゾン層が広がっている。オゾン層は、地球に降り注ぐ太陽光線に含まれる有害な波長の紫外線の大部分を吸収し、地球上の生物を守る役割を果たしている。成層圏オゾンが宇宙に浮かぶ地球の宇宙服になぞらえられるのはこのためである。しかし、近年、この大切なオゾン層が破壊されつつあることが観測されている。これは、成層圏において、これまでは強い太陽光の下で酸素からオゾンが生成される一方で、オゾンから酸素に戻る反応によりバランスがとれていたが、近年、地上で放出されたクロロフルオロカーボン(CFC、いわゆるフロンの一種)やハロン等が成層圏に達し、これらの物質に含まれている塩素原子や臭素原子によりオゾンが破壊されることによって、このバランスが崩れているためである。
例えば、南極上空では、南半球の春である9月から10月頃に広い範囲にわたってオゾン濃度が減少する「オゾンホール」と呼ばれる現象か生じるが、元年(1989年)以降4年(1992年)まで4年連続して大規模なオゾンホールが観測されている(第1-1-11図)。特に4年(1992年〉のオゾンホールの最盛期における面積及びオゾン破壊量は、過去最大であった前年の3年をそれぞれさらに約10%上回った(第1-1-12図)。昭和基地上空のオゾン全量は過去最低値を大幅に更新し、上空13〜18kmにはオゾンのほとんど無い層が1月間以上にわたって現われた。一方、同じ極地である北極においては、気象条件等の違いから、南極ほど大規模な成層圏オゾンの減少は観測されていないが、元年(1989年)及び3年(1991年)〜4年(1992年)にかけて実施されたNASA(米国航空宇宙局)の航空機を用いた調査によって、オゾンを破壊する作用の強い一酸化塩素の濃度が極めて高いことが報告されている。北極の周辺では、元年(1989年)及び2年(1990年)の2月にスカンジナビア半島付近において、また、4年(1992年)1月にバルト海上空において極端なオゾン減少域がみられた。
1992年のオゾン全量の特徴は、全球的に平年よりも少ない状況が全ての月を通じて見られたこと及び冬季北半球高緯度でオゾンが少なかったことが挙げられる。
国内においては、平成4年には札幌では4、7月を除いては平年よりオゾン全量が低く経過し、1、3、11月にはその月の過去最低値を更新した。つくば、鹿児島、那覇は概ね平年並みだったが5月に那覇で過去最高の、鹿児島でもその月の過去最高値を記録した。4年の年平均値は、過去の累年平均値に比べ、札幌で5.8%、つくばで0.6%の減少であった(第1-1-13図)。
なお、札幌では、5.6%/10年の有意な減少がみられ、冬季のみでは約12%/10年となっている。
こうしたオゾン層の減少により、地表に届く有害な波長の紫外線(UV-Bといわれ、波長は280〜315nm)の増大が懸念される。有害な波長の紫外線の増加は、人体に対して、皮膚がんや白内障等の健康被害を増加させ、植物の成長障害や海洋生態系の基礎となる浅海域の動植物プランクトンの生育障害を引き起こす。オゾン層の減少による有害紫外線量の変化を監視するため、我が国では平成2年から有害紫外線の観測を行っている。平成4年12月までの観測では、国内4地点におけるUV-Bの観測値は推定平年値に対して増加の兆候はみられていないが(第1-1-14図)、オゾン以外の条件が変わらなければ、オゾンの減少に伴いUV-Bの地上到達量が増加することが別途確認されており、今後も引続き観測を続けていく必要がある。
イ. クロロフルオロカーボン(CFC)等
CFCは冷媒、洗浄剤、発泡剤など幅広い分野で使用されており、ハロンは消火剤に使用されている。オゾン層破壊物質としては、この他に四塩化炭素、1,1,1-トリクロロエタン、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、臭化メチル等が挙げられる。我が国では、オゾン層保護のための国際的取り決めであるモントリオ-ル議定書を踏まえ、「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」に基づき、これらオゾン層破壊物質の製造等の規制を行っているとともに、排出抑制や使用合理化を進めている。
我が国では、北半球中緯度地域(北海道、岩手県三陸町綾里)及び南極地域(南極昭和基地)等においてCFC等の大気中濃度を観測している。第1-1-15図に示すように、いずれの物質も増加傾向にあったが、最近は、CFC-11、12、113の濃度の増加は、北半球中緯度ではほとんど止っている。しかし、現在のCFC等の大気中濃度は、例えば、南極でオゾンホールが観測される以前の1970年代に比べてかなり高い状況にあるので、成層圏オゾン層の状況を改善するためには、これらの濃度を大幅に低減させることが必要である。
なお、CFC等は地球温暖化問題とも密接に関係する。これらのガス自体が有する温室効果は二酸化炭素に比較して高いが、最近の知見によると、下部成層圏のオゾン層を破壊することによる間接的な温暖化に対する逆の効果を有するとも指摘されている。
(7) 二酸化炭素
地球では、大気中の二酸化炭素(CO2)やメタン(CH4)などの温室効果ガスが地表から放射される赤外線を遮蔽し、熱を宇宙に逃がしにくくしており、これにより生物の生存に適した気温が保たれている。地球温暖化問題とは、人間の様々な活動によりこれらの温室効果ガスの大気中濃度が上昇し、人類が過去経験しなかったような早さで気温が上昇することである。気温の上昇に伴い、気候が変化し、さらに海面の上昇、降水量の変化、生態系の構造変化などが起こり、人間や生物の生活環境、農業や林業などに大きな影響が生じるものと懸念されている。
温室効果ガスのうち二酸化炭素についてみると、その地球温暖化への寄与度は、世界の知見を集約している「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)の報告書(1990年)によれば、1980年代において各種温室効果ガスによる効果の合計の約55%を占めるとみられている。同じ量のガスによる温室効果という点では、メタンなどの方がかなり高いが、二酸化炭素は排出量が膨大であるため結果として地球温暖化への寄与が大きいと考えられている。大気中の二酸化炭素濃度は、産業革命以前には280ppm程度であったが、現在では350ppmを超えており、さらに年0.5%の割合で増加していると推測されている。国内では、岩手県三陸町綾里で昭和62年(1987年)から観測を実施しており、平成4年(1992年)の年平均濃度は、359.6ppmであり世界と同様年0.5%の割合で増加している(第1-1-16図)。IPCCによれば、こうした温室効果ガスの増加により、何も対策を取らなかった場合、地球全体の平均気温は、2025年(平成37年)には現在に比べて約1度、21世紀末前には約3度上昇し、海面水位は、2030年(平成42年)には現在に比べて約20cm、21世紀未までには約65cm(最大1m)上昇するであろうと報告されている。
二酸化炭素については、その発生源は主として化石燃料の燃焼であり、人間の経済社会活動の広範な分野に係わるものである。すでに先進国を中心に様々な取組が始まっているものの、決定的な処方箋はない状況である。こうした中、地球温暖化防止のための国際的に協調した取組として、1992年(平成4年)5月、大気中の温室効果ガス濃度の安定化を目指した「気候変動に関する国際連合枠組条約」が採択され、現在、本条約の発効に向けての国際的作業が行われている。我が国でも、地球温暖化防止行動計画(平成2年)に基づき、第4章第1節8に見るとおり、二酸化炭素等の排出削減などの努力がなされている。
(8) メタン、その他の温室効果ガス
温室効果ガスには、二酸化炭素のほか、メタン、一酸化二窒素(亜酸化窒素、N2O)、対流圏オゾン、クロロフルオロカーボンなどがある。メタンは、100年程度のタイムスケールでみると、同じ量の二酸化炭素の約21倍の温室効果を持っていると考えられている。さらに、メタンは、大気中で分解すると、温室効果ガスである二酸化炭素及び成層圏水蒸気を増加させ、地球温暖化を促進させると考えられている。その発生源として、湿原、湖沼などの自然発生源と天然ガスの漏出や家畜、水田、廃棄物埋立等の人為的発生源がある。また、温暖化が進むと土中及び海洋に固定されているメタンを解放し、温暖化を一層加速化させる懸念がある。
大気中のメタン濃度は、過去3000年間の古大気の分析によると、250年前まではほぼ一定であったが、ここ200年ほどの間に倍以上に増加しているものと推測されている(第1-1-17図)。国内では、岩手県三陸町綾里で平成3年(1991年)から観測を行っており、3年、4年(1991年、1992年)の年平均濃度はともに1790ppb(ppmの千分の一)であった。また、環境庁では、凍土中の有機物質が温暖化に伴って分解されやすくなり、メタンが増加すると予想される現象を解明するため、平成4年にシベリア上空の大気中のメタン濃度を測定しており、その結果によると、メタンの高度分布は、地面に近いほど濃度が高く、高高度で抵い状況であった。
一酸化二窒素は、やはり100年程度のタイムスケールでみると、同じ量であれば二酸化炭素の約290倍の温室効果を持っていると考えられており、発生源には、自然発生源である海洋や土壤などのほか、人為的発生源である化石燃科や薪等のバイオマスの燃焼、施肥農地などがある。一酸化二窒素は大気中の寿命が150年程度と長いことが分かっているが、地球規模での動態などには不明な点も多い。一酸化二窒素の平均濃度は平成2年(1990年)で約310ppbであり、毎年0.2%から0.3%の割合で増加している(第1-1-18図)。国内では、岩手県三陸町綾里で2年(1990年)から観測を行っており、3年、4年(1991年、1992年)の年平均濃度はそれぞれ309ppb及び313ppbであった。このほか、対流圏オゾンは、二酸化炭素に比較してかなりの温室効果を持つと考えられており、自動車や工場などが排出した窒素酸化物や炭化水素が光化学反応を起こして生成されることが知られている。しかし、対流圏オゾンについては、現状定量的な把握は困難であり、今後、科学的知見を蓄積していく必要がある。
(9) その他の大気汚染物質
カドミウムや塩素など大気汚染防止法で有害物質として規制されている物質については、これらの物質の発生源である工場または事業場に対し排出基準を設け、排出規制などの様々な対策を実施している。
このほか、現在直ちに大気中の濃度が問題となるレベルではなくても長期的にその濃度の推移を把握していく必要がある物質については、昭和60年度からモニタリング調査を実施している。平成3年度には、元年度に引き続き、石綿(アスベスト)、水銀及び有機塩素系溶剤(トリクロロエチレン、1,1,1-トトリクロロエタンなど)についての調査を実施したが、特に問題となるレベルの物質はなかった(主な有機塩素溶剤の性状等は第1-1-1表のとおり)。なお、4年度には、2年度に引き続き、ホルムアルデヒド及びダイオキシン類について調査を実施した。
また、特定の排出源の影響を直接を受けない一般環境の大気中における化学物質の残留状況を把握することを目的に、毎年異なる数種の化学物質について調査を実施している。3年度の調査では、調査対象16物質中ニトロベンゼン(主な用途は染料・香料中間体等)など12物質が大気中で検出されたが、検出濃度及び検出頻度などを勘案し、特に問題はなかった。
さらに、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に基づく指定化学物質及び第2種特定化学物質についても、一般環境中での残留状況を調査しているが、この結果、大気中からトリクロロエチレンなどが検出されており、今後とも調査を継続し、環境汚染状況を監視する必要があると評価された。また2年度より、指定化学物質等検討調査の一環として、新たに日常生活において人がさらされている媒体別の化学物質量に関して調査を開始した。