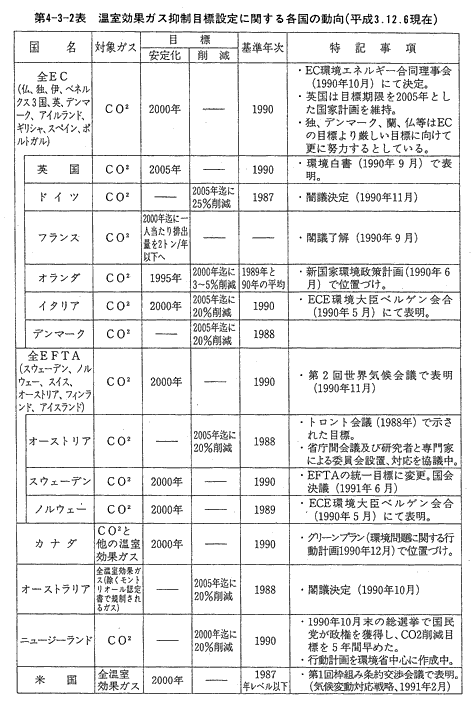
2 国内での率先した取組
地球サミットの主要な議題の検討状況について見てきたとおり、先進国と途上国との間には、環境問題の責任の所在を巡る原則的な対立が生じており、地球サミットにおいてどれだけ具体的で多数の国際合意がなされるかについては予断を許さないものがある。しかし、環境問題には迅速な対応が必要であり、議論が許される時間は自ずと限られている。地球サミットは、1972年(昭和47年)のストックホルムで開催された「国連人間環境会議」の20周年という意義も有する。同会議では、「かけがえのない地球」をモットーに「人間環境宣言」が採択されるなど環境保全のための行動が議論されたものの、必ずしもその成果が具体的な施策に結びつかず、十分な実行につながらなかったうらみがある。今回の地球サミットにおいてこうした不幸を繰り返している時間的余裕はもはやないと見るべきであろう。20年前のストックホルム会議が必ずしも十分な実行につながらなかった原因は、会議後の1980年代(昭和50年代半ば以降)に世界経済の成長が純化し、環境問題に対する関心が急速に薄れてしまったという状況と会議の成果が勧告にとどまり、具体性を持った形にならなかったことなどが拳げられる。
今回の地球サミットの機会には、なるべく広範かつ具体的な国際合意ができるように期待したいが、更に一層重要なことは、成果を確実に実行につなげていくことである。このためには、各国政府機関の努力はもとより、関係の国際機関、各国の国民、更には国境を越えて地球市民としての活動を行うNGOなど各方面の参加と協力が必要である。
我が国は、これまで繰り返し地球環境保全に向けて積極的な役割を発揮していくことを国際的に表明しており、地球サミット事務局を始め各国からも地球サミットの成功とその成果の実施に向けて我が国が積極的な役割を果たすことに大きな期待が寄せられている。
自然資源の大量消費国であり、地球環境に大きな負荷を与えている先進国の一員である我が国は、こうした期待に応えていく責務があると言えよう。我が国としては、国際的な合意形成を促進するためにも、また地球生態系の中のよき一員としての日本を確立するためにも、世界に率先して、持続可能な経済社会を築いていくことが不可欠である。我が国では、国内において公害を防ぎ、自然を保護する施策が充実強化されてきている。また、本章で見たとおり、持続可能性を高める上での取組が始まり、あるいは検討がなされている。さらに、地球全体の環境の保全の分野でも本報告の第2部第8章に見るとおり、海洋汚染防止対策、野生生物保護対策、オゾン層保護対策など多くの対策が始まっている。特に、現在、地球環境問題の中でも、最重要課題となっている地球温暖化に関しては、平成2年10月、我が国は「地球温暖化防止行動計画」を「地球環境保全に関する関係閣僚会議」において決定した。この計画は、地球温暖化対策を計画的総合的に推進していくための当面の政府の方針及び今後取り組んでいくべき実行可能な対策の全体像を明確にし、国民の理解と協力を得るとともに、国際的な枠組み作りに貢献していく上での基本姿勢を明らかにするものである。この計画に基づき、我が国は、同年11月の第2回世界気候会議において、対策の世界的枠組みの設けられていない中で、EC、EFTA諸国と同様(第4-3-2表)に率先して地球温暖化対策に取組む方針を明らかにした。その後、関係省庁において計画に沿った対策が着実に図られている。
民間においても、3年5月地球環境日本委員会が設けられ、世界に先駆けて各界挙げて地球環境問題に取組む体制を整備したほか、同年7月公益信託地球環境日本基金が設定され、各方面の善意の寄付金が少しずつ集められている。また、4年4月に、「地球環境賢人会議」の開催に協力するなど、環境保全の気運は大きな盛り上がりを見せている。
こうした官民一体となった取組の下、地球サミットの成果を国内で活かす新たな対策が求められている。