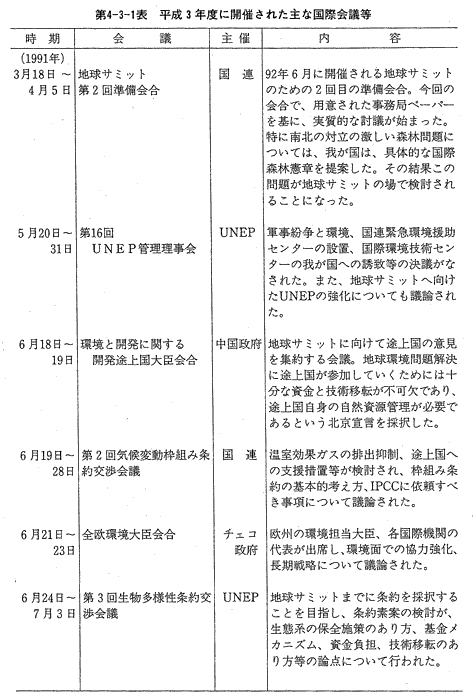
1 環境と開発に関する国連会議における今後の世界の環境政策の方向づけ
人類共通の課題となった地球環境の悪化に対応するため、様々な国際的取組が行われている。平成3年度に表に掲げるような重要な国際会議が開かれ、環境問題に取り組むための国際合意が重ねられ、地球規模の協力が進んだ(第4-3-1表)。
こうした中、我が国も、積極的に環境問題への国際貢献を行うべく努力している。例えば4年3月に京郡で「ワシントン条約第8回締約国会議」が開催され、100カ国以上からの締約国代表と非政府機関等のオブザーバーを含め1200名以上(報道関係者を除く)と、同会議史上最高の参加者を得て、2週間の会期中に附属書の改正や条約の適正履行に関する様々な討議が行われた。
今会議では、カニクイイヌやナナミゾサイチョウなど39の種または属を新たに附属書に追加し、ジェフロイヤマネコ、シロビタイムジオウム、ミュールンベルグイシガメなど18の種または属が商取引可能な附属書?から原則商取引禁止の附属書Iに格上げされた一方で、18種が附属書?から削除、7種が附属書?から附属書?に格下げざれた。こうした議論の中で特筆すべきは、野生生物の商取引が、それらの保護に役立っている場合もあるとして、このような適正な取引による利益を認識するべきであると野生生物の原産国が強く主張し、これが認められたこと、さらに附属書への掲載基準を現行のもの(通称ベルン・クライテリア)より客観的、科学的な新基準を策定する必要性が認められ、これの作業日程に関する合意がなされたことである。
このような動きは、附属書に掲載し、国際取引に対する禁止等規制措置を強化することが、直ちに野生生物の保護につながると安易に考えられがちであった従来の締約国会議の潮流を見直すものであり、今後同条約が、野生生物の種の保護と利用の調和という、その究極的な目標の実現に向けて、より実質的に機能していくために、今会議は重要なター二ングポイントになったと考えられる。
我が国では、引き続き、来年6月、釧路市において「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約(ラムサール条約)」の第5回条約締約国会合がアジアで初めて開かれることになっている。
このような流れの中で、持続可能な社会の形成のための具体的方策ヘの国際的な合意を得ることを目的として、4年6月にブラジルで「環境と開発に関する国連会議(地球サミット)」が開催される。国連総会決議により、この会議には、各国元首、首脳レベルの出席が求められており、人類史上、最高レベルの参加者が最も多く参集する会議となるものと期待されている。本会議では、これを機会に、二つの条約への署名、森林に関する合意文書の作成をすることが目指されているとともに、持続可能な開発を実現していくための基本理念や行動の原則を定める憲章的文書の採択、大気、森林等の分野ごとの行動計画の策定、行動計画実施のための資金措置や機構の整備の検討が予定されている。以下では、地球サミットで課題とされている事項のうち、個別の問題を除く横断的なものについて現状における検討状況を概観しよう。
(1) 地球を人類共通の未来のために良好な状況にしておくことを確保するための人と国家の行動の基本原則を定める憲章的文書の採択
この文書では、現在及び将未の世代の基木的義務、環境に係わる意思決定の原則、多国間関係の原則を含む環境と開発に関する一般的な権利及び義務に関する原則を定めることとし、国際的な議論が進んでいる。
検討されている項目をより詳細に見ると、前文においては、全ての個人、団体及び国家の持続可能な開発に対する責任とその分担に関すること、現在及び将来の世代が地球の生態系及び資源へ依存している事実の認識に関すること、貧困や持続不可能なライフスタイルは脆弱な地球の生態系の長期にわたる存続を阻害するものであるとの指摘、国際社会は新たな倫理に基づいて環境との共存を図るべく生産や消費の形態を転換する必要があることなどを訴えることが提案され、検討されている。
さらに、一般原則としては、開発と環境の統合、地球環境に関する責務、地球環境に関する権利、将来の世代の利益の擁護、国家間の関係の原則、予見的予防的アプローチの必要性、国家と個人及び国家間の協力、開発途上国への配慮、環境と貿易、環境と紛争、環境とライフスタイル、環境と教育、汚染者負担の原則、責務と補償、市民参加と情報公開、貧困の克服、資金供給及び技術開発・移転に関することなどを盛り込むべく検討がなされている。
この文書は、直ちに法的な拘束力を各国や個人に及ぼすものではないが、個別の取組の前提となり、今後の国際的取組の指針となることが期待されている。我が国としても、国際的検討を経た後、これが採択されたときには、この文書を尊重し、実際の行政施策にその精神を生かしていくことが必要となろう。
(2) 21世紀に向けて実施すべき具体的な行動計画を定める「アジエンダ21」
アジェンダ21は、環境と開発に関するリオ宣言(地球憲章)の理念を具体化した行動のための計画であり、行動の基礎、目的、行動(対策)、実施手段という4種の角度から内容が構成されている。現在、39分野の行動に関するアジェンダ21の素案が地球サミツト事務局より提示され、議論が行われている。地球サミットのモーリス・ストロング事務局長は、アジェンダ21の性格に関し、各国に義務を課すものではなく、各国政府、国際機関、NGO、地域ごとの各種団体及び一般市民が一致協力しかつ集中して積極的な行動を採ることを可能とするような枠組みを提供することを目的とすること、各国がアジェンダ21を踏まえて自主的に行動を採り、さらに実際に機会に応じて行動を一層拡充していくことを期待している旨を述べている。
アジェンダ21に関する主な検討内容を、代表的な分野について見ると次のとおりである。なお、これらの中には、既に我が国として実施済のことも含まれており、また、必ずしも実施を要しないことも合まれている可能性があり、今後、国際的に掘り下げた検討が行われ、連切なものとして国際的な合意がなざれるよう期待されている。
?大気保全
大気保全では、温暖化等の気候変動、オゾン層破壊、酸性雨等の越境大気汚染の3分野の議論が行われているが、このうち、気候変動とオゾン層破壊については、別に条約交渉会議等で個別に対策が議論されているため、これら二分野の条約に関する議論は行われていない。大気保全の分野の対策としては、以下の7分野が検討されている。
ア 持続可能なエネルギー開発の推進
イ 運輸部門からの有害な大気汚染物質の排出を抑制するための環境上健全な輸送システムの促進
ウ 大気に悪影響を及ぼさない工業開発
エ 大気に悪影響を及ぼさない農業開発
オ 持続可能な消費パターンとライフスタイルの促進
カ 地球大気への影響の機序に関して理解を向上させるための研究協力及びこれによる不確実性への対応
キ 成層圏オゾンの破壊の防止
?森林保全
持続可能な開発の考え方の下で、熱帯林、温帯林及び寒帯林を含む全ての森林の保全と合理的な利用を目的として、次の4分野の対策が検討されている。
ア 森林及び林地の多様な役割、機能の維持
イ 森林の保護、持続可能な経営及び保全の強化並びに植林等による荒廃地の緑化
ウ 森林が供給する財及びサービスの有効利用とその全ての価値の評価の促進
エ 森林関連の計画及び活動の立案、調査、定期的評価に資する能力の確立と強化
?淡水資源の質と供給の保護
この分野においては、資金とコストの評価、科学的技術手段、人材開発、開発途上国の対処能力の向上などを合め、検討が行われている。対策として検討されているのは次の6分野である。
ア 統合的水資源管理の促進
イ 水資源の質と量の確実な予測のための水資源アセスメント
ウ 水質及び水生態系の保護
エ 飲科水供給及び衛生の向上
オ 水資源開発及び持続可能な都市開発
カ 持続可能な食料生産のための水資源
このほか、?砂漢化及び干ばつ、?生物学的多様性、?バイオテクノロジー、?海洋保全、?有害化学物質、?有害廃棄物、?固形廃棄物及び下水関連問題を含む合計39の分野について具体的な行動計画案が提案され、我が国を始め各国の政府、さらには民間団体も参画してその内容についての真剣な検討が進められている。成案を得たならば、我が国 としても国内外においてその内容の実現に真剣に取り組んでいくことが必要となろう。
(3) 環境資金の国際的確保
環境配慮を組み込んだ持続可能な開発を実現していくべきことそのものは、先進国、開発途上国を問わず共通の認識となっている。アジェンダ21に盛り込まれている行動計画の実行に向けては、開発途上国の環境対策実施能力の強化を図るとともに、途上国において必要十分な額の資金を確保し、途上国自身が責任をもって環境を保全し得るようになることが欠かせない。しかし、既に第3章第2節で見たとおり多くの途上国の資金不足は深刻であり、このため、従未のODA等による開発途上国への資金移転(第4-3-1図)に加えた追加的な資金移転が検討されている。地球サミット事務局においては、国連総会の求めにより、地球環境保全のために、先進国から途上国へと国際移転される目安となる資金量について試算を行い、必ずしも積算根拠が明確ではないものの、その額を1250億ドル(途上国自身の負担は、この4〜5倍となる)とした。
しかし、こうして試算された資金移転額は、今日の先進国と開発途上国との間の資金の流れが官民合わせても年間高々1200億ドルほどであることを考えると、その実現は極めて困難である。さらに、途上国は資金の額が確保されるべきはもちろん、この資金の性格を巡って、環境問題を含め、開発途上国が抱えている貧困などの問題の責任は、先進国にあると主張した上、必要な資金は、先進国から「補償」の形で調達されるべきであるとしている。また、資金移転の国際的仕組みは、従来のものに加え、「新規かつ追加的」なものでなければならないとしている。
これに対して先進国の主張は、各国は、「共通のしかし差異のある責任を有する」というものである。すなわち、先進国も途上国も責任を有するが、その責任の程度は問題発生への寄与の程度、対応能力等により差があり、先進国は率先して対策に取り組むものの、途上国においても、環境保全の努力を払うべき責任があるとするものである。また、追加的資金の必要性は認めるものの、地球環境ファシリティー(GEF)、地域開発銀行、UNDPなど既存のそれぞれに実績のある支援の仕組みを強化した上で、その一層の有効な活用(例えば将来の気候変動枠組み条約とGEFの連携の強化)を図ること、併せて自然保護・債務スワツプ等民問資金の活用を図ることが重要と考えている。
こうした意見の相違はあるものの、地球サミットでは資金問題についての国際的合意が成り立つことが望まれている。これは、ある一国が環境対策を行うことにより、対策を行わない国にも利益を生じる場合、利益を得る国もその対策に要する費用の一部を負担することに合理性があり、こうした負担がないとどの国も十分な環境対策を行う動機を欠くことになるからである。逆に、ある国で十分な環境対策が行われないと、その被害は他国にも及ぶことがあり、こうした被害を避けるためにある国での対策費用の一部を国際的に負担することには、合理的な面がある。さらに、環境対策の容易さは、国ごとに異なる(第4-3-2図)。このことは、環境保全のための対策の実施を特定の国に猶予するような理由とはなり得ないが、資金を国際的に融通し合って対策の容易な国で多くの対策を行うと、世界全体の対策費用が節約され得る。現在、発展途上国における環境対策の支援の在り方が国際的に議論されているが、発展途上国で行う対策のうちには、世界全体での対策費用の節約という観点から見ても支援の意義の高いものがあるものと思われる。先進国の国内対策に加え、資金面で先進国が国際貢献することは地球全体の環境改善にとっては有効な面があるのである。
資金の国際的融通は段階的に進められるべきものであるが、現在地球サミットに向けて、環境資金を国際的に円滑に確保するための仕組みの在り方、例えば資金を管理するための国際的な仕組みの在り方、移転された資金の途上国における確実な活用策、財源確保の在り方などがとりまとめられるよう、世界の知恵が求められている。このような事情を背景に、4年4月には、東京において地球サミット事務局の主催で「地球環境賢人会議」(名誉議長は竹下元総埋)が開かれるが、このように民間も含め、我が国には世界に貢献する知恵の発揮が期待されている。
(4) 技術移転の促進
開発途上国が環境保全対策を講じていく上では、その環境問題への対処能力を高める必要がある。そのためには、先進国から途上国への環境保全上健全な技術の移転の仕組みを確立することが課題となっている。技術移転の重要性については、我が国を始め国際的に共通の認識があるものの、資金問題と同様に、先進国と途上国との間にはなお原則的な対立が存する。すなわち、途上国側は、資金負担の在り方についての考え方と同様に、先進国からの「特恵的かつ非商業的な技術移転」を求めている。先進国側は、技術の多くが政府ではなく民間で開発され、所有されている現状にかんがみ、技術開発に対する保護措置としての知的財産権の保護等を前提とし「公平かつ適正な方法」での移転が行われるべきである旨を主張している。
地球環境を保全していく上で技術移転の重要性は、資金移転に劣らないものがある。我が国は、著しい公害を克服してきた経験と人材、豊かな技術とその開発力を持っており、我が国に対する期待には大きなものがある。こうした期待に応えるべく、国際協力事業団(JlCA)や関係省庁等において既に多くの環境技術協力が進められているほか、中央公害対策審議会、自然環境保全審議全、産業構造審議会、対外経済協力審議会などの場で、今後の新たな取組の方向が検討されている。こうした検討結果を踏まえ、地球サミットの機会に、適切な仕組みが確立されるよう、我が国としても合意形成に向けてなお一層努めていく必要がある。
(5) 環境保全のための国際機構の強化
環境の保全に対する国際的な取組を強化する観点から、国連内における環境と開発に関する機構の改革、アジェンダ21を含む地球サミットの成果のフォローアップのための仕組みの確立、環境と開発に関する分野における国連と他の組織の協力の促進といった大別して3点が議論されている。これらの点に関し、国連環境計画(UNEP)の強化及び他の国際機関の総合調整については広い支持が集まっている。地球サミットのフォローアッブについても5年ごとにサミットを開催するなどの提案がなされている。地球サミットにおいて国際的な合意が成立することは重要なことであるが、最も肝要なことは、そこで得られた合意が実際に実行されることである。そのための適切な国際的仕組みの確立が望まれる。