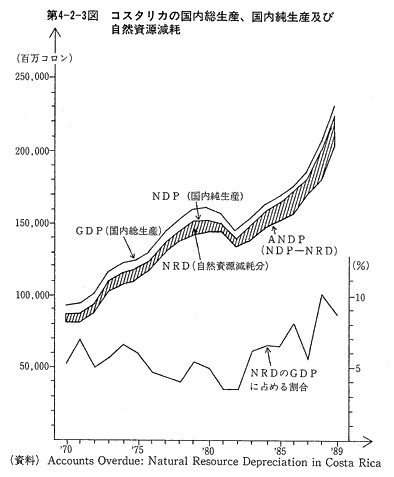
4 経済の質的な面での発展
(1) 経済と環境との関係に係る問題点
一般に、経済の拡大と環境の保全とは二者択一的な関係にあると考えられている。確かに、生産技術も生産消費のパターンも変わらない短期の間では、環境を一層守ろうとすれば、経済活動は制約を受ける。こうした制約は、環境を守るためにはやむを得ないものであり、当然の出費ではあるが、長い目で見ると、必ずしも経済発展と環境保全とは背馳するものではない。
例えば、途上国では第3章第2節で見たように貧困ゆえに環境への配慮が困難となり、環境破壊が進んでいる。そして、環境が破壊されると人々の生活の糧が失われて一層貧困を進める、という貧困と環境破壊の悪循環が見られる。第2章で見た我が国においても、同様の経験がある。「経済の健全な発展との調和」に心掛けなければならなかった初期の微温的な公害対策の下で多くの産業公害が発生した。水俣病の例では、目先の経済的な利益を重視する中で、結果として悲惨な被害が生じたほか、汚染原因となった企業も、その企業が立地する地域も順調に発展できなかった。水俣病の補償や汚染された環境の回復は、この企業の乏しい自己資金のみでは進められず、特別の配慮の下、外部の資金が借り入れられ投じられているほどである。
他方、同じく我が国の経験によれば、経済優先との誤解を生じる余地のない厳格な公害対策の下でも、官民の懸命の努力がなされた結果、経済的豊かさの向上は可能であった。経済成長の中で公害対策の資金が生み出されてくるし、より汚染の少ない産業構造への転換も円滑に進み、また、公害対策の実施が、より健全な技術を育てる契機となり経済発展に役立ったりもした。我が国の経済は、第3章で見たように、諸外国からの原材科や製品の輸入などに伴って海外の環境に影響を与えており、また内にあっては多くの環境問題を抱えており、持続可能な経済社会が実現されているわけではないが、公害対策の経験に見られるとおり、環境の保全と経済の発展との間には、長期的にみれば、互いに助け合う側面もある。このように、環境と経済との関係は複雑なものであり、環境の観点から経済活動の一層適切な方向づけのためには相応の工夫がいる。
こうしたことを踏まえると、経済の質、すなわち人間福祉の向上への経済の寄与の状況を常に間い直し、金銭的な成果物の大小だけにとらわれない発展の道を探ることが今後の課題と言えよう。
(2) 環境に配慮した経済政策目標
このためには、経済の成績評価を測る上で環境の大切さを反映した手法がまず採られるべきである。
1980年代末(昭和60年代)になり、経済政策の分野で環境に配慮した意思決定が行えるよう環境と経済を総合的に評価しうる指標の重要性が国際的に認識されるようになった。
経済に関する指標として代表的なものは国内総生産(GDP)である。GDPは、国の経済力の大きさや景気の動向を判断する上での便利な指標であるが、これは、市場価格に基づいた財・サービスの毎年の生産フローの大きさであり、例えば、大気、水等の環境汚染の局面は把握できない。むしろ、国民が環境汚染対策のために支払う支出、例えば医療費や公害防止機器の購入などはGDPを増加させる。このために、環境は悪化しているにもかかわらず、経済が成長していることをもって経済社会が順調に発展しているとの錯覚すら生じかねない。我が国のかつての状況はまさにそうした状況であった。持続可能な社会の形成のためには、このようなフローとしての環境汚染に加え、自然資源のストックを将来世代の利用が危うくならないような水準に保っておくことが必要である。例えば、短期的な利益を上げるために森林の過度な伐採をしたとしても、このことは直ちにGDPを下げはしない。将来の経済活動を著しく低下させるおそれがあるにもかかわらず、このような潜在的な損失は勘定に入っていないのである。
そこで、環境汚染や自然資源の劣化を考慮しながら、より長期的に発展のあるべき方向を指標体系、すなわち、「環境資源勘定」を確立することが求められるようになった。今までに、国連統計局、OECD、世界銀行、世界資源研究所(WRI)などによっていろいろな勘定体系が検討されてきた。そして、これらの研究を国際的に推進し、その成果を役立てるために、世界銀行等の協力のもとに国連統計局において、国民経済計算体系(SNA)の外で、その関連勘定(「サテライト勘定」)の枠組みや手法が検討されてきている。特に、1993年(平成5年)に予定されるSNAの改定に合わせて、サテライト勘定の一つである「環境・経済統合勘定(SEEA)」のハンドブツクを作成中である。また、1989年(平成元年)と1990年(同2年)の先進7カ国首脳会議(サミット)においては、OECDに対してこうした指標の開発が要請され、OECDでも、環境指標について政府の代表と専門家が参加した一連のワークショップを組織し、検討を行っている。さらに、国連環境計画(UNEP)でも、これらの検討に関わる各方面の専門家の参加を得て、主に発展途上国のために環境資源勘定を試算しようとしている。我が国でも、かつてGNPに代わる指標として国民純福祉(NNW)の試算が行われたことがあるが、新しく環境庁、経済企画庁及び農林水産省の各研究機関が研究に着手した。
これらの勘定を作成するには環境に関する詳細で的確なデータ収集と統計処理作業か必要であり、OECDでは、データの処理の標準化を進めつつ、現在、森林と水資源に関する試行的な勘定の作成を進めており、我が国も検討作業に参画している。経済活動の評価指標を改善する試みは、いくつか行われている。国運統計局は、パプアニューギニアとメキシコを対象に環境資源助定の実行可能性の調査を行っている。また、WRIも米国開発援助庁等の資金で、コスタリカを対象にして事例研究を行った。後者の研究では、自然資源の減耗(ただし、計算の対象となっているのは、森林、土壌、漁業資源のみ)は、国内総生産(GDP)から控除すべき負の投資として取り扱われ、そのGDPに占める割合は、1989年(平成元年)で8.9%に相当した。こうした自然の減耗分を差し引いた国内純生産(NDP)の平均成長率は、4.7%であり、従釆の考え方によつて測られた4.9%を0.2ポイント下回った(第4-2-3図)。
こうした経済活動の評価指標を開発することは重要であるが、さらに重要なことは、開発した指標を政策の目標に位置づけ、その指標で測った経済の質を向上させるように具体的な政策を行うことである。こうした指標がどれだけ尊重されるかは我々の英知にかかっていると言えよう。