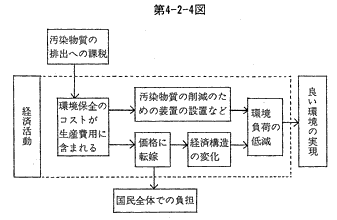
5 立場を異にする人々のそれぞれの足元での行動と互いの協力
(1) 適切な役割分担の意義
経済社会の持続可能性を高めていくためには、経済社会の隅々にまで環境保全上の配慮が行き渡る必要があると言われている。
これには、いろいろな理由が考えられるが、その一つは、環境との接点、例えば煙突や排水口においてだけ環境を守る工夫を行ったのでは非効率であることが挙げられる。例えば、温室効果ガスの二酸化炭素では、排煙中から二酸化炭素を取り除く技術が開発中であるとはいえ、相当な期間にわたって実用化は困難と思われ、対策手法としては、政府が平成2年に定めた「地球温暖化防止行動計画」にあるように、省エネルギー、エネルギー利用の効率化、エネルギー源の多様化といった対策からリサイクル、都市構造や交通体系の改善、さらにはライフスタイルの変革などといった対策まで、経済社会活動全般を変更することにより、二酸化炭素の発生そのものを減らしていく対策が必要となっている。
自然資源の採取や不用物の廃棄のいずれであるにせよ、何らかの形で、環境を直接、間接に利用する者がそれぞれの行為に関して環境保全の責任を果たすことが求められているのである。
第二に、多様な関係者が積極的に協力した方が、社会全体としての努力が節約できることがある。環境を守る対策には非常に幅の広いものがあり、そのそれぞれは異なった主体によって実施されるものであるが、これら諸対策の間の分担関係がどのようになっているかに応じて対策全体の効果が大きく異なる。我が国において大きな成果を収めた二酸化硫黄の削減対策では、既に第2章第2節で見たとおり、産業構造の変更や省エネルギーが対策に役立ったほか、輸入原油の低硫黄化、石炭、石油から天然ガスヘのエネルギー転換、重油の脱硫、排煙脱硫装置の設置、高煙突化といった各種の対策が組み合わされて実施された。各対策の間では、実施主体が異なるだけでなく、必要な費用もメンテナンスの労力も異なる。仮に、二酸化硫黄の低減努力を石油の使用者のみに行わせ、また対策技術として排煙脱硫装置しか用いなかったとしたら、社会全体のコスト負担は膨大なものとなっていたと想像される。実際、こうした対策が、一方では政府の指導や計画により、また他方、民間では主に価格メカニズムを通じて調節され、役割が分担された結果、社会全体としては、比較的少ない費用で汚染の改善を成し遂げることができた。第3章第1節で見たリサイクルの事例でも、生産者における再生資源の利用拡大だけではなく、廃品回収業の発展、地方公共団体や政府の施策、さらには、消費者における回収の実施と再生品の積極的な購入に係る行動に至るまでの幅広い社会的取組があってこそ、リサイクルは今以上に効果的に進むものと期待されている。
第三に、環境保全の責任を皆で分け持つことが必要な理由として、倫理的、道徳的なものが挙げられる。今日の社会では分業が発達した結果、それぞれの人々の環境との係わり方には軽重の開きが大きい。しかし、これは分業の結果であって、人類の環境に対する依存の度合が減ったわけではない。例えば、複雑な経済の網の目を通じて商品が加工され、流通していくが、この結果、家庭の食卓に並ぶものも地球の各地から取り寄せられたものとなっている。消費者が、また、商品の製造者がそれぞれの役割に応じて環境保全の責任を積極的に引き受けることが重要である。
さらに、人類の活動が大きくなり、地球が相対的に狭くなった今日の社会では、国の間の役割分担という問題も生じている。これが適切になされるか否かでその成果も大きく異なろう。
(2) 責任の整理と明確化
問題は、望ましい責任分担のあり方は当事者に委ねていたのではなかなか決められないということである。既に述べたように、環境には公共財的な性格があり、他人の努力の結果環境が改善されると、その便益は努力を行わなかった第三者にも及ぶ。このため、実際上は、各人が進んで努力を行ったり、その結果、社会全体として必要十分な対策が行われるという自明の保証はない。こうしたことから、多様な主体に分担されて進められる環境保全の努力が全体として最適なものとなるよう調整する政府の役割がますます必要となっている。
この点に関して、まず、責任の帰属関係を整理し、明確にすることが考えられる。我が国においては、フローとしての汚染の対策に適用される汚染者負担の原則(P.P.P.)を拡張し、公害による健康被害者の補償の責任、土壌汚染等の対策のために行われる公共事業における汚染原因者の費用負担責任が法制化されているほか、公害に係る無過失損害賠償責任も法制化されている。アメリカでは、1978年に発覚したニューヨーク州のラブキャナル(LoveCanal)での有害廃棄物不法投棄地に起因する環境汚染問題を契機として、全米各地の同様な不法投棄地が大きな社会問題となり、1980年(昭和55年)に「包括的環境対策・補償・賠償責任法」(スーパーファンド法)が制定された。同法は、大統領に対して有害廃棄物が投棄され、環境汚染が生じた場合、又は有害物質が環境に放出された場合に、その浄化のための適切な措置を講ずる権限を与え、そのために要する資金を賄うための基金を設立するとともに、一定の範囲の当事者に対し対策実施又は費用負担の責任を負わせることとするものである。基金は、石油及び特定の物質に対する課税収入等からの拠出によって賄われ、その総額は、当初5年間は16億ドルで、その後1986年(昭和61年)と1990年(平成2年)の2回にわたって改正がなされ、現在は、1995年(平成7年)までの基金総額は約120億ドルとなっている。1991年(平成3年)までに、1236ケ所が全国浄化優先順位表(NPL)に掲げられており、33ケ所で恒久措置が完了し、NPLから除外された。
本法の特色としては、第一に、石油や特定の物質に対する課税収入等から基金を設立し、浄化対策の費用に充てることであり、これによって、仮に費用を負担すべき者を容易に特定し得ない場合であっても迅速な対策を講じられるようにしたことである。第二には、当事者に対して極めて厳格な責貴任を課したことである。すなわち、責任を負う者の範囲は、汚染された施設の現在の所有者又は管理者(現在の所有者)、有害廃棄物が放出された時点での当該施設の所有者又は管理者(過去の所有者)、有害物質を発生させた者(発生者)、施設へ有害物質を輸送した者(輸送者)のいずれかであり、かつその責任は遡及効を持つこととされた。このため、スーパーファンド法施行前に廃棄された有害廃棄物の処理責任を現在の所有者が負うといった厳しい事態となっている。このように、スーパーファンド法は、有害廃棄物の処理責任者を特定することが困難な事例が多発した米国の実態を踏まえ、従来の汚染者負担の原則の考え方がフローとしての汚染対策を取り扱っていたことを超えて、実効ある環境汚染の浄化対策の実現を図ろうとしている点が特徴である。
このほか、各人に委ねられた努力の成果を評価し、必要に応じて過不足を調節する政府の役割も重要になってきている。さらに、政府自らが行う公共卓業において環境の保全に資する施設の整備やサービスを充実していくとともに、環境保全以外の目的で行われる公共事業の実施に伴う環境保全措置も引続き充実していく必要がある。環境そのもの、あるいは環境と人類の活動との関係に係わる調査研究、環境を破壊から守る先駆的な技術の開発、環境の状況や環境に影響を与える活動の状況の監視なども政府が中心となって分担すべき役割である。このほか、国民や事業者への情報提供と普及啓発、環境教育なども政府の担うべき任務である。新しい政策課題である持続可能な経済社会づくりに向けて、こうした政府の役割がますます期待されており、それが一層円滑かつ効果的に発揮されるよう、今後、不断の努力が必要であろう。
(3) 経済メカニズム自体の改善と活用
政府には、以上のとおり、期待されるところがますます大きくなっているが、現在の複雑化した経済社会では、人間の諸活動に対する政府からの働きかけとしては、必ずしも強制的な規制だけが唯一の方策とは言えなくなってきていることにも注意が必要である。環境問題は経済社会活動の歪み、欠陥として捉えられているが、こうした歪み自体を直すことが、むしろ、第2章第2節で見たような市場メカニズムのせっかくの活力を生かした効率的な問題解決になるとの考え方が、サミットやOECD等の場で出されている。また、持続可能性を高めることのように、その実現の方策が多様に存在する場合には、一律的な禁止や特定の対策のみを強制する規制は必ずしも積極的に受け入れられるわけではないという事情もある。
このようなことから、国民や事業者の対応の自由度を保ちつつ環境保全上の配慮が一層多くなされるように誘導していく経済的政策手段の活用に関心が持たれている。我が国の経済的手段の活用の事例としては、収集するごみ袋の有料化など、ごみの収集・処理のコストの利用者への転嫁を図り、その意思決定に反映させることなどによって市町村のごみ処理量が減量した例もある。ちなみに、前掲第4-1-1図に見るように国民の環境保全意識も高まっている。
また、1991年(平成3年)1月の「環境政策における経済的手段の利用に関するOECD理事会勧告」では、「各国の社会経済的状況を考慮しつつ、経済的手段を、規制等の政策手段の補完あるいは代替としてより広くかつ整合性をもって利用する」ことが勧告されている。勧告では、経済的手段として、?課徴金及び税、?排出権の市場での売買、?デポジット(頂り金)制度、?資金援助(補助金等)を挙げている。特に、経済的手段は、場合によっては、規制的手段に比較して費用効果的に環境汚染防止を図り得ること、長期的には、環境改善のための技術革新を促進させる効果を有するメリットがあると考えられ、この面で、活用の期待も高まっている。
?課徴金及び税
以上の経済的手法のうち課徴金及び税は、理論としては、無料で行われている環境利用に関し、いわば環境の使用料の負担を求め、これによって今まで環境利用者によって負担されていなかった社会的コストを経済活動の中へと内部化させるものである。環境汚染物質の排出量や環境資源の利用頻度に応じて課税などすることによって、環境資源の効率的な利用と配分を促進し、結果として環境の改善を果たそうとするものである(第4-2-4図)。
諸外国では、例えば、1990年(平成2年)のフィンランド、オランダを皮切りに、翌1991年(同3年)には、スウェーデン、ノルウェーで主に二酸化炭素の排出抑制を狙いとした税制が導入されている。これらのうち、税率の高いスウェーデンについて見ると、石炭、石油、天然ガス、ガソリンを通じて炭素1t(二酸化炭素にして約1900m
3
)当たり、約2万円の割合の課税となっている。ちなみに、ガソリン1リットル当たり10円程度である。炭素税導入に際しては、既存のエネルギー税の引き下げ等、関係する税体系の改正も行われ、全体として見ると、炭素を多く含む燃料には従前より多くの税が課されるようになった。税収は一般財源とされているが年額約3100億円(ちなみに炭素税収は同国の税収の約3%。GNPは我が国の約15分の1)と見込まれ、二酸化炭素の排出量では、現在の発生量に対して8〜16%程度に当たる量が今世紀末時点で削減されるとされている。それ以外でも、課徴金・税は従来から、国内対策として大気汚染や水質汚濁対策のために用いられている。こうした課徴金・税の活用例を示すと第4-2-1表のとおりである。環境税の活用等については、さらに現在もOECDの租税委員会と環境委員会の合同作業部会で検討が進められており、我が国もこの国際的検討に参画し、真剣な検討を行っているところである。
?排出権の売買
以上の課徴金等のほか、他の政策手段も検討されているが、このうち、排出権の市場における売員は、汚染物質の許容排出量をあらかじめ割り当てておき、その割当量を超える工場は余裕のある工場から排出権を買って操業し、全体として効率的な排出削減を図る仕組みである。課徴金の場合の税率をどのように決めるかという問題があるのと同様に、最初の排出権枠の分配の仕方をどのように行うかが難しい問題となるが、これについても、内外で検討が進められている。なお、アメリカにおいては、1980年代から、ばい煙取引制度が導入されており、酸性雨対策として二酸化硫黄を削減するためにこの制度が実地に用いられ始めている。
?デポジット(預り金)制度
デポジット制度は、リサイクルを必要とする製品について預り金(デポジット)を課し、商品の使用後に、不要製品が一定のルートに戻ったときに払い戻しをする制度である。スウェーデンでは特定の種類の飲料容器に関しデポジット制度が行われ、成果を上げている。その仕組みの概要は第4-2-5図のとおりであり、業界が出資して設立した「デポジット基金法人」が回収のための仕組みを運営している。1991年(平成3年)現在でアルミ缶回収率は82%を超えている。
さらに、同国では、自動車に関するデポジット制度が1976年(昭和51年)から実施されている。当初250クローネ(約7500円)の預り金が製造ないし輸入された車(ただし、1800kg以下の車)に課せられ、この預り金は、車の所有者がスクラップ業を認可された業者に運び込んだ時、スクラップ割増し金付きの300クローネ(約9000円)で払い戻されていた。なお、1988年(昭和63年)に預り金が300クローネ、スクラップ割増し付きの還付金が500クローネに引き上げられ、さらに1992年(平成3年)1月から預り金が850クローネ、スクラップ割増し金が1500クローネに引き上げられた。販売時に徴収した預り金は、この制度のために設けられた車のスクラップ基金に払い込まれ、スクラップ割増し金の支払いと廃車の再資源化に融資するために地方当局に対して交付される補助金とに割り当てられている。
ドイツでは、プラスチック包装容器に関して、1988年(昭和63年)12月20日付けの政令でデポジット制度が導入されているが、1992年(平成4年)1月1日からプラスチック以外のものも含めてデポジット制度が適用された。これによれば、0.2リットル以上の使い捨ての飲料水、洗剤、洗浄液、スプレー式ペンキ用等の容器について0.5ドイツマルク(約40円)を、1.5リットル以上の場合には1ドイツマルク(約80円)を、2kg以上の塗料容器については2ドイツマルク(約160円)をそれぞれ製品価格に上乗せして販売することとなる。この容器は、アルミ、プラスチック、鉄等あらゆる素材を合むものであるが、製造業者及び流通業者が管轄当局から承認された一定の地域において適切な包装容器回収システムを運営している場合には、個別業者の引き取り及び預り金還付の義務が免除される。このような免除の認められるシステムは、使用済み包装容器を直接担当地域の家庭から定期的に回収することが確実で、かつ第4-2-2表の回収率及び分別率を達成できるものである。また、既存の廃棄物処理当局による回収、リサイクル、再使用システムと整合性を有するものでなければならないとされている。ドイツ産業界では、この回収システムを担う専門企業として「有限会社デュアルシステム」を設立しており、現在約500社がメンバーとなって、包装材の引き取りを行っている。さらに、今後は、電気機器、電子機器、自動車等についても同様の引き取り義務制度が検討されている。
アメリカでは、飲料容器に関し9州でデポジット制度が採られており、また、カリフォルニア州では独自の回収システムが運営されている(第4-2-3表)。
また、我が国でもいくつかの地域で飲料容器(缶)のローカルデポジット制度等が行われている。環境庁が把握しているローカルデポジット制等の実施地域は、平成2年現在で15都県の48市町村である。このうち、埼玉県神泉村及び長瀞町、大分県姫島村では町村の全域あるいはそれに近い規模で行われているが、その他は公園、体育館、駐車場、駅前、イベント会場など市町村の一部区域で行われている。実施方式としては、10円程度の金銭を頂り金として販売価格に上乗せする上乗せ金方式、罐と引き換えに奨励金を渡す奨励金方式、メダルを渡すメダル方式、抽選補助券等を渡す発券方式などがある。実施方式の内訳は、半数が上乗せ金方式であり、他は発券方式、奨励金方式、メダル方式等の順となっている。平成2年度の埼玉県の調査結果によると、埼玉県においては、県下12地区でデポジット制度を実施しており、それによる空き罐回収率は70.9%に達している。また、平成元年12月に臨時行政改革推進審議会から出された「国際化対応・国民生活重視の行政改革に関する第2次答申」の中において、省排出物へ向けた施策の充実のため、「リサイクルを進める観点から、デポジット制度導入の条件を整備し促進するための方策を検討」することが提言されている。
?補助金等
補助金等は、環境汚染を少なくしたり、森林などの環境資源を回復する活動に対し、財政的に支援し、活動を奨励するものであるが、我が国でも一定の範囲で活用され、効果を上げてきている。これは、経済的な意味での効率性は課徴金と同程度に高いものである。しかし、場合によっては、汚染者負担の原則から考えて、社会公正上、こればかりに頼ることが許されず、強化されつつある規制の受け皿として汚染者の規制への対応を円滑に進めるなどの限られた目的で用いられているほか、諸外国の中には、例えば、課徴金と組合せ、その収入を補助金等に充てる手法が採られる場合が見られる。