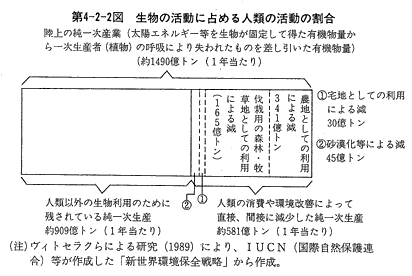
3 地球生態系での共存共栄
(1) 自然界との協調の意義と課題
人類も生物の一種である。人類の持つ遣伝子には、他の生物の持つ遺伝子と共通のものが多いが、このことに見られるように、人類は、地球生態系の一員として地球の歴史を他の生物と共有しつつ、その生存を続けている。「今日の鳥は明日の人間」という言葉があるが、生態系の一部であれそれが健全でなくなると、その影響は人間にも及ぶ。例えは、野生のトキの絶滅の原因は、採餌場である水田に農薬として有機水銀が散布されたことによるが、トキが絶滅への道を歩み始めた頃、人間に対する水俣病も発見されつつあった。これは、食物連鎖と生物濃縮といった生態系を通じた作用が深く係わっていることを示している。また、長い間、工場の煙は高い煙突から出されて環境の中に薄く広く混ぜて捨てられていたが、酸性雨の被害が生じるに至って、地球大気は無限の容量を持つごみ捨て場ではないことを人々は知った。この事例では被害の発現に大気や水の物理的な大循環があずかっていることはもちろん、さらに土壌やそこに棲む菌類があずかっていることが分かってきている。
さらに、プランクトンは海洋で二酸化炭素を吸収するため地球温暖化の将来予測の一つの鍵を握っている。破壊が心配されているオゾン層は、微生物の働きによって作られた酸素が、太陽エネルギーで化学反応を起こすことによって生じたものであるし、石油や石炭が生物起源であることはもちろん、鉄を産み出す鉱床も太古の微生物の活動の結果生成されたものである。人類は、一見、生物の活動に負っていると思えないような分野でも実は、地球生態系を構成する生物の、あるいはその産物の恩恵を受けて生きているのである。
人類が利用するこれら生物活動の産物は、究極的には太陽エネルギーによって生産されている(第4-2-2図)。生態系は、種が多様であればあるほど、その安定性が高いとされている。
このように、生態系における人類の生存は、多様な種からなる生物相の豊かさに依存している。
人類は、生態系を構成する多様な野生の生物と共存しつつ、これを生活の糧や素材としてはもちろん、科学の、教育のそしてレクリェーションや美の対象としても利用してきた。遣伝子工学の発達により、生物には遣伝子資源としての価値も加わってきた。これからも人類が生存していくため、すなわち、人類社会が持続可能であるためには、これらの多様な生物とますます適切に共存していくことが必要となっていこう。しかし、この野生生物が人為の結果失われつつあり、生物相の豊かさが失われてきているのが現状である。その保護が持続可能な経済社会づくりのために急務となっている。
このためには、まず、自然界から生み出される物の採取量を適当な範囲にすること、また、自然界に投入、廃棄される人間活動の廃物を適当な範囲にすることが必要であることは言うまでもない。しかし、現実には、第3章第1節で見たとおり、我が国について見れば、採取量も廃棄量もともに増大している。自然界からの採取、それへの投棄の両面での負荷を削減することに正面から取り組んでいくことが今後必要である。
さらに、生物の世界は、多様な構成要素から成り立っているが、この点に対する配慮に立った対策も必要である。生物界の捉え方には、生態系、生物群集、個体群、個体、遺伝子などの様々なレベルがあり、それぞれの段階での多様性こそが自然の根源とも言えるのであって、一見無用と思われる種も含め種の絶滅は防ぐべきものである。こうしたことから、絶滅の危機に瀕している種の一部については、その経済的価値はともかくとして、保護のための対策が内外で行われるようになった。しかし、保護は種そのものの保護にとどまっていてはならない。生物にとって、生息地は、それが種として進化を遂げた場であり、その生活史の全てを依存している場であることから、種と一体不可分のものとなっている。そこで、今日では、種そのものを保譲していくことはもちろん、これだけでなく、ある土地固有の多様な生物種からなる生物相を保護することや生息地そのものを保護することが課題となっている。
(2) 地球生態系の一員としての今後の取組
問題は、人命や人の健康への差し追った危険を除くために、各種の活動に制限を加える場合に比較し、生物の利用に一定の制限を課そうとする場合や、普通種も含め、ある土地に固有な生物相の全体や生息地自体の保護を行う場合には、このために支払われる社会的犠牲、努力や費用が、往々得られる利益に引き合わないとみなされがちなことである。例えば、途上国に産する熱帯林とそこに育まれる豊かな動物相を保護しようとする気運が先進国を中心に盛り上がっているが、熱帯林を有する途上国では、熱帯林の保護を強制されることは発展の権利を奪うものとして反発を生じている。こうした対立が解消されないと生態系の保護対策を円滑に行うことは難しい。公害による差し追った健康被害を防ぐことなどに比較して、人類が地球生態系の一員として、その中の生物やその他の環境と共存共栄できるようにすることは、価値として一段低く扱われ、場合によっては、人の財産や生活の利便性がこれに優先されることもこれまでには往々見られたところである。人の財産には各種の取得方法があり、利便性の低下は補償し得るものであるが、生物種は絶滅してしまえば二度と回復されることはないし、生態系の変化にも不可逆的なものがある。人類と地球生態系との間に今日とは異なる共存共栄の関係を成り立たせるためには、どの程度の強さの、どの程度の範囲の生態系の保護が、どの程度の経済的利益を犠牲にすることによって可能になるのかといった保護とそれに要する費用との間の関係を明らかにした上で、冷静な選択を行うことが必要である。この際には、保護の程度についての科学的な知見が活用されなければならないので、その充実が大いに望まれる。
地球の生態系は自然のまとまりや人間活動の影響範囲ごとに一定の単位で分けて考えることができる。地球生態系は地域生態系の積み重ねにより構成されているのであり、地域単位での取組は地球全体に対する対応の基礎となる。このため、生態系の中での人間と他の生物との共存共栄の在り方を考える際に、このような一定の空間的広がりでとらえられる地域生態系を単位として考えていくことは合理的である。
地域の生態系はそれぞれの持つ自然やその中で行われている人間活動の状況が異なったものであることから、生態系の中での共存共栄を図るために実施すべきことについては、地域の態様によりそれぞれ異なった対応を考えていくことが必要である。例えば、学術性の高い自然等の貴重な自然については、その評価と保護はある程度進んでいると言えるが、それ以外の自然についてどのように評価し、どのように対応していくのかについては基本的考え方が必ずしもはっきりしているとは言えない。この点で、貴重な自然とは言えないものの評価すべき自然として、人間活動が行われている農山村地域や都市内の身近な自然等について、地域生態系におけるトータルな自然環境の一部として積極的に評価していくことが重要である。
また、近年、生態系や”エコ”といった言葉が日常生活の中でも使用されるようになってきたが、生態系に関する正確な知識や認識といった点についてはまだ十分進んでいるとは言えない。このため、生態系の中における人間の位置づけの正確な認識が国民の間で醸成されるよう、環境教育を積極的に進めることが必要である。この場合、生物の持つ巧妙さ、精巧さを理解し、活用していくことが重要であり、いわば「工学的発想」から「生物学的発想」ヘの転換が求められよう。
具体的には次のようなことが考えられる。
地域の生態系の知見を充実していくため、調査研究予算の確保に加え、研究者やボランティアも含めた情報の収集連絡体制の整備や核となる機関の活用が必要である。このため、我が国で実施している「緑の国勢調査」のように、各国における動植物相に関する基礎的な調査を行ったり、UNESCOのMAB(人間と生物圏)計画に基づく生物圏保存地域(BiosPherereserve)などを活用しつつ主な生態系に関する現状及び経年変化のモニタリング体制を確立するなど、各国はもとより、国際社会やNGOも協力して基礎的な知見、情報を収集し、提供する仕組みづくりが求められている。また、各地域における伝統的な資源管理及び利用手法が生物多様性の維持にもたらしている役割や、生態系の持続的利用に関する事例等を草の根レベルで掘り起こすというような取組も重要である。
こうした基礎的な知見の収集・モニタリングを積み重ねながら、生物種の絶滅や特異性のある生態系の消滅が起こらないよう、これら貴重な自然について保護の徹底を図るとともに、通常の人間活動が行われている地域にあっても、人間の生活あるいは生産といった活動が生態系の許容量を超える過大な負担をかけることのないような社会システムを構築していくことが必要である。例えば、農山村や都市等、通常の人間活動が行われている地域においては、人間の生活あるいは生産といった活動を前提として、その活動との調和ある取組が必要であり、単に自然に手をつけず保存するというのでなく、むしろ、生物の多様性を保持することによる地域生態系の安定性の確保といった観点が必要である。
そこでは、まず第一に、そもそも自然の持つ生産力を生かすことで成り立っている農林業について、一層環境保全に配慮することにより作物以外の生物との共生の可能性を模索していくことが重要である。第二に、農山村や都市において、より多様な生き物が棲むことが可能となるような場の確保や環境改善を行っていくことが考えられる。さらに、それらの生物生存空間の場について、動物の移動を保障する観点から、様々な段階、形態、方法で、そのネットワーク化を図っていくことが必要である。
このような取組の代表事例として、「ビオトープ」と言われるような、動物の棲める小生物空間を確保することが実践されている。例えば、農地の一角を動物のため空間として提供することや、都市内において野鳥の繁殖のための空間をつくり出すため個人の庭やビルの屋上等を利用すること、緑地空間を活用した小生物空間を積極的に創出すること等が考えられる。ドイツにおいては、このようなビオトープの保全・創出と、ビオトープネットワークシステムの計画・建設が盛んに行われている。また、各種公共事業の実施に当たって、このような観点からの配慮を行うことも重要である。例えば、道路の法面緑化や河川改修などにおいては、自然植生の導入や、自然石利用・曲線改修等により動物や魚の生息に配慮した工法も研究されてきており、環境保全のための社会資本投資として、今後も積極的な取組が期待される。
以上のような取組を実現するためには、国民の理解と協力が不可欠であるが、そのためにも環境教育を充実させていかなければならない。この場合、人間が地球生態系の一員であり、他の生物の活動に依らなければ生存できないということから、地域の生態系における人間の位置づけまでの幅広い理解を求めることが必要である。
そして環境教育の場として、地球を実感できる国立公園等の傑出した自然から、生活空間の一部として身近なところに存在する小自然まで、様々なレベルの自然を確保するとともに、学校教育や社会教育等の様々な場を活用して認識を広められるような社会システムを作りあげていくことが求められよう。