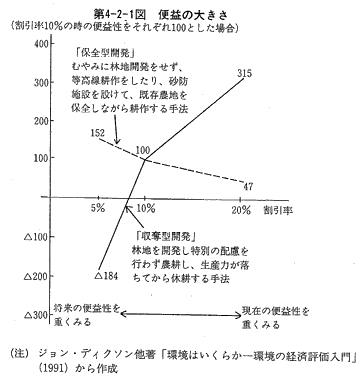
2 長期的利益の確保
(1) 長期的利益を考慮することの困難
環境は、精巧であるが、脆弱であり、現在の世代がその持てる力を無思慮に使うなら容易に破壊されよう。その回復は極めて困難か、場合によっては、元には戻らない不可逆的なものとなるおそれがある。環境には、こうした性質があり、長期的な視点に立った保全策が必要であるにもかかわらず、個々の意思決定、例えば開発プロジェクトの是非の判断などに際して、環境に対する長期的な影響が必ずしも十分に評価されているとは限らない。さらに、これが意思決定に十分組み入れられているわけでもない。市場経済は、これに参加できる現在世代にとっては大変効率的な仕組みであるが、そこには、将来の世代は参加できず、ここで行われる資源の配分が将来世代にとっても好ましいものとは言えないのである。さらに、将来を的確に予想しようとしても、技術的にはどうしてもある程度の不確実性は避けて通れない。
このほか、実務上は、将来における価値と現在における価値とをどう比較衡量するかという問題がある。将来世代の利益を市場で代弁する者がいない以上、この比較衡量は経済的になされるものではなく、価値判断と深く係わるものである。
次の図は、タイにおける農業開発のプロジェクトがもたらす便益の金銭的評価を試算したものである(第4-2-1図)。この図に見るとおり、将来の価値を現在の価値に引き直す「割引率」をどう見るかで、プロジェクトの評価は大きく異なってくる。環境に配慮した開発方法については、割引率を小さい値にし、将未の利益を比較的重く見ると、そうでない場合より、相対的に便益の高いものと判断されるが、他方、環境への配慮に乏しい略奪的な開発方法では、割引率を大きい値にし、現在の利益を比較的重く見ると、そうでない場合より、相対的に便益が高く評価されることになる。割引率や利子率は各種のプロジェクトの相互比較を行うためには欠かせない概念であるが、これを用いることは将来の価値を現在の価値に比較して軽く見ることにつながり、相当の期間の後の価値はほとんどないものと評価されてしまう。こうして将未の価値が軽く見られれば見られるほど、環境上の手当を欠いた開発の利益が見かけ上増すのである。環境保全の観点からは、割引率を低くして判断を行うのが好ましく、実際、こうした考えに沿った具体的な提案も行われている。
(2) 費用便益分析の手法の改善等
このように多くの困難がある中で、どのようにしたら我々は長期的に環境を保全し得るような賢明な判断を行うことができるのだろうか。
例えば、世界銀行では、その融資に当たってのガイドラインの中で、通常の開発事業の意思決定で用いられる費用便益分析におけるよりも長い期間(25から50年、あるいはそれ以上)についての環境影響の予測を行うことを決めている。また、開発に伴って生じる環境上の悪影響を未然に防ぐ措置については積極的に採用することとし、これによって初期投資額が通常のプロジェクトより高くなったとしても、それが必要であれぱ、融資対象に算入する措置をも講じている。さらに、回避し得ないような不可逆的な環境劣化を引き起こすようなプロジェクトには、そのことを理由に融資しないこととしている。
以上のように、環境のもたらす長期的な便益を守ろうとする場合は、通常の費用便益分析をそのまま通用せず、環境に対して特別の配慮を行うような工夫をこれに加えることが欠かせない。
このほか、開発プロジェクトの環境上の評価に当たって費用便益分析によるのではなく、あらかじめ定めておいた基準に照らして行う方法も用いられている。世界銀行では、自然保護地域等のあらかじめ環境上の理由から指定を受けた地域における開発プロジェクトについては、特別の配慮がなされない限りは融資を行わないこととしている。我が国の環境基準は公害の改善や防止に大きな効果を発揮してきたが、このように、将来の目標を定めておき、個々の開発プロジェクトをこれに照らして判断する手法もある。
(3) 世代と国境を超えた権利及び義務の原則
いずれにせよ、将来の世代に引き継ぐべき環境の望ましい水準については、経済的な判断になじまないものがあり、社会全体で真剣に検討した上、現在の世代が進んで尊重し、これに向けての努力を厭わないようなものにまで高めていくことにより、その実現を目指すことが重要である。
こうした努力の一つとして、長期的視点に立って環境のもたらす恵みを将来の世代に引き継いでいくことを各世代問の権利・義務の関係として、言わば「地球的権利及び義務」として位置付けていくことが考えられている。すなわち、各世代は地球環境の管理人であり、将来の世代の利益を擁護する義務を現代の世代は負い、逆に将来の世代は、少なくとも、前世代と同等以上の多様性を有する自然的・文化的な資源基盤を受け継ぎ、環境を利用し、その恩恵を衡平に享受する権利を有するということである。実際、我々の世代も、過去の世代が手入れをしてきた山や林、田や畑、海や川を受け継いで暮らしてきた。同じようなことを将釆の世代にもなすべきであろう。
こうした考え方は、既存の国際的な文書の中、例えば、国連憲章、市民及び政治的権利に関する国際規約等多くの人権に関する文書から導き出すことができる。これらの文書では、時間と空間を超えて人類社会の全ての構成員の尊厳と権利の平等についての基本的信念を表しており、将未の世代の犠牲の下に、現在の世代が利益を不当に享受することは、そうした基本的信念と矛盾することとなる。
特に、1972年(昭和47年)の「国連人間環境宣言(ストックホルム宣言)」は、この考え方を明確な形で打ち出し、「人は、尊厳と福祉を保つに足る環境で、自由、平等及び十分な生活水準を享受する基本的権利を有するとともに、現在及び将来の世代のため環境を保護し改善する厳粛な責任を負う」と述べ、「大気、水、大地、動植物及び特に自然の生態系の代表的なものを含む地球上の自然資源は、現在及び将来の世代のために、注意深い計画と管理により適切に保護されなければならない」とした。さらに、自然的、文化的環境を将来の世代のために保護するという考え方は、1972年(昭和47年)に採択されたロンドン・ダンピング条約及び世界的文化遣産及び自然遺産の保存に関する条約、1973年(昭和48年)に採択されたワシントン条約にも組み込まれた。
もちろん、現段階では、このような「地球的権利及び義務」の概念は、原則宣言であって、具体的な国際法上のあるいは国内法上の権利・義務として確立されているわけではない。しかし、これらは、具体的な条約の作成(例えば前記の3条約)、あるいは、国際慣習法規則の創造に寄与するような生成過程中の原則として考えられるのであって、その権利及び義務の具体的な内容は今後発展し、定着していくものと思われる。