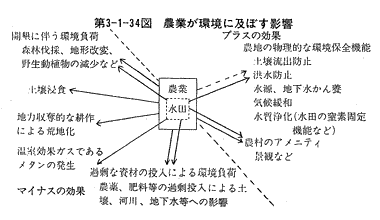
3 農林水産業の持続可能性と環境保全
(1) 農業による環境への影響
ア 農業の環境保全機能と環境への負荷
農業は、自然生態系の物質循環に基礎を置き、これを改変して農業生態系として管理し、人間にとって有益な物質の収量を拡大して生産を行う活動である。農業では、あるがままの自然は必然的に改変されることから、環境へ何らかの負荷を与える活動であり、方法によっては、過耕作、過放牧による土壌劣化や植生破壊などの環境破壊に至る可能性もある。
しかしながら、農業は、動植物である作物や家畜の生産力に頼る活動である以上、自然の物質循環と全く離れて存続できるものではない。環境を大幅に破壊してしまえば持続的な農業生産を行うことができなくなる。このため、従未、農業生産にあっては、自然の物質循環を破壊しないよう注意深い配慮が払われ、産業活動と環境との長続きする調和の一つの典型例、持続可能な経済社会の一つの在り方となることが多かった。さらに、乱開発など環境に悪影響をもたらす他の産業活動への土地の転用を防ぐという意味でも、間接的に環境保全効果を発揮する場合もあった。
特に、水田は、畦畔の造成と湛水の実施という独自の土地利用法により、土壌流出防止、窒素の吸着・吸収等による水質浄化、地下水かん養、洪水防止といった、積極的な環境保全機能も有してきた。
また、農村は、自然と人間の活動が互いに影響しながら調和している半自然の地域であり、独自の景観、居住環境などのアメニティを持つが、これも農業の環境保全機能の一つである(第3-1-34図)。
農業の持つ環境保全などの公益的機能は、現在の市場経済においては評価されない外部経済効果である。ある民間研究機関によれば、日本全国の水田の有する環境保全効果は、ヘドニック法(環境の質が地価や賃金に影響を及ぼすことを利用し、地域間での地価や賃金の差から環境の質の価格を推計する方法)を用いた試算では約12兆円、また、代替法(同程度の機能効果を提供しようとした場合に必要な施設(ダム等)の建設コスト等を当てはめて機能の経済的価値を推定する方法)を用いて代替可能な効果のみについて試算した結果、約5兆円とされた。
このように、農業は、環境保全に関して大きな効用を持つが、一方、資材等の外部からの投入により環境に負荷を与えるという一面もある。先進国では、一般に、昭和50年代半ば(1970年代末)まで農薬や化学肥料の投入量が増加した。これらが過剰に用いられると河川や地下水等を汚染し、健康や生態系への悪影響をもたらす場合がある。また、化学肥料への過度の依存や堆きゅう肥などの農地への還元の減少は、地力の低下につながるおそれがある。こうしたことを通じて農業の持続可能性が徐々に損われる可能性が生ずる。
イ 欧米における農業による環境問題の顕在化
欧米諸国では、このような農業における資材の過剰投入に伴う環境破壊が既に顕在化しつつある。オランダなどのEC諸国や米国では、肥料や農薬などによる地下水の汚染が問題となっている。肥料や家畜ふん尿の窒素分からできる硝酸塩により汚染された地下水を飲用すると健康被害につながるおそれがあるが、フランスの一部、西ドイツ、オランダ、イギリスでは、深層地下水の硝酸塩濃度が年々上昇している。また、米国などでは、不適切な耕地管理等による土壌侵食も問題となっている。
EC等ヨーロッパ諸国では、過度の生産性追求による農薬、肥科の大量投入などの集約化が環境の悪化をもたらしたとの認識に立ち、農業政策の重点を環境保全重視の方向へ変化させてきている。ECにおいては、1985年(昭和60年)に、各国が指定する環境保護地域において環境上好ましい方法で農業を行う農業者に対し補助を行うことができるという共通農業政策が導入され、1987年(昭和62年)からは、この政策費用の一部をEC当局が支出することとされた。さらに、1991年(平成3年)に提出された共通農業政策の改革案においても、こうした環境保全に係る措置の強化が提案されている。一方、米国においても、1985年(昭和60年)の農業法において、価格支持や所得保障制度を通用する際の条件の一つとして減反と土壌保全を義務づけるなど環境保全に係る措置が強化され、さらに、1990年(平成2年)の農業法においては、土壌、湿地、水質の保全のための計画の拡充、新設や、抵投入持統型農業(LISA)の促進のための研究、普及の拡大などが盛り込まれた。
ウ 我が国の状況と環境保全型農業への取組
我が国では、環境保全効果の高い水田が農地の中心であることもあり、これまで、資材投入の増加による環境への影響は顕在化していない。しかし、外部からの資材の投入量の状況を見ると、我が国の農業も、高度成長期以降、急速にその性質を変えてきている。かつては農地に投入されるのは作物残さ、堆きゅう肥などであり、自然の物質循環の範囲を大きく越えるものではなかったが、高度成長期以降、それらの投入は減少し、代わって工業的に生産された物質の投入が増加した。昭和30〜40年代に化学肥料と農薬の投入が急増し、昭和30年代半ばと比較すると、農薬で数倍、化学肥科で1.5倍程度の量が投入されている。なお、これらの投入量は、昭和50年代後半からは横ばいないしやや減少傾向を示している。また、農業機械の普及が進むとともに、電照、保温といった農業の施設化を背景としてエネルギー投入量も増加している(第3-1-35図)。
農薬、肥料エネルギーの投入量を国際比較してみると、第3-1-36図のようになる。これらの資材の必要量は気候条件により異なり、我が国のような高温多湿な地域においては、より必要性が高いとの指摘もあるため、単純な比較はできないが、我か国においてもかなりの資材が投入されている。
こうした変化により、農業の省力化と労働生産性の向上がもたらされたが、他方、資材の投入の増カ加に伴い、農業が環境に与える負荷が大きくなることが危惧されている。また、農地から流入する窒素分やリン分が湖沼の水質への負荷の一つとなっている事例も見られる。
このように、我が国においても、肥料、農薬等の外部からの資材の投入の増加は、農産物の生産性を向上させるという利益を生む反面で、これらが過剰に投入される場合には、環境への負荷を増大させたり、農業自体の持続可能性の低下につながることが懸念される。
また、区画整埋や農業用用排水施設の整備といった農地改良のための事業も、労働生産性を向上させ、農地としての土地利用を継続させるという点において農業の環境保全機能の維待に資する一方で、コンクリート水路の整備や農地に残された樹木や植栽の除去等を通じて農地の生態系の豊かさを減少させるおそれがあり、環境保全を考慮した事業の実施が求められている。
一方、山間地域などでは、過疎化や高齢化等を背景として耕作放棄地が増加している(第3-1-37図)。こうした土地においては、農業が有する環境保全機能が失われる一方、自然植生に即した植林などの適切な処置がとられない場合には自然環境が復元するまでに一定の期間を要し、その間、水源かん養機能の低下、土壌流出などの環境への悪影響がもたらされることがあり、こうした面での環境への悪影響も懸念される。
こうした中で、将来にわたって農業を持続可能なものとしていくためには、農業の環境保全機能を増進しつつ、化学肥科や農薬等の資材の投入に伴う環境への影響に配慮し、環境への負荷ができるだけ少ない農業を推進していくことが必要である。こうした観点から、資材投入量の削減やより生態系に調和した農業システムの開発等の環境保全に資する技術開発や普及等を内容とする環境保全型農業推進のための施策が平成4年度から農林水産省により始められるほか、自治体レベルの施策などでも、環境保全に関する申し合わせを行う例や、化学肥科、農薬の使用量削減に取り組んでいる事例がみられる。
このように、環境保全に配慮し、環境への負荷ができるだけ少ない農業を推進していくためには、肥料や農薬等の資材の効率的投入が経営の改善にもつながる等、こうした農業経営が生産性の向上とも調和したものとしていくことが重要である。また、山間地域などでは、耕作放棄地が増加し、農業が有してきた環境保全機能が失われるおそれがあるので、地域の特色を生かした農林業や地場産業の振興等を通じた地域の活性化を図っていくことが重要である。
第3-1-36図 各国の農業集約度(農地1km
2
(2) 林業の動向と森林の環境保全機能
ア 森林の環境保全機能と林業
森林は、木材という資源を人間に提供するのみならず、環境保全に資する多様な機能を持つ。地球規模の視野で考えれば、森林は地球上の熱収支、水収支、炭素循環に大きくかかわっており、地球を生物の生息に適した環境に維持する上で、不可欠なものとなっている。さらに、森林、特に熱帯林には多様な生物が生息しており、生物の多様性を維持する上でも大きな役割を果たしている。地域のレベルでは、森林は、降雨を地下へ浸透させ、河川への流出を穏やかにし、河川水量を平準化する水源かん養の働きや、土砂流出を防ぎ、山地災害を防ぐ働きを持つ。また、野生生物の生息の場を提供するほか、気象緩和、大気汚染物質の吸収、自然とのふれあいの場を提供するなどの多様な効果を持っている。
また、地球温暖化問題への対応が求められる中で、森林の二酸化炭素固定の機能が注目されている。森林の二酸化炭素固定量の試算にはいくつかの方法が考えられるが、森林の成長量に着目し、その増加量がすべて二酸化炭素を固定すると考えるなど一定の仮定をおいて、我が国の森林による二酸化炭素固定量を考えてみると、我が国では森林蓄積量が毎年人工林で約5,900万m
3
、天然林で約1,000約万m
3
ずつ増加し、これに加えて毎年約3,900万m
3
の立木が伐採されており、これにより毎年炭素量にして約5,400万トンの二酸化炭素が固定化されている計算になる。これは、我が国の二酸化炭素排出量の約17%に相当する量である。
我が国は国土面積の67%を森林に覆われており、このような森林の多様な環境保全機能の恵みを大きく享受しているといえるが、こうしたが国の森林は林業と密接に係わって存在している。我が国の森林の4割を占める人工林は播種、植林といった林業活動により形成されたものである。また、残りの天然林についても、森林の落葉、落枝等の農業的な利用や薪炭材の利用が継続して行われてきたため、我が国では全く人為の加わっていない原生林は稀であると言われている。
我が国では、戦中、戦後に荒廃した山林の復興と、旺盛な木材需要への対応を目的として、昭和20から30年代に、木材生産の観点から、天然林を皆伐してスギ、ヒノキ、カラマツなどの人工林に転換する拡大造林が広く行われた(第3-1-38図)。その結果、今日では、我が国の人工林は1,033万ヘクタール(平成2年3月末現在)となり、森林面積のうちの41%、国土面積全体の27%を占めるに至っており、天然林は1.352万ヘクタール、森林面積の54%となっている。
人工林と天然林を比較した場合、人工林は木材の生産量において優れているが、水源かん養、土砂流出防止などの環境保全機能を十分に発揮させるためにも、枝打ちや間伐などの施業を行っていくことが必要であり、天然林に比べより投資を必要とする面がある。一方、天然林についても、農山村に近いいわゆる里山の天然林などは、用材、薪炭材の採取等の林業活動を通じて管理されてきたものであり、期待される機能の発揮のためには、通切な施業等の管理を行っていく必要がある。
一般に、均一の樹種、樹齢の森林は、植物、昆虫、動物などの生態系の多様性の面では混交林などの多様な樹種を持つ森林に比べて相対的に低く、また、多様性を持つ森林よりも風雪害などに弱いと言われているが、こうしたことも踏まえ、人工林、天然林を間わず、森林の状況やその森林に期侍されている機能に応じて適切な施業を選択しつつ、林業等の人間の活動により適切な管理を進めていくことが重要である。このような意味において適切に実施される林業は、人間の生産活動と自然とが共存する、持続可能な活動である。
イ 森林の管理の状況と環境保全機能
我が国の林業は、安価な外材の輸入増加等を背景とする国内木材価格の低迷、造林費などの生産コストの増大の中で停滞し、丸太の生産量は42年をピークに減少してきた。こうした中で林家は所得源として他の就業機会を求めるようになり、林業に投入される労働力は減少してきた(第3-1-39図)。
一方、戦後、拡大造林を含めて大規模に造林された我が国の人工林は、間伐などの手入れを要する時期を一斉に迎えている(第3-1-40図)。しかし、材価の低迷、労働力の不足、機械化や生産基盤の立後れ等から手入れが行き届かないという問題も生じており、森林の健全性が損われることが懸念される。人工林においては、間伐などの管理が十分なされないと、細い樹木が密生することになり、風雪害や病虫害、火災の被害を受けやすくなったり、林内に光が入らないため下草などが生育せず、表土が流出し、保水力が低下するなどの悪影響が生じる。
昭和60年当時、以後5年間に緊急に間伐を要する民有林が190万ヘクタールあり、この間、実際に148万ヘクタールの間伐が行われたが、現在、なお、民有林においては間伐を行うべき時期にありながらこれが実施されていない森林が約140万ヘクタールある。このため、森林の健全性の悪化によるこれら森林の機能の低下が憂慮されており、引続き間伐の促進が期待されるところである。こうした中で、平成3年度には森林法が改正され、森林計画制度の改善、森林整備事業計画制度の創設など、森林管理の新たな取組が始められたところである。
森林の環境保全機能への国民の期待が高まりを見せる中で、我が国においては、森林法に基づく森林計画制度の適切な運用や、造林、林道等の公共投資の実施、各種の補助事業の推進、金融・税制上の措置等によるほか、自然環境保全法、自然公園法等の諸制度においても、それぞれの目的に応じた運用を通じ、森林全体の機能の高度な発揮が図られているところである。しかし、こうした森林の多面的な機能は、市場経済の原則のみを追求した場合には、価格などの面では評価されないため、木材生産という観点で引き合う範囲内においてしか、その保全・管理が図られにくい面もある。次節で触れるように、一部の途上国においては、外貨獲得の要請から製造原価が切り詰められるなどして持続可能性に欠ける自然資源の開発が行われ、森林の減少・劣化にいたる例も見られる。
我が国としては、地球規模での森林の保全・造成に努めていくとともに、国内においても、我が国の森林が国内の環境保全のみならず地球環境保全の観点からも重要な環境資源であることを認識し、環境保全機能を高度に発揮させるよう適切な保全、管理、造成を進めることが必要である。このため、一斉に間伐期を迎えている人工林の間伐等の管理の推進、複層林施業や長伐期施業など環境保全等の観点を一層重祝した整備等の推進、天然林の適切な整備や保全、管理の推進などが必要となっている。
(3) 漁業の持続可能性の動向
ア 海洋環境と漁業の持続可能性
漁業は、自然には再生しない鉱物資源に依存するところの大きい工業とは異なり、再生可能な生物資源の一部を利用して食糧生産等を行う活動である。したがって、適切な方法や水準が維持され、海洋生態系の許容量の範囲内で漁獲が行われる限り、永続的に食糧供給等を行うことが可能であり、適切に実施ざれる漁業は、本質的に、自然環境と調和した持続可能な人間活動である。
近年、地球環境問題への関心の高まりと経済活動の持続可能性への要請の増加、人口増加等を背景とする水産資源への国際的な需要の増大の中で、公海等における漁業において、資源保全の観点から漁獲規制を求めたり、野生生物保護等の観点から漁獲禁止を求める動きが国際的に強まっており、地球環境問題の観点からも、海洋環境の保全と資源管理を通じて漁業の持続可能性を確保していく必要性が広く認識されるようになっている。本年(平成4年)6月に開催される「環境と開発に関する国連会議(地球サミット)」においても漁業資源の問題が取り上げられ、生態系や沿岸域管理等の視点を含め、持続可能な漁業資源の利用のための基本的な方向が議論されることになっている。
漁業は、海洋などに生息する野生生物の捕獲を中心とする産業であることから、農業や林業以上に自然生態系に依存する度合が高い。したがって、漁業活動を持続させていくには、海洋生物の生態系を含めた海洋環境を良好に保全していくことが不可欠である。こうした観点から、我が国における漁業と海洋環境との関係を概観し、漁業の持続可能性について考えてみる。
漁業は、過度に水産資源を捕獲した場合に生態系に影響を加えるとともに、養殖における餌料等の投入などによっても環境に負荷を与える。一方、漁業は、工場排水、生活排水、埋立などの沿岸開発といった漁業以外の経済活動からの環境負荷に大きく影響される。漁業と環境との関係を考え、漁業の持続可能性を評価するには、これらの、漁業が環境に与える影響と他の経済活動の環境負荷が漁業に与える影響との両面を考慮しなければならない。
イ 漁業による海洋環境への影響
まず、漁業が海洋生態系に及ぼしている影響を見てみる。我が国の漁業生産量は、第1章にみたとおりであるが、このうち、我が国周辺水域においては、漁船性能の向上(第3-1-41図)等による漁獲強度の増大等から、底魚類(海中の底層部に生息している魚類)を中心として総じて資源量が減少傾向にあり、漁業全体としてはともかく、魚種によっては、今後の資源状況が懸念されるものもある。
海中を自由かつ広範囲にわたり移動する海洋生物には所有者や管理者を決めることが難しく、仮に完全な自由競争の下に置かれたとすれば、個々の漁業者の短期的な利益が追求され、生態系の許容量を超えた、いわゆる乱獲が行われる可能性がある。従って、そのような場合には、持続可能な漁業生産を行うために何らかの資源管理が必要となる。
このため、我が国では、漁業法、水産資源保護法等に基づく資源、漁業の管理か行われているところであるが、こうした公的制度に加え、地域の特性に応じた漁業者等による自主的な管理の推進が重要である。漁協などの地域単位では、かねてより禁漁期や禁漁区の設定、漁船の規模や漁具、漁法の制限などの資源管理の事例がかなり見られるが、さらに、近年、湾、灘等の規模での複数の漁業者組織による取組など広域的な資源管理の事例が出てきている。例えば、愛知県、三重県においては、両県の入会漁場におけるイカナゴの漁獲について解禁日、操業終了日の決定などの資源管理が行われ、この結果、漁獲量も比較的高い水準で安定している(第3-1-42図)。政府においても、こうした自主的な資源管理の取組を支援すべく、資源状況を予測する海域別のシミュレーションモデルの作成などの取組が水産庁により行われている。漁業の持続可能性を高めるために、こうした資源管理型漁業への取組の着実な推進が求められている。
一方、天然資源に依存した漁業の制約を克服するべく、養殖業、栽培漁業が行われている。これらは水産資源を積極的に培養、増大させる意味で持続可能性を持ち得るものである。近年の消費者嗜好の高度化を背景として増加している高級魚の養殖は、その生産量よりも多くの餌を必要とするが、イワシ等多獲性魚類のうち食用に供されていない部分を利用し、国民の二一ズにあった魚に変換しているものである。しかしながら、海洋の分解能力を超えた過度の餌の投与は海洋汚染をもたらし、養殖業自体に悪影響をもたらすおそれがあることも指摘されており、環境に見合った適切な飼育を行うなど、漁場環境の維持・保全のための対策が必要である。
ウ 環境汚染による漁業の持続可能性への影響
漁業は以上のように環境に影響を与える一方で、他の経済活動による海洋等の環境への負荷の影響を受ける、いわば被害者としての面を持っている。
我が国周辺海域では、瀬戸内海などの閉鎖性水域を中心として、赤潮や油濁などの海洋汚染による漁業被害が高度成長期に急増した。その後、汚染はやや改善したものの、なお年間100件以上の被害が生じており、被害額は平成2年には約33億円にものぼっている(第3-1-43図)。赤潮をもたらす富栄養化の要因としては、近年では生活排水による負荷の割合が大きく、この抑制が重要となっている。
また、我が国では高度成長期以降、工業用地造成などを目的とした埋立てが進められ、現在では、我が国の海岸線(島しょを除く)のうち36.5%が人工海岸となっている。沿岸地域は生態学的に最も豊かな地域の一つであり、多くの生物種が生息し、また高い水質浄化機能を持っている。埋立て等の沿岸域の開発は、漁場、産卵場及び稚魚の育成場の喪失をはじめ、工事に伴う土砂流出、開発された土地の経済活動による汚濁負荷や水質浄化機能の低下による水質の悪化などをもたらし、漁業に悪影響を与える場合がある。近年、ウォーターフロント開発やマリンリゾート開発等による沿岸域の開発が活発化しており、これに伴う埋立による漁業への広範な影響が懸念される。
さらに、かつて水銀による汚染が大きな問題となったように、人体に有害な影響を及ぼすおそれのある化学物質により魚介類が汚染されると、国民の健康に影響が及ぶことも懸念され、また、漁業の持続可能性を損なうことになる。近年では、例えば、船底や漁網の防汚剤として使われていた有機スズ化合物による汚染が問題となり、既に製造等に対する規制などが行われている。今後、魚介類の汚染を未然に防止することが重要である。
この他、海洋廃棄物による漁場汚染も問題となっている。
これまで見てきたように、我が国の漁業をめぐっては、周辺海域の漁業資源の一部に減少傾向を示すものがある一方、海洋汚染等による他の産業活動からの漁業への悪影響もあり、こうした中で漁業の持続可能性の確保が課題となっている。このためには、海洋の環境を良好な状態に維持する対策を強化していくとともに、資源管理型漁業の推進等を通じ、資源を漁業による持続的な利用が可能な適正水準に維持して行くことが重要である。