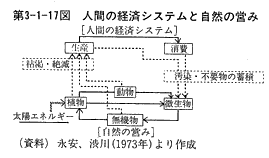
2 大量消費、大量廃棄型社会への変化
(1) 採取量、排出量の増大による持続可能性の減少
人間の経済活動は、自然界から鉱物資源や生物資源を採取し、消費した後、不用になった物を排水、排気ガス、ごみなどとして再び自然界の中に排出することにより成り立っている。経済活動の規模が小さいときには、資源供給源及び排出物吸収源としての白然の容量が無限であるかのように行動することが可能であったが、活動視模が飛躍的に拡大するにつれ資源採取による資源の枯渇や種の絶滅、不用物排出による汚染物質の蓄積といった現象が生じ、地球の自然は有限であるという事実が実感を持って認識されるようになった。経済活動を持続可能なものとしていくためには、究極的には、自然から採取する再生可能資源(ここでは森林や漁業資源のように自然により再生産される資源をいう)の量を自然の再生産能力の範囲とし、自然に排出する物質の量を自然が受容可能な量の範囲にすることを目指すことが大切である(第3-1-17図)。
我が国の経清活動への資源の投入、不用物の排出などの物質量の流れを試算した物質収支(マテりアル・バランス)を見ると(第3-1-18図)、平成2年度には、我が国は、国内と海外から20億4千万トンの資源等を採取し、12億4千万トンの物質を建築物や耐久消費則として国内に蓄積し、7億9千万トンを廃棄、輸出等の形で我が国の経済活動の外へ排出した。また、この排出のほかに1億8千万トンがリサイクルにより再び投入に回された。
環境への負荷を減らし、持続可能性を高めるためには、適切な配慮や処理により資源採取及び不用物排出の方法を環境影響の小さいものとすべきことはいうまでもないが、それだけではなく、採取と排出の量自体を減らすことが重要である。このためには、まず不要な物資の消費を減らすとともに、リサイクルされる物質量を増やすことが必要である。
かつて、重厚長大型産業を中心に生産の拡大が追求された高度経済成長の時代には、重量からみた生産量、消費量が豊かさの尺度とされたが、地球の有限性が表面化している今日では、こうした価値観はもはや成り立たない。我が国においても、すでに、自然とのふれあい、余暇、文化などの物質面以外の豊かさを求める声が高まっている。生活水準の維待向上に必要な生産・消費の確保は当然であるが、我々は、今後、「発展」を追求する方向を転換し、物資の「量」では表せない、真の豊かさを模索する必要がある。
こうした観点から、我が国のマテリアル・パランスの経年変化を見ると、昭和60年度に公共投資の抑制等による建設事業量の減少により一時的に蓄積が減少しているものの、廃棄や消費といった排出は一貫して増加しており、平成2年度の投入量及び産出量(有用物として蓄積された量と輸出量に廃棄量等を加えたもの)は20年前の45年度の約1.5借にも達している(第3-1-19図)。特に、廃棄及び消費という、有用物の生産とは直接には関係のない排出量の変化を一人当たりで見ると、近年その増加が加速化している(第3-1-20図)。
マテリアル・バランスのうち、資源の採取、投入について見ると、我が国は、世界から大量の非再生可能資源(ここでは化石燃料や鉱物資源のように自然により再生産されない資源をいう)を輸入している。世界の生産量に占める我が国の輸入量は、例えば石油では6.0%、鉄鉱石では18.0%にも上っている(第3-1-1表)。また、再生可能資源の世界の輸入量に占める我が国の輸入量の割合にも高いものがある(第3-1-2表)。このように、我が国の経済活動は世界経済全体の持続可能性にも大きな影響を与えている。
廃棄物について見ると、廃棄物発生量は、投入量の増加のスピードを上回り(第3-1-21図)、昭和45年度から平成2年度までに約2倍に急増している。このように廃棄物が増大する一方、廃棄物の減量化、再生利用は必ずしも円滑に進んでおらず、地価高騰による用地難や産業廃棄物処理事業者の資本力の不足などもあって、最終処分場の残余容量が減少してきている。また、最終処分場の確保が困難なことなどを背景として、廃棄物が山林、原野等に捨てられる事件か発生しており、廃棄物不法投棄で警察に検挙された件数は約1,500件(平成元年度)に上っている。このまま新たな処分場が作らなければ、全国で、産業廃棄物処分場は1年半、一般廃棄物処分場は8年で一杯になると予測されている。特に首都圏などの大都市圏では、処分場不足が深刻化し(第3-1-22図)、処分場を求めて産業廃棄物が東北、北陸などの遠方まで運ぱれる現象が起きており(第3-1-23図)、不法投棄等の不適正な処分が目立っていることなどを背景に、こうした廃棄物の流入を制限する地方公共団体も出てきている。例えぱ、首都圏について見ると、これまでと同様のぺ一スで処分場が確保されたとしても、平成12年度(2000年度)までには累積で山の手線の内側に積み上げると2.8メートルにもなる量の最終処分場の容量不足が発生するとの「大都市圏における環境資源の保全創造に関する懇談会」(環境庁企画調整局主催)の試算もある。最終処分場が不足すれば、生活環境への支障を生ずるおそれがあるほか、産業自体の円滑な活動の障害ともなりかねない。こうした中で、廃棄物の最終処分場の確保に努力が傾注されているが、これとても、山地の渓谷や海面の埋立などによって確保せざるを得ず、自然の環境を代償として失うことなしには得られないものである。
そもそも、我が国の資源利用に関する政策の歴史を振り返ってみれぱ、戦後まもなく、我が国の進むべき基本方向を示した、昭和26年の経済安定本部資源調査会の報告において、「日本の工業原科資源問題に対処すべき基本的態度」の4つの原則として、「(1)世界的な技術の発展傾向に則して考慮する、(2)我が国工業原料資源の特殊性を十分把握する、(3)我が国原科資源の一般的な保全を考慮するとともに我が国の原料資源の賦存状況に適した消費の編成を考える」といった原則に並んで、「(4)自然の統一性を破壊しかつ他資源の利用に損害を及ぼすような利用方法を改め、むしろ自然の循環法則に積極的寄与を与えるような方策を考える」との原則が示されている。同報告では、この原則のもととなる基本認識として、「自然というものは一つの統一体として存在しておりそれ自体として循環の法則を持っている。つまり各種の自然資源は相互に関連し合いながら均衡を保っている。従ってこの法則を無視してある特定の一部資源を採取あるいは処理すると、この均衡が破れて恐ろしい影響をわれわれの生活に及ぼすことがある」との考え方が示されている。今から40年も前に、自然の循環や生態系を基本とした、環境への負荷の少ない資源利用の考え方が示されていた。しかし、これまで見てきたように、この問、我が国の資源採取、廃棄物排出量は急連に増大し、大量消費、大量廃棄型の経済社会か形成されてきており、結果としてみれば、この報告の趣旨は実現されなかった。
このように、我が国の経済社会構造は大量消費、大量廃棄型へと向かっており、こうした物質の使用量の面で持続可能性が減じていることが憂慮される。
(2) 消費生活の変化による物質消費量の増大
前述したように、我が国の経済活動の持続可能性を高めるためには、まず第一に、有用性の低い物資の消費を減らすことが必要である。しかしながら、昭和60年代からの好況の中で、消費者の嗜好は持続可能な方向とは逆に、高級品、大型品へと移行しており、新製品への買い換えも頻繁になっている。例えぱ、販売される白動車も次第に大型化しており(第3-1-24図)、また、家電製品や白動車が廃棄されるまでの使用期間についても、短期化したり、あるいは、長期化してきた動きが停滞する傾向も見られる(第3-1-25図、第3-1-26図)。我が国では、製品のモデルチェンジは、例えば家電製品では1年程度、自動車では4年程度の周期で行われている。こうした頻繁なモデルチェンジは、技術革新を促し品質向上につながるなどの利点もあるが、一方では、既存製品を陳腐化し、消費者の買い替え意識を刺激することにより、消費量、廃棄量の増大の一因となっている。このほか、使用中の自動車や各種の製品に関する制度についても、その実際の運用の仕方によっては製品の使用期間を短くするという指摘もある。以上のような点に留意しつつ、物を大切に長持ちさせて使うような社会を作っていくためには、生産者、消費者、行政などの一致した検討と協力が必要となっている。
(3) りサイクル推進上の課題
ア リサイクル推進の価値と必要性
人間の経済活動は、資源を自然から採取し、不用物を自然に排出しているが、リサイクルにより、排出物を再び投入に回し、人間活動の系の中で物質を循環させることができる。これを進めることによって、生活に必要な消費を確保しつつ、自然生態系からの採取、自然生態系への排出を減らし、経済活動の待続可能性を高めることができる。
しかし、回収された古紙やスクラップなどの再生資源は、処女資源と比較しつつ原料として価格づけされるため、資源としての価値しか評価されず、廃棄物の減量化、廃棄物処理に伴う環境負荷の低減、製造段階におけるエネルギー使用量及び汚染物質排出の低減などの多様な効果は、現在のシステムの中では価格に反映されない。また、資源としての価値自体についても、リサイクルの待つ、資源採取を減らして将来世代に残すという効果は、今日の意思決定においては評価されにくい。
このように、リサイクルは現在の経済システムの下では十分に評価されない、大きな効用を持つ。その大きさを考えるために、一例として、定量的に評価しやすい廃棄物の処理費用について考えてみる。リサイクルが進んでいる沼津市では、一人一年当たりの一般廃棄物(ごみ)の排出量は321.7kg(昭和63年度)と、全国平均の386.5kg(同)を17%も下回っているが、仮に全国でリサイクルが進み、一人当たりのごみの排出量が沼津市なみになったとすると、約1,900億円にものぼるごみ処理費用が節約できることになる。しかし、現在、一般廃棄物処理費用は基本的に地方公共団体が一般の税金により賄っているため、国民が商品を購入したり捨てたりする際には、廃棄物処理に要する費用の負担は意識されない。この結果、リサイクルによる費用節約の利益も実感されにくい。
廃棄物発生の抑制効果以外に、リサイクルは汚染物質排出削減、資源・エネルギーの有効利用等の持続可能性を高める効果を持っており、定量的な把握は困難だが、これらはかなりの大きさにのぼると考えられている。このように、現在の経済システムの中ではリサイクルのもたらす価値が十分には評価されていないため、現在のシステムにおいて引き合う範囲内だけでリサイクルを行うことは、リサイクルの価値を正しく反映した場合に比較し、より少ないリサイクルしか行われないこととなる。したがって、リサイクルの多様な効果を十分に発揮させるためには、社会全体として、より一層のリサイクルの推進に努める必要かある。
以下では、こうした事情をリサイクルの現状に探り、今以上にリサイクルを進めるに当たって何が課題となっているのか考えるために、国民に身近なスチール缶と古紙を例に取り上けてみる。
イ スチール缶のリサイクル
スチール缶は、飲料缶と食科缶の生産の約70%(昭和63年)を占めている。スチール缶は、地方公共団体によりはほぼ回収され、そのうち4割程度が分離選別され、再生資源業者等によりプレス(圧縮)されたりシュレッダーで破砕され、スクラップとして全国に約40社ある電炉メーカーに引き取られる。電炉メーカーではこれを溶解、精錬、加工して、建築、土木資材などに用いられる丸棒などの鋼材を生産する。
鉄をリサイクルすることにより、廃棄物の減量化、資源の節約になることは言うまでもないか、さらに、鉄鉱石から鉄を生産する場合に比べ約65%のエネルギーの節約になるとの試算がある。また、製造工程からの大気汚染物質の発生を約85%、水質汚濁物質の発生を約76%低減することになるとの試算もあり、再生鋼の品質維持については相当の努力を要するものの、スチール缶リサイクルの環境保全効果は大きい。また、スチール缶などの缶容器については、ぽい捨てによる空き缶の散乱が依然として改善されておらず、身近な環境を悪化させるものとして問題となっているが、こうした面からも、空き缶を確実に収集し、再生利用することは重要である。
スチール缶の再資源化率は、地方公共団体の分別回収の推進等により、62年頃から徐々に上昇している(第3-1-27図)。しかし、その実状を見ると、スチール缶の引き取り価格は、60年の円高以降、輸入スクラップや鉄鉱石の価格低下と軌を一にして大幅に下落しており、さらに、平成3年後半からは、景気の減速の中での電炉メーカーの減産による需要の減少から一層下落した(第3-1-28図)。このため、地方公共団体などの回収者から再生資源業者への引き取りの段階では、逆に業者に費用を支払って引き取ってもらうケースが出るなど、廃スチール缶の資源としての価値はこの段階でははとんど評価されなくなってきている。
一方、再生資源価格の急落は、再生資源業者の経営基盤を脅かしている。再生資源業者は、回収した物を一定量が集まるまで蓄え、分別した上で、卸売業者やメーカーに納入しており、主に都市近郊に、ある程度の広さの用地を確保して営業している。前述した鉄くず価格の低迷により収益性が悪化したことに加えて、大都市圏で地価が高騰し、転廃業を余儀なくされる業者も多く、業者数は昭和50年代の後半から減少している(第3-1-29図)。さらに、平成3年後半からの鉄くず価格の一層の下落により、鉄くずのスクラッブ回収に携わる再生資源業者は、現在、非常な苦境に立たされていると言える。これまでリサイクルを支えてきた再生資源業者が減少すれば、今後、リサイクル推進の大きな障害となるおそれがある。
鉄くずの需給の今後の見通しを考えるために、鉄くず全体の発生量を見てみると、我が国では鉄の蓄積量が急速に増加し続けていることから、それに伴い老廃スクラップの発生量も増加し続けていくことが予想される(第3-1-30図)。一方、鉄くずの需要側を見ると、老廃スクラップの大部分は電炉メーカーにより建設用鋼材などの普通鋼の製造原料として用いられており、スチール缶については、現在、高炉における使用拡大のための実験が開始されたところである。原理的には、老廃スクラップはストックの量に比例的に発生するのに対し、製品の需要は年々のフローの量にとどまることになる。このため、今後、国内における鉄くずの需給均衡を維持するためには、高炉における使用拡大や新たな製品への利用の拡大などへの取組、海外への輸出等の対策が必要となってきている。
このように、スチール缶のリサイクルは、引き取り価格の下落を最大の要因として困難な状況に置かれている。飲料容器等の引取価格が下落することにより、逆に業者に費用を支払って引き取ってもらうケースが生しており、市町村の財政負担が増加している。3年に起こったスクラップ価格の暴落により、スチール缶の引き取り価格は、現状の経済システムの中では、電炉ノーカーの景気の動向によって、鉄くずのリサイクルか収益性のなくなる水準にまで下落し得るものであることが明らかとなった。現在の経済システムの中では、リサイクルの持つ環境保全効果が十分に発揮されているとは言いがたい。したがって、今後、経済システムの中で安定的なリサイクルが維持されるためには、適正なコスト負担をどう実現していくかが課題となっている。
ウ 古紙のリサイクル
紙のリサイクルによる効果としては、廃棄物減量化、木材資源使用の削減に加え、製造段階でのエネルギー使用量を約70〜75%、大気汚染物質の排出量を74%、水質汚濁物質の排出量を35%削減できるとの試算もある。また、紙の焼却に伴う二酸化炭素排出量の削減、木材資源の保護に伴う二酸化炭素吸収量の増加も期待できる。
我が国では、製紙メーカーが古紙を国産資源として重視してきたこと、ちり紙交換などの独自の回収システムが存在したことなどにより、従来から紙のリサイクルは欧米諸国よりも進んでいた。吉紙の回収率の推移を見ると、徐々に上昇して、昭和60年頃には50%に達していた。
60年代になると、景気の上昇やオフィスにおけるOA用紙の使用の拡大から、紙の生産は急増した。しかし、こうした生産量の増加に比べて古紙のリサイクルは進まず、古紙回収率は低下し、紙ごみの排出量は急増した。国内の消費供給量から回収量を除いた分が廃棄されたとして試算すると、昭和55年度の約880万トンから平成2年度の約1,430万トンヘと、10年間で紙ごみの排出量は約1.6倍になった計算になる(第3-1-31図)。
このように古紙回収率が低下したのは、60年からの円高の影響などから、古紙の輸入量が増大する一方、古紙の引き取り価格が低位で安定したことなどが大きな原因となっている(第3-1-32図)。特に、使用が急増したOA用紙については、回収システムが確立されていなかったこと、機密文書の取扱などの問題もあり企業も回収に消極的だったことなどから、回収利用は進まなかった。このため、古紙回収率は低下を続け昭和63年には47.5%となった。この間、製紙段階での古紙の利用率は低下しなかったが、この原料は輸入古紙により賄われていた。
また、カーボン紙、ビニールなどのコーティング・ラミネート紙、感熱紙などの複合素材が増加しているが、これらの素材が回収の際に混入すると、生産の過程で処理が困難となる。こうした複合素材の増加もりサイクルの障害となっている。
昭和63年になると、環境保全意識の高揚からリサイクルの気運が高まり、古紙の回収率、利用率は再び上昇し始め、平成3年の古紙回収率は50.8%に達しているが、今後、古紙価格の低位安定、再生資源業者の不振といった悪条件の中で、古紙の回収をいかに促進して行くかが課題となっている。
一方、再生紙の需要が広がらなければリサイクルは進まない。55年に神奈川県とF製紙(株)が古紙を70%使用した再生紙を開発したことにより、消費が急増するOA用紙など、従未は上質紙が使用されていた分野での再生紙の使用が始まった。再生紙は、バージンパルプ紙よりは紙粉が多く、白色度が低いなどの面もあったが、逆に、白い紙より目にやさしい、両面印刷時に乾きが早いなどの利点もあり、品質的には十分に使用し得るものであった。しかし、色の点などから再生紙のイメージが悪かったこと、購入量が少ないため価格が割高だったことなどから、当初、使用は広がらなかった。平成元年ごろからは、地球環境問題への関心が高まる中で、官公庁での使用が広がったことなどをきっかけとして再生紙の需要が拡大し始めた。しかしながら、なお、再生紙の価格が割高であることや再生紙を低級品と見てイメージの低下などを懸念する考え方があり、これが再生紙の利用の一層の拡大の障害となっている。
このように、現在、古紙のリサイクルには、回収、利用の両面で課題があり、リサイクルの推進のためにはこの両面での対策が求められている。
古紙の利用サイドにおいては、製紙メーカーの団体である日本製紙連合会が、向こう5年間で、古紙利用率を55%に上昇させるという「リサイクル55計画」を平成2年に打ち出しており、3年10月に施行された「再生資源の利用の促進に関する法律」の判断基準の中では、古紙利用率が6年度までに55%に向上することが目標とされている。こうした目標の確実な達成が求められる。
しかし、昭和60年代には紙の使用量は非常に増加しており、仮に、ここ数年と同じ傾向で生産量と消費量が増え続けたとすれば、古紙利用率55%が達成されても、製紙原科としての木材パルプの消費量と紙の廃棄量はなお増加し続けることになる(第3-1-33図)。資源採取量と廃棄量を減らし、経済の持続可能性を高めていくには、製紙メーカーによる古紙利用の推進のみならず、回収コストの低減、再生紙の需要拡大など社会経済全体としての取り組みが求められている。
本項では、我が国の物質収支をめぐる動きを見てきたが、経済規模の拡大や消費行動の変化などの中で物質消費量が増大する一方で、再生資源価格の低迷などにより、古紙やスチール缶について見たようにリサイクルには課題を抱えているものもある。こうした中で、自然からの採取、自然への排出量はともに増大しており、こうした面で我が国の経済社会の持続可能性の低下が懸念される状況となっており、その向上のための一層の取組が期待される。