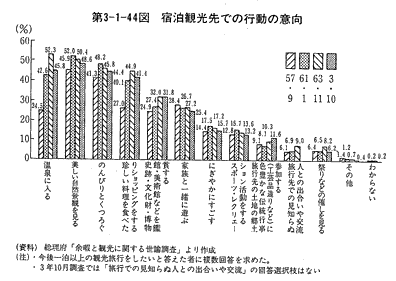
4 観光、余暇活動と自然の保護
(1) リゾート・ブームの背景
自然環境は、人類を含むあらゆる生物の生存基盤であるだけでなく、観光活動のいわば資本として、また、市民がそこで自然とふれあうことにより潤いや安らぎを見いだす場、あるいは感動等を得る場としても重要である。しかし、自然環境のこうした利用も、適切な配慮を欠くと環境破壊の原因となり得るものである。例えば、世界有数の観光地である地中海地域では観光施設の急速な拡大、観光客の集中により、水質汚濁、大気汚染、廃棄物の増大に悩まされている地域がいくつかみられる。アジアにおいても、例えぱネパールのヒマラヤトレッキングでは急増したトレッカーがごみを散乱していくという問題が生じている。我が国も例外ではない。過去を振り返ると、昭和40年代の観光ブームとそれを当て込んだ乱開発ブームは、各地で自然破壊を招き、大きな問題となった。そして近年のいわゆるリゾートブームでも自然破壊を懸念する向きが出てきている。
こうしたリゾート地の開発、特に近年のリゾートブームはどのような背景によって生じたのだろうか。
リゾートを需要する側の最大の要因は、余暇活動の拡大である。総埋府が行っている「国民生活に関する世論調査(平成3年5月調査)」を見ると、今後の生活の力点として、レジャー・余暇生活をあげている人がほぼ一貫して増加している。国民のこうした選択は、余暇時間の増大や所得の向上に伴うものである。余暇時間の便い道としては様々なものがあるが、旅行先の行動においては、自然とのふれあいを求める人が多い。世論調査によると、宿泊観光で何をしたいかについてみると、「美しい自然景観を見る」(48.6%)、「温泉に入る」(45.8%)は約半数の人が望む行動となっている(第3-1-44図)。こうした自然の中で身体と心を休め、日頃欠けている自然との一体感を回復したいという人々の欲求が、リゾートを求める要因となっている。
こうした需要側の要因のほかに、人々の訪問を受ける側、サービスを提供する側の要因として、過疎からの脱出という切実な願いを指摘することができる。平成元年における人口自然減の市区町村数は全国3246市町村のうち、1312市町村、40.4%に達する。特に農業地域で人口減少市町村が多く、山間農業地域では71.4%もの市町村で人口が減少している。このような過疎は、就業機会が少ないことに起因する若年層の村離れによるものとされ、いわゆるリゾート開発は就業機会を増加させ、地方に活気を取り戻す切り礼として歓迎された。このほかの供給側の事情として、宿泊施設やレクリエーション施設の整備、運営を行う企業の事情も大きい。こうした余暇社会への移行、一部の地方公共団体で見られたりゾートによる振興志向を踏まえ、多くの企業が、62年頃からの金余り現象の中での有利な投資先として、いわゆるリゾート産業へ参入してきた。また、リゾート開発が貿易黒字減らし(内外均衡)のための内需拡大策の一つの柱として公の支援を受けた事情もあった。こうして、60年代以降、次々とリゾートと呼ばれる地方観光施設の整備が進み、62年の「総合保養地域整備法」の成立を契機としてさらに大きな流れとなっていった。
(2) 観光・余暇活動の環境影響
このように盛り上がってきたリゾート開発であるが、これと自然保護との関係を心配する向きも生じてきている。総合保養地域整備法の目的にもあるように、そもそも「良好な自然条件を有する土地」かこうしたリゾートの基盤である。しかし、我が国の過去の事例や、諸外国の例が示すように、観光のための開発がその基盤である自然資源を掘り崩す可能性は否定できない。
まず我が国の過去の例をみてみよう。我が国では30年代後半から40年代にかけて観光ブームが訪れた。人々は様々なレジャーを求め、豊かな自然に触れようとする人も多かった。自然を求めて大挙して押し寄せた人々の存在は、皮肉にも、求めてきた自然を悪化させていった。
観光地に位置する湖沼では、水質の悪化が進み、透明度が低下していった。例えば阿寒湖では、大正6年(1927年)では透明度が8〜9mであったのが、昭和48年(1973年)には2.2〜5.6mに低下している。同様に富士箱根伊豆国立公園の芦ノ湖は昭和のはじめには透明度が13mであったものが、40年代後半には5m前後まで低下している。こうした汚濁の進行は、観光客の急増とそれに伴って湖周辺で急速に進んだ開発によるものと考えられている。日光国立公園内にある湯の湖における当時のBOD値の季節変化を見ると、夏季に高く、冬季に低い。これは観光客数が夏季に多いことと対応しており、夏季には自然的条件からBOD値が高くなる傾向にあるものの、湖沼の汚濁は当地を訪れる観光客によるところが大きいものと考えられた(第3-1-45図)。このため、これら各湖沼の水質の保全を図る目的で、特定環境保全公共下水道等の下水道事業が推進されてきた。さらに45年、自然公園法が改正され、国立公園の特別保護地区内の35の湖沼、湿原を指定し、こうした湖沼、湿原に直接又はこれらの湖沼へ流入する周辺1km以内の流水へ、排水設備を設けて排水を行う場合には、許可を必要とすることとされた。
また、当時の観光ブームの特徴の一つに、マイカーによる観光の増大がある。各地の観光地へのマイカーの集中によって、自動車の道路敷外への乗入れによる自然環境への悪影響や自動車の吐き出す排気ガスによる汚染も見られた。46年の長野県上高地で行った調査では、一酸化炭素の濃度が2.8ppmになり、これは当時の一般環境大気測定局の年平均値より若干高い値である。こうした自動車利用の増大による自然環境への影響等を懸念して、上高地へのマイカーの乗入れが規制されるようになった。また、北アルプス立山においても、山岳道路の開通時に、自然環境保全等の見地からマイカーの乗入れを規制することとなった。
このような40年代の観光ブームに見られた環境悪化は、観光客の急増と環境への配慮に乏しい受け入れ体制とによるものと考えられる。悪化した環境を元にもどすために、かなりの費用、労力が費やされた。こうした経験に学び、清澄な環境を保った形のリゾート開発を行うよう、細心の注意を払うことが必要である。
(3) より良いりゾートであるための課題
今日の状況を見てみよう。休日をリゾート地で過ごす人に向けたいわゆるリゾートマンションの建設は63年頃から飛躍的に増加し、新潟県湯沢地域など一部地域への集中が見られた(第3-1-46図)。こうしたリゾートマンションの建設は、環境への適切な配慮を欠いたり、環境保全のために必要な施設を整備しなかった場合、美しい景観が失われると指摘されたり、排出物の処理のための公共施設の整備が追い付かず、廃棄物の処理に困難をきたし、生活環境に悪影響を及ぼしているといった指摘がなされている。
国民の間にゴルフに対する根強い需要があることを背景に、リゾート開発にはゴルフ場を核とするものが多い。例えば「総合保養地域整備法」に基づく基本構想に盛り込まれている新たに整備予定のゴルフ場の数は増設を含めて約180箇所となっている。このようなことから、全国に約1700ヶ所あるゴルフ場の数も近年増加している(第3-1-47図)。ゴルフ場については、農葉による水質汚濁、広域にわたる地形、自然植生の改変、野生生物を含む生態系や景観の変貌といった自然への影響が懸念されている。こうした状況を背景として、平成2年度中に都道府県公害審査会等に係属した紛争(105件)のうち、ゴルフ場建設に係る事件は30件に達している。平成2年に、環境庁が定めた「暫定指導指針」に基づき都道府県は、ゴルフ場排出水の水質調査を行ったが、その結果によれば、大部分で農薬を検出しなかったものの、いくつかの検体で指針値を超える農薬が検出され、ゴルフ場に対する指導が行われている。また、ゴルフ場の総面積を制限するため、ゴルフ場の建設許可を厳しくしたり、農薬の使用量について業者側と自治体が協定を結ぶ例も見られる。
現在、総合保養地域整備構想に盛り込まれているリゾート計画においては、地域の特性を生かして、多種多様な施設整備が目指されているが、核となる施設はゴルフ場、スキー場、マリーナといった共通の施設が各地で見られるとの指摘もある。また、一方で自然とふれあいたいという人々の要求を満たしていくためには、非収益的な公共施設の充実も重要となっており、63年に日本観光協会が実施したリゾートに関するイメージ調査では、リゾートに必要な施設やサービスとして温泉や森林公園、自然遊歩道といった特別の道具などを使うことなく直接に自然とふれあうことができる施設を挙げる人が多いという結果が出ている(第3-1-3表)。
自然歩道や自然教育施設などの公共施設の整備は、自然地域の持続的利用という面で必要性がますます高まってきているが、整備予算の低さから立ち遅れており、今後の課題として取り組む必要がある。
また、リゾート開発の経済効果、収益見込みについては、冷静な評価が求められている。リゾート開発の中には、経済・社会情勢の変化にうまく対応し、地域振興に役立っているものもあるが、一部のリゾートにおいては、地元からの物品、労働力の調達がさほど見込めず、地元にとっての経済効果は一時の期待ほどは大きくないといった指摘もある。また、リゾート地の宿泊施設は季節ごとの入り不入りの幅が大きく、年間を通じてみると都市のホテルに比べて、客室利用の状況がよくないとの指摘もある(第3-1-48図)。リゾート開発が自然環境に及ぼす影響が懸念されている。環境への配慮を十分に行うとともに、地域の振興に役立つ開発のあり方をも冷静に見極める作業が必要である。
現在こうした状況を踏まえ、環境や自然との一体感を求める国民の要求に応え、地域の願いである地域の活性化を実現させるような開発を行っていくことが求められているといえよう。一時期のリゾート開発ブームともいえる事態が収まりつつある現在は、その良い機会である。
いくつかの先進国ではこうしたリゾート開発と環境保護に関する問題を既に経験している。特にヨーロッパ諸国では余暇活動の開花が日本より早く、いわゆるリゾートブームを以前に経験し、こうした問題への対処について、我が国より経験が豊かである。その例として、フランスのスキーリゾート開発がどのように変化してきたかを見てみよう。
フランスでは1936年(昭和11年)に有給休暇法が制定され、その後、1956年(昭和31年)に3週間、1967年(昭和42年)には4週間と有給休暇の日数が拡大していた。拡大する国民の余暇活動を受け入れるべく、夏のバカンス、冬のスキーのためのリゾートづくりが進められた。フランスのスキーリゾートは、4つの時期に分けることができると言われている。第1世代は、昔ながらの山村がそのままスキー場を中心とするリゾート地に変化している。山村の良さを残しているものの、計画性は欠いていることを意味する。第2世代は、より標高の高い土地に、スキー場を中心に、宿泊施設などが整備された人工的なリゾートである。第3世代では1968年(昭和43年)のグルノーブルオリンピックを期に拡大したリゾートブームを背景にし、統一的な計画、イメージのもと、大規模な統合型のスキーリゾートが作り出された。リゾート地の標高はさらに高くなり、例えば標高1,800m以上の森林限界を超えた山の岩盤の上に、宿泊施設、商店街、レジャー施設といった都市機能のすべてを収容した巨大建築物を建設し、大量の人々を効率的に収容した。強力な計画の下で統一的なイメージを持つ新しいリゾートになっているが、自然景観に巨大な人工物を持ち込み、自然環境保全上問題があると指摘された。第4世代は、1970年代(昭和40年代後半)以降自然保護への関心が高まってきた中で、第3世代のスキーリゾートが余りにも自然と対立的であったことを反省して、自然との共存を基本コンセプトに開発が進められたものである。スキー場の標高は第3世代まで一貫して高くなっていたが、第4世代の立地箇所は森林限界の下の比較的標高の低い所となった。建築物は地域の伝統的な農家を模し、森林より高い建物は建てないなど自然景観に調和するように作られている。こうした開発の基本方針は、第3世代に確立した強力な計画的整備手法によって担保され、乱開発は避けられている。また第4世代のリゾートは、施設とともに、様々な自然の中でのスポーツ、芸術に触れ合う機会を提供するなどソフトにも力を入れたものとなっている(第3-1-4表)。
平成4年の冬季オリンピックはフランスのアルベールビルで開催されたが、自然との調和を基本テーマとして開催された。既存施設を利用し、不要な施設はオリンピック開催後には撤去するなど、不必要な巨大施設の新設は極力避けられ、自然への新たな圧力と過重な財政負担を避ける運営がなされた。その背後には、グルノープル才リンピックで大きな赤字を出したことへの反省とともに、スキーリゾート地に関する考え方が、第4世代に入り、自然との協調を重視するようになっていることがある。フランスの経験が全て我が国に有用であるとは考えられないが、フランスというリゾート先進国の失敗の轍を踏むことなく我が国なりのリゾート開発が考えられていくべきである。自然との調和は、リゾート整備の基礎に位置付けられなくてはならない。我が国でも、いくつかの自治体では、リゾート地の整備に備え、自然環境保護条例等を策定し、環境破壊を未然に防止しようとする動きが見られる。地域振興の観点からも、短視眼的な開発は必ずしも経済的ではない。地域に残された数少ない比較優位のある資源である豊かな自然を浪費するようなことなく、地元の農林水産業の活用も含め、地域の環境、文化を生かす幅広い視点での地域振興を考えていくことが必要となろう。リゾート開発はその中の選択肢の一つと位置付けられるべきものである。