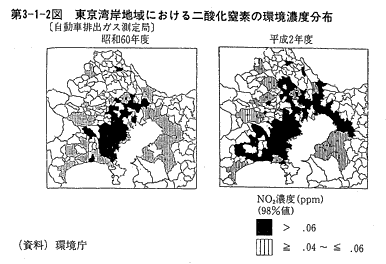
1 大気への負荷の増大
(1) 大都市圏における窒素酸化物汚染の悪化
第1章で見たように、東京、横浜や大阪といった大都市圏では、近年、窒素酸化物による大気汚染の改善がはかばかしくなく、悪化傾向も見られ大きな問題となっている。環境基準の達成状況をみると、大都市地域においては、一般環境大気測定局では約半数の測定局で、自動車排出ガス測定局では大多数の測定局でそれぞれ環境基準が達成されておらず、また、達成されている測定局の比率は、近年では概して減少傾向にある。汚染地域の広がりについてみても、環境基準を超過している地域が拡大していく傾向が見られる(第3-1-2図)。
これは、自動車交通量全体の増加と、その中でのディーゼル車の比率の増加などが、自動車一台ごとの排出ガス規制の効果を打ち消していることによる。
自動車交通量は、走行距離数(第3-1-3図)や自動車保有台数の増加(第3-1-4図)に表れているように、消費の高度化に伴う自家用車の増加や貨物輸送における自動車依存の増カ加によって着実に増加している。全国平均で見ても、世帯ごとの自動車保有率は75%を超え、また、約30%の世帯が複数の自動車を保有している。利便性を重んじる宅配やジャストインタイム方式の増加も自動車による貨物輸送の増加の一因となっている。また、交通量が増加する中で、大都市圏では、交通混雑が慢性化しており、東京都と大阪府では、昼間の交通量の平均値が道路の交通容量を超過する状況となっている。こうした道路混雑は、交通の効率を悪化させ、交通量当たりの窒素酸化物などの排出量を増加させることになる(第3-1-5図)。
一方、車種についてみれぱ、ガソリン車よつも窒素酸化物排出量の多いディーゼル車の増加が著しい。特にトラック・バスについては、ディーゼル車の占める割合が、昭和60年に50%を超え、平成元年度には約65%に達している。ディーゼル車の中でも、副室式に比べて窒素酸化物排出量の多い直噴式ディーゼル車が急速に増加しており(第3-1-6図)、このような傾向が定行自動車一台当りの窒素酸化物排出量を増加させている。ディーゼル車の燃料の軽油は、ガソリンに比較し、税額や取引形態等の差から小売価格が安価である。こうした軽油の価格に加え、ノンテンスの容易さ、燃費効率が良いなどの面での経済的な優位性がディーゼル化の大きな原因となっている。環境保全の観点からは、このような経済的要素と環境との関係についても検討を加える必要がある。
このような中で、窒素酸化物汚染を改善すべく、自動車一台ごとの排出ガスについては、平成元年12月の中央公害対策審議会答中「自動車排出ガス低減対策の在り方について」に基づいて規制強化が行われ、ディーゼル車を中心に今後10年以内に窒素酸化物排出量を3〜6割低減させていくことになっている。また、この規制強化を早期に実現するため、ディーゼルエンジンの窒索酸化物対策の一環として、エンジンの技術開発や軽油中の硫黄分の低減のための真剣な努力が行われている。この規制強化がなされると、交通量が昭和60年の水準に抑えられている場合には、東京地域などの汚染レベルの高い地域においても、地域全体の窒素酸化物排出量については、環境基準を概ね達成できる排出量を下回ると推計される。しかしながら、このまま交通量の増大が続くと、大都市地域の窒素酸化物汚染の十分な改善は期待できず(第3-1-7図)、自動車利用の在り方にまでさかのぼる強力な対策が求められている。政府としては、こうした状況を踏まえ、詳しくは各論第2章第2節で見るとおり、「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法案」を国会に提出した。
(2) 二酸化炭素排出量の増加
地球温暖化は、人間活動に伴う二酸化炭素、メタン、亜酸化窒索等の排出により、大気中の温室効果ガスの濃度が上昇して温室効果が強まり、気温が上昇し、人類や生態系がその基盤をおいている気侯が変動することをいう。現在、国際的に、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出抑制が重要な課題となっている。IPCC報告書によれは、温室効果ガスの増加要因としては、石灰石の使用に伴う二酸化炭素の排出、森林伐採等による二酸化炭素吸収源の減少、バイオマス燃焼等によるメタン、亜酸化窒素の排出等も重要であるが、二酸化炭素は人間活動による地球温暖化への寄与の55%を占め、このうちエネルギー消費に伴う排出が約8割を占めるとされており、エネルギー消費に伴う二酸化炭素の排出は、人間活動による地球温暖化の要因の中で最大のものと考えられている。
我が国では、昭和61年度以降エネルギー消費量が増勢に転じている。このため、エネルギー消費に伴う二酸化炭素排出が、近年増加している。我が国は、GDP1単位の生産に要するエネルギー消費は他の先進国より小さく、これに合わせて二酸化炭素排出量も経済現模に比較して小さいものとなっており、エネルギー消費の構造は、環境の観点から見て他の先進国より効率の良いものとなっているといえる。この背景には、第二次石油危機以降産業部門における省エネルギー化が進んだこと、工ネルギー価格が比較的高いこと、他の先進囲に比ベ暖房需要が少ないこと、地形等の要因によりエネルギー効率の高い鉄道や内航海運への依存度が高いことなどがある(第3-1-8図)。
これまでのエネルギー消費起源の二酸化炭素排出量の推移を見ると、48年の第1次石油危機以降、産業部門をはじめとした各界の省エネルギ一努力や製品の高付加価値化によりGDP当たりのエネルギー消費(以下「エネルギー集約度」という)は低下を続け、エネルギー消費及びエネルギ一消費起源の二酸化炭素排出量ははぼ横ばいで推移し、一人当たり排出量は減少傾向を示した。しかし、61年度以隆、エネルギー集約度の抵下傾向が鈍化し、一方経済活動も活発化したことから、エネルギー消費及び工ネルギー消費起源の二酸化炭素排出量は増カ加に転じた(第3-1-9図)。環境庁の試算によれぱ昭和61年度から平成2年度に排出量は19%増加し(年率平均4.4%/年)、一人当たり二酸化炭素排出量は昭和48年度の水準に到達している。政府が平成2年に定めた「地球温暖化防止行動計画」は、二酸化炭素については、一人当たり排出量について2000年以降概ね1990年レベルでの安定化を図るとともに、革新的技術開発等が現在予測される以上に早期に大幅に進展することにより、排出総量が2000年以降概ね1990年レベルで安定化するよう努めることとしているが、平成2(1990)年度の排出総量の対前年度伸び率は、同じく環境庁の試算によれば3.8%%と依然として高く、厳しい状況となっている。
こうしたエネルギー集約度低減の鈍化傾向は個別の経済活動においても見ることができる。例えは自動車の消費動向をみると、排気量の大きい大型車の販売が増加し、上昇を続けてきた新車の燃費も全体としてみれぱ低下に転じている(第3-1-10図)。家電製品の消費電力も、近年、低下が止まっている((第3-1-11図)。ビルにおける冷暖房の設定温度をみても、省エネルギーが停滞している(第3-1-12図)。また、産業部門においても石油危機時代に急速に進行した生産物量当たりのエネルギー使用量の低減が近年停滞している(第3-1-13図)。
こうした傾向の背景には、石油危機以降高騰していた原油価格が、昭和60年頃からOPEC(石油輸出国機構)による生産調整の体制が崩壊したことや円高の影響により暴落し、石油危機以前の水準よりも実質的には低くなっていることがある(第3-1-14図)。石油の価格が低下し、また、省エネルギーが進み製造原価に占めるエネルギー経費の割合が下がったため、民間の省エネルギー投資は56年度をピークとして低下を続けている。
企業は、競争市場の中で活動している以上、投資によって省エネ型設備導入などによる省エネルギー対策をとるか否かの意思決定は、その投資が全体としての生産コストを低減させるか否かを基準として行われる。すなわち、対策によるエネルギー消費量の削減がもたらす燃科費用の節約効果などと、設備導入などの投資コストとを比較し、前者の方が大きい場合に限って対策が行われる。このような企業の意思決定過程において、理屈の上では、設備の耐用年数全体で省エネルギー投資が引き合えば良いはずだが、これまでの実際の企業行動においては、投資のコストが約2年以内に回収されないと対策が行われていないという指摘もなされている。このように、実際の省エネ投資実施の意思決定に当たっては、燃科費用がどれだけ節減できるかが投資が行われるかどうかの大きな鍵となっているが、理論的な損益計算以上に優れた燃科費用節減効果が要求されている。このため、二酸化炭素の排出抑制に資するような企業の行動は、省エネルギー投資としては、取られにくい面もある。
また、家庭においては、上記の企業のような厳密な損益計算は行われないものの、その行動にはエネルギー価格が大きな影響を及ぼしている。例えば、太陽熱温水器の普及が近年停滞していることにも見られるように、日常生活においてエネルギー消費を節約し、省エネ型の商品を購入するかどうかは、それにより節約できる費用の大きさにより決められる部分が大きく、エネルギー価格に大きく影響される。
前述したようなエネルギー消費量の動向の要囚を考えるために、例えば、エネルギーの中で大きな比重を占めている石油消費量に着目して、部門ごとにその変化を見てみる。石浦の消費量は、原油価格の動向を反映して、昭和48年度までは増加、48年度から60年度までは概して停滞もしくは徴減、60年度以降は増加してきた。これらの期間ごとに部門別の石油消費量の変化を見てみると、製造業部門の消費量は48年度から60年度までの石油価格が高水準にあった時期には減少したが、60年度以降再び急速に増加している。また、運輸部門の消費量は一貫して増加しており、60年度以降増加が加速していることが分かる(第3-1-15図)。
我が国の平成2年度の二酸化炭素排出量の内訳を見ると、環境庁の試算によれぱ第3-1-16図のようになっている。我が国の排出総量316MtC(炭素換算百万トン)のうち、エネルギー消費によるものは、292MtCとなっている。発電に起因する排出量を電力消費に応じて転嫁して各部門について見ると、鉄鋼や窯業土石に代表される産業部門は排出総量の約半分の約48%を占め、前年度に比べ3.3%伸びている。家庭のエネルギー消費などの民生部門は、シェアは約23%(家庭12%、業務11%)と産業に比べ低いものの、伸びは対前年度5.0%と高いものとなっている。また自動車の排出量が約9割を占めると推定される運輸部門(家庭のマイカーも含む)についても、シェアは約19%であるが、その伸びは対前年度4.4%増と高い。
このように、エネルギー消費は人類の経済活動を支える一方で地球温暖化の原因となる二酸化炭素を排出している。近年、エネルギー消費に伴う二酸化炭素排出量が増加しており、人類社会の持続可能性への影響が懸念される。
また、エネルギー起源以外の二酸化炭素排出には、石灰石の分解や廃棄物の焼却によるものなどがある。環境庁の試算によれぱ、石灰石からは平成2年度に、12.7MtCが排出されているとみられる。廃棄物の焼却による排出の見積は困難であるが、一般廃棄物の焼却物からは2年度に8MtC程度の排出があったと推計される。しかしながら、廃棄物起源の二酸化炭素の中には、紙、木片等、生物が大気中から固定したものがかなり含まれている。
以上、我が国の二酸化炭素排出について分析してきたが、この排出抑制のためには、上記の試算に見られるとおり、産業、民生、運輸の各部門を通じた幅広い分野での強力な取組が推進されなけれはならない状況となっている。また、地球温暖化対策としては、これに加えて、メタンや亜酸化窒素等の排出抑制や二酸化炭素の吸収源の強化等に対する取組も推進していく必要がある。さらに、地球温暖化のメカニズムの解明等に関し、今後、科学的知見の一層の充実が求められている。
「地球温暖化防止行動計画」では、こうした状況を踏まえ、都市構造、交通体系、産業構造、エネルギー供給構造からライフスタイルに至る分野での各種の二酸化炭素排出抑制対策を始めとして、メタンその他の温室効果ガスの排出抑制対策、二酸化炭素の吸収源(森林等の緑)対策、科学的調査研究、観測・監視の推進を含む幅広い温暖化対策が盛り込まれており、こうした広範な対策の着実な推進が必要となっている。