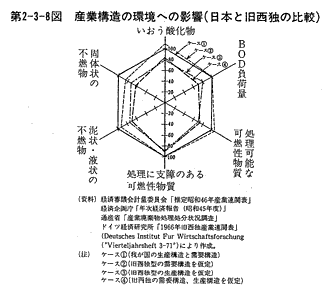
2 企業の努力とその成果
日本では、環境政策が大きな成功を上げたと言われる。
日本における戦後の驚異的復興は「日本の奇跡」と言われるが、激しい公害問題を短期間で克服しながらも企業経営及び経済全体に対して深刻な影響を生じなかったことが「日本のもう一つの奇跡」と評されている。この節では、この「日本のもう一つの奇跡」が生じた理由を明らかにするため、公害防止に貢献した企業活動として、企業の直接的な努力と考えられる公害防止投資活動及び公害関連技術開発、さらに、結果として環境保全に資することとなった省エネルギーと産業構造の変化をとりあげ、我が国の企業の努力を振り返ってみた。これによると、経済活動を所与のものとして放置したまま公害防止が図られたのではなく、規制の長期的・計画的な強化、政策金融等による支援、低公害型の製品を受け入れる市場の整備などの工夫を凝らした政府の施策の下で、企業の積極的努力が起こり、市場経済の活力が積極的に生かされた結果、すなわち、経済社会のメカニズムが環境保全的なものに変わっていく中で、公害防止に配慮した成長が行われるようになったと言えよう。
(1) 石油危機を契機とした産業構造の変化と省エネルギーの進展とによって後押しされた公害克服
? 産業構造の変化と環境
産業構造の高度化が進展していく過程では、環境と深い係わりを持つエネルギー消費や用水使用等の状況にも変化が見られた。
昭和47年当時の経済白書では、我が国の産業構造が旧西独の産業構造と比較し汚染の発生のしやすさがどの程度異なったかを分析している。この分析では、経済構造を構成する要素として、産業構造(投入・産出構造)と需要構造を取り上げている。経済活動を構成している様々の産業部門の生産活動は原料、中間財、最終製品などの取引を通じて相互に複雑に関連しあっており、これら関連のメカニズムは各国によって差があるが、ここでは、これを産業構造(投入・産出構造)の差としてとらえている。また、生産活動を誘発する個人消費、民間設備投資、輸出などの需要の内容も各国それぞれ異なっているが、ここではこれを需要構造の差としてとらえている。このような考え方の下で、生産活動に伴う汚染因子発生量を旧西独と比較した場合、需要構造の違いよりも生産構造の差によって1割程度汚染因子の発生量が多いという計算結果が得られた(第2-3-8図)。このことから、我が国の汚染発生を増加させる経済構造上の要因には、生産構造に起因する部分があったと言うことができよう。
我が国の高度経済成長においては、第2次産業、中でも基礎素材型産業がその索引車的役割を演じていた。48年、54年の2度の石油危機による石油価格の急沸は、全エネルギーの4分の3を輸入石油に依存していた我が国産業に大きな衝撃を与えた。生産とエネルギー消費の動向を業種別に見ると、40年代前半までは全ての業種について生産、エネルギー消費とも大幅に増大しているが、50年以降については、エネルギー消費量の相対的に小さな機械工業等加工組立型産業の生産が大幅に増加している一方で、化学、鉄鋼等の基礎素材型産業ではエネルギー消費原単位の低下は顕著なものの生産の伸びの鈍化が著しい。エネルギー・原材料コストの製造原価に占める比率の高い基礎素材型産業では、生産コストの大幅な上昇、内需の落ち込み、相対的な国際競争力の低下等により、生産・出荷の伸びが鈍化し、縮小・合理化が進められた。一方、電子部品、精密機械に代表される加工組立型の産業は、先端技術製品の開発等による需要創出に加え、輸出の堅調な伸びもあって、出荷を着実に拡大し、製造業におけるウエイトを高めていった(第2-3-9図)。このような生産構造の変化による、高付加価値・高機能型の加工組立型産業への産業構造の変化は、市場原理に起因するものであって環境保全上の意図から生じたものではないが、結果的には、付加価値を増加させつつ、全体として生産量当たりの環境への負荷量を減らすこととなったと考えられる。
? 省エネルギー・省資源気運の高まりと環境
省エネルギー・省資源は、その大宗を輸入に依存している我が国にとって独自の努力によってエネルギーや資源の量的制約を緩和しうる手段であって、企業にとってはコストの制約に直接結び付くことから、コスト節約という純粋な経済行為として行われてきた面が強い。我が国企業は、二度の石油危機を契機として省エネルギー・省資源のための大きな努力を払ってきた。国民総生産で見ると昭和48年度から62年度までの14年間で1.7倍の拡大となったが、エネルギー需要は、ほぼ横ばいで推移しており、この間のマクロ的なエネルギー生産性(1単位のエネルギーによって生み出される産出額)は1.65倍に向上している。特に、製造業におけるエネルギー生産性を見ると、同期間で1.8倍と産業全体のエネルギー生産性の改善を上回る改善が行われた。
また、40年代には大幅に増大した用水使用量も、その増加が抑制されてきている。用水には淡水及び海水があるが、このうち淡水使用量には新たな水使用となる補給水量と、一度使用した水を再利用する回収水量が含まれる。淡水使用量に占める回収水の割合を占める回収利用率の推移を見ると、40年の36.2%から56年の73.9%まで大幅な上昇を示しており、用水使用量の伸びの低下とあいまって補給水量は49年以降減少している(第2-3-10図)。
こうした省資源・省エネルギー等に向けた企業努力によるコスト削減は、企業の体質を強化するとともに、加工技術の向上とあいまって国際競争力を高め、輸出を増加させ、石油危機のもたらした不況をいち早く脱し、安定成長経路へと経済を軟着陸させるのに寄与した。
省資源・省エネルギーは、各種汚染物質の潜在的な発生量そのものを減らす性質を持っている(第2-3-11図)。例えば、回収水量の増加は、河川の流量を減らさないことに役立つほか、回収を行う企業における水の管理や使用後の水の処理を徹底させ、結果として、水域に流出する汚濁負荷量を減らすことに役立つ。我が国における公害問題の克服は、たまたま生起した石油危機への対応の中で進められていったが、このことが、企業の投資額を短期的に増幅させた反面、経済的動機から生じた全産業あげての省資源・省エネルギーへの取組が、本来の直接の目的ではなかったにせよ結果的には「環境保全」に大いに貢献したことも見逃せない。我が国における公害の克服に際しては、対策の一部は経済的に引き合う対策として行われていたのである。公害を克服するに当たっては、このように別の見地から必要とされる対策と連携を取ることが有効であると言えよう。
なお、エネルギーと資本の相対価格を見ると、エネルギー相対価格は58年以降低下に転じており、平成2年には、ほぼ第2次石油危機前の水準にまで低下している。このため、石油危機後にエネルギーの割高感が強まったことが資本設備の省エネルギー化の要因となったのとは逆に、エネルギー割安感が資本設備の省エネルギー化のテンポを鈍化させ、ひいては環境改善を減速させる要因となることが懸念される。
(2) 積極的な公害防止投資がなされた背景
? 産業公害が激化した当時の経済状況、企業の財務状況と公害防止投資動向との比較(第2-3-12図、第2-3-13図)。
昭和30年代から40年代央にかけての高度経済成長期には、技術革新やスケールメリットを追及して高水準の設備投資が行われ、消費も拡大を続けた。この次期の我が国経済の成長速度は世界に類のない高さにあった。45年まで実質経済成長率(年平均増加率)は10〜11%前後と、欧米先進国のほぼ2倍を上回る成長を長期にわたって続けてきた。企業の財務状況も良好で着実に内部蓄積を重ねていった。
48年秋の石油危機により、経済活動に欠かせないエネルギーの価格は大幅に上昇し、我が国経済はいわゆる「新価格体系」に移ることを余儀なくさせられた。さらに、この石油価格の上昇に伴う所得は海外に流出し、国内の購買力は減少した。こうした中で不況下の物価上昇、いわゆるスタグフレーションが起こり、さらに買いだめ・売り惜しみといった経済混乱も生じた。こうした事態に対応して採られた総需要抑制策により、我が国経済は、49年度に戦後初めてのマイナス成長を体験した。これに伴い企業の財務状況も急激に悪化した。なお、52年以降、経済は回復の兆しを見せ始め、経済成長率は高度経済成長時代に比べれば約半分の年5%程度に低下したものの依然として欧米先進国を上回る安定成長を続けており、55年に国民総生産は1兆ドルを超え、昭和62年には一人当たり国民総生産の額でアメリカを抜き、国民総生産の大きさそのものについても世界1位のアメリカとの格差が縮小しつつある。
高度経済成長の過程で我が国経済はその歪みというべき深刻な公害問題に直面することとなった。しかし、高度成長期を通じて国民の間では経済的福祉の追求に重きが置かれ、企業はもっぱら経済効率の改善を追求し、生産活動によって生ずる環境汚染については規制等の外部的要因がない限り防止策を講じる動機も必要性も乏しく、また、公害に対する科学的知見の水準が低かったこともあり、高度成長の末期に至るまでは公害防止投資は低い水準にとどまっていた。
48年秋の石油ショックに深刻な経済状況の下で、企業の設備投資額は48年以降52年まで減少している。このような状況の下、公害防止投資額も50年度をピークとして減少して行くが、設備投資額に占める公害防止投資の割合(以下、「公害防止投資比率」という。)については40年代半ばから増加を続け、特に49年から51年までは20%近くの極めて高い水準で推移していた。40年代前半及び55年以降の水準が2〜3%であったことを考え併せれば、企業をとりまく経営環境の厳しさから、生産には直接につながらない投資である公害防止投資についてはむしろ後退が予想された次期に、逆に高水準で推移していたことになる(第2-3-14図)。
石油危機の影響で既に経済が混乱状態にあったところに多額の公害防止投資や公害防止設備の運転費用の支出を強いられ、企業経営に生じた影響はかなり深刻なものとなったと考えられる。この厳しい経営状況の中、日本の企業は公害防止投資に対して世界にも類を見ないほどの努力をした(第2-3-7表)。また、この努力の結果は、環境に如実に反映した。汚染濃度の改善はもちろん、国民からの評価として、発生源別苦情件数の推移を見ると、公害発生型企業が含まれる製造事業所の改善度が他に比較し高かったことからもこの点は裏付けられよう。
なお、50年以降公害防止投資額は急激に減少していくが、この背景として、成長率の低下による新規の設備投資が減少したことが挙げられるが、公害防止投資比率も減少しており、これには、かつて激甚であった硫黄酸化物やばいじんなどによる大気汚染対策がおおむね軌道に乗り、民間需要の大きな部分を占めていた重油脱硫装置、排煙脱硫装置などの設置が一巡したことがあずかっていると考えられる。
? 企業が公害防止投資を決意した動機と規制
個々の企業にとっては、環境破壊に伴い企業の外部に発生するおそれのあるコストは不明であり、予想される社会費用、例えば損害賠償額とこれを回避するための公害防止コストを比較して、自主的、合理的な判断の下に公害防止設備を設置するという判断を欠くのが常態である。そのため、企業の自主的行動に任せていたのでは、生産に直接結び付かない公害防止投資は回避されることはあっても、積極的に促進されることは難しい。実際、NHKの行った一流企業100社の社長に対するアンケート調査から公害問題に対する経営者の意識の変化を見ると、第2-3-15図のとおり、45年当時は半数近くが公害の発生をやむを得ないものとしていた。しかし、公害反対の世論の高まりや政府による規制強化が進んだ2年後の47年では、経済成長を抑えても公害防止に努めるべきだとしているものが6割となった。
規制、官公庁の助言指導、住民の苦情などの外部的要因が企業行動の変化の大きな要因となったことは、公害防止投資の実施動機についての調査結果にも示される。例えば、東京都環境科学研究所が都内企業3000社を対象に実施したアンケート調査によると、公害防止投資の動機は「規制の強化」、「官公庁の助言指導」、「住民の苦情」などの外部的要因が8割以上を占めており、「企業独自の意志から」というよりも規制等による外部からの圧力が公害防止投資の最大の要因となっている状況が見てとれる(第2-3-8表)。また、環境庁が中小企業庁とともに実施した「中小企業公害防止投資動向調査」からも同様の結果が見られる(第2-3-9表)。このほか、規制等外部的要因の返還と我が国全体の公害防止投資額の推移を比べてみると、両者の間に密接な関係がある(第2-3-16図)。
公害防止投資も設備投資の一種であり、相当の費用を投ずる必要があるものである以上、景気動向を始めとする経済環境の変化に応じて公害防止投資額が左右されるのは事実である。しかし、設備投資動向と公害防止投資動向を比較すると、前述のとおり、石油危機の直後の時期では全体の設備投資額が伸び悩む中でも公害防止投資は突出して実施されており、この時期には、業況よりも、激化した公害に対応し後追いで急速に強化された規制等の外部的要因が、企業に公害防止投資を実施させる大きな要因となったものと考えられる。こうした経験から見ると、企業の意思決定がどうあるべきかを示す明確なシグナルが与えられることが、環境の保全にとって極めて重要と言えよう。
(3) 企業における公害対策費用の負担の実態、負担感と対策費用の調達
? 公害対策費用の負担実態と負担感
公害防止投資が企業収益をどの程度圧迫したのか、どれほどの負担になったかについては、経営者の主観的判断によるところも大きく、また、ここの業界、個別の企業の体力やその他の様々な事情により異なるため一般化するのは非常に難しい。このため、大胆な仮定を置いて、業種別に公害対策費用の負担の程度の評価を試みた。なお、試算した公害防止費用には、設備投資を要しない形での公害対策、例えば一部の燃料転換や公害防止のための研究開発に要する費用については、資料上の制約があり含めていない。ここでは、別途の統計がある公害防止設備の初期投資額に基づき、この投資に係る減価償却費(年10%と仮定)、金利(年10%と仮定)及び運転費(設備投資額の年20%が毎年必要と仮定。)の合計額を公害防止費用として算出した。この試算は、各業種(資本金10億円以上の企業に限る。)について行ったものであり、個々のプラントごとの公害防止費用を積算したものではないことに注意を要する。
試算の結果は、第2-3-17図のとおりであり、汚染の原因となる可能性が高い業種では、特に、50年前後の公害防止投資の負担度は、公害防止投資を実施しなかった場合に生じたであろう利益を半減させるほどのかなり大きなものであった。「企業が血を流すような努力をした結果、公害防止が進んだ。」と言われることがあるが、この50年前後の状況はこの表現に近いものがある。規制等の外部的要因への対応のため、短期間で汚染物質の排出を抑制するために我が国企業は損得を省みず全力を尽くしたと言えよう。
しかし、このことは見方を変えれば、それに先立つ時期に公害防止投資が不足であったことを示している。公害防止投資額が増加していった40年代には、第2-3-13図に見るとおり、公害防止投資にもかかわらず企業の利益率はなお高かった。高度経済成長期に早めに十分な投資を実施していれば、環境の悪化も未然に防げ、かつ企業にとっても一層軽い負担感で公害防止投資を行えたことを示している。順風満帆の経済成長の中でこそ公害対策への配慮が必要であり、効果的なのである。
公害防止費用の経営への影響度は業種別で様々であるだけでなく、企業の規模によってもその強弱の度合いが違う。
例えば、東京都環境科学研究所が55年度に(社)中小企業診断士協会に委託して行った「財務分析による公害防止投資の影響度」調査結果によれば、企業の規模と経営に対する影響度との間の相関関係が認められる。企業の利益の大小を示す「収益性分析項目」及び企業の安定度を示す「財務流動性分析項目」の両者について、規模が小さくなるほど公害防止投資の影響度が大きくなっており、逆に、規模の大きい企業では、公害防止投資費用の負担力と吸収力が大きいため、その影響はほとんど財務諸表上に現れていない(第2-3-10表)。
大企業の経営と公害防止費用の負担との関係を示す一例として、大企業のみによって構成されている電力業界の場合を見てみよう。電力業界9社を対象とした、50年当時の公害関連コストの経営に与える影響予測(第2-3-18図)に見られるように、公害規制の強化は営業利益率に深刻な影響を与えるものと懸念されていた。しかし、この後の実際の営業利益率(実績値)の推移を見ると、石油危機直後の大不況時は別としても、度重なる規制強化にもかかわらず順調に利益率は伸びていったことがうかがわれる。このように規制強化の最中に試みられた企業の経営への影響予測と実績地との間の差があることは、公害対策の実行局面では、合理化、高付加価値化等の経営努力のほか、公害対策費用の価格への転嫁、公害防止機器の性能向上によるコストパフォーマンスの向上等により、公害防止費用が企業の財務状況に影響しなかったことを示すものである。結果的には、経営資源を大量に保有し、豊富な選択肢を持つ企業であるほど、当初考えられていたほどには公害防止投資が大きな負担にはならなかったと考えられる。経済の成長に伴い生じる公害への対策は、成長自体が生み出す経済的果実によって賄い得たことをこの日本の経験が示している。
? 公害対策費用の資金調達
高度経済成長から石油危機前の経済環境が良好な時期においては、高度経済成長を通じて蓄積された潤沢な内部資金及び低利の借入れによって、企業は公害防止投資を実施することができた。他方、その後の石油危機による収益減少に起因する内部保留の低下、一連の総需要抑制政策による高金利の状況では、元来より自己資本比率の低い日本企業が非生産的な公害防止投資に対する資金を外部から調達することは非常に苦しかったと言えよう(第2-3-19図)。しかし、40年代後半以降逐次強化されていった規制等への対応から、外侮からの資金調達に頼りながらも公害防止投資を実施することに迫られた。
民間の商業銀行は、収益を生み出さない公害防止投資に対しては必ずしも熱心に融資するわけではないため、政府系金融機関等の特別な金融機関が利用できることが公害防止投資の資金調達面において役立った。この時期の、政府系金融機関の融資額の公害防止投資額全体に占める割合を見ると、これら期間による設備投資資金融資額が設備投資額総額に占める割合に関してはそれほどの変化がないことに比較し、公害防止設備投資資金融資額が公害防止投資額に占める割合については大きく伸びている(第2-3-20図)。公害防止投資の実施に際しては、政府系金融機関からの長期的かつ比較的低金利の融資に民間の企業が相当程度依存していたことが見てとれる(第2-3-11表)。公害防止投資を行う上での障害の一つとなり得る資金調達に関し、政策的配慮を行うことが有効であった。
低利の外部資金に一時的に依存することができたにせよ、それを長期にわたって返済するなどの形で、公害対策費用は企業が結局は負担しなければならないものである。必要な費用を企業はどのように捻出したのであろうか。
まず第1に考えられるのは、製品価格への転嫁であるが、公害防止投資額が最も大きかった時期が石油危機直後と重なるため、価格上昇のうち、公害防止関連支出の転嫁分と石油危機に起因するいわゆる狂乱物価の影響分(例えば燃料高、商品の需給関係等)とを厳密に判別することはできない。しかし、民間企業を対象とした「公害関連の費用増加への対応策」に関する東京都の調査結果(前出)によると、業種によるばらつきはあるものの、一般的には負担が非常に大きい企業では「利益を圧迫」したり「製品価格への転嫁」をしたりするケースが多く、負担の程度が低い事業場では、他の経費の合理化により吸収し価格への転嫁はほとんどなされなかったことが分る(第2-3-21図)。また、規模別にみると、規模が大きい企業では「合理化により吸収」するケースが多いが、規模の小さい企業では「利益を圧縮」したり「価格点嫁」したりするケースが多い。規模の小さい企業にとっては、経営努力の余地が限られ公害防止にかかる費用は経営努力では克服しきれずに、かなりの負担になっていたと考えられる。また、中小企業庁の調査によっても、「合理化」、「売上増加」によって公害対策費用を吸収することについては予想以上に進んだが、価格転嫁については当時の経済状況から見て思うように進まなかったことが見てとれる(第2-3-22図)。我が国の公害対策では、公害対策努力の企業間の配分に当たっては、一般に、大規模な施設に対して比較的に厳しく、小規模な施設に対しては比較的に緩い規制基準を適用している(第2-3-23図)。また、政策的な融資においても中小企業への特別な配慮がなされている。これは、施設が大規模になるほど公害対策にも規模の経済が発揮されることを考慮しているためであるが、公害対策の立案において企業の状況をきめ細かく考慮に入れていくこのような手法が必要であったことは、これらの調査の結果でも裏付けられよう。
なお、企業利益を極度に圧迫すると株主配当や労働分配率が低下したり、将来の技術革新への投資が減少したりして、社会にとっても損失となる。実際にどの程度の損失が社会に生じたかは国民経済全体についての分析を要するが、本来、公害防止費用は価格に転嫁され、その消費者によって負担されるのが望ましく、消費者側の意識の向上、特に、環境対策を十分に講じている企業の製品への選好の高まりなど消費行動の改善が今後の環境政策に当たっては大いに望まれるところである。
(4) 積極的な環境保全技術の開発がなされた背景
昭和40年代後半から50年代前半にかけて我が国の民間企業において公害防止技術の開発が飛躍的に進んだ。その背景には、一方で、公害問題における世論の高まり、技術評価を通じた将来的な技術的対応可能性を踏まえた国・自治体による適切な水準の規制・指導の実施や技術開発への支援、他方で、そのような規制・指導を遵守するための企業における技術開発への取組があったものと考えられる。総理府の調査によると、環境規制の強化が集中して実施された40年代後半から50年代初めにかけて環境保護関係研究費が飛躍的に伸びている(第2-3-24図)。政策選択の結果が技術の開発動向にも影響した様子がうかがえる。
過去の事例を顧みると、上記の要因が適切に組み合わされた場合に優れた実績をあげてきている。すなわち、企業が技術的に対応できないような過度の規制を実施する場合には、米国のマスキー法に企業が対応できず結局失敗に終わったように、対策技術の開発普及につながらない。他方、明確な規制基準が設定されず、企業自身の判断により環境関連の技術開発が進められている場合には、環境保全技術開発が経営環境の変化に左右されやすい。例えば、環境保全に資することが古くから知られている太陽電池及び電気自動車について率先して取り組んだ企業について見てみると、これらの分野においては「規制」という共通の前提がなく、常に「技術開発が市場に受け入れられるか否か」、また「商品が市場で競争力を持つか否か」によって技術開発の促進が左右される面が強い。すなわち、外国為替相場や石油価格の動向を始めとする経済環境の変化にその開発の促進度が大きく左右された。日本の太陽電池生産量の推移を見ると、第1次石油危機以降急激に伸びてきたが、内需に比較し外需への依存度が高いため、円高による輸出競争力の低下から61年以降63年まで停滞しており、平成元年以降地球環境保全への関心の高まりを受けて再び増加に転じている(第2-3-25図)。また、電気自動車の最大手メーカーE社の国内の電気自動車販売台数の推移を見ると、第1次石油危機以降やはり急激に伸びてきたが、58年から63年までの原油価格の低下を受けて、この間の販売台数は著しく低下し、地球環境保全への関心の高まりを受けて平成元年以降再び伸び始めている。(第2-3-26図)。
これに対し、技術評価を通じた将来的な技術的対応可能性を踏まえた適切な水準の規制・指導が実施される場合には、実効ある対策が進むことが多い。
例えば、日本の自動車業界の排出ガス規制への対応について、50・51年度規制適合車の型式数を見ると、規制が完全実施された52年3月末に先立つ51年8月末までに、国産常用車の国内販売台数のほとんどが51年度規制対策車になっている(第2-3-27図)。技術力なしに規制適合車の生産はできないことを考えれば、技術評価を通じた将来的な技術的対応可能性を踏まえた適切な水準の規制とそれへの対応を共通の前提として、企業間で厳しい競争が行われたことが技術開発を進展させる一つの要因になったと言える。
より具体的に、昭和40年代に公害対策への取組を行った自動車メーカー2社を取り上げる。これら2社について、排出ガス関連研究開発費や排出ガス関連研究員の推移を、それぞれ昭和40年、42年を100として指数化してみると、排出ガス関連研究費については、自動車排出ガス規制が段階的に強化される45年から50年に向けて急激に伸びており(第2-3-28図)、また、排出ガス対策関連研究員の割合についても45年から48年に向けてやはり急激に伸びている(第2-3-29図)。自動車メーカー各社は、排出ガス対策について最優先課題として取り組んだが、この2社の場合は40年代前半に公害関連の特別部署が設けられており、既存の研究開発部門は公害対策以外にも多様な研究課題を抱えている中で、排出ガス規制への対応に向けて、企業の内部において、資金的にも人材的にも排出ガス対策部門に重点的な手当がなされたことが推察される。なお、現在においては、排出ガス対策のみならず、トレードオフの関係にある、燃費、騒音、安全、リサイクル等の需要が複雑に絡み合った状況であり、これら諸要因を高次元でバランスさせるために、なお一層の研究課題に自動車メーカーは取り組んでいる。もちろん、適切な規制・指導の実施のみで技術開発が進むものではない。企業の技術開発には様々なリスクが伴うことから政府の積極的な支援も重要である。政府が規制・指導等の対策を長期的見通しの下で実施するとともに、必要に応じ技術開発への支援等を講じることになるが、環境に与える影響の少ない製品等の市場の形成を促進することになる。
一般的に技術革新には3つの段階があると言われている。第1は発明の段階であり、第2は技術開発の段階、そして第3は事業化の段階である。第1の段階に近いほど技術的不確実性は高いが、所要資金は少なくて済み、第3段階に進むにつれ技術的不確実性が低くなるかわりに市場に受けられるかという「市場の不確実性」が大きくなり、さらに、商業的な生産のための膨大な設備資金が必要になると言われている。自動車排出ガス削減技術の開発に成功した理由については、次のとおり、技術開発の中で第2段階から第3段階へ進む過程で政府が相当の役割を果たしたことも否定できない。
第1に、この時期に発生する市場の不確実性については、政府が規制スケジュールを明示したことが、厳しい規制に適合した車種の市場を確保し、量産体制を可能にし、技術開発の初期の段階で懸念されたような高コストをある程度克服することを可能にしたと言えよう。日本の製造業における最大の主観的投資決定要因が第2-3-12表に見るように、「製品需要の見通し」であることを考え併せると、規制強化が、「市場の不確実性」を低減した意義は大きい。このような排出ガス規制の下で、自由経済の中での企業間の競争が行なわれ、環境保全技術の開発及び実用化が推進されたのである(第2-3-13表)。
第2に、自己資本比率が欧米より低い日本企業にとって、事業化段階における本格的量産体制への製造工程変更にかかる莫大な費用については、自己資金を重点投下するという全社的な対応によっても賄いきれない部分があったが、このような時期に実行された排出ガス対策を条件とした日本開発銀行等の政府系金融機関からの低利かつ長期の融資は大きな支援となったと考えられる。
第3に、厳しい規制に適合した車種の販売価格は、それまでの研究開発費及び生産ライン変更による設備投資費を回収するため高く設定される傾向があり(第2-3-14表)、市場での需要減退が懸念された。このような状況に対し、当時、厳しい排出ガス規制を満足した車種であるか否かが消費者にとって十分識別可能な状態になっていたことと、激しい規制に適合した車種に付与された税制優遇措置によって消費者の環境保全的な選択がしやすかったことが販売面でプラスの効果をもたらしたとも推測される(第2-3-15表)。市場の条件を整備するこうした各種の支援策が、企業による公害対策技術開発費用の回収を容易にしたと考えられる。
(5) 公害関連技術開発によって企業に生じた利益
公害防止技術の開発には、厳しい公害規制を満たした上で、従来のとおりの規模の生産活動を継続し得るという意義があったが、さらに、こうした消極的な意義だけでなく、その後の企業経営を向上させる積極的意義をもたらしたことは注目に値する。
自動車業界についてみると、世界で一番厳しいと言われる自動車排出ガス規制の強化に際して、公害対策装置を取り付けることによって自動車の価格が10%程度上昇すること、さらに、低公害化による燃料経済性や走行性能の低下を招くこと等により、自動車に対する需要の減退を引き起こし、ひいては国全体の製造業生産額が大幅に減少する、という悲観的な予測が支配的であった。ところが実際には、価格は確かに上昇したものの需要は伸びる一方で、また、走行性能を実用上問題のない程度に保った上での燃料経済性の維持、改善にも大きな努力が重ねられた結果、51年度時点で既に、51年度規制適合者の燃料経済性は48年度規制適合車と比べてさほど低下していないものが多くなった。その結果、排出ガス規制の実施にもかかわらず自動車産業は大いに発展し、日本の経済も拡大していった。また、前述の自動車会社2社に対する環境庁の調査によれば、低公害技術開発という未知の課題を克服したことで、「いかに困難な課題でも挑戦すれば道は開ける」というフロンティア精神が生まれ、社員の勤労意欲ひいてはモラルの向上につながったこと、社会的意義の高い低公害技術の開発に挑戦する姿が国民に評価され、企業イメージの向上に大きく貢献したといったこと等も聞かれた。さらに、例えば自動車排出ガス規制の進展は、単に公害防止のためだけでなく、燃焼制御技術の進展、さらには品質管理法の改善というような副次的、波及的な技術開発をもたらし、現在の国産車のように、高い燃費効率と低公害性を両立したガソリン自動車の製造を可能にし、日本製自動車の海外における圧倒的な競争力につながっていった。
企業の環境関連技術開発を「採算を無視して環境保全を第一に考えた行動」の結果であると評価することはいささか過大な評価に過ぎよう。むしろ、採算、特に長期的な採算を第一と考えた企業本来の行動が有効に機能したことが、自動車排出ガス対策の向上につながったと言えよう。重要なことは、環境保全に対する努力をした企業が社会的にも十分評価されるような社会システムを構築することであろう。
(6) 公害防止投資の国民経済への影響
公害防止投資が活発になされた40年から50年にかけての民間公害防止投資の累計額は約5.3兆円(45年価格)であったが、この公害防止投資がこの間の日本経済に与えた影響について検討してみよう。
公害防止投資が経済に与える影響については、大きな枠組みとして、投資に伴う費用増が価格に与える影響と、投資のための需要増が所得面に与える影響の2つの側面が考慮されねばならない。
第1の価格面に与える主要な影響については、製品の需給関係によって異なるものの公害防止投資による費用増加はその製品価格に影響を及ぼすこととなる。これは、この製品を部品又は原材料として購入する産業の製品価格に影響を与え、さらに最終消費財の価格にまで影響が波及する。これらの価格が上昇すると、各材の需要の価格弾力性(価格の変化に対する需要の変化の割合)に応じて、それぞれの需要を減少させる。この結果は、各産業における設備投資を減少させ、それが供給力の低下要因となる。
第2の所得面に与える主要な影響については、公害防止投資はその投資をした産業の費用であるが、同時にその投資を受注した産業の需要増加となることである。さらに、公害防止産業における需要増は公害防止投資の資材、部品の需要増となり、関連産業の投資を増大させ、供給力の増大要因となる。
以上見たように、第1の効果は実質国民総生産を減少させる要因(価格効果)であるのに対し、第2の効果は実質国民総生産を増加させる要因(所得効果)である。公害防止投資の経済的影響を実態に即して論じるためには、他に考慮すべき要因も少なくないが、2つの効果に焦点を当て、環境庁で開発した計量モデルでこれらの効果を総合した結果を推定すると、第2-3-30図に示すとおり、公害対策を行なわなかった場合に比較し、50年において、実質民間設備投資が約7.4%増加し、実質個人消費が約0.4%増加し、実質経常海外余剰が約3,000億円(45年価格)減少していたこととなり、実質国民総生産では約0.9%増加していたものと計算された。消費者物価指数については、50年で170.4(45年=100)の水準にあったものを、公害防止投資によって約1.2%上昇させたことになる。これは40〜50年の年平均約8.3%の物価上昇立を8.4%に引き上げたことになる。また、卸売物価指数については、50年で154.2(45年=100)の水準にあったものを約1.7%上昇させたことになる。これは年平均では5.5%の物価上昇率を5.7%へと引き上げたことになる。
以上の試算結果を見る限り、公害防止投資の経済的影響は、各産業ごとに異なるものの、国民経済全体に対しては、過去の高度経済成長過程においては大きな衝撃とはならなかったと考えられる。諸外国における経験もほぼ同様で、OECDでは、「公害防止投資が国民総生産に与える影響は、中立的ないしは無視できる程度である」としている。高度経済成長時代のように、生産能力増強投資にまい進していた時期ならばともかく、公害防止投資のピークと重なる石油危機後の不況時について言えば、公害防止投資の実施が停滞していた需要を喚起し、設備投資や雇用をある程度下支えする役割を果たしていたと考えられる。
市場経済においては、製品やサービスの供給者はできるだけコストを下げ、低廉な価格で優秀な製品を作り、競争に勝ち抜かねばならない。市場におけるこのような競争を通じて、社会全体として資源が効率的に使われ、最適な資源配分がもたらされるというのが市場メカニズムの原理である。環境の使用に当たっては普通は対価を支払わなくてよいが、何らかの形でその費用が経済計算においてコストとして算入されるような仕組みが作られた結果、市場経済には環境汚染という形の外部不経済を自ら除去するインセンティブが働き、環境を含めた各種の資源が市場を通じて効率的に配分されていった。我が国のかつての公害対策の場合も、公害規制の強化に伴い企業の環境コストは高まったが、経済は全体として成長を続けた。この陰には、市場による効率的な資源配分機能が働いていたと言えよう。言うまでもなく、環境を使用した費用をコストに算入しない場合とこれを算入した場合では、経済の姿は異なる。環境費用が内部化されると、汚染を発生しやすい業種の製品の価格は上がり、その製品の需要は減って、同じような機能を有する別の製品で、製造に当たって汚染の少ないものは相対的に多く需要されるようになる。こうした過程を通じて産業構造も消費パターンもダイナミックに変わっていくが、ダイナミックに変化するからこそ、産業間で資本などの円滑な転移が進み、経済全体としては不必要な痛みやロスが少なくて済むのである。第1章に見た旧ソ連や東欧の事例に照らせば、自由経済の持つこのようなダイナミズムを今後とも維持することが、環境対策の強化に伴う社会的な負担を軽減する上で重要なことが見てとれよう。日本の経験に即せば、経済成長の中でそれが生み出す果実を便って一層円滑に公害対策を進める余地は十分あったと考えられるが、それにしても、激化する公害を後追いして急速に強化された対策の下であってさえ、自由な経済の効率性と政府の政策が活かされ、個々の企業や業種について見た場合、厳しい負担を被った企業があったものの、国民経済全体を見た場合は、公害対策が必ずしも経済成長に対して非常な重荷とはならなかった。